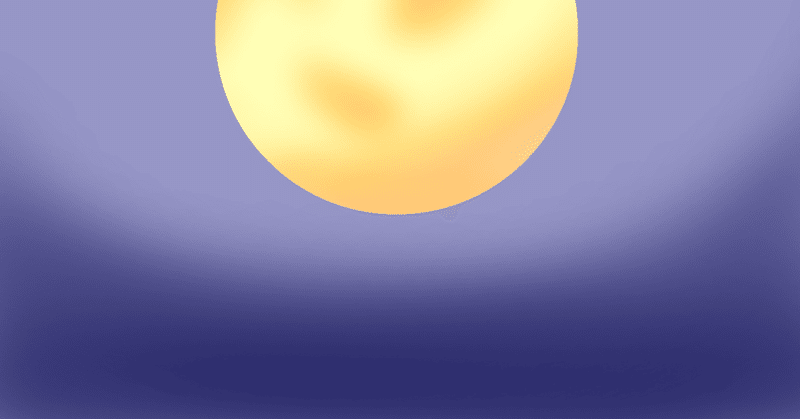
【短編小説】自責
「シロちゃんは幸せだったと思うよ」
スマホの変えられずにいるロック画面をぼんやり眺めていると、向かい合うように座ってコーヒーを啜っていた友人が、遠慮がちにそう言った。
「そうかな」
「そうだよ。あんたにそんな愛されてさ
私がまだ子猫だったシロちゃんを譲った時、あんた何て言ったか覚えてる?こんなワガママそうなの、どうせすぐに手放すか脱走するに決まってるって…表情1つ変えずにボヤいてたんだよ?」
当時を思い出したように、友人は軽く笑った。きっとそんな顔をしたのは、私を励ます為のような意図も込められていたのだろう。
それでも私は、つられて笑うことも元気づけられた気も持てなかった。
「…。やっぱりもう、動物を飼う気はないんだ?」
私の纏う空気を察したのか、友人は今日2回目になる質問を投げかけてきた。
「役に立てなくてごめん。思ったよりシロの存在が大きくなっちゃってたみたいでさ、もうそういう喪う経験はなるべく避けたいっていうか…」
語尾が消えかける程のか細い声で応えると、友人は「そっか」とまたこちらを気遣うように笑った。
「謝らないでいいよ。気持ちは分かった
じゃあ今度の譲渡会からは不参加だって、他のスタッフにも伝えとくね。あんたもう常連だったから、急にこなくなったらみんなからの連絡が怒涛だろうし」
ここは奢っとくよ。無理に呼び出してごめんね。
そう言った後、友人は会計を済ませ店を出て行った。近々また譲渡会を開くと言っていたし、色々と繁忙期なのだろう。彼女が足早に駅へと向かって行くのが店内から見えた。
友人の姿が見えなくなってから、私は深くため息を吐いた。
本当にあの子は、幸せ…だったのかな。彼女には言えなかったけれど、私がシロを死に追いやってしまったんだ。その事実はこれからもずっと変わらない。
「なんで、あんな…っ」
気付けば湿った声でそう零し、頭を抱えていた。
ごめん。ごめんね、シロ。
許して欲しいなんて言わないよ。
いつものように躾を下しただけだった。まさか、その時強めに叩いた箇所の打ち所が悪くて逝ってしまうだなんて。
彼女の主催する譲渡会には今後参加しない、とは言ったものの、もう他の友人達にはシロのことを話しているし、数人からは抱っこやスキンシップをしてみたいとも言われている。
彼らにシロの死と真相がバレる前に、どうにかして似たような猫を手元に置いておかなきゃ。それにいつまでも落ち込んでいたら、きっとシロだって浮かばれない。
思い立ったが吉日だ。
私は店を後にし、何駅か先のペットショップに向かうべく、友人の彼女に遅れて駅のホーム目指し雑踏の中に歩を進めた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
