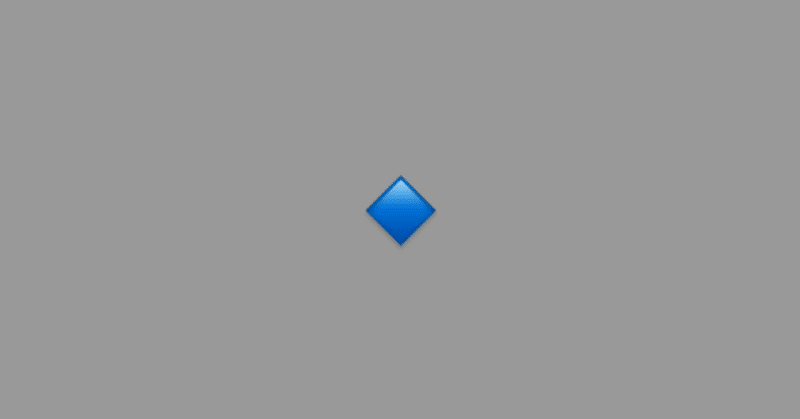
青いボタン
6月23日、木曜日。天気は雨。
今日の鬱警戒レベルは5段階中の4。
世界は空前の自殺ブーム。政府は自殺防止のためと、一昨年からこんなものを天気予報に加えたのだ。
それにしても最悪な天気だ。
低気圧のせいか、頭が痛い。
体が重いが、僕は仕方なく駅に向かう。
電車に駆け込む地味なサラリーマン。
何かブツブツと呟いている奇妙なおばさん。
片手に缶ビールを持って、ICカードの使い方が分からず苛ついている男。
細い足を組んで、ふんぞり返って椅子に座る女子校生たちの下品な笑い声。
いつも通りの、憂鬱な2番線だ。
学校にギリギリ間に合わない電車に僕は乗った。
今日はサボろう。
行ってもどうせ楽しくないんだから。
この電車にずっと乗っていよう、そう思った。
急停車のアナウンスで僕は目覚めた。
何か重たいものがぶつかる、鈍い音がした。
また人身事故だ。
今月で14件目か。
誰も利用していないのでは無いかと思うほど、田舎の小さな駅。
ここで誰かが線路に飛び込んだようだった。
この駅で乗客全員は降りるようアナウンスが流れた。
僕以外の客はこの駅で次の電車を待っているようだったが、僕はこの田舎を歩くことにした。
本当に誰もいない。
気味が悪いほど静かな街だ。
砂利がローファーにこびりついて足が重い。
雨も強くなってきた。
どこかで雨をしのごうと歩き始めると、後ろから誰かに声をかけられた。
「今日は素敵な天気だねぇ。」
背の低い老婆がこっちを見ていた。
どこが「素敵な天気」なんだ?
今日の天気は大雨だ。
晴れる確率は0%。
鬱警報だって出ている。
僕は少し怖くなって、軽くお辞儀をして逃げるように早歩きした。
「おい!」
老婆は大声でそう叫んだ。
他でもない、僕に向かって。
僕は固まって振り返った。
老婆が近づいてくる。
怖くて逃げられない、足が動かない。
老婆は足を止め、僕を見上げてゆっくりと言う。
「駅に戻って、青いボタンを押しておくれ。」
青いボタン…?そんなもの駅にあっただろうか。
「ホームの向かいの柱だ。さっき人が死んだだろう?だからそのボタンを押して欲しいんだ。」
老婆は僕から目をそらすと、雨雲を見上げた。
皺だらけの顔に雨が滴っている。
「そのボタンを押すと、何か起こるんですか…?」
老婆は上を向いたまま 「さぁね。」 とだけ言うと、俯いて山の中へと消えていった。
僕は駅に戻った。
そこには誰もいなかった。
あの電車に乗っていた客もいなくなっていた。
屋根がないので僕は雨ざらしだった。
靴が泥だらけなのもあって、タイルが敷きつめられたホームで何度も滑りそうになった。
ホームの向かいには、確かに何本か柱が立っていた。
1番奥の柱をよく見ると、確かに青いボタンがついていた。
人工的で無機質なコンクリートの柱から飛び出したそれは、思っていたより小さく、四角かった。
ホームから降りて線路を渡る。
恐る恐るボタンに指を伸ばす。
悪寒がする。
もしかしたら感電してしまうのでは無いか。
もしくは爆発するかもしれない。
手が震える。
力が入らない。
その瞬間、ホームにアナウンスが流れる。
〈間もなく、1番線に、貨物列車が通過します〉
このままでは轢かれてしまう。
僕が轢かれてしまったら、またはここからボタンを押さずに逃げてしまったら、このボタンはもう二度と押されない、僕が今、押さなければならない、そんな気がする。
僕は深呼吸して、人差し指に力を込め、
思い切り青いボタンを押した。
そしてすぐに指を離してホームをよじ登った。
貨物列車が通り過ぎた。
6月24日、金曜日。今日も雨が降っている。
疲れていたからだろうか、何だか目覚めが良かった。
家の電話が鳴った。
担任からだ。
「歯科検診があるので、今日は学校に来てくださいね。」
昨日と同じように僕は駅に向かった。
地味なサラリーマン。
ブツブツと呟きながら早歩きしているおばさん。
片手に缶ビールを持った、ICカードの使い方が分かない男。
細い足を組んで椅子に座る、女子校生たちの笑い声。
世界は何一つ変わっていない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
