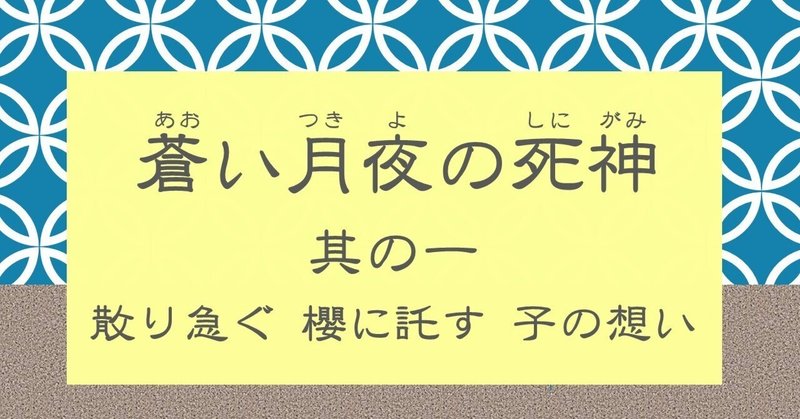
蒼い月夜の死神 其の一「散り急ぐ 櫻に託す 子の想い」
水生の国青空藩白雲にある、九士町。その中央を流れる早瀬川沿いに、世見道場は建っていた。剣術を学ぶべく、沢山の子供達が毎日元気に通っている。門下生の内、七割は町人の子供で三割が武士や百姓の子供だ。世良廉太郎、見須奈頼乃輔の二人が始めたこの道場も、今はその二人を含めた大神欣司、宰嗣之進、八重樫朔也と言う五人の師範と、五十嵐鞍悟、長谷亙と言う若き二人の師範代を抱えるまでになった。とまあこれは、あくまでも表向きの話である。実は、世見道場には裏の顔があった。それは、殺し屋。蒼い月夜の晩に多く現れるので、通称蒼い死神と呼ばれている。今日も何処かで困っている者達の声を聞きつけ、五人の男達は闇夜を奔走する。(299文字)
「こっ…殺しぃーっっっ?」
春の穏やかな、陽気の中。
居眠りをしていた朔也は、突然起き上がって語尾を裏返らせた。
「は、はい…」
頷いた鞍悟が静かに俯き、髪の毛に付いていた薄紅色の花びらをはらりと落とす。
「どうやら、冗談ではないようなのです。決意も固いらしく、このようなものまで押し付けるように寄越して。あまりにも真剣でしたので突き返す事も出来ず、一応預かると言う形で受け取っては参りましたが…」
そう言う亙の手のひらに乗っていた、飴玉一個分にも満たない額の小銭を見て、朔也は深い溜息をついた。
水生の国青空藩白雲にある、九士町。
その中央を流れる早瀬川沿いに、世見道場は建っていた。
剣術を学ぶべく、沢山の子供達が毎日元気に通っている。
道場の創設者である二人の内、一人は世良廉太郎。
明るくとっつきやすい男ではあるが、女好きで惚れ易い性格が難点。
一寸いい女を見ると、すぐに声を掛けたがる。
だが、廉太郎程のいい男ともなると、彼自身が声を掛けるまでもなく、女達の方から寄って来るのであった。
同じく創設者であるもう一人は、見須奈頼乃輔。
真面目でしっかりしており、廉太郎とは正反対の堅物な男だ。
いつもふらふらとして頼りない廉太郎の、御守り役でもある。
彼は過去、剣術の他に拳法も学んでいた。
なので道場では、剣の苦手な子や剣だけでは物足りない子達に、拳法も教えている。
十五年前に故郷の風切藩が取り潰され、敢え無く浪人となってしまった二人がその二年後、生計を立てる為に建てたこの道場。
朝昼夕と三回練習時間が設けられており、現在通っている門下生は七十七名に上る。
門下生の内、七割は町人の子供で三割が武士や百姓の子供だ。
二人で始めたこの道場も、今は二人を含め五人の師範と、二人の師範代を抱えるまでになった。
まずは、一人目。
無口で無表情、自分の事は決して語らない謎の男、大神欣司。
八年前の春、早瀬川の河川敷に血で染まった櫻の花びらに、埋もれるようにして倒れていたのを、廉太郎と頼乃輔に拾われた。
胸に大きな刀傷を負っていた為、二人はすぐに欣司を知り合いの医者に診せた。
その時、咄嗟に見せた鋭い目付きと、抜いた刀から放たれた殺気、そして血の匂い。
二人は何も訊く事無く、欣司に道場の師範にならないかと誘った。
最初は怪しんでいた欣司も、文句を言わずに此処にとどまり、現在に至る。
二人は、未だに欣司の事を何も知らない。
彼が一体何者なのか、八年前のあの日何故早瀬川の河川敷に倒れていたのか、そして彼を斬った人物は今何処に。
訊きたい事は山程あったが、子供達を相手に仕事はきちんとこなしていたので、今はそれでいいと思っている。
次に、二人目。
宰嗣之進は、此処青空藩白雲奉行所の与力をしている父親、良左衛門の一人息子である。
父親の口利きで、同心となった嗣之進。
だが、正義感の強い彼は上役の意見が間違っている場合でも、黙って頷かなければならぬ苦を強いられる奉行所勤めを負担に感じ、五年間勤めた後に辞職する。
新たな職を求めて、口入屋「遊作屋」に立ち寄った嗣之進は、主人の迅壱から世見道場の代稽古を紹介された。
其処で嗣之進は、あっと言う間に道場の子供達の人気者となる。
奉行所にいた頃から人に良く相談事をされたり、男やもめの同僚が夜勤の時にはその子供を預かったりしていたので、それらの経験が役に立ったとでも言うべきか。
最初は一月だけの臨時雇いだったが、二月三月と徐々に長引いて行き、一年後には正式に師範となる事を許されたのである。
昔も今も、相変わらず子供にだけは甘い嗣之進だが、相手が大人となると話は別。
物事をはっきり言い過ぎる傾向もある為、彼を慕う者と嫌う者とは、きっぱり二分されるのだった。
そして、三人目。
風の吹くまま気の向くままに、ぶらりと旅をしていた身寄りのない浪人、八重樫朔也。
大きな屋敷の勝手口から残り物をくすねたり、百姓から握り飯を分けてもらったりして何とか食い繋いでいたのだが、ついに困り果てた朔也が三年前に叩いた門が、この道場だった。
何でもするから食わしてくれと言う朔也を、廉太郎と頼乃輔は小間使いとして雇い、道場の掃除や皿洗いをさせるつもりだった。
だが、朔也は根っからの怠け者らしく、どれをやらせても三日坊主。
働きもしない者に、ただ飯を食わせる訳には行かないと、困り果てていたある夜。
たまたま開いていた朔也の部屋の隙間から、中の様子を垣間見た廉太郎と頼乃輔は、思わず目を見開いた。
自分の刀を手入れしていた朔也は、普段の物臭な彼とは違い、凄まじく強い気を放っているように感じた。
小間使いよりは、遙かに役に立つであろう事を確信した二人は、それ以来彼をこの道場の師範として雇う事にしたのであった。
続いて、師範代の一人目。
青空藩旗本五十嵐翔内の長男、鞍悟。
十三年前、この道場が出来た頃から通っていた鞍悟は、去年その剣の腕を見込まれて師範代となった。
素直で正直、上の者の言う事も良く聞く心優しい青年だ。
しかし少々のんびりしている面があり、危なっかしい所も多々あるので、廉太郎達も心配で目を離せずにいる。
そして、師範代二人目。
青空藩旗本長谷竜次郎の長男、亙。
鞍悟とは幼馴染みで、十二年前からこの道場に通い続けて来た彼は、今年師範代として引き抜かれた。
のんびり屋の鞍悟とは正反対の性格である亙は、何事にも前向きに取り組み、諦めずに頑張り通す粘り強い青年である。
だが、自信過剰で向こう見ず、猪突猛進型なので何かと世話が焼けるのであった。
とにかく、まだまだ新米の鞍悟と亙は、毎日休む事無く道場に通っては、子供達に剣の指導をしていた。
残りの五人はと言うと、師範は一度にそう何人も要らないので、交代で教える事になっていた。
今日は、朔也の日。
二階が鞍悟と亙を除く五人の寝所となっているのだが、廉太郎も頼乃輔も欣司も嗣之進も、朝から出掛けて留守だった。
朝の練習が終わり、これから昼飯だと言う時に先程の話題は出たのである。
それはほんの今しがた、鞍悟と亙が子供達を表まで送り出した時の事だった。
「皆、気を付けて帰るのだぞ!」
「五十嵐先生、長谷先生…」
皆がそれぞれの家へと帰って行く中、一人踵を返してこちらへ駆け戻って来たのは、朝練習に参加している志保だった。
「どうしたのだ?」
鞍悟が、優しく話し掛ける。
「あ、あの…」
志保は、何やら言いにくそうに口ごもっている。
「志保…何か、あったのか?はっきり、言って御覧」
亙に促され、頷いた志保は握った右手を差し出した。
「こ、これ…絶対に、返すだなんて言わないで下さい!」
亙が、黙って手のひらを差し出す。
無理矢理握らされたのは、ほんの僅かな小銭だった。
「何だ、これは…」
唖然としながら亙が訊くと、志保は目を潤ませて答えた。
「こ…殺しの依頼を、受けて下さい!」
『えっ?』
鞍悟と亙は、思わず声を上げた。
同時に吹いた風が、落ちた花びらを再び舞わせる。
彼らを語るのに、忘れてはならない事実。
世見道場には、裏の顔があった。
それは、殺し屋。
蒼い月夜の晩に多く現れるので、通称蒼い死神と呼ばれている。
しかし、その事はその筋の者のみが知る事であって、志保のようなまだ十にも満たない子供や、近所の町人達が知るような事ではなかった筈だった。
それが、何故…顔を見合わせる、鞍悟と亙。
新米の二人は師範代になった今も、その事実を知らされてはいなかった。
だが二人とも、もう大人しく言われるがままに竹刀を振るだけだった頃の子供ではない。
師範達が、道場以外の表沙汰には出来ない仕事を請け負っているであろう事は、嫌でも感じざるを得なかった。
しかし十三年、あるいは十二年もの間、師範達を信頼してついて来た二人は、たとえそれが殺しであったとしても、決して間違った行いではないのであろう事を信じていた。
だからこそ、敢えてこちらからは何も訊く事なく、今後も共に歩んで行こうと心に決めたのだ。
勿論、二人は実際に人を殺めた事はまだない。
廉太郎達も、二人が殺しの依頼を引き受けるか否かを決めるのは、俺達が死んでからでいい…と考えている。
尤も、剣の腕も五人の師範に比べれば遙かに未熟な為、殺しはまだ無理だった。
「わた坊、これは話を聞く前に一度道場に戻って…」
「も、戻ると言ったって…」
亙は、顔を顰める。
「今日の師範は、八重樫殿だぞ?相談するには、少々…いや、かなり心許ない。せめて、宰様でも居て下されば良かったのだが」
「でも、他の皆さんは朝から出掛けられているではないか。八重樫殿でも、私達二人で決めるよりは良い知恵を貸して下さる筈だ」
八重樫朔也師範、さり気なく散々な言われようである。
二人が何やらひそひそ話しているのを、志保は不安そうな面持ちで見つめている。
「分かった…鞍ちゃんの、言う通りにしよう」
亙はしゃがみ込み、志保の肩に手を置いた。
「志保、良く聞くのだ。これは、一応私が預かっておく。先生方が帰って来られたらお前の事を話してみるから、こちらから出向くまでは勝手に自分だけで動いてはいけないよ。いいね?」
少々不服そうな志保ではあったが、仕方無く頷くと丁寧に頭を下げて、川原沿いの道を走って行ったのだった。
「不味いよ…」
話を聞き終えた朔也は、頭をぐしゃぐしゃと掻きながら床に座り込んだ。
「不味い不味い、不味いって…あぁーっ、不味いっ!」
「ま、不味い…ですか?」
鞍悟が恐る恐る訊き返すと、朔也は髪を掻き乱して言った。
「不味いっしょ、やっぱ!」
「でっ、ですが、八重樫殿っ!」
「おい、わた坊…」
言い返そうとした亙を、朔也は静かに見上げた。
「お前それ、志保に返して来い…今すぐだ」
「しっ、しかしっ!」
「いいか、わた坊っ!」
声を荒げた亙に怒鳴り返した朔也は、深く溜息をついた。
「駄目だ…首を、突っ込まん方がいい」
「しかし、志保は涙を堪えていたのですよ?余程の事があったに、違いないのです!それが分かっていて、どうして知らない振りをする事が出来ると言うのですかっ!」
怒鳴る、亙。
場が、しんと静まり返る。
「あ、あの…や、八重樫、殿?」
鞍悟が顔を覗き込むと、朔也は不貞腐れたように床に寝転がった。
「だぁーっ、もう勝手にしろっ!言っておくが、俺は加勢せんぞ…絶対になっ!」
そう言ったきり、朔也は目を瞑ってしまった。
鼻からふんっと息を吐き出した亙は、鞍悟に言った。
「行くぞ、鞍ちゃんっ!」
「え…ど、何処へ?」
「決まっているではないかっ!世良先生と、見須奈先生を捜しに行くのだっ!」
亙は、物凄い剣幕で駆け出して行った。
戸惑いながらも頷いた鞍悟は、寝転がったままびくともしない朔也を振り返りつつ、亙を追って道場を出た。
そんな二人の後ろ姿を、朔也は薄目を開けて見ていた。
「ったく、何も分からん若造共めがっ…あの勢いだけは買ってやってもいいが、所詮はあの二人も危険を顧みる事を知らん、ただの阿呆だったと言う訳だ」
ぐうと言う腹の音が、誰もいない道場内に響き渡る。
「あ、昼飯だった…」
起き上がった朔也は、いそいそと台所へ入って行った。
廉太郎と頼乃輔は、早瀬川で釣りをしていた。
水面に、落ちた櫻の花びらが浮かんでいる。
船着場で船頭の晩造から小舟を借り、朝から粘ったお陰で今日は珍しく大漁だった。
「今晩は川原で火を焚き、焼き魚にでもするか」
魚籠の中の魚を覗きながら頼乃輔がそう言うと、廉太郎は途端に腕を組んだ。
「となると、酒がいるなあ。じゃあ、俺はちょっくらさくらにでも…」
「おい、廉さん…」
頼乃輔は、訝しげに眉を顰めた。
「そんな事、言って…また、女将にでも会いに行く気だろう」
「なっ…ばっ、莫迦な事を言うな、頼さんっ!」
慌てて口ごもる所を見ると、どうやら図星らしい。
居酒屋「さくら」は廉太郎達行きつけの飲み屋で、女将のさくらは評判の美人だ。
十八になる娘のおはると旦那の陽八、そしてお民、喜助、新吉と言う三人の使用人から成っている。
「他人の女だぞ…いい加減、やめておけ」
真面目な顔をして言う頼乃輔に、廉太郎は笑って答える。
「安心しろ、本気な訳ではない。それに、見るだけならただだし…まあとにかく、今日は酒を買って帰るだけだ。行こう」
溜息をついた頼乃輔は、ゆっくりと舟を漕ぎ始めた。
船着場で晩造に借り賃を払った二人は、河川敷を町へ向かって歩いた。
魚籠の中の魚が、ぴちゃぴちゃと跳ね回る。
「頼さん、あれ…」
ふと、廉太郎が立ち止まった。
「どうした?」
頼乃輔も、立ち止まる。
川の向こう岸にある杉ノ森と呼ばれる森の奥に、人影が見えた。
一人ではない。
数人いるように見えたが、木々に隠れてはっきりとした人数は、確認出来なかった。
「あれは…敷丸屋の旦那だな?」
そう気付いたのは、頼乃輔だった。
廉太郎も、目を細めて見る。
「た、確かに。って事は…あ、ありゃあ、志保の親父さんか?」
杉ノ森にいた一人は呉服問屋「敷丸屋」を営む志保の父親、徳十だった。
残りの人間は皆、やくざや浪人風体である。
「物盗りか、それとも…まっ、まさか、殺しではあるまいなっ!」
頼乃輔は気が気ではないらしく、そわそわしている。
「どちらにしろ、此処からでは助けてもやれん。かと言って、舟で行っては見つかって逃げられてしまうかもしれんしなあ…やはり、渚橋まで走るしかないか」
そう言って、廉太郎は渚橋へ向かって駆け出した。
頼乃輔も、後を追う。
土手を登り、川原沿いを走って渚橋を渡った二人は、急いで杉ノ森へ向かった。
しかし、辿り着いた時には既に徳十達の姿は消えていた。
「あれ…ど、何処へ行った?」
廉太郎が、息を切らしながら辺りを見回す。
森の奥を一通り見た頼乃輔は、首を横に振った。
「いない…森を反対側に抜け、表の通りに出たのかもしれん」
「そうか…」
息をついた廉太郎は、腕を組んで考え込んだ。
「しかし、何故敷丸屋の旦那があんな柄の悪い連中と…」
「志保が…」
「え?」
訊き返す廉太郎に、頼乃輔は言った。
「いや…最近、志保が元気無いように見えないか?」
「志保が?」
廉太郎は、目を丸くした。
頼乃輔は、溜息をつく。
「気が付かなかったのか?あの朔也でさえ、気が付いたものを…」
「さっ、朔也がっ?」
廉太郎の目が、更に見開かれる。
「恥ずかしい…途轍も無く、恥ずかしい…」
肩を竦めた頼乃輔は、呆れた顔をした。
「とにかく、最近の志保は少々様子がおかしかったのだ。だから、ひょっとして今の出来事と志保の様子は、何か関係があるのではないかと思ってな…」
それを聞いて暫く黙り込んでいた廉太郎は、頼乃輔の肩を叩いて言った。
「よし…さくらに行く前に、ちょっと敷丸屋にでも寄ってみるか」
頼乃輔も頷き、二人は再び渚橋へ向かって歩き始めた。
「天麩羅蕎麦、一つ」
嗣之進は、蕎麦屋「一味庵」に来ていた。
蕎麦を頼んで奥の席に座ろうとした嗣之進は、手前隅の席に欣司の姿を見つけた。
「大神さん」
嗣之進は、欣司の向かいに腰掛けた。
「御一緒させてもらいますよ」
欣司は、黙っている。
女将のお静が茶を運んで来て、再び戻って行った。
欣司は既に蕎麦を食べ終え、銚子を一本ちびちびと飲んでいる。
天麩羅蕎麦が来るのを待ちながら、嗣之進は欣司をじっと見つめていた。
欣司は、黙って酒を飲み続けている。
「はいよ、天麩羅蕎麦」
「あ、ああ…」
お静の声で我に返った嗣之進は、箸を掴んで言った。
「そんなに、気になりますかい?」
欣司が、ちらりと嗣之進を見る。
嗣之進は格子窓から外の表通りを眺め、この向かいに建っている店の方を顎で指した。
「だからほら、敷丸屋ですよ。見た目は、普段と何ら変わりないんですがねえ…」
そう言って蕎麦をすする嗣之進を、今度は欣司が見つめた。
一味庵の真向かいは、何と敷丸屋である。
欣司は酒を飲みながら、視界の隅で敷丸屋を絶えず捉えていたのだった。
嗣之進は、それに気が付いていたらしい。
欣司は、再び酒を飲み始めた。
「優しい所、あるんですねえ…見掛けによらず」
そう言って嗣之進が上目使いに見た時、欣司は銚子ごと酒をぐいと飲み干すと、突然立ち上がった。
そして嗣之進を見下ろし、机を思い切り叩いたのである。
それに驚いた店の者や他の客が、一斉にこちらを見た。
嗣之進は気にせず、蕎麦をすすっている。
欣司は、こちらを見ている客連中にぎろりと睨みを利かせると、黙って店を出て行ってしまった。
「あ、あの、お客さ…」
「お代、此処」
お静が訊こうとした事を察して、嗣之進は机の上を指差した。
机を叩いた欣司の手の中には、ちゃんと銭が握られていたのだった。
「あら、ほんと。じゃあ、ちょいと失礼して…」
嗣之進に頭を下げたお静は、机の上の銭を勘定し始めた。
「ひい、ふう、みい…あ、あれまあ!どうした事だろうねえ、これは!」
驚いたお静は嗣之進の顔を見てはっとし、もう一度銭を数え直し始めた。
「ひい、ふう、みい…ははあ、なるほど。やっぱり、そうだよ」
ぶつぶつ呟いているお静を見て、嗣之進は言った。
「どうした…足りねえのかい?」
「え?ええ、いえね、それがその逆でして…」
嗣之進は、箸を止めた。
「逆って…じゃ、じゃあ、多かったって言うのかい?」
「はい。ですから、考えをちょいと変えて勘定し直してみたら…これがまあ、ぴたりと一致しますんでね…恐らく御自分の分と旦那の分も、一緒に御支払いになって行かれたのではないかと…」
「お、俺の分も?ご、ごほっ、ごほっ…」
咳き込む嗣之進に、お静は頭を下げた。
「そう言う訳ですんで、どうぞごゆっくり…」
途端に嗣之進は立ち上がり、店を飛び出して表通りをぐるりと見回した。
しかし、欣司の姿は既にない。
「ちっ…冗談じゃねえ」
嗣之進は再び席に戻り、椅子に座った。
時々吹く風が、店の中へ花びらを運んで来る。
蕎麦の汁をすすりながら、嗣之進は口の端を上げて小さく微笑んだ。
「やっぱり優しい所があるんじゃねえですかい、見掛けによらず…」
「八重樫先生…」
道場の床に寝転がり、朔也は居眠りをしていた。
「八重樫先生ってば!」
朔也は、自分を呼ぶその声で目が覚めた。
「あ…ああ、何だ、おさきじゃねえか」
昼の練習に来ている菓子舗「中村屋」の娘、おさきだった。
どうやら、彼女が一番乗りらしい。
他の子供達は、まだ来ていない。
「ねえねえ、八重樫先生。あたしとおひろちゃん、朝の練習に移りたいって前に言ったでしょう?」
「え?あ、ああ、そうだったっけか…」
曖昧に返事をしながら、小指で耳の穴をほじる朔也。
おさきは、自分の竹刀を探しながら言った。
「あれね、やっぱりやめる」
「何で?」
朔也は、ちらりとおさきの後ろ姿を見やった。
「お前ら、志保と仲いいから朝に移って、一緒に頑張るんだって言ってたじゃねえか」
そう言いながら、朔也は耳かすをふっと吹き飛ばしている。
竹刀を取ってこちらを振り返ったおさきは、残念そうに表情を曇らせた。
「だって志保ちゃん、此処やめるかもしれないって言うんだもん…」
「何だって?」
朔也の動きが、止まる。
同時に、欣司が戻って来た。
「よ、よう、欣の字…」
寝そべったまま、軽く手を上げる朔也。
「大神先生、こんにちは」
おさきも、頭を下げる。
欣司は黙ったまま、通り過ぎようとした。
「おい、欣の字」
目の前を行く欣司の着物の裾を、朔也は足の指でぐっと掴んだ。
立ち止まった欣司が、朔也を鋭い目付きで見下ろす。
「今の…聞いてたろ?」
朔也の質問に答える事無く、欣司は肩に付いた花びらを払い落とし、道場を突き抜けると奥の階段を上って行ってしまった。
「ふーん…話がしたいなら、部屋まで来いって訳ですか」
尻を掻きながら、朔也は階段の方を見据えて言った。
「ああ、同居生活早三年。俺も、大分欣ちゃんの言いたい事が、理解出来るようになって来たんだよなあ」
ふと見ると、おさきはいつの間にか来ていた他の子供達と共に、竹刀を振り回して遊んでいる。
「こらあー、竹刀で遊ぶなあー、駄目だぞおー…っと」
やる気のない大声で子供達を注意した朔也は、よいこらしょと重い腰を上げた。
「くそっ、鞍とわた坊の野郎は何処まで行きやがったんだ…」
昼の練習をする子供達が、続々と集まって来る。
「お、おいおい…もしかしてこの餓鬼共、全部俺が一人で見なきゃ駄目って奴?」
朔也は、半分泣きそうになりながら天井に向かって叫んだ。
「きっ、欣司様ぁーっ!お願いですから、手伝って下さりませぇーっ!後生で、後生で御座りまするぅーっ!」
改めて、師範代の有り難味を知る朔也であった。
鞍悟と亙は、町へ向かっていた。
船着場で晩造から、廉太郎と頼乃輔は町へ行ったらしいと聞いたからだ。
「なあ、わた坊…」
不安そうな表情で、鞍悟が言う。
「もう、昼の練習が始まる頃ではないか?一旦道場に戻って、夕方先生方が戻られるのを待った方が…」
「やはり、八重樫殿に相談したのは間違いであった!何の解決にも、ならなかったではないか!それに、先生方も何をなさっていたのだ!晩造さんの話では、川向こうをうろついていたと言うし…全く!」
亙は先程の朔也の態度が気に食わなかったらしく、機嫌が悪い。
鞍悟は、慌てて宥める。
「ま、まあ、そう案ずる事はない。世良先生が酔狂な事をなさったとしても、見須奈先生が必ずついて下さっているのだから。それに町の方と言う事は、恐らくさくらへ行かれたに違いないよ。世良先生は、彼処の女将さんを大層気に入っていらしたようだから」
亙も、大きく頷いた。
「成程…そうかもしれん、行ってみよう」
足早に町へと入った鞍悟と亙は、表通りをさくらへ向かって歩いた。
「五十嵐、長谷!」
其処で、何処からともなく二人を呼ぶ声がした。
辺りを見回す、二人。
「此処だ、此処だ!」
そう言って一味庵の暖簾から顔を出したのは、嗣之進だった。
『宰様っ!』
同時に叫んだ二人は、すぐさま嗣之進の許に駆け寄った。
「丁度良かった、もう先生方を捜している暇はないのです!宰様に聞いて頂くのが、一番!さあ宰様、お席はどちらで?」
一味庵に入った亙は、嗣之進を急かして席を案内させると、自分も向かいの椅子に腰掛けた。
鞍悟も、その隣に遠慮がちに座る。
「い、一体…何が、どうしたってんだい?」
嗣之進が呆然としていると、亙は固く握っていた拳を開いて見せた。
「宰様、これが何だかお分かりになりますか?」
「何って…ただの、はした銭じゃねえか」
「違いますっ!」
一瞬声を荒げた亙は、顔を近寄せ小声で言った。
「じ、実は…志保から預かった、大切な銭なのです」
「志保だと?」
眉間に皺を寄せた嗣之進は、ちらりと窓の外を見やった。
それに気付いた鞍悟も、窓の外を見る。
亙は、目の前の嗣之進を見据えたまま言った。
「志保から…殺しの依頼を、受けました」
嗣之進の目が、かっと見開かれる。
「詳しい話は、まだ何も聞いておりません。ただ殺しを依頼したいと言われ、この銭を預かっただけで…」
亙はそう言って、手のひらの銭を再び握り締めた。
腕を組み、ゆっくりと目を閉じる嗣之進。
暫く、沈黙が続く。
「あ、先生方だ…」
その鞍悟の声に、嗣之進ははっと目を開けた。
表通りを、廉太郎と頼乃輔が歩いて行く。
立ち上がった嗣之進は、黙って店を出た。
『つっ、宰様っ!』
鞍悟と亙も店を出ると、慌てて嗣之進に追いついた。
「宰様、お待ち下さい!」
「お代は、どうなさったのですか?」
「いいんだよ、ある心優しい御方の奢りだからな」
二人にそう答えた嗣之進は、前方を歩く廉太郎と頼乃輔に声を掛けた。
「世良さん、見須奈さん!」
振り向いた廉太郎は、笑顔で手を上げた。
「おう、嗣之進」
頼乃輔も振り返る。
「鞍悟に、亙まで…あれ、お前達道場はどうしたのだ?」
「そ、それが…」
口ごもる、鞍悟。
「今日は、八重樫殿の番なのですっ!八重樫殿が、お一人できちんとやっていらっしゃるのではないですかっ?」
亙の怒りに満ちた態度を見て、廉太郎と頼乃輔は思わず顔を見合わせた。
「何だ何だ?やけに、機嫌が悪いなあ?」
面白がってにやける、廉太郎。
「朔也と、何かあったのか?」
困った顔の頼乃輔を見て、嗣之進は言った。
「まあ、こんな道の真ん中で立ち話もなんですから…取り敢えず、川原へ向かって歩きませんかい?」
「ああ、そうだな。今日の晩は、川原で焼魚を食べる予定なのだ。だからお前達の話は、焚火の準備をしがてら聞く事にでもしようか」
頼乃輔の意見に全員が頷き、五人は川原へ向かった。
「なっ、何ぃーっ?敷丸屋の旦那がぁーっ?」
朔也は、目を丸くした。
道場の二階、欣司の部屋を朔也は訪れていた。
今度、料理茶屋「壽美屋」で晩飯を奢ると言う約束で、朔也は欣司に昼の練習を手伝ってもらったのだ。
夕方の練習まではまだ時間があるので、先程の件について二階で話し合っていた所である。
「やくざや浪人風体の野郎共とつるんで、杉ノ森から出て来るのを見た。そいつらと別れた敷丸屋は町へ戻り、明門寺の境内裏で佐取屋と待ち合わせた後、二人で敷丸屋へ入って行きやがった…」
「さっ、佐取屋だとぉーっ?」
欣司の話を聞いた朔也の頭の中は、酷く混乱していた。
「そ、その、佐取屋ってのは…あ、あの、佐取屋、だよなあ?」
「下らん事を、一々訊くな。佐取屋なんて虫唾が走る名の店、この藩じゃ一軒しかねえだろうが…」
「ま、待てよ待てよ。てえ事はだ…」
朔也は、頭の中を整理した。
「普通に、考えると…敷丸屋は、佐取屋が回したやくざもんに杉ノ森で囲まれた。やくざもんは、何やかんやといちゃもんをつけて来たが、敷丸屋はそれに負けず頑なな態度を取り続けた…」
欣司は、黙って聞いている。
「これじゃあ埒が明かねえってんで、敷丸屋を佐取屋が待つ明門寺へ向かわせ、二人は話をつける為に敷丸屋へ一緒に入って行ったと…」
「そう考えるのが、妥当だろう…しかし」
そう言って煙管を銜えた欣司に、朔也は飛びついた。
「しかし、って…ま、まさか!」
「佐取屋と敷丸屋のやり取りは、光英が全部聞いている。知りたきゃ、光英に訊け」
「えーっ!俺、あの坊主、苦手なんだよーっ!一人で、この世の全てを悟ったみたいな顔しやがってよお!」
騒ぐ朔也を見ながら、欣司は黙ったまま静かに煙を吐く。
「欣ちゃん、知ってんだったら教えてくれたっていいだろーっ!」
「酒の本数を、追加しろ」
欣司のその台詞に、朔也は唖然となった。
「ま、まさか、壽美屋の件?そ、それは、金銭的に無理が…」
「だったら、光英の爺に訊け」
煙を吐く欣司を見ながら、朔也はがっくりと肩を落とした。
「志保が、殺しの依頼を?」
頼乃輔は、薪を拾う手を止めた。
「そいつは、穏やかじゃねえな…」
廉太郎も、顎を摩りながら唸っている。
「廉さん、やはりあれは何か関係があるんじゃ…」
「ああ…どうやら、そのようだな」
廉太郎と頼乃輔は、志保の殺しの依頼について、何か心当たりがあるようだった。
「先生方、何か御存知なのですか?」
亙が訊くと、頼乃輔は辺りを見回しながら小声で言った。
「我々が、酒を買いにさくらへ向かおうとこの河川敷を歩いていた時、向こう岸の杉ノ森にやくざや浪人風体の男達が集まっていたのだ」
「其処に、誰がいたと思う?」
廉太郎の質問に首を傾げる嗣之進、鞍悟、亙。
「それがな…敷丸屋の旦那だったんだよ」
その答えに、三人は目を丸くした。
「志保のお父上が、そのような輩と…そ、それで、一体、何をなさっていたのですか?」
鞍悟が訊くと、頼乃輔は首を横に振った。
「それがな、此処からでは遠過ぎて良く見えなかったのだ。我々が向こう岸へ渡った時には、既にいなくなっていた…」
それを聞いた三人は、残念そうに顔を見合わせた。
「では先生方は、志保の依頼とその事とは、何か関係があるのではないかと睨んでいる訳ですね?」
亙の質問に、廉太郎と頼乃輔は目を合わせながら頷いた。
「やはり…それで先生方は、これからどうなさるおつもりなのですか?」
更に亙が訊くと、頼乃輔が答えた。
「実は先程、様子を見に敷丸屋へ行ってみたのだ」
「まあ、普段呉服屋とは縁もないような我々が、突然行ったら怪しまれると思い、取り敢えずは志保の剣の腕が上達した旨を伝えに来た等と言いつつ、女将にさり気なく話しながらどう探ろうかと考えていたら…何と、奥から佐取屋が出て来やがってな」
『さっ、佐取屋ぁーっ?』
廉太郎の話に、三人は声を揃えて驚いた。
嗣之進が、唖然としながら訊く。
「さ、佐取屋って…あの隣町の?」
頷く廉太郎。
「ああ、隣町飛沫町の呉服問屋だ。あくどい商売してるって話だが、その佐取屋が何で敷丸屋に…」
頼乃輔も、腕を組む。
「飛沫町の目明し銀介から聞いた話じゃあ、過去に何軒もの呉服屋が、佐取屋に吸収されたって言うだろう?だから、恐らく敷丸屋も…」
「標的にされた、と言う訳ですか。では、志保のお父上は杉ノ森で佐取屋の手の者に囲まれて…まさか!志保はそれを危惧して、佐取屋を殺してくれなんて言うのではっ!」
「それは、ねえだろ」
亙の意見を聞いて、嗣之進は言った。
「大体、志保が自分とこの商売のそんな小汚え裏の話を知っているとは、到底思えねえ。それにな、こう言う事は志保みたいな子供が一人出しゃばってどうこうしようったって、出来るような問題じゃねえんだよ」
皆が黙り込んだその時、土手を朔也が駆けて行くのが見えた。
「あれ…お、おい、朔也!」
廉太郎が、慌てて呼び止める。
気が付いた朔也は、こちらへ駆け下りて来た。
「よう、皆さんお揃いで…って、おい!鞍、わた坊っ!」
鞍悟と亙の姿を見つけた朔也は、眉を吊り上げて怒鳴った。
「てめえらなあっ!あれから出てったっきり、戻って来もしねえで…一体、どう言うつもりだっ!」
「ま、まあ、落ち着かんか、朔也。ほら、鞍悟と亙も練習に出なかったのは事実なのだ、謝りなさい」
頼乃輔にそう言われ、顔を見合わせた鞍悟と亙は渋々頭を下げた。
『申し訳御座いませんでした…』
「分かれば、宜しい!」
偉そうに踏ん反り返った朔也に、嗣之進が訊く。
「ところで八重樫、お前こそどうした?夕練、もうすぐだろ」
「ああ、欣ちゃんに代わってもらったから」
『えぇーっっっ?』
皆が、一斉に叫ぶ。
「まっ、待て待て!本当に、あの欣司がお前と代わってくれたのか?」
訊き返す、頼乃輔。
「珍しい事も、あるもんだなあ…」
廉太郎は、目を丸くして驚いている。
「で、でも…まさか、無償じゃあねえんだろ?」
そう訊いた嗣之進に、朔也は小さく呟いた。
「壽美屋で、晩飯奢らされる羽目になった…」
顔を見合わせる、五人。
「そ、そいつは、高くついたなあ…」
廉太郎が苦笑いすると、亙は突然意気込んで言った。
「大神さんも、お一人ではさぞかし大変でしょう!私と鞍ちゃんで昼練に出なかった分、夕練で頑張らせて頂きます!なあ、鞍ちゃん?」
「えっ?あ、は、はい…」
勢いにつられ、鞍悟も何となく頷く。
「そう言う訳ですので、これにて御免っ!」
頭を下げた亙は、鞍悟を引っ張って土手を登った…そして。
「あ…先程の件、何か分かった事が御座いましたら、後程お教え下さい!」
そう叫び、道場の方へ駆けて行ってしまった。
そんな二人を見ながら、朔也は憤慨する。
「ったく…ぬわぁーにが、大神さんもお一人ではさぞかし大変でしょう、だっ!一人残された俺の事も、ちっとは考えろってのっ!」
「まあ、そう怒るな。亙も一本気な男だから、志保が心配で仕方がないのだろう…しかし朔也、お前これから何処へ行くつもりだったのだ?」
頼乃輔が訊くと、朔也は顔を近寄せて言った。
「皆さん、志保の件に関して御存知のようなんで言いますけどねえ、欣ちゃんの話だと敷丸屋に、隣町の佐取屋が付き纏っているそうなんですよお…」
「今、その話を俺達もしていた所だ」
と、廉太郎。
「なーんだ、そうだったの。だったら、話は早いんだけど…どうやらこの話、裏がありそうなんだよなあ」
「裏?」
朔也の話を聞いて、嗣之進が眉を顰める。
「普通、佐取屋の悪事を知っている奴なら誰でも、敷丸屋は脅されてんじゃねえかって思うだろ?」
「ち、違うのか?」
頼乃輔が訊くと、朔也は肩を竦めた。
「その真実を確かめに、これから明門寺へ行くのよ。光英の野郎が、敷丸屋と佐取屋のやり取りを聞いてたらしいからさ…」
「あの爺さんも、抜け目ないよなあ…」
廉太郎は、感心している。
「どうだ、一緒に来るか?」
朔也が訊くと、頼乃輔は薪を見せて言った。
「今晩は此処でこの満開の櫻を見ながら、焼魚を食う予定だ。焚火の準備もあるから、俺は遠慮する」
「じゃあ、俺も…後で、必ず報告してくれ」
そう言って、廉太郎も断った。
「分かった…んで、嗣ちゃんは?」
朔也に訊かれ、嗣之進は言った。
「じゃあ、俺がついて行こう。世良さん、見須奈さん、あとお願いします」
廉太郎と頼乃輔が、黙って頷く。
嗣之進と朔也は、明門寺へ向かった。
世見道場では、夕方の練習が始まっていた。
鞍悟と亙が中心となり、門下生を一人一人見て回る。
朔也と代わった師範の欣司は、その様子を黙って見つめていた。
「御免下さい」
その時、一人の客人が道場を訪れた。
「ああ、小川先生」
「お久しぶりで御座います」
鞍悟と亙が、出迎える。
客人は、この近辺の子供達に読み書きを教えている、手習師匠の小川鏡院であった。
鏡院は何度もこの道場を訪れているので、師範達とも顔馴染みである。
すらりとした色白の美形なので、子供達と言うより母親達から人気があった。
「あの…仙太は、おりますかな?」
「仙太ですね?少々、お待ち下さい」
亙は、仙太を呼んだ。
気が付いた仙太が、鏡院の許へ走って来る。
「あれ、小川先生…一体、どうしたんだい?」
鏡院は、手に持っていた習字の半紙を何枚か差し出した。
「ほら、これを置き忘れて行っただろう?折角、三重丸をあげたと言うのに…」
「あっ、いっけねえ!」
はっとした仙太は、半紙を受け取って頭を掻いた。
「これでは、おっかさんに褒めてもらえませんよ」
「あーあ…おいら、すっかり忘れていたよ。小川先生の所から帰ってすぐ、利松と遊びに行っちまったから…わざわざ届けて下すって、有り難う御座いました!」
頭を下げた仙太は、再び練習に戻った。
鏡院は、側にいた鞍悟に言った。
「師範に、話があるのですが…宜しいかな?」
「あ、はい。どうぞ」
鞍悟が、快く頷く。
中に入った鏡院は、欣司の許へ歩いて行った。
「大神殿」
欣司が、ちらりとこちらを見る。
鏡院は、軽く頭を下げた。
「その後、様子はどうですかな?」
「調べている、最中だ…」
欣司が、無表情で答える。
実は、鏡院も志保の異変に気付いた内の一人であった。
書物を読ませても、文字を書かせても、常に上の空の志保が心配になり、同じように毎日志保と顔を合わせているこの道場の師範に、相談に来たのだった。
その日に師範を務めていたのが欣司だった為、鏡院は欣司に志保の様子を探るよう頼んでいた。
「ところで…今日の師範は、八重樫殿の筈では?」
「訳あって、俺が代わった…」
鏡院の質問に、短く答える欣司。
鏡院は、苦笑いする。
「ま、まあ、何か変わった事がありましたらお知らせ下さい。では…」
頭を下げ、道場を出る鏡院。
欣司は、志保の事を考えていた。
「志保…お前は一体、誰をこの世から抹殺しようとしている…」
欣司の心は、落ち着かなかった。
廉太郎と頼乃輔は、ようやく焚火の用意を終えた。
「よーし!魚も串に刺したし、薪も用意した。櫻も綺麗だし…後は、練習が終わるのを待つばかりだな」
そう言って伸びをしながら立ち上がった廉太郎は、ふと土手の方を見た。
「お、おい、頼さん…」
呼ばれた頼乃輔も、顔を上げて土手を見る。
「何だ…あ、敷丸屋の番頭…」
土手を町へ向かって歩いていたのは敷丸屋の番頭、清太郎だった。
「よう、番頭さん!」
土手を駆け登った廉太郎は、清太郎に声を掛けた。
「これはこれは、世見道場の世良先生。いつも、お嬢さんが御世話になっております」
清太郎は、深々と頭を下げた。
「いやいや…それより、どうしたのだ?まだ、店仕舞いの時間ではないだろう」
廉太郎が訊くと、清太郎は言いにくそうに微笑んだ。
「はあ、ちょっと永翠先生の所へ…」
「え、永翠って…何だ、何処か悪い所でもあるのか?」
廉太郎の質問に、清太郎は笑って見せるだけだった。
「そ、それでは、急ぎますので、これで…」
頭を下げた清太郎は、足早に行ってしまった。
「何だって?」
土手を下りて来た廉太郎に、頼乃輔が訊く。
「永翠先生の所に、行っていたらしい」
「永翠先生の所?何処か、悪いのか?」
「さあ…何も言わなかった」
頼乃輔にそう答えた廉太郎は、清太郎の後ろ姿をいつまでも見つめ続けた。
「ま、茶でも…」
明門寺の和尚光英は、嗣之進と朔也に茶を出した。
湯飲みの中に、櫻の花びらが一枚浮かんでいる。
「おい、糞坊主!正直に話さねえと、この場で容赦なく叩っ斬るぞ!」
「よさねえか、八重樫…仏の前だぜ?」
朔也を宥める、嗣之進。
光英は、微笑んで言った。
「八重樫殿はいつもお元気なご様子、大変宜しゅう御座います」
「んなこたあ、訊いてねえんだよ!」
「だから、落ち着けって。ったく、おめえはどうしてこういつもいつも、和尚と気が合わねえんでえ…」
嗣之進は、呆れている。
朔也は、息巻いて言った。
「とにかく、さっさと教えやがれ!」
「はいはい…」
茶を一口飲んだ光英は、静かに話し始めた。
「確かに敷丸屋は、佐取屋に狙われておるようですな…」
「ほーら、見ろ!やっぱり、思った通りじゃねえか!ったく、欣の野郎!しかしだの案山子だのって、勿体ぶった言い方しやがっ…」
「しかし」
光英がそう言ったのを聞いて、得意顔だった朔也は目を丸くした。
「何でえ、和尚…続きがあるのか?」
嗣之進が訊く。
光英は、頷いて言った。
「敷丸屋のご主人、徳十さんは…どうやら、佐取屋の回し者だったようですよ」
『えぇーっっっ?』
嗣之進と朔也は、それは驚いた。
「どっ、どう言う事だよ!」
朔也が訊くと、光英は静かに茶をすすった。
「つまり…徳十さんは、元から敷丸屋を吸収するつもりで身元を偽り、婿に入ったと言う事です」
嗣之進と朔也は、黙って顔を見合わせる。
「私が知っているのは、此処までで御座います。続きをお知りになりたいのであれば、御自分達でお調べになられると良い…ああ、そうじゃ。折角寄って下さったのですから、座禅でも組んで行かれますかな?」
光英の厚意を、二人は思い切り首を横に振って断った。
練習が終わった後、七人は夜桜を見ながら川原で魚を焼いて食べた。
朔也が、光英から聞いた事を皆に話す。
「しっ、敷丸屋の旦那が、佐取屋の回し者だとぉ?げっ、げほっ…」
廉太郎は、思わず咳き込んだ。
「おい、大丈夫か?」
頼乃輔が、背中を摩る。
「徳十は、はなっから敷丸屋を吸収する為の、佐取屋の駒だったんだとよ…あの糞坊主、そう言ってたぞ」
そう言って、朔也は魚にかぶりついた。
「ですがね、徳十が敷丸屋に丁稚奉公に上がったのは、もう三十年近くも前の話なんですよ。其処を考えると、どうも納得が行かねえんだ…」
その嗣之進の意見に、頼乃輔も同意する。
「確かに…何故、三十年も前から敷丸屋を狙っていたのか。そして、当時はまだ子供だった徳十を、どうして佐取屋が駒として使う事が出来たのか」
「調べてみる必要があるな…」
そう呟いた欣司は、酒をぐいと飲み干した。
廉太郎も、酒を一口飲んで言う。
「そうだな…その為にはやはり、志保の依頼内容を詳しく聞いてみなければならん」
「れ、廉ちゃん!」
朔也は、慌てて止める。
「それだけは…っ」
「八重樫殿は、何故そのように批判的なのですかっ!」
亙は、突然怒鳴った。
「困っている志保を、救ってやろうと言う気持ちは無いのですかっ!」
「だからこそなのだよ、亙」
興奮する亙を宥める、頼乃輔。
「志保を思えばこそ、朔也は否定的にもなっているのだ」
「仰る意味が、分かりませぬっ!」
息巻く亙に、頼乃輔は静かな口調で言った。
「良く、考えてみろ。その筋の者しか知らん殺しの依頼等と言う行為を、何故志保ような子供が知っていた?それを知っている時点で、既に志保は危険な事に足を一歩踏み入れていると言っても、過言ではない」
「で、ですが…っ」
「此処で更に我々が依頼を受けたら、どうなる?間接的とは言え、志保は九つにして人殺しの肩書きを背負う事になるのだぞ」
亙は、はっとした。
「長谷…お前の気持ちは、良く分かる。一本気な所も、決して悪いとは言わねえ。だがな、その向こう見ずな考えが、とんでもない結果を招く事になるかもしれねえんだ。五十嵐のようにのんびり過ぎるのもどうかと思うが、もう少し冷静になって物事を考える事を覚えろ」
嗣之進にもそう言われ、亙は返す言葉がなかった。
「それになあ、亙…我々五人は皆、三十年近くもの間この世を生きて来たんだ。こんな奴でも、お前達よりは遙かに人生経験が豊富なんだから、あまり莫迦にしていると痛い目を見るぞ?」
廉太郎はそう言って、朔也を見ながらにやけた。
「うっ、煩えなあ!」
朔也は口を尖らせ、不貞腐れている。
亙は砂利の上に正座し、両手を付いて頭を下げた。
「やっ、八重樫殿っ!誠に、申し訳御座いませんでしたっ!数々の御無礼、どうぞお許し下さいませっ!」
土下座する亙に、朔也は慌てて言う。
「よ、よせよ、わた坊…この俺に頭下げるなんざ、お前らしくねえぞ」
「さてと、無事仲直りした所で…」
廉太郎は、酒を飲み干した。
「明日の師範は、俺だったな。朝練が終わったら、鞍悟、亙と三人で志保から話だけでも聞いてみよう。依頼を受けるか否は、二の次にしてな。頼さん、欣司、嗣之進、朔也は、敷丸屋と佐取屋の繋がりについて、もう少し詳しく調べてみてくれ」
皆は、同時に頷いた。
翌日、欣司と嗣之進は町医者北条永翠の許を訪れた。
昨日、何故敷丸屋の番頭清太郎が、永翠の所へ行ったのかを調べる為だ。
永翠は、部屋で医学書を読んでいた。
「先生、一寸いいかい」
嗣之進は、上がり框に腰掛けた。
「何だ、健康そうな道場の師範が二人して…まさか、具合が悪い等と申すのではあるまいな?」
書物から顔を上げた永翠は、静かにそう言った。
「北条…貴様は大人しく、我々の質問に答えていればそれでいい」
「そう言う訳には、行きますまい」
欣司にそう言い返した永翠は、開いていた書物をぱたんと閉じた。
「やはり、客人には茶の一つも出してやらねばな…とは言っても、この家には薬湯くらいしかないが」
「余計なもんはいらねえから、さっさと本題に入らせてもらえませんかねえ…まあ、取り敢えず上がりますよ。さあ、大神さんも」
そう言って草履を脱いだ嗣之進は、畳の上に座った。
戸口に立っていた欣司も、その隣に座る。
「やれやれ…お前達には、敵わんなあ。まあ、世良と見須奈が何も訊かずに治療をしてやってくれと、訳ありの大神を連れて来た時からの付き合いだ。大人しく、そちらの御用件を伺うと致しますか」
永翠はそう言って、ちらりと欣司を見た。
欣司は、そっぽを向いている。
八年前のあの日、胸を斬られて倒れていた欣司を、廉太郎と頼乃輔が運んだのは、この永翠の所だった。
年齢は廉太郎の一つ上でしかないが、医者としての腕は確かなので、廉太郎達からはかなりの信頼を得ている。
「ではまず、敷丸屋の番頭の事から…」
「清太郎さんの事か…」
嗣之進の質問に、永翠は勿体ぶって答えた。
「まあ、本来なら余所者に患者の個人的な内情を漏らすのは、御法度なのだが…」
「さっさと、吐け…」
苛立つ欣司に、嗣之進は宥めるように言った。
「大神さん、そう急かさずに…何だか、八重樫に似て来ましたねえ」
すかさず嗣之進を睨む、欣司。
嗣之進は、黙って肩を竦めた。
「清太郎さんは胃痛で、一月程前から通って来ておるのだが…あれは実際には、半年も前から痛んでいるような様子だったな」
「胃痛か…原因は?」
欣司に訊かれ、永翠は答えた。
「恐らく、精神的なものかと…」
「精神的?」
腕を組む、嗣之進。
「てえ事は、清太郎は胃を痛める程の悩みか何かを、抱えてたって事ですかい?」
頷いた永翠は、思い出すように言う。
「そう言や…店の事で色々と、とか何とかって言っていたな」
「やはり、店絡みか…」
欣司が呟く。
其処で、永翠がぽんと手を叩いた。
「ああ、そうだ。もっと詳しい事が知りたければ、夏さんの所へ行ってみたらいい」
「夏貴の所へ?どうして、また…」
嗣之進が、驚いた顔をする。
夏貴が営む薬種問屋「富貴屋」は永翠御用達の薬種屋で、永翠が処方した薬を患者に届けてくれている。
「つい先日も夏さんに、薬を清太郎さんの所へ届けるよう頼んだのだ。ひょっとしたら、店の中の様子について色々と話が聞けるかもしれない」
それを聞いた欣司と嗣之進は、顔を見合わせて頷いた。
頼乃輔と朔也は、壽美屋に来ていた。
「ええと…はいはい、空いておりますよ。では今月十五日の夜、二名様の御予約で承りました、と」
女将のお壽美が、帳面に記入する。
朔也は、項垂れたように椅子に座った。
「くっ…懐具合が、妙に淋しい」
「仕方あるまい、男と男の約束だ。特に相手が欣司となると、破った時に後で何をされるか分からんからな」
人事である頼乃輔はそう言って笑うと、朔也の肩を叩いて向かいに腰掛けた。
使用人のお三音が、茶を運んで来る。
「ところでさあ…お二人とも、予約する為だけに来たんじゃないんでしょう?」
「おっ…流石はお三音、勘が鋭いなあ」
そう言って、頼乃輔はお茶を一口飲んだ。
「どうせ、旦那様に御用があるに決まっているんですよ。ねえ、女将さん?」
脇で、空いている机を拭いていた使用人のお由奈がそう言うと、お壽美は頷いた。
「ええ、お由奈ちゃんの言う通り。そうなんでしょう、旦那方?でもお生憎様、うちの鉄砲玉は何処吹く風…昨日の晩だって、結局帰って来やしなかったんですからね」
「こんな調子で女将さん、朝からご機嫌斜めなんです…」
と、困った顔をしながら、使用人のお璃乃が定食を運んで来た。
「お璃乃ちゃん…悪いけどそのお膳、奥の座敷に運んでくんない?行こ、頼ちゃん」
朔也の言う事に頷いた頼乃輔は、立ち上がった。
「ではお壽美、後で風佑と飛朗を寄越してくれ」
お壽美が黙って頷くと、お三音が嬉しそうに言った。
「やっぱり、何かあったんだ…」
そして、頼乃輔に耳打ちする。
「敷丸屋…違う?」
目を丸くする、頼乃輔。
お三音は、悪戯っぽく微笑んだ。
「図星でしょ、頼さん。あたし、おもよちゃん達に頼んで既に色々探ってるんだ」
「よせって、お三音。いつも、言っているだろう?」
困った顔をする、頼乃輔。
朔也も、同意する。
「そうだぞ。おもよにも、きつく言っとけ」
「いいんですよ」
お壽美は、首を横に振った。
「放っといてやって下さいな。この子もおもよちゃんも、止めたって無駄。好きでやってるから、やめらんないの」
「し、しかし…」
戸惑う頼乃輔に、お壽美は言う。
「特にこの子なんか、うちの人に憧れてこの水生の国に来たくらいなんだから…当時は呆れて開いた口も塞がらなかったけど、今じゃ黙認してるんですよ。まあ、多少なりとも見須奈の旦那方のお役には立ってるようだしねえ」
「もう、女将さんったら…多少、はないんじゃない?」
口を尖らせる、お三音。
「だ、だが、危険な役回りをさせるのは、男の風佑と飛朗だけで十分だ。女のお三音やおもよにまで、迷惑を掛ける訳には…」
「頼さんが優しいのは、すっごく嬉しいんだけど…でも女だからこそ、探り出せる真実もあるでしょう?それで、何度助けられたっけ?」
頼乃輔の心配を余所に、お三音は得意満面である。
溜息をついた頼乃輔は、頭を下げた。
「こ、今後とも、宜しくお願い致します…」
「合点承知!」
ぽんと胸を叩いたお三音は、お璃乃と共に座敷の準備をしに行った。
呆れた顔で、朔也は言う。
「ったく、此処の女共は気が強くていけねえや。特に、女将を筆頭とし…」
「何か言ったかい、朔さん?」
お壽美が、ぎろりと睨む。
「い、いえいえ、別にこっちの話…ああ、鬼一親分が家に寄りつかねえのも、分かる気がするわ」
そう呟いた朔也は、そそくさと奥の廊下を歩いて行った。
側で聞いていたお由奈が、くすくすと笑う。
頼乃輔も肩を竦めながら、朔也について行った。
「あ、二人ともこっちこっち!」
廊下で待っていたお三音はそう言って、頼乃輔と朔也を座敷に招き入れた。
「じゃあ私、風佑さん達を呼んで来ます」
お璃乃は頭を下げて、部屋を出て行った。
「今日、他に客は?」
頼乃輔が訊くと、お三音は酌をしながら言った。
「お座敷は無し。それより二人とも、あたしの集めた情報知りたくない?」
「その前に…何で、敷丸屋の事だって分かった?」
頼乃輔の質問に、お三音は静かに答えた。
「彼処の、お嬢さんの…確か、志保ちゃん?あの子がね、霧谷神社の境内で泣いていたんですよ」
「志保が?」
朔也が、箸を止める。
お三音は、頷いて言った。
「声掛けてみたら志保ちゃん、おとっつぁんにお前はいらない子だとか、太一がいればそれでいいんだとか言われたって。そりゃあね、お店の事考えたら跡取りの太一坊がいてくれれば、それでいいんだろうけど…でも、あんまりな物言いでしょう?」
頼乃輔と朔也が、顔を見合わせる。
「だからね、あたし可哀想になって月田屋でお汁粉奢ってあげたの。そうしたらね、志保ちゃん食べながらこう言ってた。お祖父ちゃんが死んでから、おとっつぁんは人が変わっちゃったって」
お三音の話を聞いて、再び頼乃輔と朔也が顔を見合わせた時、廊下で声がした。
「風佑、飛朗、参りました」
「入ってくれ」
頼乃輔がそう言うと障子戸が開き、使用人の風佑と飛朗が入って来た。
「二人とも、お三音の話は聞いたのか?」
朔也が訊くと、風佑は静かに頷いた。
「はい。敷丸屋について調べてみようと言い出しましたのも、実はお三音でして…」
驚く頼乃輔。
「じゃ、じゃあ、お前達二人も、既に調べをつけているのか?」
飛朗は、思わず苦笑いした。
「いやあ、あっしらも志保ちゃんに同情しちまいましてね、それで少し調べてみたんですが…物凄い事実が、分かりましてねえ」
「な、何だ?」
朔也が、身を乗り出す。
飛朗は、顔を寄せた。
「実は…志保ちゃんは、徳十の子じゃねえんですよ」
「何だと?」
頼乃輔が、眉を顰める。
「ど、どう言う事だ?」
朔也が訊くと、お三音が答えた。
「色々訊いて回って、志保ちゃんを産んだ時の産婆さんを突き止めたの。でも、本人は五年前に亡くなっていて。だからおもよちゃんと千郎太さんに頼んで、夜中に忍び込んでもらったんだ。帳面か何かに、記録が残ってるかもしれないでしょ。そうしたら…」
「残っていたんだな?」
頼乃輔の言う事に、頷くお三音。
「女将の久美が、産んだ直後に産婆にだけ漏らしたらしいんです。この子は、徳十の子では無いと…」
そう言って、風佑は記録の写しを出して見せた。
「だったら、志保は誰の子なんだ?」
朔也が訊くと、飛朗は首を傾げた。
「さあ…それは記録にもな無い所を見るに、恐らく女将も言わなかったんでしょうねえ。こっちでも、もう少し調べてみますよ」
頼乃輔は、考え込んだ。
「その事…自分が徳十の子では無いと言う事を、志保は知っているのか?」
「多分、知らないと思う」
お三音は、思い出しながら言う。
「確かにきつい事言われたり、昔から太一坊ばかり可愛がられて、志保ちゃんは蔑ろにされていた気味があったらしいの。でも、太一は跡取りだけど自分はそうじゃないから、おとっつぁんが自分に辛く当たるのもしょうがないんだよねって言って…」
皆が、黙り込む。
「まさか実の子じゃないからだとは、露とも思ってやしないよ」
「なあ、頼ちゃん…」
朔也が、静かに口を開く。
「この事と依頼は、何か関係があると思うか?」
頼乃輔は、黙ったまま考え込んでいる。
「依頼って…何の事で?」
飛朗の質問に、朔也が答えた。
「実は昨日の朝、志保から殺しを依頼されたんだ…」
『えぇーっ?』
お三音、風佑、飛朗が同時に声を上げる。
「って事はよ、もしかして憎いおとっつぁんを殺して欲しい…とか?」
「志保は、そんな子じゃねえよ」
朔也は、お三音の言う事に反論した。
「とにかく、危ない事には巻き込みたくねえ。絶対に、反対だ」
「見掛けによらず門下生思いなんだよねえ、朔さんは…」
お三音が呟く。
頼乃輔は、其処で首を傾げた。
「朔也の意見には俺も賛成なんだが、しかし…どうして志保は、俺達の裏の顔を知っていたのか。これが、謎なんだ」
「では、其処の所もこちらでお調べ致します」
「ああ、頼む」
風佑の申し出に、頼乃輔は頷いた。
一方、欣司と嗣之進も富貴屋の夏貴から、重大な事実を聞かされていた。
「そ、そいつは…本当かい?」
嗣之進が、目を丸くして驚く。
夏貴は、頷いて言った。
「ええ…佐取屋の口から、直接出た言葉ですから」
「敷丸屋徳十が、佐取屋の実の息子だったとはな…」
欣司はそう呟くと、眉間に皺を寄せて静かに目を閉じた。
話によると夏貴は先日、永翠に頼まれて調合した薬を番頭の清太郎に届ける為、敷丸屋を訪れた。
女将久美の許しを得た清太郎は、夏貴を奥の座敷に案内した。
服用方法等の説明が終わった後、座敷を出た清太郎と夏貴は、廊下で徳十と佐取屋の二人に出くわす。
互いに頭を下げた後、徳十はそのまま佐取屋を自分の部屋へ招き入れた。
夏貴は咄嗟に厠を借りたいと言い出し、用が済みましたら私は勝手に帰りますので…と、先に清太郎を表の方へ帰した。
其処で立ち聞きしたのが、その事実だったのだ。
佐取屋は『徳十、まさかお前がこの佐取屋徳兵衛の実の子だとは、誰も思ってはいまい』…そう言ったのである。
「それで、謎が解けた。まだ子供だった徳十を、佐取屋が使う事が出来たのは、徳十がてめえの息子だったからってえ訳だな」
嗣之進が納得していると、欣司が目を開けた。
「しかし、何故三十年も前から敷丸屋に送り込む必要があった?」
「それは、恐らく…何か恨みを買うような事を、敷丸屋が佐取屋にしたのでしょうねえ…三十年前に」
「敷丸屋が?」
夏貴の意見に、嗣之進は疑問を抱いた。
「そりゃあおめえ、若いから知らねえんだろうが…敷丸屋は老舗中の老舗で、昔っから評判もいい。逆に佐取屋は、他人のお店を奪ってのし上がって来た、悪名高い店だぜ?」
「ええ、存じております」
「だったら佐取屋が恨みを買う事はあっても、敷丸屋が恨みを買うような事をするってなあ、どう考えたって有り得ねえ話だって事くらい、分かるだろう?」
其処で夏貴は、思い出したように言った。
「そう言えば、三十年前…献上反物と言うのがあったそうですね、御殿様への。この青空藩中の呉服屋の中から敷丸屋と佐取屋が勝ち残り、最終的に殿がお選びになったのは敷丸屋だったと言うではありませんか」
欣司と嗣之進は、黙って聞いている。
「それ以来、敷丸屋は流石老舗と益々大繁盛。片や佐取屋は、他人のお店ぶん取って外見ばかりを大きくしたって、中身が殿に認められないようじゃあ意味がないと、益々莫迦にされる始末。佐取屋が敷丸屋を恨むには、十分の出来事だったと思いますが…」
夏貴の話を聞いて、嗣之進は唖然とした。
「お、おめえ…そんな昔の話、良く知ってやがるなあ」
「薬届けに年寄りの家を回っていると、皆さん昔の話を良く聞かせて下さるのですよ」
そう言って、夏貴は微笑んだ。
「だが、敷丸屋が恨まれる筋合いの話じゃねえだろ、それは」
と、嗣之進は言ったが、欣司は首を横に振る。
「確かにそうかも知れんが、奴らに正しい道理を求めようったって、そうは問屋が卸さねえ。敷丸屋を潰すと決めたら、理由がどうであろうと構いやしねえって事だ…」
皆が黙り込んだ時、店に客が入って来た。
「済みません。お薬、頂きたいのですが…」
「少々、お待ちを…」
表の客にそう返事をした夏貴は、二人に小声で言った。
「申し訳ありませんが、お客様がいらしたようですので、これで…」
頷いた嗣之進は、立ち上がった。
「おう、邪魔したな…行きましょう、大神さん」
欣司も黙って立ち上がり、二人は富貴屋を出た。
「最初っから、話を繋げてみると…」
通りを歩きながら、嗣之進が言う。
「三十年前、献上反物に負けた腹いせに敷丸屋を潰そうと考えた佐取屋は、息子の徳十を送り込んだ。成長した徳十は、敷丸屋の一人娘久美と夫婦になり、店の主人となる。大旦那だった志保の爺さんが死んだのは、確か昨年でしたかねえ?」
頷く欣司。
「敷丸屋は、完全に徳十の支配下となった。其処へ悪の根源佐取屋徳兵衛が、ようやく顔を出して来たってえ訳だが」
「疑問点がある…」
欣司は、眉を顰めた。
「佐取屋は、どう言う連中から成っているのか…主人の徳兵衛ばかりで、他の人間の影が全く見えて来ねえ」
「まあ、確かに…」
「それからこの三十年もの間、何故徳十が佐取屋の息子だと言う事が、ばれなかったのか。敷丸屋へ奉公に上がる前、餓鬼の頃の徳十は何処に住んでいたんだ。親子なら、一緒に佐取屋に住んでいた筈だろう」
黙り込む、嗣之進。
「だがその事実があるなら、徳十が佐取屋の息子だと言う事は、既に知られていなければならん」
欣司の話を聞きながら、嗣之進は唸った。
「これじゃあ、いつまで経っても志保の依頼の謎には辿り着けねえなあ…まあ大神さんの出した謎については、銀介でも取っ捕まえて訊いてみるしかねえか」
欣司も、黙って頷いた。
その日の夜、七人は道場の奥の部屋に集まっていた。
今日一日で仕入れた情報を、互いに伝える。
「で、どうだった?志保の奴、何つってた?」
朔也が訊くと、廉太郎は沈んだ声で言った。
「それが…志保は今日、稽古を休んだのだ」
『えぇーっ?』
皆が、声を上げる。
鞍悟は、話を続けた。
「勿論、様子を見に私がすぐさま志保の家へ参りました。女将さんに伺いましたら、志保はお父上に叱られて出て行ってしまったらしく、番頭の清太郎さんが捜しに出られた所だとかで…」
「お三音がこの間出くわした状況と、全く同じだな…恐らく、また霧谷神社ででも泣いていたのだろう」
そう言って、俯く頼乃輔。
「私も、志保が番頭さんと二人で連れ立って歩いている所を、良く見掛けます…」
鞍悟も、静かに言う。
「父親は冷たく、母親は仕事で忙しい…恐らく志保の心の拠り所は、あの優しい番頭さんしかいないのでしょうね」
「なるほど…確かに、そのようだな。しかし…まだ残っている謎が解けない事には、気になって夜も眠れねえや」
嗣之進の言う事に、廉太郎も同意する。
「徳十の過去と佐取屋の内情、それに徳十が佐取屋の息子だと言う事を、果たして敷丸屋の人間は知っているのかどうか。あと…志保の本当の父親は、一体誰なのかと言うのも気になるな」
「明日は、俺が道場を見る番だ。明日こそは、志保から話を訊いてみる」
頼乃輔がそう言うと、亙も意気込んで立ち上がった。
「志保は色々と辛い目に遭っていたと言うのに、気が付けなかった自分が情けない!私は、必ず志保を救い出して見せます!先生方、私に出来る事が御座いましたら、何でもお申し付け下さい!」
「燃えてんなあ、わた坊」
にやける、朔也。
「門下生の事を心配し、助けになってやろうと思う心は大切だ。なあ、亙?」
「はいっ!」
廉太郎の言う事に、元気良く返事をする亙。
熱い亙を見て、皆は同時に吹き出した。
翌日、志保は道場にやって来た。
練習が終わり門下生が徐々に帰って行く中、頼乃輔は志保を呼び止めた。
「志保…一寸、いいか?」
頷いた志保を連れ、頼乃輔は奥の部屋へ入った。
中では、鞍悟と亙が既に待機している。
志保を座らせた頼乃輔は、自分も腰を下ろした。
「お前は、我々に殺しを依頼したそうだが…取り敢えず、話だけは聞いてやろう。但し、勘違いするなよ。依頼を引き受けるか否かは、また別の話だからな」
「は、はい…」
頷いた志保は、か細い声で言った。
「殺して欲しい人は…私です」
頼乃輔達は、息が止まるような衝撃を覚えた。
「私を、殺して欲しいんです。だから、道場も…おさきちゃんやおひろちゃんには、やめるつもりなんだって言いました」
呆然とする、亙。
「し、志保、お前一体、何を言って…」
「その理由を、申してみよ」
頼乃輔が、冷静に訊く。
志保は、俯いた。
「私は、いらない子なんです」
「いらない…子?」
鞍悟が、訊き返す。
「おとっつぁんはいつも、太一がいればいいって言う…だから私、死にたいんです」
「お前が死んだら、お母上が悲しむではないか!」
亙がそう言うと、志保は首を横に振った。
「おっかさんは、私のせいでいつもおとっつぁんからぶたれてるんです。お前が志保を産んだから、いけないんだって…私が死ねば、おっかさんもぶたれずに済む。きっと、喜んでくれる筈です」
「つまらん事を、言うな!」
頼乃輔は、怒鳴った。
「自分の子供が死んで喜ぶ親が、何処にいる!」
「でもっ!」
志保は、涙混じりに叫んだ。
「おっかさんは、いつもおとっつぁんの機嫌を取ってばかりで…私には、見向きもしてくれないもん!」
皆が、黙り込む。
鞍悟は、呟くように言った。
「恐らく…お母上も、ご自分の身を守るのが精一杯で、志保を庇ってやる余裕が無いのでしょうね…」
「おとっつぁんも、昔はこんなじゃなかったんです。去年、お祖父ちゃんが死んでから急に、あんな風に、変わっ、ちゃっ、て…」
泣きじゃくる志保の頭を撫でながら、頼乃輔は優しく言った。
「なあ、志保…清太郎は、どうだ?」
顔を上げる、志保。
「清太郎は、殊の外お前を大事にしているそうではないか。お前が辛い時、泣きたい時、いつも側にいてくれたのは清太郎ではなかったか?」
頼乃輔にそう訊かれ、志保は素直に頷いた。
「清太郎は、私が何処にいても必ず見つけ出してくれます。落ち込んでいる時はいつも慰めてくれるし、いい事があった時は一緒に喜んでくれる…清太郎は、私の一番大切な人です」
「だったら…」
頼乃輔は、志保の顔を覗き込んだ。
「清太郎は悲しむんじゃないのか、お前が死んだら…何故なら、清太郎もお前の事を一番大切に思っているからだ。分かるな、志保」
再び、志保の目から涙が零れ落ちる。
「死ぬ事は、いつでも出来る。しかし、自分を思ってくれる人と同じ時を共に生きる事は、今しか出来ん。どうだ、志保。この依頼、当分の間保留にしてみては…」
そう言って、頼乃輔は預かっていた小銭を志保に握らせた。
「見須奈先生…」
頼乃輔を見上げる、志保。
「それにな…」
頼乃輔は、肩を竦めた。
「折角の優秀な弟子を、師が自ら始末してしまうと言うのも…何だか、少々勿体無い気がするのだ。ほら、この道場貧乏だろう?だから金銭の面においても、門下生に欠けられてしまうのは…」
「せっ、先生、何と言う事を!」
慌てて、亙が注意する。
悪戯っぽく微笑む頼乃輔を見て、鞍悟と志保は同時に笑い出した。
「おお、少しは元気が出て来たな?」
頼乃輔に背中を叩かれ、志保は元気に頷いた。
「やはり、志保はそうでなくては…なあ、わた坊?」
鞍悟にそう言われ、亙も力強く頷く。
志保は、立ち上がって言った。
「有り難う御座いました。それでは先生方、これで…」
「志保」
頭を下げて帰ろうとした志保を、頼乃輔は呼び止めた。
「いいか?これだけは、良く覚えておけ。お前が死んだら、誰が泣かずともこの道場の七人の男達だけは、必ず泣くぞ…恥も外聞も無く、思い切りな」
「見須奈先生、有り難う…」
志保は笑顔で頷き、鞍悟と亙は思わず目頭を熱くしたのであった。
廉太郎と嗣之進は、壽美屋の暖簾をくぐった。
「まあ、世良の旦那に嗣さん!いらっしゃいませ!」
すぐさま、お三音が出迎える。
「よう、お三音。相変わらず、元気だな」
「ええ、勿論!旦那も、相変わらずいい男っ!ああ…やっぱいい男ってのは、いつ見ても見飽きないわあ…」
「まあ、それ程でも…有り難うよ、お三音」
廉太郎とお三音の会話を、皆が呆れながら聞いている。
お壽美は、思い出したように言った。
「ああ、そうそう。旦那方がいらっしゃると思って、お座敷取っといたんですよ。さあ、奥へどうぞ」
「流石はお壽美、相変わらず気が利くなあ」
「あ、あら、そうかしら?うふふっ…」
廉太郎に褒められ、お壽美は機嫌を良くしている。
嗣之進は、溜息をついた。
「世良さん、愛嬌を振り撒くのはそれくらいにして…早速、座敷へ参りましょうや」
「あ、ああ…じゃあ、お三音、風佑、飛朗も一緒に来てくれ」
『はい』
廉太郎に返事をした三人も、共に座敷へ入った。
早速、風佑が報告する。
「昨日、見須奈の旦那と朔さんがお帰りになった後、色々調べてみたんですが…志保ちゃんに旦那方の事を漏らしたのは、どうやら佐取屋の手の者のようです」
「佐取屋が?」
嗣之進は驚いたが、廉太郎は納得したようだった。
「やはりな…嗣之進、お前がまだ道場に来る前、佐取屋に騙された者達からの依頼で、何人かその手の者を斬った事があったんだ。恐らく向こうも、斬った相手が俺達である事を突き止めたんだろうな」
「でしょうね…しかも、佐取屋のやり方が汚いったらねえんですよ!」
怒りを露にする飛朗の話によると、志保がいつものように霧谷神社で泣いている所に佐取屋の手の者がやって来て、徳十が志保に死んで欲しいと言っていた等と、残酷な話を吹き込んだと言うのだ。
それを聞いた志保はかなりの衝撃を受け、自分で死ぬのは怖いからおじさん達に今すぐ此処で殺して欲しい、と頼んで来た。
しかし、子供を斬ったのが佐取屋の手の者だと知れたら、とんでもない事になる。
其処で、お前が通っている道場の師範達は殺し屋をしていると言う様な事を、志保に告げたのだった。
「志保ちゃんの優しさにつけ込み、旦那方の裏の顔を教えて、自ら命を絶つよう仕組んだんすね…」
飛朗は、苦々しい顔をした。
「くそっ…許せんな」
嗣之進は、きつく拳を握り締めた。
廉太郎も、険しい表情をしている。
「あ、あの…志保ちゃんの実の父親の事なんだけどね、今おもよちゃんと千郎太さんに調べてもらっている所だから、もう少しだけ待っていて頂戴ね」
お三音の言う事に、廉太郎と嗣之進は黙って頷いた。
中庭の櫻が、ひらひらと舞い落ちて行く。
「欣ちゃーん、一寸休憩…」
朔也は、人通りの多い道端のど真ん中に、突然座り込んだ。
通行人が、ちらちらと朔也を見る。
欣司もほんの一瞬だけ朔也を振り返ったが、何も言わずに再び歩き出した。
「ちょっ、一寸、欣ちゃん!おいっ、この人でなしっ!」
欣司の眉が、ぴくりと吊り上がる。
「じょ、冗談だよ。まあ、そう怒んなさんなって…」
渋々立ち上がった朔也は、着物に付いた花びらを払い落とし、欣司に追いついた。
「なあ、欣ちゃん。闇雲に捜し歩いたって、埒が明かねえんじゃねえの?かと言って、地道に待った所であの野郎が帰って来るとも思えねえけどよお…」
二人は隣町、飛沫町に来ていた。
目明しの銀介から、佐取屋の事を訊く為だ。
しかし、番屋にも長屋にも銀介の姿は見えず…仕方無しに、二人は町内を当ても無く歩いていたのだった。
「行くぞ…」
「えーっ…」
欣司に言われ、朔也が厭々歩き出そうとしたその時。
「き、欣ちゃん、此処…」
朔也は、突然欣司の袖を引っ張った。
欣司が、振り返る。
朔也の指差した先には、何と佐取屋があった。
「此処が、佐取屋だったのか…」
驚く欣司。
大きな店構えと、沢山の客…佐取屋が繁盛している事は、一目瞭然であった。
「他人の金で成り上がった店でも、こんなに客がつくもんなんだな…」
欣司がそう呟いた時、再び朔也が袖を引っ張った。
「きっ、欣ちゃん、欣ちゃん!あれ!」
「さっきから、何なん…あ、あいつ!」
佐取屋の脇、狭い路地裏から銀介が顔を出しているではないか。
「よう、銀!お前、そんな所に隠れて何してん…」
「ば、莫迦野郎っ!な、何言って…さ、朔のおたんこなすっ!うすらとんかちっ!」
銀介は、路地の陰から声にならない声で叫んでいる。
「おい銀っ、てめえっ!なすだの、とんかちだのって…んっ、んぐっ!」
文句をつけようとした朔也の口を咄嗟に塞いだ欣司は、朔也を引きずって銀介のいる路地へ素早く滑り込んだ。
銀介は、口をぱくぱくさせながら青筋を立てている。
「ば、ばっきゃろうっ!てめえ、こちとら仕事で張り込んでんだ!もし見つかっちまった日にゃあ、どう落とし前つけてくれる気なんでえ!えぇっ?」
「そっ、それは…」
口ごもる、朔也。
欣司は、無表情で言った。
「銀介…こいつがてめえの張り込みに気付くような、頭の冴えた男に見えるか?」
それを聞いた朔也が、引きつった顔で欣司を見る。
「あ、あのお、欣ちゃ…」
「それより銀介、佐取屋がまた何かしでかしたのか?」
朔也に有無を言わせず、欣司は銀介に訊いた。
「え…あ、ああ。佐取屋の野郎、今度は九士町の敷丸屋を狙ってるって聞いてよお」
銀介がそう言うと、朔也はきょろきょろし始めた。
「で…曾野津田の勘ちゃん、何処?」
「なっ、何だとっ!」
銀介は、再び青筋を立てた。
「耳の穴かっぽじって、よーく聞きやがれっ!曾野津田の旦那なんぞに任せてたら、捕まえられるもんもみーんな逃げちまうんだよっ!」
「お前さあ…」
苦笑いする、朔也。
「いくら勘ちゃんがお人好しで、頼りなくて、のんびりしてて、へらへらしてて…」
「てめえ!曾野津田の旦那を莫迦にしやがったら、この俺が承知しねえぞっ!」
「いや…それ、台詞違くない?」
怒る銀介を宥めて、朔也は話を続ける。
「この場合、俺が言うべき事だと思うんだけど。勘ちゃんがたとえそう言うお人だったとしても、お前にとっちゃあお偉い上役様なんだから、莫迦にするんじゃあありませんよと、こう俺がお前を諭すってのが本筋じゃねえの?」
銀介は、苛々しながら言った。
「ええいっ!本筋だろうが何だろうが、関係ねえやっ!ともかく俺は張り込んでんだ、邪魔すんなっ!」
「お前さあ…」
朔也は、腕を組む。
「気付いてるかどうか分かんないけど、俺ってこれでも武士なんだよねえ…貴方様は確か、町人でいらっしゃいましたよねえ?それに俺は、お前より二年も長く生きてんだぞ!どうだ、参ったか!はっはっはーっ!」
「莫迦言ってんじゃねえやっ!」
得意気な朔也に、銀介は唾を飛ばす勢いで言った。
「いいかっ?俺は、てめえより二年も遅く生まれてんだよ!その俺に、この近所の三角稲荷に供えられてた油揚げ食ってる阿呆面晒したなあ、何処のどいつだ?」
「うっ…」
言葉に詰まる、朔也。
「そう言う糞っ垂れ野郎を、お武家さんだあ、二歳上だあって、お慕い申し上げられるかってんだよ、このみそっかすっ!」
「町人風情に此処まで言われて、反論出来ない自分が悲しい…」
頭を抱える朔也に、欣司が言う。
「今更、何言ってやがる。口喧嘩で銀介に勝った事等、一度もねえだろうが。いい加減、諦めろ」
「きっ、欣ちゃーんっ!」
欣司に泣きつく、朔也。
それを無視して、欣司は言った。
「そんな事より…銀介、佐取屋について二、三、訊きたい事があるんだが」
最初は眉を顰めていた銀介だったが、やがて溜息をついた。
「ま、大神の旦那の頼みとあっちゃあ、断わる訳にも行かねえか…ついて来な」
銀介は二人を、先程も話題に上った三角稲荷に連れて来た。
「へーっ、此処も櫻が綺麗だなあ…」
口をぽかんと開けながら、朔也が櫻の木を見上げる。
銀介は、先程の質問に答えた。
「佐取屋ってなあまず主人の徳兵衛、そして番頭、手代、丁稚、女中…まあ全部合わせて、ざっと五十人はいらあな」
「ごっ、五十人っ?はーっ、こりゃあたまげた…」
朔也は、呆気に取られている。
欣司は、腕を組んだ。
「今の話、徳兵衛は一人者だと受け取っていいのか?」
「あ、ああ、その事についてなんだが…徳兵衛には、女房も子供もいたんだよ。だがな、今から三十年くらい前に二人とも死んじまってるんだ」
「二人とも?何で…病か?」
朔也の質問に、銀介は首を横に振った。
「自害、って事にはなってるが…」
「自害だと?」
眉を顰める、欣司。
「いや、何しろ三十年前なんて俺が生まれる前だから、詳しい事は知らねえんだけどよ。どうも、自害にしちゃあ腑に落ちねえ点が、多々あったってえ話だ。ほら、嗣之進様のお父上である宰様が、与力だろ?その宰様が、まだ同心だった頃の事よ」
「ふーん…」
頷く朔也。
銀介は、話を続ける。
「当時は宰様も大分抗議したらしいが、上の連中が取り合わなかったんだと…俺はその話を聞いて、ぜってえ佐取屋が上役に金を積んで、自害に見せ掛けるよう仕組んだんだと見てるんでえ」
「じゃあ、お前はその女房と子供は、佐取屋に殺されたと考えているのか?」
欣司に訊かれ、銀介は頷いた。
「だってよお…女房子供が死んだ後、佐取屋はすぐに別の女と一緒になりやがったんだぜ?しかもだ…その女とは、死んだ女房と夫婦になる前から、付き合ってたってえんだから…なあ?」
「だったら、何で徳兵衛はその死んだ女房と一緒になったんだ?」
「徳兵衛は、小僧の頃から佐取屋に丁稚奉公しておってなあ…で、故郷には幼馴染みのおしげと言う女がいたんだそうな…」
朔也の質問に、答えたのは…鳥居の陰から突然顔を出した白雲奉行所同心、曾野津田勘兵衛だった。
先程朔也と銀介が話題にしていた、その人である。
「あれ、曾野津田の旦那…どぶさらいは、終わったんで?」
『どぶさらい?』
銀介の発言に、欣司と朔也が声を上げる。
「い、いやあ…櫻の花びらが、泥と絡まって詰まってしまったらしくてな…近所の長屋の連中が一生懸命やっているのを見たら、拙者も手伝わねば申し訳ないような気になって、つい…」
そう言って笑う勘兵衛を見て、銀介は頭を抱えた。
「ったく、すーぐこれだ…同じ同心仲間からも、莫迦にされてんの知っててやってんだから、尚の事始末が悪いや。かーっ、もう呆れて物も言えねえよっ!」
勘兵衛の人の良さは白雲奉行所内でも有名であり、その名をもじって「そのつだ、かんべえ」「その都度、勘弁」してもらえると、罪人共の間では捕まるなら勘兵衛がいい等と言われる始末である。
「勘ちゃんも、相変わらずなんだなあ…そう言やあ、三年前に俺が此処の油揚げ盗み食いした時も、こいつは莫迦みてえに大騒ぎしてやがったが、勘ちゃんは俺が食い終わるまで温かく見守ってくれてたっけ」
懐かしげに当時を思い出す朔也に、銀介は言い返す。
「ありゃあ、立派な窃盗だっ!それを俺がしょっ引こうっつってんのに、まーた曾野津田の旦那が、阿呆みてえな事抜かしやがって…」
「上役に向かって阿呆とは何だ、阿呆とはっ!」
朔也は、完全に勘兵衛の味方についている。
「っんだとっ?阿呆な野郎に、上役も何もあるかっ!阿呆を阿呆と言って何が悪いんでえ、このすっとこどっこいがっ!」
「すっ、すっ…なっ、何ぃーっ?」
拳を震わせている朔也を宥めながら、勘兵衛は言った。
「まあまあ、落ち着きなされ。八重樫殿が食べた分は、きちんと拙者が新しい油揚げをお供えしておいたのだから、それで良いではないか」
「そう言う問題じゃねえんだよっ!」
銀介は、いきり立つ。
「こいつが食い終わるまで待った後、余程腹が空いていたのだな?なーんつって、自分が昼に食う筈だった握り飯まで、渡しちまいやがんの…あれを見た日にゃあ、はらわたが煮えくり返るかと思ったぜっ!」
其処で朔也は、思い出しながら言った。
「でもよお、あの後お前らと別れてから俺、真面目に働こうと思って世見道場の門叩いた訳。で、中入って何か仕事くれって廉ちゃん達と喋ってたら、急に腹が痛くなって来てさあ…いやあ、今まで生きて来てあれほど酷い差し込みはなかったなあ」
「そうか、そりゃあ災難だったなあ…はっはっは」
笑う勘兵衛に、朔也は呆れた顔を見せる。
「あのねえ、災難だったなあじゃねえっつーの。あれは、勘ちゃんにだって責任があるかもしんねえんだぞ?だって此処の油揚げが当たったのか、勘ちゃんの握り飯が当たったのか、未だに謎のまんまなんだからよお」
勘兵衛は、朔也の肩に手を置いた。
「もし拙者の握り飯が原因だったとしても、其方の食った油揚げを買い替えてやったのは、拙者…と言う事でまあ、恨みっこなしだな?がはははは!」
「そ、そうだよなあ?あはははは…つか、本当にこれでいいのか?」
一緒に笑いつつも、首を傾げる朔也。
「けっ!てめえが腹下したのは、お稲荷さんの罰が当たったからに決まってらあ!」
銀介だけは、憎まれ口を叩いている。
其処で、一連の会話を黙って聞いていた欣司が、口を開いた。
「おい…この莫迦の昔話や、差し込みの原因なんぞはどうでもいい」
それを聞いた朔也が、再び引きつった顔で欣司を見る。
「い、いや、あの、欣ちゃ…」
「それより曾野津田、先程の話の続きを聞かせろ」
口を挟んで来る朔也を、無視する欣司。
勘兵衛は、腕を組んで首を傾げる。
「話?はて、拙者は何の話をしておったか…」
「佐取屋の話だ、佐取屋のっ!徳兵衛には、おしげっつう幼馴染みがいたんだろ?自分のしてた話くらい覚えてろっつうんだよ、阿呆んだらっ!」
「ああ、そうだった…いやあすまねえなあ、銀介」
怒鳴る銀介に、勘兵衛は微笑みながら話を続けた。
「将来佐取屋を継ぐ事が出来たら、一緒になろうと約束していたそうな。それから徳兵衛は必死に働き、佐取屋を手に入れる事だけを考えて来た。順調に番頭にまでのし上がった徳兵衛は、佐取屋の一人娘だったおまさと一緒になり、見事佐取屋の主人に収まった」
「はあ?佐取屋の娘と?それで、おしげは納得したのか?」
朔也の質問に、勘兵衛は頷いて答える。
「自分が番頭になった時、徳兵衛はおしげを故郷から呼び寄せて、近所の長屋に住まわせているのだ。それでちょくちょく会っては、二人で佐取屋を乗っ取る機会を窺っていたらしい。おまさと一緒になるのも、計画の内の一つだったと言う訳だな」
「へぇーっ…そのおまさって女も、気の毒だったな」
朔也が呟く。
「三年後、徳兵衛とおまさとの間に跡取り息子が生まれた。それに安心したのか、大旦那がその半年後にぽっくり逝ってしまったのだ」
「ようやく、徳兵衛の天下だな?」
朔也の言葉に、頷く勘兵衛。
「ああ、その通りだ。同業者の吸収も、この頃から始まった。小さな店はどんどん潰され、佐取屋は徐々に大きくなって行った。その五年後だ、あの有名な献上反物の事件が起こったのは」
「佐取屋が敷丸屋に負けたと言う、あれか…」
欣司が、腕を組んで呟く。
「向こう三年間、佐取屋は敷丸屋に負け続けた。それと同じ頃、おまさと息子の正吉が部屋で死んでいるのが見つかったのだ。二人とも、心の蔵を一突きだ…」
「しかも、後ろからだぜ?明らかに殺しだったんだが、さっきも言った通り奉行所が自害で片を付けちまったもんだから、近所の連中も献上反物に負け続けたのと、徳兵衛の悪事に堪えかねたのが原因で、息子と心中したんじゃねえかなんて噂する始末だ」
と、銀介。
「その後、徳兵衛はすぐにおしげと一緒になり、現在に至ると言う訳だ。死んだおまさは生前、おしげの存在を知らなかったと言うし…自分の旦那に騙されていたとも知らずに、おまさは死んで行ったのだな。まあ、一番可哀想なのは何の罪もない息子の正吉だが」
勘兵衛の話を聞きながら、朔也は溜息をつく。
「確かに…それにしたってひでえ話だなあ、それ」
「その、おしげとの間に子供は?」
欣司が訊くと、勘兵衛は答えた。
「いや、それがいないのだ。佐取屋の使用人達も、跡取りがいないのを酷く気にしていてな。徳兵衛が死んだら、誰が店を継ぐのかと…」
「でもほら、例の子が一人…」
銀介が思い出したようにそう言うと、勘兵衛もぽんと手を叩いた。
「ああ、そうだ。大分昔に、おしげは子を一人産んでいるのだ。恐らく父親は、徳兵衛と見てまず間違いないだろうが…その息子は、すぐに住み込みで何処かのお店へ丁稚奉公させられてしまったらしい」
「なあ、欣ちゃん…」
朔也は、すぐさま欣司に耳打ちした。
「その息子って、もしかして…」
欣司も、黙って頷いた。
昼の練習を終えた頃、道場に客人が訪れた。
「ちょいと、邪魔しますよ」
「あ…おもよさんではありませんか」
「千郎太さんも、御一緒で…さあ、どうぞ」
鞍悟と亙が、出迎える。
客人は、おもよと千郎太だった。
おもよはめん引き(女掏摸)、十六太は鍵師をしている。
この二人も壽美屋のお三音、風佑、飛朗同様、廉太郎達の助っ人だ。
「おう、二人とも…どうした?」
頼乃輔は、奥の部屋にいた。
「ああ、今日のお師匠さんは頼の旦那でしたか…入らせてもらいますよ」
おもよと千郎太が、部屋に入る。
鞍悟と亙が客の二人に茶を出した所で、ようやくおもよが口を開いた。
「それが大変なんですよ、頼の旦那」
「何が、大変なんだ?」
頼乃輔が訊く。
おもよは言った。
「久美と清太郎、徳兵衛と徳十…この二組が明日の晩、お互い別々に殺す計画を立ててるんです」
『えっ?』
鞍悟と亙が、同時に声を上げる。
「勿論久美と清太郎は、これ以上佐取屋徳兵衛と旦那の徳十をのさばらせておく訳には行かないと考えているから。そして徳兵衛と徳十、この二人は敷丸屋を乗っ取るのに一番邪魔なのは、女将の久美と番頭清太郎の存在だと考えているからですよ…」
顔を見合わせる、三人。
「全く、莫迦げてるったらありゃしない!」
おもよの話を聞いて、亙は拳を握り締めた。
「何と言う事だ、お互いに殺し合うだなんて…残された志保や太一は、一体どうなってしまうのですか!」
「久美達は、お店が徳兵衛達に乗っ取られるよりは、よっぽどましだと考えているようです。志保と太一さえ生きていてくれれば、きっと敷丸屋はやって行けるって」
「そ、そんな…」
悲しげに顔を歪める、鞍悟。
「徳兵衛達は、久美達さえ始末出来れば志保と太一の事は、志保が旦那方に自分自身の始末を自ら頼むよう仕向けてあるから、問題はないって…」
おもよがそう言うと、亙は頼乃輔に縋りついた。
「見須奈先生っ!女将さんや番頭さんは、決して悪くありませんよねっ?志保や太一だって、そうですよ!それなのに…あんな連中の為に人生をふいにしてしまうのは、あまりにも何と言うか…」
頼乃輔も、頷く。
「恐らく、その計画を立て始めた頃からなのだろう、番頭さんが胃痛で永翠先生の所へ通い出したと言うのは。そのように気の弱い人間が、奴らを殺すのは無理だ。かかって行った所で返り討ちに遭い、逆に殺されてしまうのが落ち…」
鞍悟も、強く言う。
「志保や、太一の為にも…そう言った最悪の状況だけは、避けねばなりません!」
「で、では、見須奈先生…」
亙が、頼乃輔を見つめる。
頼乃輔は言った。
「我々が、殺るしかあるまい……」
皆が、黙り込む。
そよ風と共に花びらが入り込み、道場の床に滑り落ちた。
おもよが、静かに口を開く。
「それからねえ、頼の旦那…鞍さんと亙さんも、驚かないで聞いて下さいよ?」
「まだ、何かあるのか?」
頼乃輔が訊くと、おもよは静かに頷いた。
「志保と太一の、本当の父親は…何と、番頭の清太郎だったんですよ」
『えっ?』
頼乃輔達は、同時に顔を見合わせた。
「たっ、太一もか?」
驚く頼乃輔に、おもよは微笑む。
「私達、敷丸屋に忍び込んで根こそぎ調べて来たんです、間違いはありませんよ…ねえ、千郎太?」
黙って頷いた千郎太が、懐から紙切れを一枚取り出す。
おもよは言った。
「これ、久美と清太郎が志保と太一に当てて書いた遺書の写し。千郎太が、見つけて来たんです」
頼乃輔は、千郎太からそれを受け取った。
確かに、志保と太一の本当の父親は清太郎だと書かれている。
「成程…番頭さんが志保の面倒を親以上に見てやっていたのも、そう言う事だったからなのか…」
頼乃輔は静かに呟き、溜息をついた。
その日の夜。
鞍悟と亙を帰した後、五人は奥の部屋に集まった。
「徳兵衛と徳十の繋がりや敷丸屋乗っ取り計画、その他の謎が明らかになったはいいが、女将と番頭がそんな事を考えていたとなると、こちらもぼやぼやしてはいられないな」
廉太郎はそう言って、酒を一口飲んだ。
朔也も、酒を注ぎながら頷く。
「こんな裏の話、志保や太一が知ったら一体どうなっちまうんだろ…」
「志保は、ああ見えて芯がしっかりしている。自分の意思も、きちんと持っているしな。しかし、一番心配なのは太一だ。あの子はまだ五つか六つ、赤ん坊に毛が生えたようなもんだろ?出来れば、今回の事は知らないまま育って欲しいんだがな…」
と、嗣之進。
頼乃輔は、腕を組む。
「それにしたって、志保と…まさか太一までもが、番頭さんとの子供だったとはな」
「本当、たまげたねえ。女将と番頭…二人してひたすら隠して来たんだろうなあ、この事実をよお」
朔也がそう呟くと、欣司は考え込むようにして言った。
「それが徳十に対する、女将と番頭のささやかな抵抗だったに違いない…」
「兎にも角にも全ては皆、徳兵衛と徳十と言う名の壁蝨が、この世に居ついているせいだろうよ…手早く、掃除せねばな」
立ち上がった廉太郎は、壁に立て掛けてあった自分の刀を掴んで、振り返った。
「女将と番頭が動くのは、明日の夜だったな…俺達は、どうする?」
「そりゃあ勿論、二人が動く前…出来れば今晩中に、片を付けた方がいいんじゃねえですかい?」
嗣之進はそう言って、にやりと笑った。
頼乃輔は、黙って酒を飲んでいる朔也に訊いた。
「朔也、お前はこの件に関わる事を酷く嫌がっていたが…」
「よせ、見須奈…」
欣司は、立ち上がって言う。
「臆病風吹かせてるような野郎に、何を訊いても無駄だ。ついて来られても、迷惑なだけだからな…」
「きっ、欣ちゃん!」
いきり立つ朔也を抑えて、嗣之進は言った。
「大神さんの言ってる事は、間違っちゃいねえよ。迷いの生じてる奴は、足手まといになるだけだ…さあ、早いとこ腹決めちまいな」
黙り込む、朔也。
廉太郎は、微笑んで言った。
「そう、朔也を責めるな。今回の件の発端は、志保のあの一言。流石の朔也も、大事な門下生を巻き込む訳には行かないと考えたのだ。しかし内情が明るみに出るにつれ、恐らく朔也の考えも変わって来た事と思う…どうだ、朔也?」
朔也は、考えていた。
皆が、黙って朔也を見つめる…そして。
「分ぁーった、分ぁーった!やるよ、やりますよ!年寄りばかりには、任せておれんからな…この若き剣豪、八重樫朔也が共に出陣してやろうではないか!はっはっは!」
そう言って立ち上がった朔也を見上げながら、頼乃輔が呟く。
「何が年寄りだ、お前より五つ上なくらいで老人扱いされるとは…俺も、見くびられたもんだな」
「全くだ。一番年の近い俺なんぞ、二つしか離れてねえってのに…」
肩を竦める嗣之進の背中を叩き、廉太郎は言った。
「ほら、やると決まったらさっさと行くぞ!」
「早くしろ。阿呆の言う事なんぞ一々真に受けていたら、時間が勿体無い…」
「あ、あの、欣ちゃ…」
欣司の厳しい言葉に呆然とする朔也を置き、四人は剣を携えて素早く道場を後にした。
夜中、徳兵衛と徳十の二人は慌てて互いに自分の店を出ると、人目を避けながら杉ノ森へ向かった。
『 店の件にて、大事な要件あり。至急、杉ノ森へ来られたし。 』
と言う投げ文が、徳兵衛の所には徳十から、徳十の所には徳兵衛からそれぞれ届いたからである。
だが説明するまでもなく、これらは全て廉太郎達がおもよ達に頼んで仕組んだ罠だ。
「とっ、徳十!」
息を切らした徳兵衛は、先に来ていた徳十に飛びついた。
「こんな時間に、呼び出して…なっ、何かあったのか?」
「何かあったのか、って…」
徳十も、目を丸くする。
「文を投げて寄越したのは、おとっつぁんじゃありませんか!一体、何があったって言うんです?」
それを聞いた徳兵衛は、開いた口が塞がらなかった。
徳十も徳兵衛の様子を見て、唖然としている。
その時だった。
「莫迦な親子だよ、お前らは…」
暗闇からの声。
「だっ、誰だ!」
徳兵衛が、敏感に反応する。
木々の間から姿を現したのは、廉太郎だった。
「親父は、佐取屋を乗っ取る事に成功。邪魔になった女房子供を、すぐに刺し殺した」
「息子も、敷丸屋を乗っ取る事に成功。邪魔になった女房子供、そして…番頭までもを殺そうと、企んでいる。そうだな?」
頼乃輔も姿を現し、徳十に問い詰める。
徳十は、はっとした。
「わっ、分かったぞ…貴様らだな、我々を偽の文書で此処へ呼び出したのはっ!」
「ほう、察しがいいな…」
嗣之進も、木々の陰から出て来て言った。
「罪のねえ人間を、てめえの私利私欲の為に殺そうと考える、その汚え根性が気に食わねえんだよ!」
欣司も刀に手を掛けながら現れ、ゆっくりと近付いた。
「てめえらは、俺達があの世へ送ってやる…覚悟しやがれ」
蒼白い月の光に照らされ、不気味に微笑む欣司。
徳兵衛は、唖然としながら呟いた。
「まっ、まさか、お前達、あの道場の…あ、蒼い死神か?」
朔也も出て来ると、にやりと笑った。
「へえ、俺らを知ってんのか。そいつぁ、名乗る手間が省けていいや…とっとと、片付けてやらあ!」
慌てた徳十は、叫んだ。
「ね、念の為に、仕込んでおいて助かった…お、おいっ!野郎共っ!」
森の奥からやくざや浪人達が、刀を構えてぞろぞろと出て来る。
「えーと、ひい、ふう、みい、よ…まあ、ざっと数えて三十五、六はいるか?」
廉太郎が人数を数えると、朔也も指を折り曲げる。
「って事は、俺達五人で割ると、えーと…え、あれ?」
「七人だ!てめえのねえ頭使って計算してたら、夜が明けちまうんだよ!」
嗣之進にそう言われ、朔也は黙って口を尖らせている。
欣司は、刀を抜いた。
「一人当たり、七人だな。よし…人の獲物一人でも多く斬りやがったら、代わりにてめえらの首飛ばしてやるから覚えておけ」
「ぶ、物騒だな、欣司…ま、七人以上斬らんよう気を付けるとするか」
そう言って、頼乃輔も刀を構えた。
「なっ、何を、ぶつぶつ言ってやがるっ!」
徳兵衛は、苛々しながら怒鳴った。
「野郎共、殺っちまえっ!」
『おりゃぁーっっっ!』
やくざや浪人達が、一斉にかかって来る。
五人は相手の刃をうまく躱しながら、次から次に刀を振り落として行った。
『うわぁーっ!』
『ぎゃぁーっ!』
あっと言う間に倒されて行くやくざや浪人達を見ながら、徳十は悔しそうに歯軋りをしている。
「えーっと、ひい、ふう、みい、よ。俺は、あと三人だ…な!っと」
数えながら、ばっさりと叩き斬って行く朔也。
「よし…俺は、あと一人だ…さあ、最後に俺に斬られてえ奴は、遠慮無くかかって来やがれ!」
意気込む嗣之進を見て、やくざや浪人達が思わず後ずさりする。
「しかし…数えながら斬ると言うのも、少々面倒だな…っと、これで確か六人目だったか?」
頼乃輔が呑気に数えていると、欣司がはっとなって走り出した。
「おい、お前ら!余所見している場合じゃねえ!あいつら、逃げて行くぞ」
五人がやくざや浪人達を相手にしている間に、徳兵衛と徳十は逃げようとしていた。
「てめえら…一体、何処へ行く気だ?」
欣司がすかさず追いかけ、二人の目の前に立ちはだかる。
「ひっ!」
「おっ、おとっつぁんっ!」
震える二人に、欣司は言った。
「俺はとっくに、七人殺っちまったんだが…ああ、丁度いい。この物足りなさを、てめえらで埋めさせてもらうとするか…大人しく、斬られるんだな」
欣司の血走った両眼から、恐ろしい殺気が放たれる。
蒼白い月に仄かに照らされた櫻は、不気味な薄紫色に見えた。
腰を抜かした二人は、欣司を恐怖の眼差しで見つめている。
「あーあ。欣司の奴、また本気になっちまった…よっと、これで七人終わりだ」
廉太郎が最後の一人を斬ると、朔也も倒れた浪人にとどめを刺した。
「こっちも終わり、っと。後は…あ、欣ちゃん。まーた美味しいとこ、持ってっちゃうんだあ」
「そう言うな、八重樫。あの目、見てみろ…あれだけが、大神さんにとって唯一の楽しみなんだよ」
そう言ってふっと笑った嗣之進は、刀をしまって欣司を見つめた。
頼乃輔も、深く頷く。
「嗣之進の言う通りだ。おい、欣司!勿体ぶってないで、さっさと殺ったらどうだ?」
欣司は、じりじりと歩み寄る。
「そうだな…さあ、どっちが先に殺られたい?」
「お、お、お、お、お前っ!お前が、先に行けっ!」
無情にも、徳兵衛は息子を突き出した。
徳十は、目を丸くしている。
徳兵衛は、震える声で言った。
「こっ、こいつが、全部悪いのです!敷丸屋で悪知恵つけられたのか、この年老いた親を使って店の乗っ取りや、殺しをしよう等と企みましてね…ええ、本当なのですよ!」
「おっ、おとっつぁん!そりゃあ、ねえだろ?元はと言えば、おとっつぁんが…」
「えーい、煩い煩いっ!」
徳十の口を押さえて、徳兵衛は言った。
「とっ、とにかく、私には全く罪はないので御座いまして…」
唖然とする、徳十。
欣司は、鬼のように恐ろしい形相で言った。
「その面見てるだけで、胸糞悪いんだよ…両方、一遍に叩き斬ってやる!」
悲鳴を上げる間もなく、徳兵衛と徳十は同時に欣司の刀で斬られた。
声も出ずにもがき苦しみ、息絶えるまで二人の様子を見つめていた欣司は、満足気に微笑みながら静かに刀をしまった。
「ふん…地獄に落ちやがれ、下衆野郎」
どす黒い血を含んだ花びらは、湿った土と同化している。
「じゃあ…行くか」
そう言う廉太郎に、皆が頷いて見せる。
五人は真っ暗な森の中を、蒼白い月の光を頼りに歩き出した。
軽やかに舞う花びらは、無数の死体の上に薄く降り積もった。
翌日、道場に客人が訪れた。
「誰か、おるか?」
「はい…ああ、富田様に全吉さん!」
「ささ、どうぞお上がり下さい。今、お茶を御用意致しますので」
いつも通り、鞍悟と亙が出迎える。
客人は、白雲奉行所同心富田眞太郎と、九士町目明しの全吉だった。
「大神…世良達はいるか?」
「奥だ…」
眞太郎の質問に、欣司が短く答える。
「相変わらず、愛想の無い男だ…」
そう呟き、肩を竦めながら眞太郎は奥の部屋へ入った。
「よう、富…そろそろ、来る頃だと思っていたよ」
廉太郎は軽く手を上げ、茶をすすった。
隣には、頼乃輔も座っている。
「それでは、私共は失礼致します」
「ごゆっくりどうぞ」
鞍悟と亙は茶を用意し、頭を下げて部屋を出て行った。
明門寺の光英和尚に倣い、湯飲みの中には櫻の花びらが浮かべられている。
「へえーっ。中々風情があるじゃねえですかい、鞍ちゃんもわた坊も…それじゃあ、頂きますよ」
鞍悟と亙に感心しつつ、全吉はすぐに茶をすすった。
「どっわぁちーっ!」
湯が熱かったのか、驚いて舌を出す全吉。
眞太郎は溜息をつくと、眉間に皺を寄せた。
「騒がしいぞ、全吉…ところで今朝方早く、杉ノ森から三十数名の死体が見つかった…お前達だな?」
「さあ、どうだろうな…」
廉太郎が、にやけながら答える。
「いやあそれがね、三十数名の内の二人は敷丸屋の旦那と、隣町の飛沫町にある佐取屋の旦那だったんですよ!」
全吉は、茶をふうふう冷ましながら言った。
「まあ、佐取屋の悪事は知らない者はいないってなくらいだったし、敷丸屋との繋がりについても、大方飛沫町の銀から聞いてましたんでね、まあ何と言うかこっちとしても、しょっ引く手間が省けて助かったと…痛っ!」
眞太郎は、全吉の頭をぽかりと殴った。
「なっ、何すんですか、富の旦那っ!」
「お前が、いらん事まで言うからだろうがっ!」
「は、はあ、すんません…」
眞太郎に怒鳴られ、全吉は頭を摩りながら謝った。
そんな二人を見ながら、頼乃輔が訊く。
「それで、その件に関してはどうなりました?」
眞太郎は、茶を一口飲んでから答えた。
「佐取屋に脅された敷丸屋が逆上し、ならず者共も巻き込んで相討ちになったと…」
「ほう…中々の筋書きだなあ」
「これ、からかうでない!」
にやける廉太郎を制し、眞太郎は言った。
「全く、お前達のせいで我々がどれほど骨を折っているか、分かっているのか?」
「ですがねえ、富の旦那。こっちも、世良さん達がちゃんちゃんばらばらとやってくれるお陰で、悪者共を一掃出来て助かっている面も多々あるん…痛っ!」
全吉は、再び殴られた。
眞太郎は、咳払いをして言う。
「と、とにかく…与力の宰様が別件でお忙しかった為、今回は同じく与力の若村様がお口添えをなさって下さったのだ」
「へえ、靖さんが?」
廉太郎が驚くと、頼乃輔もくすっと微笑んだ。
「あの人もまた、随分と酔狂なお方だからな…まあ、靖さんの口添えがあったなら、安心していいだろう」
話題の男は、白雲奉行所与力の若村靖臣。
眞太郎達の上役である。
呑気な二人に呆れながら、眞太郎は言った。
「そう言った訳で、今回の件も無事解決した。以上!行くぞ、全吉!」
「へっ、へいっ!」
立ち上がった眞太郎は、全吉を連れて部屋を出た。
道場では、隅の方で仁王立ちしたままびくともしない欣司が、目玉だけをぎょろりと動かし、門下生達の様子をじっと見ている。
「大神」
眞太郎が、声を掛ける。
欣司は、無反応だ。
眞太郎は、気にせず言った。
「佐取屋と敷丸屋に、直接手を下したのは…お前だな?」
欣司が、眞太郎を睨みつける。
眞太郎は、ふっと笑った。
「相変わらず、見事な斬り口だったよ…」
そして眞太郎は全吉を連れ、道場を後にした。
「ふん…」
欣司は無表情のまま、花吹雪で霞む眞太郎達の後ろ姿を見つめた。
「はい、どうぞ!今日は、どんどん飲んで頂戴ね!」
お壽美が、櫻の一番良く見える座敷に酒を運んで来る。
道場の練習を終えた七人は、壽美屋で晩飯を食べていた。
鞍悟と亙は座敷ではなく、表の席でお由奈やお璃乃と共に若い者同士、楽しく会話を弾ませている。
「悪いなお壽美、こんなに酒を奢らせてしまって…」
申し訳なさそうな廉太郎に、お壽美は笑って言った。
「いいんですよ。あたしらが旦那方にしてあげられる事って言ったら、これくらいしかないんだから」
「でもさ、お陰で何だかこっちもすっきりしたよ。佐取屋の悪事には皆、腹が立ってたんだから…それもこれも、全て旦那方のお陰!蒼い死神様々、って奴ですか?」
そう言って、お三音は酌をして回った。
『失礼致します』
其処で障子戸が開き、風佑と飛朗が入って来た。
「おう、どうだった?」
廉太郎が訊くと、風佑は頷いて言った。
「女将の久美と番頭の清太郎は正式に夫婦となり、志保や太一と共に敷丸屋を盛り立てて行くようです」
「そうかい、そいつぁ良かった。きっと、志保も安心しただろうよ」
嗣之進は笑顔でそう言い、酒をぐいと飲み干した。
「で…佐取屋は?」
欣司が訊く。
飛朗が、頷いて答えた。
「佐取屋は、無論取り潰しですよ。可哀想に使用人達は皆、故郷へ帰されちまいました。一人残されたおしげは、先程首を吊って死んでいるのが店で見つかったって…そりゃあ、酷い騒ぎでしたよ」
「まあ、仕方がないだろう…自業自得だな」
頼乃輔がそう言うと、朔也は銚子を持ち上げた。
「兎にも角にもだ、無事解決したんだしい…今夜は、飲もう!ほら、風と飛も一緒に飲め!な?」
風佑と飛朗は嬉しそうに頷き、朔也に酒を注いでもらった。
「おい、お三音!お前も飲め!」
「えっ、いいの?やったーっ、朔さん大好き!」
朔也に酒を勧められ、お三音も杯を突き出す。
「朔也、すっかり出来上がってるな…」
呆れる頼乃輔に、廉太郎が笑って言う。
「まあ、いいじゃないか。今回の件に関しては、朔也が一番喜んでいるかもしれんのだからな。普段はいい加減でも、門下生を思う心は人一倍強かったと言う事だ」
「女将、酒!酒、持って来てくれ!」
朔也は、完全に酔っ払っている。
「はいはい…でも朔さん、飲み過ぎは駄目よ!」
立ち上がったお壽美が障子戸を開けると、何と其処に鬼一が立っていた。
「おっ、お前さんっ?」
「おう、今帰ったぜ。お由奈に訊いたら、皆さん此処にいらっしゃるって言うから…」
元忍びの鬼一はお三音、風佑、飛朗のような若者が憧れて会いに来る程、その道では名の知れた男だ。
忍びを抜けてからは、幼馴染みのお壽美と一緒になり、此処壽美屋を開いた。
しかし、実際に店を切り盛りしているのはお壽美で、鬼一はと言うと廉太郎達のような訳ありの者達から依頼を受けて、内情を探ると言う密偵の仕事をしている。
その為に全国各地を回るので家に戻る回数は少なく、いつもお壽美の頭を悩ませているのだった。
「どうも旦那方、御無沙汰しておりました」
「よう、鬼一!お前、一週間は此処を空けていただろう?」
頭を下げた鬼一に廉太郎がそう言うと、嗣之進も笑ってお壽美を見た。
「お陰で女将は、ずっと機嫌が悪かったそうだぞ」
「つっ、嗣之進の旦那っ!」
お壽美が、顔を赤らめる。
朔也は、杯を持ち上げた。
「おお、親分!ひっく…」
「朔さん、既に御機嫌じゃねえですかい」
鬼一が笑う。
朔也は立ち上がり、鬼一の肩を叩いた。
「まあ親分、再会を祝して一緒に飲みましょうや!ね?」
「無粋な事を言うな、八重樫…」
そう言ったのは、欣司だった。
「あぁ?」
むっとした朔也が、欣司にもたれかかって絡む。
「よお、欣ちゃん…無粋ってなあ、どう言う事だあ!俺が、いつ無粋な事したってんだよお!えぇ?」
「おい、朔也…」
廉太郎は、苦笑いして言った。
「分からないのか?折角、鬼一が久しぶりに帰って来たんだ。せめて今夜くらいは、お壽美と二人っきりにさせてやれって言ってるんだよ、欣司は…」
「あ…」
朔也が、はっとなる。
「い、嫌ですよお、皆して…」
お壽美が再び顔を赤くすると、皆は一斉に笑った。
櫻の木々はもう、緑の葉を茂らせつつある。
― 完 ―
二〇〇三・三・八(土)
by M・H
次話(其の二)
同じ地球を旅する仲間として、いつか何処かの町の酒場でお会い出来る日を楽しみにしております!1杯奢らせて頂きますので、心行くまで地球での旅物語を語り合いましょう!共に、それぞれの最高の冒険譚が完成する日を夢見て!

