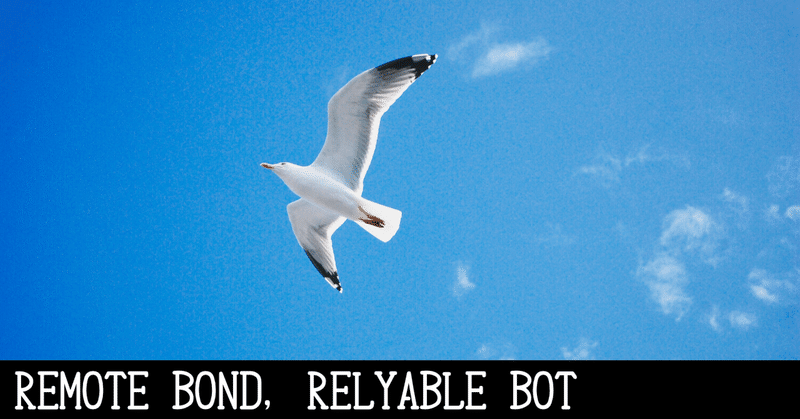
【リモート・ボンド、リライアブル・ボット】
【この作品は『ニンジャスレイヤー』の二次創作小説です/約42000文字】
#1
『ナボタタ・リゾートへようこそ!』
『そこは地上の楽園! 晴れ渡る空! 青い海! 忙しい日常を離れ、雄大な自然でリフレッシュしよう! 飛行機? ポータル? 一切不要! UNIXデッキの前から本物の南国体験! バーチャルではありえない感動をあなたに! エメツ・テックが叶えます!』
『ナボタタ・リゾート! ナボタタ・リゾート! そこは地上の』
――ブツン!
ウノエ・ヒロカワがモニタの電源を切ると、タタミ4枚分の部屋からは一切の光が消えた。ここはナボタタ・リゾート地下寮、通称『アリの巣』302号。簡素なベッドと、持ち帰りの書類仕事用のデスクが室内のほぼ全てだ。後は自社の広告プログラムを無限再生するモニタと、天井に描かれた社長直筆の『忍耐』のショドーしかない。
「ハァ……」ため息を吐いて横向きに寝転がると、その先には壁がある。誰の意図もない、無機質なコンクリートの壁。それがウノエを唯一癒やしてくれるものだった。
『ナボ……』『……リフ……』電源を切っても広告音声は漏れ聞こえてくる。薄い布団にくるまる。『……叶……』まだ聞こえる。耳を塞ぐ。『……』聞こえなくなった。直後。『ナボタタ・リゾート!』タダーン! 大音量! 隣で再生が始まったのだ。『そこは地上の』「ジゴクだ」
――――――――――
……その翌朝!「イヤッホオオオオオウ!」SPLAAAASH! ウノエが海に飛び込むと激しい水しぶきが上がった。ナボタタのエメラルドグリーンの海水は透明度が極めて高く、ガラスめいて濁りがない。足をバタつかせながら色鮮やかな熱帯魚たちを追い回すと、慌てて逃げていく。その愚かさも愛おしい。
思う存分に泳ぎ、浜辺に戻るとハワイアン・オイランが彼を出迎えた。オイランはウノエの首にレイを掛け、軽くキスをした。「最高!」ワイルドなステーキに舌鼓を打つ!「最高!」マリンスポーツを自在に楽しむ! ウノエは思わず叫んでいた。「最高だよ! ウノエ=サン!」
「アリガトゴザイマス!」ウノエはその場でオジギした。誰に? 無論、ゲストにだ。彼のニューロンには今、ネオサイタマ・サラリマンの意識が宿っている。五感を共有し、肉体を共に操作する……「光栄です!」共有は思考の領域には及ばず、彼らの交流は一人芝居めいて行われる。
「素晴らしいね! エメツ・テックは!」「ハイ!」ウノエは即答した。エメツ・テック。それは『実現した』を意味する接頭語だ。詳細は誰も気にしない。ウノエにとっては僥倖だった。
その後も彼らは存分に食い、サケを飲み、オイランを抱いた。心地よい疲労感が全身を包み込むころには、オレンジ色の夕日が降りている。美しい景色だ。初めて見た時はそう思った。今は、ただの終業チャイム代わりだ。
「名残惜しいなあ。毎日がこうならどんなに幸せなんだろうね」サラリマンは笑った。「そうですね」ウノエは苦笑した。憤りは既に摩耗している。「君は恵まれてるぞ! こんな素晴らしい場所で働けて!」「ハイ!」「また来るよ!」「是非どうぞ!」「それじゃあ!」――ブツン!
サラリマンがログアウトした途端、視界がブラックアウトし、ジジ……と不快な雑音が鳴り始めた。五感に混ざったノイズは徐々に薄れ、やがて正常に戻っていく。それが視界がチカチカと赤く切り替わる程度に収まると、ウノエは地下寮の入り口へと向かった。
地下はコンクリートの世界だ。じっとり濡れたアロハシャツに冷たい空気が染み込み、外との温度差に反射的にくしゃみする。道なりに歩いていると、うずくまる同僚がいた。彼は体を抱き込むように震わせていたかと思うと、おもむろに嘔吐した。「オゴーッ!」爽やかな南国カクテルの香りと胃酸の臭いが混ざりあい、強烈な異臭を放った。
新入りだろう。「オイオイ、大丈夫か?」モップを取ってきてやると、泣きながら清掃を始めた。ウノエは懐かしさに僅かに苦笑し、階段を降りていく。手伝いはしない。疲れているからだ。だが彼は直後、手伝わなかったことを後悔することになった。
「ウノエ=サンではないか! 久しいな!」「アイエエエ!? ブラックハチェット=サン!」従業員寮の各フロアにある、自主勉強会用のスペース。そこを個人専有する小柄なニンジャ存在に、ウノエは即座にドゲザした。
「調子はどうだ。ン?」ニンジャは低く押し殺したデス・ヴォイスで言った。それがウノエを震え上がらせる。黒地に金糸の刺繍を入れたニンジャ装束。腰に備え付けられた2本のハチェット(手斧)。その全てが恐ろしい。
このニンジャは、人間がニンジャの体を操作する全く新しいリモート実験の被験者らしい。だがウノエには関係ないことだ。彼はこの暴力存在から逃げる口実を探そうとした。間に合わない。
「なあ、ウノエ=サン。先輩は?」「神様です!」「その命令には?」「絶対服従!」ウノエはやけくそで叫んだ。「相変わらず物わかりがいいやつだ!」ニンジャは下品に笑うと、おもむろに立ち上がり、ドゲザするウノエの尻を蹴り飛ばした!
「アイエエエ!」「まずサケだ! いつものだぞ!」「ハイヨロコンデー!」ウノエは走り出す! 機嫌を損ねればさらなる暴力だ!
自室の財布を取り、自販機の前にドタドタと駆ける。財布の中にはトークンが1枚。彼の1週間の稼ぎだ。それでもウノエはためらいなく硬貨を投入し、ラインナップを吟味する。暴君の『いつもの』はランダムで決まるのだ。「……これだ!」キャバァーン! 吐き出されたビール缶を持ち、全速力で駆け戻る!
「おお、これだよこれ! 気が利くな!」ブラックハチェットは愉快そうに笑った。今日は当たりだったようだ。ウノエは荒く呼吸してへたり込む。それでも週に一度の晩酌はフイだ。「さて、次はどうするかな?」「エッ!? まだ何か!?」「当然だろうが!」
「後輩は先輩に尽くすべし! 美しい企業文化だろ! まずはビールだ! もう一本だぞ!」「もうカネが」「ダマラッシェー!」「アイエエエ!?」「工面しろ! 10分以内にだぞ!」「アイエーエエエ!」
ウノエは泣きながら自室へ走った。彼はベッドやデスクを動かし、小銭が落ちていないか探した。あるわけがない。落とせば絶対に気づく。「アイエエエ……ど、どうすれば……」すると背後から声。「何やってんの?」
振り向くと長い黒髪に褐色の肌を持つ、年若の女性がいた。「カレナ=サン?」「何、やってんの?」カレナは指を突きつけて詰問した。「そ……その。模様替えを……」ウノエは強がろうとした。だがブラックハチェットの笑い声が聞こえてくると、体が反射的にびくんと跳ねた。「あー……なるほどね。事情は分かった」
カレナはため息を吐いた。「前から言ってるじゃない。アンタとあの野郎に上下関係はないって。しゃんとしてれば良いんだよ」「でも」「いいよ、もう」カレナは手を振った。「アタシが話しつけといてあげるから、寝な」それきり踵をかえし、勉強スペースへと向かった。
「ア……」ウノエは手を伸ばそうとして、引っ込めた。カレナは振り返らなかった。その言葉に続きがあることを、そもそも期待されていないのだ。
少しして、暴君とカレナが言い争う声が聞こえ始めた。ニンジャとモータル。その絶対的な差はあれど、社の階級上は彼女らは同格だ。ゆえにこうして戦うことができる。当然ウノエにも、その権利は与えられている。彼は数秒逡巡した。それだけだった。何をしても惨めさが増すだけとしか思えなかったからだ。
ベッドに入っても眠気は湧いてこない。目を閉じていると、とりとめもないことばかりが思い浮かぶ。(この生活はいつ終わる?)(カレナ=サンは俺を軽蔑してるんだろうか)そして。(俺はなぜ、こんなところに来た?)
「……ッ!」心臓を鷲掴みにされたような恐怖感! ウノエは跳ね起きた。毎度のことだ。そこに思考を巡らせようとすると、こうなる。すっかり目の冴えたウノエはモニタの電源を入れた。タダーン! 利用料めいた不快な広告音声とともに室内に光が生まれた。
デスクには封筒。明日の客のデータだ。それを元に最適なリゾート・プランを勧めるのもウノエの仕事だ。中の書類を一瞥すると、そこには珍しいタイプの客の顔写真が載っていた。軽薄そうで、薄汚い……「ハーフ・ガイジン?」
#2
ピザ・タキ地下アジト。その床にはいつにもまして大量の資料が散乱し、新種のタイルめいて彩っていた。「いいか、お前。整理してやる」タキが言った。「必要ない」ニンジャスレイヤーが答える。「黙って聞け。あのな、俺たちはだ」タキは言葉をつまらせた。
「まず……お前だ。平和に暮らしてた善良な俺を、クソニンジャがさらった。ストリングベンドとか言ったか。覚えてるか?」「初耳です」コトブキが口を挟んだ。タキは無視した。「そんでコイツも来た。それからお前が色々ニンジャを殺して……」「何が言いたい」ニンジャスレイヤーが問うた。
「アー、つまりだな。その……」タキは口ごもった。大見得を切ってみたが、伝えたいことは上手く言語化できていないのだ。「苦労したよな、俺は」コトブキが横目でニンジャスレイヤーを見る。何も答えない。「その苦労の結晶がコイツだ」モニタには『ブラスハート』の文字。
「それがどうした」「コイツをシメれば、お前は目標にグイっと近づく。そうだろ」「そうかもしれんな」
「なら他のニンジャをわざわざアサルトする必要はねえ。そうだろ!」「かもしれん、と言ったぞ」ニンジャスレイヤーは冷たく否定した。「ブラスハートがサツガイの居場所を知る可能性は高い」「だろ!」「だが絶対ではない」「要領を得ました」コトブキが一人頷く。
「つまり保険なのですね。この……」「ヤメロ! 捨てろそんなもん! 不吉だ!」コトブキが見ているのはナボタタ・リゾートのパンフレットだ。そこに掲載されている、社長のアツバラ・シナキ。黒髪に白髪交じりの初老の男は……「よせ!」
「いいか、これは忘れろ! 無駄足だ!」タキはパンフを引ったくり、紙ふぶきめいて放り捨てた。ニンジャスレイヤーはもはや構わず言った。「ブラスハートについて調べるには時間が掛かると言ったな」
「調査自体は外部委託できるとも言ったぞ」ジゴクめいて有無を言わさぬ声に、タキは脂汗を流す。ムンバイから帰還したニンジャスレイヤーがクラバサINCの社名を出した時、タキは大いに肝を冷やした。調査を進めるごとに事態はより深刻化した。オムラ・エンパイア。企業軍責任者。浮遊要塞。卑近なワードはゼロ。
絶望的な情報の奔流に、タキがまず取ったのは逃避だった。ニンジャスレイヤーには時間が掛かると嘘の報告をし、疑惑の目を逸らすために適当な情報をやった。それはタキがシンケン・タメダ本社に英雄的なアサルトを決めた際、デシケイターの棚からガメておいたものだった。薬物的リフレッシュのための時間稼ぎだ。
中身はカネになりそうもなく、タキにとってはガラクタ同然だった。だがそれがマズかった。そこにはニンジャと、彼の経営する施設のデータがあり、しかもそれはサンズ・オブ・ケオスの構成員。ニンジャスレイヤーにとっては値千金の情報だったのだ。
そのうえ今は侵入の最適タイミングであり、この期を逃せばいつ機が回るかわからない。「不運ってこんなに重なるか?」「何の話だ」「いや、いい」タキは額を抑え、理由を探す。「だがな、その。ブラスハートは強敵だろ。今は静かに……」「理由はさっき言ったぞ」ニンジャスレイヤーは低く言った。「この機を逃す気はない」
タキはちらりとコトブキを見やった。彼女はすでにアロハシャツを着ており、二枚のパンフを交互に見ている。これはダメだ。視線を察したか、彼女は慌てて取り繕った。「これは情報収集です! 形から入るタイプなんです」「そうか」タキは思考する。この調子では奴らは止まらない。だが己が巻き込まれるのは避けたい。
(クソッタレニンジャ野郎め。病み上がりをこき使いやがって)非人道的な蛮行にタキは憤った。だがそんな彼のニューロンには引っかかるものがあった。ナボタタ・リゾート。ナボタタ。ナボタタ? どこかで聞いた。「ンン」目を閉じ、記憶の海を探る。
「どうした」ニンジャスレイヤーが問う。コトブキが答える。「後遺症かもしれません」「それはねえ」タキは否定し、より深くへダイヴ。やがて記憶の底から一つの情報が引き上げられた。それはこのクソッタレたクエストをボーナスステージへと変えるかもしれない情報だった。
だが一つ、気がかりな条件がある。「カネが掛かるぞ。誰が出すんだよ」「おれが出す」条件が整った。「わたしは自分で払います」コトブキが言った。
――――――――――
……その翌朝!「イヤッホオオオオオウ!」SPLAAAASH! ウノエが海に飛び込むと、激しい水しぶきが上がった。エメラルドグリーンの海水は透明度が極めて高く、ガラスめいて濁りがない。足をバタつかせながら魚たちを追うと、慌てて逃げていく。
思う存分に泳ぎ、浜辺に戻るとハワイアン・オイランが彼を出迎えた。オイランはウノエの首にレイを掛け、軽くキスをした。「最高!」ワイルドなステーキに舌鼓を打つ!「最高!」マリンスポーツを自在に楽しむ!
「最高! 最高だぜ!」タキは水上ハンモックに半ば寝そべり、蛍光グリーンのトロピカル・カクテルのストローに口をつけた。カクテルには丸くすくわれたアイスが載せられ、チェリーがトッピングされている。勢いよく吸い上げると口の中が爽やかな清涼感に満たされ、汗を流していることすら忘れそうだった。
最高の気分だった。景色は美しく、メシは美味く、サケは飲み放題。オイランはホットで、厄介事は一切ない。そして何より、支払いがニンジャスレイヤーなのだ!「オイ、ウノエ=サン! カネならあるぜ。もっといい課金サービスねえか!」富豪めいて豪遊!
幼少期のタキにとって、海とは落ちれば死ぬ以外のものではなかった。だがそれが、こんなに楽しい場所だとは。ウノエはタキのあまりの低俗さに呆れつつもその貪欲さを羨んでいた。それは彼には戻ってこないものだからだ。
「そうですね、後は……」ウノエは視線を浜辺に走らせつつ、新たなプランを立てようとした。しかし思わずその視線は止まった。オレンジ色のアロハシャツに身を包んだカレナがいたからだ。彼女も仕事だろうか。
「なかなかホットじゃねえか。いくらだ」タキがヘラヘラ笑った。ウノエは慌てて弁解する。「彼女はそういう仕事は……」「なんだよ。同僚か?」タキは憮然とする。「ええ。スミマセン」ナボタタ・リゾートでは他客との直接接触は禁じられている。ビズに発展しかねないからだ。
一度取引先の人間と出会ってしまえば、豪華なリゾート休暇は露と消え、日常的上下関係に基づく社交レースが始まる。そうなれば台無しだ。だからルールで縛った。ネオサイタマ・サラリマンはそうでもしなければのんびり休めないと、アツバラ・シナキは経験則で知っていたのだ。
カレナは軽快な足取りで浜辺を歩くと、売店に目を留め、走っていく。タキはその尻を目で追った。だが直後、彼は大いに肝を冷やす羽目になった。「わたしピザを探してるんです。でも売ってなくて。ここにありますか!」
大声を上げるカレナに周囲の視線が集まった。だが誰も近づかない。「ピザです! ピザ!」カレナは二回も繰り返すと海に視線を向けた。タキは慌てて目を逸らし、サングラスを目深に被った。「お客様?」ウノエが尋ねた。「シーッ!」タキは手で口を覆った。「アレはヤベえやつだ」
#3
ティティ、ティティ……20分の仮眠を終えるアラームに、アツバラ・シナキはパチリと目を開けた。ナボタタ・リゾート社長室。海岸沿いの高級ホテル群の経営を行うその部屋は、対照的にひどく小ざっぱりとしている。質実剛健。彼の座右の銘だ。
トン、トン、トン。規則正しい3回のノック。「ドーゾ」「オジャマシマス」入ってきたのは山のような書類を抱えた女性。彼の秘書だ。「こちらの書類の確認をお願いしたく」「ウム」仕事量は普段にも増して多く、まとまった睡眠は取れていない。だが社長が弱音を吐くなど許されない。
「なかなかの量だな」アツバラは苦笑する。秘書は目を伏せ、言った。「やはりその、エドゥアルト=サンの件が」「フム……」エドゥアルト・ナランホ。リゾートの大口出資者であり、大株主でもある。その彼が死ねば経営の混乱は避けられない。備えはしていたが、それでもダメージは甚大だった。
惜しい男であった。アツバラは追想する。彼には有り余る才覚と、それをカネに替える行動力があった。ゆえに彼は、常に勝者だった。だが、乾いていた。常に数字を増やし続ける人生。それは見方を変えれば、数字の大小に全てを決められた奴隷であることに等しい。
理想もないままカネを貯めて、何になる。カネはあくまで手段であり、目的ではないというのに。(エドゥアルト=サン。お前は幸せだったのか?)初老の男は心中で手を合わせ、若者の死を悼んだ。だが立ち止まってはいられない。リゾートの経営は順調だ。ここでケチがついてはいけない。頬を叩いて気合を入れる。彼の責任は重い。
ナボタタ・リゾートの非日常体験は、エメツを触媒とした、アツバラの……ヴァーミリンガのジツで成立している。ニューロンとニューロンを術者を経由して半P2P的につなぐ、極めてユニークな複合ジツである。複合? 然り。1つは彼に憑依したダマシ・ニンジャクランのソウルに由来するもの。もう1つはサツガイに授けられたタナバタ・ニンジャクランの秘技だ。
「……」授けられた。ヴァーミリンガは顔を顰める。その体験を思い出す時、彼は憤りに駆られる。だがそれは過去だ。彼には今の生活があり、今の部下がある。守ってやらねばならない。
このリゾートは彼のカイシャであり、ドージョーでもある。ヴァーミリンガは高給を餌に、大望を抱く若者たちを集め、過酷な就労体験を通じて徹底的に鍛えあげる。脱出不可能なナボタタの地は、忍耐を鍛えるのにうってつけの舞台だった。忍耐。彼が最も尊ぶ言葉だ。全ての成功は忍耐から生じている。
無論、高給の話が立ち消えたわけでもない。リゾートでの就労期間中に渡されるのは小遣いめいた端金にすぎないが、稼いだカネはしっかりと記録され、貯蓄されているのだ。そして島を出る時、夢を叶えるための軍資金として手渡される。数年後、あるいは十年後に――
――愛する社員たちは忍耐の心と十分なカネを得て社会へと羽ばたいていくのだ。旅立ちの瞬間、彼らはどれほど喜んでくれるだろうか。その表情を想像するだけで、アツバラは頬がだらしなく緩むのを感じる。(ム。イカンな。これはイカン)頬を叩いてキアイを入れると、秘書が怪訝そうな目で見た。社長は咳払いでごまかす。タフであらねば。
その時、アイエエエ、アイエエエ……とドアの外から小さく声が聞こえた。声は近づき、続けざまに3回のノック。「ドーゾ」「オジャマシマス!」入室したのはベテランのヤシザキ。そして襟を掴まれ引きずられ、泣き叫んでいるのは新入社員のノリタだ。
「オジギだ!」ヤシザキが乱暴に背中を押し、ノリタを突き倒す。「アイエエエ!」「よせ」アツバラが手で制すと、ヤシザキは渋々引き下がった。
「アイエエエ……」ノリタはぐすぐすと涙を流し、顔を上げた。その先に恐怖存在がある。「アイエエエ! 社長!」「ノリタ=サン」アツバラはしゃがんで視線を合わせた。「気は変わらんか? ン?」口調こそ柔らかいが、その声に優しさの色はなく、処刑人めいて冷たい。「ア……ア……」ノリタは呻いた。社長は次の言葉を待った。やがてノリタは言った。「嫌です」「何?」
「もう嫌なんです! この島も! 島での生活も! 日本に帰りたい!」「ノリタ=サン!」アツバラは一喝!「ここに来た理由を思い出せ! その辛さこそがお前を一人前へと」「嫌です! 嫌なんです! 帰らせてください! アイエーエエエ!」ノリタは子供のように泣き叫ぶ!「もう嫌だーッ!」
「愚か者ーッ!」ヴァーミリンガはおもむろに立ち上がり右腕を振るった! 途端、ノリタの体はなにかに絡め取られ、無理やり立ち上がらせられていた!「アイエエエ!?」螺旋状に体を覆う冷たい金属の質感にノリタは恐怖した。「イヤーッ!」「アババババーッ!?」
おお……ナムサン! ヴァーミリンガが腕を引くと、ノリタの体はコマ回しめいて急回転! それだけではない! 全身に溝めいた傷が出来たかと思うと、勢いよく鮮血が噴出したではないか!「アバーッ!」薔薇めいて血を撒き散らす!
「フゥーッ……!」ヴァーミリンガはザンシンした。ノリタはやがて回転を終え、床に強かに頭を打ち付けた。もはや悲鳴も上げられず、喉を潰されたようなくぐもった音が出た。「しゃ、社長……!」秘書は絶句していた。ギュン、ギュン……ニンジャはムチめいた獲物を床を叩くように振って血を払うと、それを懐へとしまった。
「……愚か者……!」ヴァーミリンガは微かに声を震わせた。「社長……!」ヤシザキが呻いた。その目の端から大粒の涙がこぼれ落ちていた。「心中お察しいたします。一番辛いのは、社長であらせられるのに……!」「言うな……」社長は沈痛な面持ちで答えた。秘書がとうとう泣き出した。
ナムサン……彼はなぜこのような暴挙を? 社員を愛していたのではなかったのか? 然り。彼は社員を心の底から愛している。ゆえに命を奪ったのだ。ナボタタ・リゾートから逃げようとすることは、人生のあらゆる困難から逃げようとすることと同義である。それは忍耐の心から最も遠い行いだ。
忍耐を失ったものが夢を叶えることができようか? 答えは否である。であれば待ち受ける運命とは? 何も成し遂げられず、叶えられず、惨めに老いさらばえて死んでいくのだ。ヴァーミリンガは愛する社員にそんな人生を歩ませることを是としない。ゆえに命を奪った。未来を断つことで、未来から救ったのだ。
ナボタタ・リゾートの社員の大部分はその理屈を受け入れている。ノリタの死は、たかだか半年の連続勤務に耐えられない彼自身の責任なのだ。哀れみなど不要。
激痛と失血で、ノリタの意識は消えかけてしまっていた。(帰る……か、え、る……)彼はそれでも微かな力で床を這い、この場から逃げようとした。「アバッ」絞り出すような断末魔は、誰の耳にも届いていなかった。
一通り悲しみ終えたヴァーミリンガは、やがて息絶えたノリタを見留めた。「企業墳墓に丁重に葬ってやれ。オンセン・リゾート建設……その夢を追い、志半ばに斃れたセンシの屍をな」なんたる深い愛か! 社員たちはもはや涙を隠せず、一様に号泣した!「ウウーッ! 光栄です!」「慈悲深い!」ナムアミダブツ……!
ノリタの死体を運び出させると、アツバラは今日の来客者名簿へ手を伸ばし、パラパラとめくった。自身の夢の結晶がどれだけの善き人々を癒やしているか確認し、喪失感を埋めようとしたのだ。だが……「ム?」彼は顔をしかめた。「何だこの男は!?」
そこにはいかにも軽薄そうな面構えをしたハーフ・ガイジンの顔があった。「秘書ッ! 貴様か、此奴を島へ入れたのはッ!」「アイエエエ! 昨日は忙しかったのでチェックが甘く!」「言い訳無用! 反省文100枚だ!」「アイエーエエエ!」秘書は失禁!
アツバラは憤怒の表情で書類を吟味した。見れば見るほど締まりのない顔だ。人生において忍耐など経験したことのない男の顔だ! ピザ・タキ店主? 大方何の苦労もなく、父親の経営している店でも継いだのだろう! そのような男が俺の血と汗で築き上げたリゾートへと土足で踏み込んでいるとは!
彼の中でストーリーが紡ぎあげられていくとともに、ぶくぶくと憎悪が膨れ上がった。やがて想像の中のタキに唾を吐きかけられると、彼の怒りは頂点に達した!「担当は!」「ウノエ=サンです!」「よしッ!」彼は部下のニューロンに直接通信を繋いだ!「タキ=サンとやらをVIPルームへ案内しろ!」
#4
「そんな!」絶望的な指示にウノエは思わず呻いた。彼らは浜辺から少し離れた海上にいた。カレナの、いや、コトブキの捜索の目から逃れるためである。「オイ、どうした?」タキが怪訝そうに尋ねると、視線が左右に泳がされた。視界は共有している。「答えろよ」
「その……VIPルームにご招待するようにと」「マジでか!?」タキは思わず息を呑んだ。噂だけは聞いていた。一定回数の訪問か一定額の利用で招かれるという、伝説めいた最上級スウィート・ルーム!
そこにはあらゆる種類の薬物が用意され、副作用フリーで味わい尽くせるという。意識だけを共有し、肉体を共有しないナボタタのシステムが為せる技だ。とばっちりを食うのは従業員に任せ、客はただ快楽に溺れるだけでよい。なんたる退廃的かつ非人道的な快楽空間か……!
当初タキはこのVIPルームの噂を根拠に、検証と称して豪遊するだけして、作戦失敗に終わらせる腹積もりだった。だがまさか、実在したとは。「でもよ、なんだってこんな辺鄙な島に?」タキは内心の高鳴りを隠すようにもったいぶった。
「だからですよ、お客様。お硬いネオサイタマと違って、どの企業の目も届かない。真の無法地帯がここにあるんです」ウノエはすらすらとセールス・トークを並べた。地道な自己研鑽の為せる技だ。だができれば、使う機会は来ないでほしかった。
副作用フリー? それは脳以外の話だ。ミラーリングされたニューロンは薬物由来の快楽をダイレクトに受け取り、深く焼き付ける。そうなれば異常中毒者となるは必至。VIPルーム? 欺瞞だ。その実態は度の越えた迷惑客や産業スパイへの私刑部屋である……!
セールス・トークにいちいちタフぶるタキは、澄まし顔をしながら千切れんばかりに尻尾を振る犬めいていた。その純粋さがウノエに罪悪感を抱かせた。彼はそれなりに長い期間ここにいるが、VIPルームの利用経験はない。
無論、過酷なデトックス期間への恐れもある。だがそれ以上に。(これがお客様のためになるはずがない……!)長年刷り込まれた『客に奉仕せよ』という教えに反していたのだ。
(仕方ない、仕方ない、仕方ない……)ウノエは己に言い聞かせる。彼は何らかの偶然がこの退廃的インシデントを破壊してくれるのを願った。浜辺。海岸。屋台地帯を抜け、ホテルのロビーへ。起こるわけがない。「ウノエです。キーを」「……かしこまりました」受付嬢が一瞬視線を泳がせた。後ろめたさは同じか。それがウノエの心を少しだけ軽くした。
タキの観察眼は、彼らの不可解な動きに若干の危機感を抱かせた。だが未知の快楽への探究心が勝った。彼らはクルマに乗り込んだ。
窓の外では、海と空の境目に夕日が溶けはじめていた。浜辺から島の奥、中心部へと向かう車道を二人は進んでいく。車道の側面に森が混じり始めても、舗装は完璧で揺れ一つない。ウノエは速度を緩め、徐行運転していた。彼にできる最大限の抵抗だった。
彼らは知る由もないが、ここでクルマを降りて森を抜けていけば、そこには残り少ない現地住民が暮らす家屋地帯が広がっている。家屋は草やバンブーを組み合わせて作られた、自然と調和したトラディショナルな様式がほとんどだ。だがそれらの家々には、夕方だというのに明かりはまばらだ。簒奪者への無謀な抵抗の末路である。
自然との調和など、一個歯車である労働者には最も不要なものだ。それらはエドゥアルトの合理性にも、アツバラの思い描いたリゾートにも存在しないノイズだった。ゆえにその存在は黙殺され、打ち捨てられ、再利用を図られることすらなく、主の死とともにガラクタへと変わった。今や野生動物や巨大昆虫がその主である。
そして今、そんなことは誰も気にしない。ウノエにもタキにも、そこはただの未開発地帯に過ぎないのだ。彼らの目には、舗装アスファルトとガードレールだけが続く退屈な道だけが映っている。「海辺を出ると何もねえのな」タキがつまらなそうに呟くと、「そうですね」とウノエが同意した。
やがて二人の共有する目に、三つの建物が見えてくる。無駄な飾りのないビル。何らかの施設らしき平屋。そして最後の一つが……「アレだな」「ええ」それは欧風の洋館をイメージさせるヴィンテージ・スタイルの建物だった。「ゲストハウスです。取引先の方やリゾートにとって大切な方が宿泊されます」ウノエが説明した。
「フーン」タキは生返事した。どうにもいけ好かない建物だった。クルマを降り、白い砂利の質感をサンダル越しに感じながら、玄関へ。
他の客はいない。アツバラにとっても、儀礼的なもてなしなどしている暇はないのだ。靴の汚れを落としていると、もったいぶった速度で照明が灯った。暖色の光が豪奢な家財を照らし、シックな反射光が室内を彩った。
「「ヘェ……」」2人の反応は、このような景色に馴染まぬものに共通のものだった。「すごいでしょう。僕らもなかなか来れる場所じゃないんですよ」ウノエは笑いかけた。「アー、ウン、そうだな。なかなかだ」タキは格好をつけた。慣れない雰囲気だからだ。
「それで? どの部屋だ」「一番奥です」二人は豪華な調度品や絵画に傷をつけないよう、少々ギクシャクした動きで廊下の中央を歩いた。
ギィ……ドアを開くとともに、噎せ返るような薬物アロマの香りが噴き出す。部屋の中央にはキングサイズよりもなお大きなベッドと、淫靡な字体で『ヨシ』『ダメ』と印字されたハート型の2つのクッション。その前で足を組むホットなハワイアン・オイラン衣装の美女。タキの警戒心が掻き消えた。「な……なかなかだな」
「ゴユックリ」ウノエはそう言い残し、黙り込む。無論、彼らの五感は共有されており、痴態はウノエにも筒抜けとなる。気分の問題だ。
ベッドに腰を下ろすと沈み込むような柔らかさと心地よい弾力感。サイズも相当にデカく、上で何をしていても転げ落ちる心配は無用。「フーッ……」滾ってきた。タキは横目でオイランを見た。豊満の胸の谷間に何か挟んである。少々乱暴に掴み取る。「アーン……」オイランが身を捩らせた。
「注射器?」「オトオシドスエ」オイランが美しく微笑んだ。見ているだけで何でも出来そうになるほどの蠱惑的な笑み!「まあ、ウン」タキは知的さを演出しようとクールに言った。「なかなかだな」「ウフフ」オイランが笑った。「さ、ドーゾ」「おう」タキはぶっきらぼうに言った。こういうメリハリが女心を惹きつける。
醜態を演じるタキをその身に感じながらも、ウノエは落ち着かなかった。(本当にこれでいいのか?)彼の薬物耐性は低い。すでに思考はぼんやりと靄が掛かっている。それでも考えずにはいられなかった。(お客様にご奉仕するのが、俺の……)そこで彼は思い至る。その葛藤は彼自身のものではない。
(なら、誰の?)決まっている。社長の、アツバラのものだ。そしてタキをここに連れてくるように命令したのも彼だ。(じゃ、いいか)ウノエは思考を手放した。矛盾に苦しむくらいなら何も考えたくなかった。それに、もしこれで壊れてしまうのなら、それでも良かった。
タキは慣れた手付きで血管を探り、注射針を押し当てる。チクリとした痛み。未知なるエクスタシーの予感に彼は悶えた。オイランは人形のように美しく、無感情に微笑み続けていた。「さて、お手並み拝見と行こうかね」タキは生粋のアウトローめいてタフに決めた。その時だ。
「ハイヤーッ!」KRAAAAAAAAAASH!「「アイエエエ!?」」「アーレエエ!?」ドアを蹴破り、長く美しい黒髪の女性が飛び込んできたのだ!「カレナ=サン!?」ウノエは思わずその名を呼んだ。カレナは素早くベッドに飛び乗り、オイランの首筋にチョップした!「ゴメンナサイ! ハイヤーッ!」「アーレエエエ!?」昏倒!
「ア、ア……?」タキは注射器を持ったまま固まっていた。「タキ=サン! もう演技は大丈夫ですよ!」「ア? 演技? いやお前、そもそもナンデ……オイどうなってる! そいつはオレの……」滅茶苦茶に指し示す。「整理しましょう」コトブキは言った。その間もカレナは体を動かし、ドアをひとまず元の位置へ直した。
「ナボタタ・リゾートに潜入したわたしは、まずタキ=サンを探しました」「気づかなかったんじゃ……」「あれはわたしのウカツでした」コトブキは目を伏せた。「あんなやり方で探し回れば、タキ=サンと合流できても目をつけられてしまいます。咄嗟に他人のフリをしてくれて助かったんです」「ア?」
「とにかく、わたしはタキ=サンを見つけました。それでこっそり見ていたら様子がおかしくなったので後を着けたんです。ここでもタキ=サンの徐行運転に助けられました」「ア?」「おかげで生身で追えました。カレナ=サンの教えてくれた近道もありましたが……」
コトブキは振り返り、カレナを紹介しようとした。だがそこには当然誰もおらず、同じ体であることを思い出すと、バツが悪そうに胸に手を当てた。
「ドーモ、カレナです。アンタがタキ=サンね」「ア、ああ」タキは平静を装った。カレナはその手を取り、真っ直ぐに瞳を見た。「コトブキ=サンから話は聞いてる。頼りにさせてもらうわ」「話……?」答えたのはウノエだったが、カレナには分からない。「ヴァーミリンガをブチ殺すんでしょう?」「社長を殺すですって!?」
ウノエが素っ頓狂な声を上げた。「……?」カレナが眉を顰める。「その反応、ウノエ=サン? 意識があるの?」「みたいです」コトブキが言った。「おそらくウノエ=サンも協力者になってくれたのかと」「違うんじゃない?」「どうなんですか? タキ=サン」「え、あ、いや……待て」タキは額に手を当て、言った。「整理させろ」
#5
聡明なカレナにとって、ナボタタ島の大らかさは怠惰と同一だった。島は非効率と因習に支配され、論理は軽視され、集団的な感情が全てを取り決める。初めて大人たちの集会に参加する前夜、母に「大切な話がある」と呼び出されて教えられたのは、秘伝のポーク・チョップのレシピだった。
カレナは曲がったことが大嫌いだった。不正に悠然と歯向かい、矛盾を堂々と指摘し、虐げられる弱者を守った。しかしそれらを優しさと呼ばれることは嫌った。主題がズレていたからだ。それでも島民はこぞって彼女の優しさを称えた。
もっとも、それでカレナが島を嫌うこともなかった。口さがなく、融通の利かない彼女を島の人々は大らかに受け入れた。ここが帰る場所なのだと自然に思えたし、島に満ちる不満はゆっくりと時間を掛け、変えていけばいい。そう思っていた。
それが、今は、こうだ。「ザッケンナコラー!」「カエレ!」「バカ!」集会所に怒号めいた罵声が満ちている!
そこにはめったに使われないパイプ椅子が並び、新品のホワイトボードに『リゾート建設の意義が』の題字。設営は全体的に右に傾いている。慣れていないのだ。
先ほど登壇したエドゥなんたらいう投資家は、たかだが2、3の質疑応答でナボタタの大人たちを残らず憤激させ、理性を失わせた。その尻拭いめいて前に出てきたのが……確かアツバラ・シナキ。
「落ち着いてください」アツバラはハンケチで汗を拭う。「確かに我々は皆さんに立ち退きをお願いさせていただきますが、その分、十分な補償を用意しておりまして……」腰は低いが、話の内容としては投資家とさして変わらない。順番が逆ならともかく、これで場が収まるわけもなかった。「カエレ! バカ!」「スッゾー!」
「ちょっとみんな! 落ち着いて!」カレナは儀礼的に叫んだ。止まるわけはないが、後々冷静さを示す根拠となる。「これが止まれっかよ! 追い出すってんだよ! 俺たちを!」誰かが怒鳴った。「これはあくまで提案で……」「話にならない!」「それについては同感だ」投資家が低く言った。
「どうした?」アツバラの問いには答えず、エドゥアルトはおもむろに立ち上がる。「少しは楽しめるかと思ったが、興ざめだ。ここまで理性が足りんとショウにもならんよ。俺は帰る」「エドゥアルト=サン! 島民を煽らんでくれ!」「逃げるな!」誰かが野次った。「ハッ!」投資家は鼻で笑い、外へ出ようとした。そこに大柄な男が立ちふさがった。「ン?」
「マウイ=サンだ!」「ヤッチマエー!」誰かが口笛を吹いた。マウイは漁場で鍛え上げた筋肉を誇示する。「よう投資家さんよ。アンタ、ちょっとワガママすぎだ」マウイは不敵に笑う。「痛い目を見ねえうちに」「どけ」エドゥアルトは押しのけようとしたが、敵わない。敵わない?
ゴウ! 風めいた音が鳴り、マウイの姿が消えた。消えた? 消えてなどいない。それらは島の常識で予測した未来と現実の、認知の不整合が起こした錯覚に過ぎない。エドゥアルトが触れた途端、マウイはミイラめいた乾燥死体となり、いとも簡単に押しのけられ、壁にぶつかって砕けた。それが実際に起きたことだ。
「エ……」「マウイ=サン?」ナボタタの島民は、今起きたことを誰も理解出来なかった。投資家は一瞥だにせず外に消えた。「まるでニンジャ」誰かが言った。彼にとってそれは冗談のつもりだったのかもしれない。しかしそれは、あまりに的を射ていた。恐怖は具体的なイメージを与えられ、反響し、増幅する!「「「「アイエエエ!?」」」
「ニ、ニンジャ! ニンジャナンデ!?」「ミイラ!」「ニンジャ!」「落ち着いて!」カレナは叫んだ。打算を含む余裕はなかった。「ニンジャが……実在したんだ! 本当だったんだ!」「そうだ!」誰かの声が重なった。その場の視線が一斉に壇上へと集められた。
「……ケコア=サン?」カレナは呆然と呟いた。「ニンジャは実在する! そして……」彼は誇らしげにアツバラへ視線を向けた。何かを察したか、アツバラは止めようとした。間に合わない。「こちらのアツバラ=サンもニンジャ! その名もヴァーミリンガだ!」「「アイエエエ!?」」
その言葉が真実か否か、その場にいるものたちに知るすべはなかった。だが行き場のない恐怖感情は、アツバラがニンジャであるという認識を、貪欲に受け入れる! 「「アイエエエ!?」」出口に殺到!「やめ……アバーッ!?」「アイエエエ!」「アイエーエエエ!」「誰かーッ!」
最も出口に近かったのはラキだった。彼は転ぶように倒れたのを最後に、見えなくなった。人混みの中からくぐもった音が漏れていた。「愚か者!」「アイエエエ!」アツバラの叱責の声に、カレナは思わず振り向いた。
「若造どもめ……よくもこんな、取り返しのつかんことを……!」「ケコア=サン!」カレナは思わず幼馴染の名を呼んでいた。「ア、か……カレナ=サンじゃないか」ケコアの顔には、彼女が今まで見たことがないほどに醜悪な笑みが浮かんでいた。「……ナンデ?」カレナは呆然と言った。
「ナンデ? 愚問だね!」島長の孫はオーバーなゼスチュアを作った。「この島は古い! 排他的! ダメ! だから変えるんだ! デシケイター=サンとヴァーミリンガ=サン! そしてこの僕が!」「リゾートなんて! みんなの島が」「観光資源だ! それが経済だろ!?」ケコアは一笑に付す。
大言壮語を吐くが、主張にまるで具体性がない。いつものケコアだ。それが余計にカレナを混乱させた。気づけば両目から涙が溢れていた。理由はわからなかった。
口から血を垂らすラキを残し、他の大人は既に集会場から消えた。しかし彼らの目には最初からお互いしか映っていなかった。ケコアは勝ち誇るように言った。「そういうことだよカレナ=サン。だから僕はもう、君に――」
――――――――――
「カレナ=サン! カレナ=サン!」「ン……」誰かの声に、カレナは意識を取り戻す。「ここは」見慣れぬ場所。今のナボタタだ。「記憶は大丈夫ですか? 健康的?」口をついた他人の言葉にカレナは頷く。これも、今だ。
「良かった! 心配したんですよ」ゲストハウス2階。その廊下。「アタシは?」「薬物アロマにやられたんです。非常に危険な状態でした」コトブキは神妙に言った。「スミマセン。わたしには気づけなくって……」「そういえばアンタ、人間じゃなかったのよね」「ええ」
ウキヨのコトブキには薬物は効かない。だがカレナは違う。当初コトブキはそのことに気づかず、カレナが意識を失ってからもしばらくの間、平然と薬物アロマの中で会話していた。それがマズかった。その上カレナのニューロンは、ネオサイタマ育ちのタキやウノエと違い、極めてオーガニックだった。
「情けないとこ見せたわね」カレナは立ち上がろうとした。「いけません!」コトブキは座っていようとした。矛盾した二種類の命令はニューロンに認知エラーを引き起こす。「ンアーッ!?」結果、カレナは立ち上がりかけた体勢で転倒し、床に顔をぶつけることになった。「まあ!」コトブキが慌てる。
「やはり薬物が!」「アンタが余計なことするからよ」カレナは額を擦りながら言った。「体は基本的にアタシが動かす。必要になったら言って。アタシは動かない」「わかりました」コトブキがシュンとした。カレナは漸く立ち上がり、尋ねた。「UNIX探索はどう?」「ウノエ=サンとタキ=サンが」
ヴァーミリンガの暗殺。その荒唐無稽であまりにも唐突な計画に、当然ウノエは巻き込まれたくなかった。だがあの直後、カレナが彼の胸ぐらを掴み、なかば恫喝する形で説得したのだ。(アンタ、あんな死んだ目で一生ここで暮らす気?)(でも……)(ダメならいいわ。でもアタシたちがもし失敗したら、協力者にアンタの名前を出すわよ)
その言葉にウノエは簡単に折れた。意見を変えることには慣れていた。屈することにもだ。その場の恐怖から逃れられればいい。
ニンジャスレイヤーたちが立てた計画は極めてシンプルだった。タキとコトブキがリゾートに潜入。ゲストハウスに隠されたジツ制御UNIXに侵入し、ニンジャスレイヤーをニンジャの体へとニューロン接続させる。その体でヴァーミリンガを殺す。
ジツ制御UNIX? 然り。ヴァーミリンガは多忙な社長である。そんな彼がいちいち数百ものアカウントのアクセス管理など行ったりはしない。並行すればどちらかの作業に支障をきたすのは歴然だ。そこでUNIXが必要となる。デシケイターの資料……ヴァーミリンガの事業計画書に記されていた情報だった。
そして島の労働者名簿には、好都合にもブラックハチェットの名があった。タキが調べた範囲では無名の、おそらくさほど強力でないニンジャであり、その情報はカレナとウノエの証言で裏付けられた。ニンジャスレイヤーの弱体化は余儀ないだろうが、贅沢は言っていられない。
「カレナ=サン? 体は……」ウノエだ。「もういいわ。それよりUNIXは?」「まだです。でもタキ=サンが心当たりがあると」「ああ」タキが言った。「UNIXの特性を考えりゃ場所は絞り込める」
「特性ですか?」コトブキが問うた。タキは職人めいて腕を組み、頷いた。「いいか、当然だがUNIXは機械だ。電源がなきゃ動かねえし、故障だって起こす。定期的なメンテも必須だ」「していたんですか?」コトブキが目を丸くした。「当然だろ。俺はプロフェッショナルだぞ」タキは胸を張る。大きなエラーはないので、たぶんしている。
「で、そういう手がかかるマシンな上に、ぶっ壊れた時の対応もいる。ならどこかに隠すにしても、誰かがいたら入れねえ、なんて場所には隠さねえはずだ。クソほど不便だからな」タキは体験に基づいて言った。それが彼の言葉に説得力を生む。「なら地下ね」カレナが断定する。
「どうしてです?」ウノエが尋ねた。「施設はだいたい調べてる。ここ、少なくとも地上部分に隠し部屋だとか秘密の部屋なんてのはないわ。なら地下でしょ」「調べた?」タキが目ざとく聞いた。「アタシの目的のためにね」「フーン」彼は深入りしなかった。
「で、地下となると……一部屋しかないわね」カレナは何も告げず、早い足取りで階段を降りていく。「アッ、ちょっと……」ウノエが追おうとした。タキが足を止め、引き止めた。「まあ、ここはあいつらに任せようぜ」「ですが……」「他の部屋は俺が調べたんだ。ちょっとくらいサボってもバチは当たらねえ」
つい先程までウノエは上階を探索していた。その最中、タキは妙にカリカリしていたが、思考中に声を掛けられたくなかったのだろう。先の推察は見事なものだった。「フゥーッ……」タキは堂々と深い息を吐く。昼間の醜態が嘘のようだ。これが彼の本性なのか。
「ところでよ、ウノエ=サン。これはただの世間話なんだが。ログアウトって特別な操作がいんのか?」唐突にタキが言った。ウノエは戸惑いながらも答えた。「いえ、強く念じれば済むはずですが」「ア? じゃあなんでさっきから成功しねえ」「エッ?」「いや、なんでもねえ」タキはごまかした。
「ありました! 地下への入り口です!」やがて下階からカレナの……コトブキの声が聞こえると、彼らは立ち上がった。「推理通りですね」「マジかよ」「エッ?」
#6
ゲストハウス地下。『忍耐』の掛け軸裏に隠された入り口から梯子を降りた先は一本道の地下通路だ。足元のボンボリ・ライトが2つの体を照らす。4人は顔を見合わせ、カレナを先頭に、慎重に進んでいった。
暗闇の先には2人のクローンヤクザの人影。儀仗隊めいた姿勢でマシンガンを持っている。明らかな過剰戦力。偶然迷い込んだ人間への威圧目的か。その奥には扉。
「どうしましょう」コトブキが声を潜めた。「いきなり撃ってくるってことはなさそうね」カレナは推察する。リスクとリターンを天秤にかける猶予は彼らにはない。ヴァーミリンガはアカウント管理権限を持つ。侵入が露見すればニューロン接続は遮断されるだろう。
「アンタは足、アタシは腕」カレナは暗号めいて言うと、まっすぐにクローンヤクザの元へ向かった。銃口がカレナに向いた。「そこで止まって。部外者は立ち入り禁止です」クローンヤクザが言った。「撃たないで! 従業員です。アツバラ=サンにUNIXの調子を見るようにと」
「そういう連絡は来ていません」「エッ? そんなはずありません。確認してください!」強い調子で突っぱねるとクローンヤクザは顔を見合わせる。それは彼らの教育プログラムに特有の動きだった。ゆえにそれは明確な隙だった。コトブキは強く踏み込んだ!
途端に向けられる銃口! だが遅い!「ナンオラー!?」「ハイヤァーッ!」「グワーッ!?」「アバーッ!」カレナの手足は、まるで別の生き物が動かしているかのように同時に動いた。カレナの拳がクローンヤクザAの顔面を捉え、コトブキのハイキックがBの首筋を捉えた!
「ムン」Bは急所を蹴られ気絶! だがAは違う! 多少鍛えられてはいても所詮は闇雲な素人の拳だ!「ワドルナッケングラーッ!?」Aは砕けたサングラスには構わず発砲した!
「アッ……」カレナは死を覚悟し、絶望的なクロスガード体勢を取っていた。その合間も足だけが動いていた。緩急を付けたステップは、至近距離のクローンヤクザにとって瞬間消失の魔術めいていた。「アッコラーッ!?」弾丸は壁に衝突! 彼は照準を補正しようとした。「ハイーッ!」「アバーッ!?」コトブキのトーキックが喉を潰した!
「わたしが足です。先程も言いましたが、わたしは強いです。頼っていいんですよ!」「そうね」カレナは苦笑する。足の先にはゾッとしない感触があった。少なくとも、姿形は人間だ。
――――――――――
扉の奥に台座めいて安置されたUNIXデッキを、放射状に並んだ補助UNIXが取り囲んでいる。これらがヴァーミリンガのジツ制御を代行し、同時多数並列ニューロン接続を可能としているのだ。「ではタキ=サン」「おう」タキはウノエの首筋からLANケーブルを伸ばし、接続した。
ウノエは一瞬痙攣した。ナボタタ・リゾート従業員には全員、生体LAN端子がついている。それはアツバラがあった方が便利だろうと考え、参考書を買ってやるような気安さで開通させたものだった。しかしタキの意識がコトダマ空間にダイヴしている間、非認識者たるウノエにできることはない。
無論、何もできないのはコトブキたちも同じだ。「危うく死にかけたわ」「スミマセン」「お礼よ、これは」カレナは自嘲げに言った。「鍛えたつもりだけど。全然ダメね」「大丈夫です」コトブキは笑いかけた。
「わたしはカレナ=サンを応援してます! ともに頑張りましょう! 悪いニンジャから故郷を取り戻すんです! ガンバロ!」しかし彼女が想像したような反応はなかった。「……ちょっと誤解があるわね」カレナは顔を顰めていた。「誤解?」コトブキは聞き返す。
「別にアイツに恨みはないわ」「エッ?」コトブキは耳を疑った。「変な話だけどさ」カレナは前置きした。「この島は確かに古かった。アタシが島を変えるのが先か、世界がこの島を踏みにじるのが先か。どちらかだと思ってた」「え、ええ」コトブキは意図が飲み込めない。
「つまりさ、こういうカタストロフはいつか来るって思ってたのよ。その実行役がたまたまアイツだった。だから特別な恨みとか、別にないの」カレナはあっけらかんと言った。
「エ、ちょ、ちょっと待ってください! ヴァーミリンガはナボタタの皆さんにひどいことを……」「確かに切っ掛けはアイツね。でもこっちにも非はあるわ」カレナは他人事めいて冷静だった。それがコトブキを余計に戸惑わせた。
「アイツの部下を何人も殺した。見せしめよ。直接戦えば絶対に勝てないものね」「それは……でも」「これは現実よ」カレナは言った。「どっちが絶対に悪いなんて、ない」
「それに故郷を取り戻すって何。今更取り戻してどうするの?」「エッ、そ、それは……」コトブキはたじろぐ。部外者視点が怒らせてしまったのか。違う。カレナの声色は平静なままだ。「仮に支配権を取り戻せても開発は済んでる。元の生活なんて絶対に無理。ナボタタ島はもう、死んでるのよ」
「……わかりません……」コトブキは考え込む。彼女の経験は、それがカレナという人間なのだと明確なアンサーを出していた。だがその思考に、捉え方に、うまく馴染めなかった。カレナは頭を掻いた。
「別に混乱させる気はなかったんだけど。……ともかく、アイツを殺すところまでは利害は共通してる。今は力を合わせましょう」「ならどうしてカレナ=サンは彼を?」「目的はその影」「影?」
「もう話したでしょ。島にアイツを呼び込んだ男のこと」「ケコア=サンのことですか?」「そう」カレナの声色が初めて感情を帯びた。
「アイツは島長の一族なのよ。土地の権利を受け継いだ。発展させる義務があった。でも全てを投げ出して、破滅を呼び込んだ。それが許せない。あの男だけはこの手で殺す。両手両足を撃ち抜いて、ブザマに命乞いをさせて、肺を撃ち抜いて殺すの。今のアタシはそのためだけに生きてる」
コトブキは口を挟もうとし、逡巡し、やめた。何を言えばいいのか、何を言うべきなのか、そして自分が何を言いたいのか、何一つわからなかった。やがてモニタに文字が浮かび上がった。
『ここは終わったぜ』
#7
「イヤーッ!」「「アイエエエ!」」「イヤーッ!」「「アイエエエ!」」ブラックハチェット……否。それは今やニンジャスレイヤーであった。彼が動作確認めいたカラテ演舞を終えると、取り巻かされていた哀れな過剰勤労働者たちは気絶した。
彼は舌打ちした。何だこの体は? 鈍く、固く、しなやかさに欠ける。その上……「オイ! テメエ!」ニンジャスレイヤーの口が言った。
「お前誰だ。ニンジャだな!? どうやって俺にログイン……」「黙れ……!」強烈な殺意がニューロンを満たす!「アババババーッ!?」ブラックハチェットの意識は悶絶し、ニューロンの片隅に押し込まれ、一切の意思決定を封じられた。ナラク・ニンジャの手綱すら握る強靭な精神力に、サンシタが太刀打ちできる道理などない。
『オイ、ニンジャスレイヤー=サン』タキからIRC通信。普段ニンジャスレイヤーが使用するものと違い、UNIXと携帯端末によるベーシックなものだ。今の彼に使えるのは、この弱体ニンジャの能力が全てである。
『乗り移れたよな?』「ああ」『そりゃいい。マズいことになった。オレのせいじゃねえが……』「話せ」『UNIXがもう1台ある。ハッキングを手伝え。道路の先にいる』「分かった」通信断絶。地下から飛び出す!
彼は色付きの風めいた速さで疾走し、ゲストハウスへと向かった。すでにタキは地上へと出ていた。「お前がタキ=サンか?」ニンジャスレイヤーは問うた。「見りゃわか……んねえのか」タキは唸った。「つーかお前、何だその……まあいい」「ああ」
既に夜闇が訪れ、月光が白い砂利をつやつやと照らしている。2人はザッザッと音を立てて歩いた。体は従業員ゆえ不自然性はない。「要するにだ」タキは説明する。
「お前が野郎とカラテして、ブッ殺しかけたとする。だが奴はいつでも逃げられる」「強制ログアウトか」「ああ。防ぐためには要求を突っぱねる権限がいる。それが1つ目のUNIXだ。それはもう確保した」「もう1台あるが」「それが問題だ」
「奴とそのUNIX。2つのアカウントから要求されれば、こっちが抵抗しても無駄だ。多数決だからな」「ならばそのUNIXも奪う」「最終的にはそうだがよ……」タキは立ち止まった。
「そもそも2台あるのが妙なんだ。いいか。オレとお前が言い争いしてるとする。オレが『行かねえ』。お前が『行く』。するとどうなる」「何も起こらんな」ニンジャスレイヤーは余計な口を挟まない。喩え話だからだ。「そうだ。だがな、ここにコトブキのやつがいたとする」
「コイツはお前にいつも賛成だ。じゃあどうなる」「おれの提案が通るな」「そうだ」タキは頷く。「つまりだな。このジツ管理システムは狂ってやがるんだ」「狂う?」「ピザタキと同じだ。店主がオレなのに、クソみてえな居候がいれば、その意見が反映されなくなる。立場が弱いんだ。アワレだろ」
「……奴がそんな配置をするメリットは薄い、ということか」ニンジャスレイヤーは最後の言葉を意図的に無視した。「ああ」タキは頷く。「じゃあアイツは、わざわざ自分が不利になるようにUNIXを設置したってことになる。つまり……」「罠だ」ニンジャスレイヤーは断言した。「だな」
タキはため息を吐く。「そんでオレたちは、そこに飛び込むしかねえってことだ」「罠ごと潰すだけだ」死神は決断的に言った。「どの道、奴は殺す。障害が一つ増えただけだ」「ああ、そうかよ」タキはかぶりを振った。ログアウト不能の恐怖は呆れの中で薄まった。ウノエは静かにしていた。口を挟める知識は彼にはない。
「せいぜい頼りにさせてもらうぜ」「そうしろ。UNIXはどこだ」「あそこだ」タキは本社ビルを指した。「通信速度とping応答時間で測った。まず間違いねえ。だが騒ぎは起こすなよ」タキは注意する。ニンジャスレイヤーがBANされれば、詰みだ。
「珍しく乗り気だな?」「でないとオレがログアウトできねえ」「お前が?」「封じられた。奴は恐れてやがんだ。テンサイ級ハッカーのオレをな」タキは時系列を意図的に無視した。「そうか」
――――――――――
本社ビルは煌々とした光を放っていた。既に終業時間は大幅に超過しているが誰も帰ろうとはしない。忍耐を養うためだ。今苦しめば苦しむほど、よりよい未来が待っている。受付嬢の瞳には、濁った光が穏やかに輝いていた。「オコシヤス」
来客者はウノエとブラックハチェット。ともに本社勤務ではない。彼女は多少訝しむ。ニンジャが口を開く。「用事がある。多少中を回る」「エッ?」明らかに不自然な言葉に、彼女は聞き返す。「どうしてですか? 正当な理由を……」瞬間、笑顔が凍った。
「今、おれに意見したか」ブラックハチェットからドス黒い殺気が発された。彼女もその暴虐ぶりは知っている。だがアトモスフィアが違った。それは疎放な暴威ではなく、洗練された刃物めいていた。「い、いえ」「余計な詮索はするな」「ハイ」
かくしてニンジャスレイヤーらは穏便に本社ビル内へと足を踏み入れた。彼らは真っ先に倉庫へ向かったが、そこには何もなかった。その後も彼らは次々にフロアを探索し、UNIXデッキを探した。
ブラックハチェットの姿は効果覿面だった。社員は彼らを一目見るだけで一様にドゲザし、口を出さなかった。タキにもウノエにもその恐怖は分かった。だが何か妙だった。どこかアトモスフィアが違う。
「あいつら喜んでねえか?」3階の物置で、タキはとうとうその疑問を口に出した。それは彼が感じていた違和感を最も端的に表した言葉だった。「そのようだ」ニンジャスレイヤーが同意した。「何でだよ。変態か?」「どうでもいい。この状況は利用できる」彼は備品を音もなく破壊しながら言った。
だがタキには何か気がかりだった。どこか不気味で、落ち着かない。彼は尋ねた。「オイ、ウノエ=サン」「エッ?」急に話題を振られ、ウノエは戸惑った。「こいつらなんなんだ。何考えてやがる」「さあ……そうですね」ウノエは考えながら答えた。「忍耐でしょうか」「忍耐?」「ええ。苦しめば苦しむほど強くなれる。そういう企業風土なんです」
「要は全員マゾ野郎ってことかよ」タキはせせら笑う。卑近な言葉を使うことで不気味さが和らいだ。ウノエは否定した。「違いますよ。これは試練です」何年勤務しても忍耐を獲得できない自分を恥じるように、彼は苦笑していた。「ニンジャに脅されるのも、過剰勤務も、全部人生の試練なんです。試練に忍耐することで人は強くなれるんですよ」
「ン? エ? ハ?」タキは目を白黒させた。何かがおかしい。「タキ=サンも色々大変みたいですけど……」ウノエは羨むように言った。タキは彼と違い自立している。忍耐がある。試練を力に変えられる。「その苦難はきっとタキ=サンを一回り強くしてくれますよ。試練に感謝ですね」
「ハ?」ぞわりとした悪寒に、タキは凍りつく。それは隣人の顔の皮が剥がれ、中から爬虫類の顔が出てきた時のような嫌悪感だった。「何言ってんだ、お前」「エッ? 僕は……」「クソなもんはクソだろうが!」タキは思わず声に出していた。ますます怒りがこみ上げた。
「だいたいあの時からそうなんだ。オレを散々こき使いやがって。何が貸しだ! オレが気の毒だ。アワレだぜ! あのクソニンジャ野郎!」「おれを呼んだか」ニンジャスレイヤーが作業の手を止めた。「……ヴァーミリンガとかいうクソ野郎!」
タキは慌てて取り繕った。フロア内のものには聞こえただろうが、構わなかった。どうせここのクソどもには何も出来まいからだ。ニンジャスレイヤーは作業に戻った。
静寂が場を支配した。「ケッ」タキは吐き捨てた。だが沈黙が続くと、やがてウノエに問うた。「お前も野郎に恨みとかねえのかよ」「恨み」ウノエはオウムめいて返した。「そうだ。なんかあんだろ?」「……夢」
反射的にその言葉を口に出した瞬間、ウノエは慄いた。それは思考停止が、無意識下にかけられたロックを外したことによる、押し込めていたものの噴出だった。途端に彼は、心臓が握りつぶされそうな恐怖を感じた。
「夢?」タキが聞いた。ニンジャスレイヤーは手を動かす。「夢が、あったんです」「どんな夢だよ」「わかりません」ウノエの声は震えていた。タキは呆れた。「わからねえ? なら……」「わからないんです。でも。……大切なんだ。大切だったんです。大切な……」それは自問めいていた。
タキは閉口した。このクソリゾートの連中が、ますます分からなくなった。「……ここにはない。次に行くぞ」ニンジャスレイヤーが言った。
――――――――――
それから数分後。ニューロンがちりつき、ヴァーミリンガにアクセス権限の変更をアラートした。彼は目を細めた。二台目のUNIXを掌握したか。「来るか」彼は不敵に笑った。
#8
ナボタタ・リゾート5階。社長室の隣室は、極めて殺風景な応接間。つまり、そういう手合のためのものだ。ドン、ドン。乱暴なノックが2回鳴ると社長は苦笑した。「ドーゾ」返答はない。社長は立ち上がり、訪問者を呼んだ。「入ってくるがいい! ニンジャスレイヤー=サン!」
「イヤーッ!」KRAAAAAAASH! ドアが蹴り飛ばされる! それは身構えるヴァーミリンガに弾丸めいた速度で飛来する!
「イヤーッ!」裏拳で叩き落とす! コンパクトな打撃ゆえ後隙は軽微。即座に対空ポン・パンチの構えに移る! ドア弾の対処直後の隙を狙ったニンジャスレイヤーは作戦変更を強いられる! その思考猶予時間、わずかコンマゼロ数秒!「イヤーッ!」
「何!」ヴァーミリンガの拳は空を切った。死神は空中で姿勢転換し、敵の伸ばした右拳を支点に再跳躍したのだ! 天井の隅へ飛び、そのままトライアングル・リープを決め……その時、ニンジャ第六感が警鐘を鳴らす!「イヤーッ!」リープ中断! 垂直落下し、ブレイクダンスめいた動きで隙を殺す!
「フ……」ヴァーミリンガは微笑した。彼は伸ばした腕を、半ば緩慢とすら言える速度で戻し、敵へと向き直った。それは余裕の表れだった。死神は先手を取ってオジギした。
「ドーモ、ヴァーミリンガ=サン。ニンジャスレイヤーです」「ドーモ、ニンジャスレイヤー=サン。ヴァーミリンガです」社長は死神の目を見、口元を歪めた。「気になっているようだな。なぜワシが、貴様の襲撃を予見しておったか……」
「どうでもいい」ニンジャスレイヤーは遮った。「サツガイという男を知っているか」「ハッ!」ヴァーミリンガは苦笑した。「愛想のない男よ! ……しかしサツガイ。サツガイとな。まあ、サンズ・オブ・ケオスの連中を狩ってきたとなれば当然の帰結よな」
「知っているのならば、話せ」「よかろう」彼はカラテ警戒を解いた。死神は眉根を寄せる。
「……あれは数年前か。ワシがニンジャとなり、独立したばかりのことよ」ヴァーミリンガは無防備に目を閉じ、述懐した。「取引先のビル。そこに奴は突如として現れた。トリイ・ゲートの向こうからな」「トリイ?」
「然り」社長は頷く。「無論、元よりあったものではない。何というべきか……2つの景色が重なり合っているようだった。現実と、超自然の景色が」彼は憎々しげに続けた。「襲来の予兆とでも言うべきか。スリケンが乱れ飛び、その場にいたモータルを殺した。乱れ八ツ刃のスリケンだった」
「……!」ニンジャスレイヤーの体からオーラめいて憎悪が噴出した。「皆殺しだ。取引先のものも、ワシの大切な部下どももな」「何故だ」押し殺したような響きの言葉に、ヴァーミリンガは冷徹に答える。「知らぬ。そもそもあれに理由があるのか? あれは天災だ。超自然の災厄ぞ」
「哲学めいた話はどうでもいい」ニンジャスレイヤーは低く言った。「他は。貴様は何を知る」「その程度よ。ワシは……情けない話ではあるが……身動き一つ取れなかった。奴はそんなワシにジツを授け、いずこかに去った」ヴァーミリンガの瞳が一瞬、後悔に揺れた。だがすぐに収まる。
「ワシの話はこれで終わりだ。これ以上を知りたくば、次なるニンジャを追うがいい」「その名は」「まあ待て」手を伸ばし、遮る。「ワシは貴様の質問に答えた。次は貴様がワシの質問に答えよ」
ニンジャスレイヤーは当然この問いには答えず、即座に暴力に訴えようとした。だが止まった。礼儀作法が彼を縛っていた。問い返し……平安時代より連なるニンジャの礼儀作法である。「サツガイを知り、なんとする」「殺す」死神は即答した。「ほう!」ヴァーミリンガは目を丸くした。
「あれは超次元の怪物ぞ。それを殺すと?」「おれに二言はない」その言葉には強靭な意思の重みがある。ヴァーミリンガは目を細めた。「なるほど。ならば……ニンジャスレイヤー=サン。貴様に提案がある」彼は厳かに言った。「ワシの部下になれ」「何……?」
「考えても見よ。貴様がやつに勝てる道理があるか?」「道理の問題ではない。殺す」「ワシにたやすくアンブッシュを防がれる程度のワザマエでか?」「……」ニンジャスレイヤーは一瞬言葉をつまらせた。ヴァーミリンガは滔々と言った。「貴様は実際それなりに強い。それは認めよう」
「だがそれに何の意味がある。敵は埒外ぞ」「何が言いたい」「今の貴様ではサツガイに勝てん」彼は断定した。「なれば貴様に必要なのは何か、分かるか?」彼は答えを待たずに続けた。「忍耐だ。ただ只管にカラテを鍛え、イクサすることよ」
「ワシの部下となれば、直々に稽古をつけてやる。それが物足りなくなれば、より強き者を紹介してやろう。コネを通じてイクサも与えてやる。その繰り返しだ。貴様のカラテは効率的に研ぎ澄まされ、極限まで鍛え上げられる。サツガイに挑むのはそれからだ」
「……」ニンジャスレイヤーは答えない。それを肯定と見たか、社長は呵呵と笑った。「どうだ、ニンジャスレイヤー=サン。ワシの部下になるか?」
「だいたいわかった」ニンジャスレイヤーは言った。「ならば」「お前はここで殺す」死神はカラテを構えた。「何……」「黙って聞いていれば、くだらん話をべらべらと。おれの道はおれが決める」「それでサツガイを殺せると? そんなことは」「二言はない、とおれは言ったぞ」彼は決断的に言った。
「おれがお前に選ばせてやるのは2つだ。ニンジャの名を吐くか、吐かされるかだ。今すぐに選べ」「なんたる増上慢!」ヴァーミリンガは唸った。「……だがそれでこそよな!」そしてカラテを構えた!
「来い! ニンジャスレイヤー=サン! 貴様に敗北を教えてやろう!」「イヤーッ!」ニンジャスレイヤーが挑みかかる!
――――――――――
ゲストハウス地下。「タキ=サンがシステム・トラップを仕掛け終えました」コトブキが言った。「ヴァーミリンガがログアウト……つまり死ぬと、偽の退避命令が出ます。皆さんを逃さねばなりません」「皆さん、ね」カレナは言った。
「……社長が死ねば、ウノエ=サンや……カレナ=サンは相当恨まれるはずです。従業員の皆さんも大変困りますから。困らせたいわけではないですが……実際困ります。逃げなければ」「そう」カレナは聞き流す。「実際危険です」コトブキは続けた。
それから彼女は、しばらく言葉を並べ続けた。間をつなぐように。会話の終わりを拒むかのように。「……そろそろ終わった?」やがてカレナが遮った。重い沈黙が場を支配した。数十秒、あるいは数分の沈黙の後、カレナは言った。「ねえ、コトブキ=サン。アンタ、何か勘違いをしてない?」
「これはビズよ。アンタたちがヴァーミリンガを殺す、その協力をする。代わりにアタシは目的を果たす」「その先は」「何様のつもり? アンタに言う必要はないわ」コトブキは黙り込む。カレナは呆れたように問う。「何。まだ何か言いたいことでもあるの?」
「……キタノ・スクエアビル」「え?」意図の分からぬ言葉に、カレナは聞き返す。コトブキは続けた。「ネオサイタマの商業施設です。その地下にピザ・タキがあります。わたしはそこで働いています」「何を……」「会いに来てください」コトブキは言い切った。
カレナはその言葉に奇妙な力強さを感じた。だがそれも、今の彼女にはどうでもいいものだった。
「行けたら行くわ」カレナは無感情に答え、話題を打ち切った。それきりコトブキも黙り込んだ。カレナは黙考する。もうすぐだ。もうすぐ全てが終わる。あの時から続いてきた苦しいだけの時間が。あの男の死とともに。
――――――――――
「イヤーッ!」「グワーッ!」「イヤーッ!」「グワーッ!」「イヤーッ!」「グワーッ!」ヴァーミリンガは渾身の溜めを作り、解き放つ!「イイイイ……ヤアアーッ!」「グワーッ!」渾身の右ストレートがニンジャスレイヤーを壁面に叩きつけた!
「どうした、ニンジャスレイヤー=サン。立派なのは口先だけか?」彼はざしざしと歩み寄る。「ほざけ……!」死神は向き直った。「いい目をしておる……何事にも屈さぬ、忍耐を知る男の目だ」ヴァーミリンガは言った。「だが足りぬ。もっと苦しまねば上には行けん」「黙れ」
「そのためには……ここは手狭よな! イヤーッ!」トビゲリだ! だがその狙いはニンジャスレイヤーではない。窓を蹴り割り、5階の高さから飛び降りる!「追ってくるがいい! ニンジャスレイヤー=サン!」「イヤーッ!」死神は後に続く!
ニンジャ装束を夜闇にはためかせ、2人のニンジャは落下する。上を取るのは当然、ニンジャスレイヤーだ!「イヤーッ!」スリケン連続投擲! 位置エネルギーを加えヴァーミリンガを狙う!「イヤーッ!」ギギギン! 甲高い金属音が響いた。金属質の何かがスリケンを弾いたのだ。だが闇に紛れて見えない。
2人の体は本社ビルの隣、何らかの施設めいた平屋へと落下していった。「イヤーッ!」ヴァーミリンガはギリギリまでスリケンを弾くと、カワラワリの構えに移った。「イヤーッ!」スリケン!「グワーッ!」体を微細に動かし、致命傷回避!「……イヤーッ!」衝突直前に拳を振り下ろす!
KRAAAAAAAAAAASH! 凄まじい破壊音とともに天井が砕け、侵入経路が確保された!「イイヤアアーッ!」ニンジャスレイヤーは破砕粉塵の中へとスリケンを連続投擲し、対空迎撃の余裕を殺さんとした。
「イヤーッ!」煙の中からヤリめいて何かが突き出す!「イヤーッ!」死神は投擲を中断、隆起箇所を掴み、空中座標を強引に変えた! 何かは空を切り、煙の中へ戻った。彼は飛び込んだ!
前転で落下ダメージを殺し、ニンジャスレイヤーは即座にカラテ警戒した。タタミ数十枚ほどの開けた空間には、壁や天井を除き、行動を阻害するオブジェクトが一切ない。「お気に召したかね、ニンジャスレイヤー=サン」背後から声!「イヤーッ!」連続側転で距離を取り、向き直る。
「ここはワシの専用カラテ・トレーニンググラウンドよ。貴様もここで修練を積むこととなろう」「落下の際に頭でも打ったか。だが殺す」「それは無理だ。何故なら」ギュパン! ギュパン! ヴァーミリンガが腕を振るたび、重量物が空を切る音が鳴り響いた。その手には表面のみを鉤爪めいた逆棘に覆われた奇怪なムチがある!
「これはアリクイ・シタ・ムチだ。ニンジャスレイヤー=サン」ヴァーミリンガはムチを両手で伸ばしてみせた。手の端からムチの先端がこぼれ、ヘビめいてとぐろを巻いている。凄まじい長さだ。「表面の鉤爪が見えるな? これがカエシだ。一度食い込めば容易に離れん。肉を引き裂き、爆ぜさせるまではな」
「よく喋る男だ」「これから貴様の身に起こることを伝えておかねばならんのでな」ギュパン、ギュパン……金属質の細工で覆われたムチは、まるでそんなものがないかのように宙を舞う。強靭なニンジャ膂力の為せる技だ。「恐怖は筋肉を硬くする……より痛くなるぞ」ヴァーミリンガは笑った。「……」ニンジャスレイヤーが睨めつける……!
「イヤーッ!」ニンジャスレイヤーは右後ろにバク転し、スリケン連続投擲!「イヤーッ!」ムチが叩き落とす!「イヤーッ!」スリケン!「イヤーッ!」ムチ!「イヤーッ!」スリケン!「イヤーッ!」ムチが伸び切った。敵の手元に引き返す暇もあればこそ、死神は飛びかかる!
「甘いわ!」ギュオン! ムチは右ベクトルをキープしつつ、より力強く加速。ヴァーミリンガの周囲を一周した!「ヌウーッ!?」ニンジャスレイヤーの拳の先に、凶悪なカエシの付いたムチの表面がある! 拳を引く! 間に合わぬ!
「グワーッ!」右手の甲を強打!「イヤーッ!」インパクトの瞬間、ムチの運動エネルギーがゼロとなる刹那、ヴァーミリンガは思い切りムチを引いた!「イヤーッ!」「グワーッ!?」手の甲にカエシが突き刺さる!「グッハハハ!」ヴァーミリンガはムチを振り上げ、拳破壊を狙う!
「イヤーッ!」ニンジャスレイヤーは反射的にカエシを掴み、あえてムチの動作に合わせて飛んだ。拳破壊回避!「ほう!」ヴァーミリンガはムチを引く!「……!」このまま付き合えばジリー・プアー(徐々に不利)か。死神は拳を抑えた!「グワーッ!」手の甲が引き裂かれ、肉が爆ぜた! だが破壊は最小限に留まる!
「ヌウーッ……!」拘束を解除し、再び距離を取る。接近するにもあのムチが厄介だ。潰さねばならぬ。だが、その手段は? ギュパン、ギュパン……ムチが威圧的に空を舞う。過去にもこのようなことがあった。あのとき彼は撤退を選んだ。今回もそうするか? 否。断じて否! ヴァーミリンガはサツガイに連なるニンジャなのだ!
「イヤーッ!」ニンジャスレイヤーの目が殺意に燃えた! スリケンを連続投擲し、グラウンド内周を連続側転で旋回!「何をするかと思えば!」ギギギギン! 激しい金属音とともに全てのスリケンが叩き落される。「イヤーッ!」更にムチを伸ばし、ニンジャスレイヤーを狙う! ここまでは同じだ。だが!
「イヤーッ!」連続側転の体勢のまま、彼は空中で片手を伸ばし、ムチの先端を掴んだ!「取ったぞ……!」ムチの内側にはカエシはない! ニンジャスレイヤーはムチの先端を握り潰し、思い切り横回転した! 遠心力によってヴァーミリンガをムチごと手繰り寄せ、殺害する腹積もりだ!「イイイ……ヤアアアーッ!」だが敵は即座にムチから手を離していた!
「そんなに欲しくばくれてやろう!」ヴァーミリンガはほくそ笑む。確かにムチは奪われた。だが今のニンジャスレイヤーは、自ら巨大なロープによって拘束されに行くに等しい。彼はただ、ムチの回転に巻き込まれぬよう接近すれば良いのだ!(これが経験の差! 実力の差よ!)
「イヤアアアーッ!」ヴァーミリンガは連続側転を打ち、ニンジャスレイヤーに近づいていく! ニンジャスレイヤーは回転を継続! アブナイ! このまま回転を止めねば雁字搦めとなってしまうぞ!「イイヤアアアアーッ!」だがニンジャスレイヤーはむしろ回転を早め、思い切りムチを巻き取った!
(何!)ヴァーミリンガは困惑した。自殺行為! だが彼とて急に行動を変えることは出来ぬ!「イヤーッ!」ただ連続側転の終点で跳躍し、速度を乗せたチョップを繰り出すのみだ!
ドクン! その瞬間、時間認識が泥めいて鈍化した。ニンジャスレイヤーの回転は想像より早く、ムチを全身に巻き取っていた。そしてその中心、ムチの持ち手に手が届くまで到達すると、絶妙な力加減によって、カセットテープめいてムチをたるませたのだ!
交錯の刹那、ヴァーミリンガの目に映るのは、台風の目めいた半径1mほどの空間に佇むニンジャスレイヤーだ!「馬鹿な!」死神は体を沈ませ、チョップを回避! 直後、角度90度の対空ポムポム・パンチを放った!
「イヤーッ!」「グワーッ!?」ヴァーミリンガは空中に吹き飛ぶ! ギュパン! その耳に聞き慣れた金属音! 死神は既に、散々彼を苦しませた凶悪なカエシの付いたムチを握っている!
「イイヤアアーッ!」ギュルルルル! 重い音とともにに振り上げられたムチはヴァーミリンガの腹筋を強打!「グワーッ!」インパクトの刹那、ニンジャスレイヤーはムチを思い切り引いた!「グワーッ!?」インガオホー! カエシが突き刺さる! 彼は思わず腹を抑えた。腹の皮を破られれば、さしものニンジャとて内臓を露出させて死ぬ!
ニンジャスレイヤーはその機を逃さぬ! 巨大な鎖鉄球めいて、ヴァーミリンガの体を壁に叩きつけた!「イヤーッ!」「グワーッ!?」右!「イヤーッ!」「グワーッ!」左!「イヤーッ!」「グ……グハハハハ! やりお……」右!「イヤーッ!」「グワーッ! ……やりおるわ!」左!「イヤーッ!」「イヤーッ!」空を裂くカラテ・シャウトとともにヴァーミリンガは拘束から解き放たれた! だが腹部は爆ぜぬ!
それは何故か!? ニンジャ動体視力をお持ちの読者の方は、彼の腹部に着目されたし! そこには未だ逆棘が突き刺さったままだ! 異常な腹筋の収縮、そしてニンジャ握力が逆棘をムチの根本からへし折ったのだ!
「ヌウーッ!?」ニンジャスレイヤーはすでに、鉄球叩きつけめいた一連のルーティーン動作の中にある。その隙をヴァーミリンガは見逃さぬ! 振り回された力を利用し、強力なトライアングル・リープからトビゲリを放った!「イヤーッ!」「グワーッ!?」ニンジャスレイヤーはムチを手離す!
「返してもらうぞ! イヤーッ!」「グワーッ!」背中にコンパクトなパンチを二撃!「イヤーッ!」「グワーッ!?」逆に膝を折るがごとく強烈な水面蹴り!「イヤーッ!」「グワーッ!」体勢を崩した死神を背中から蹴り上げる! ギュパン! ムチを確保!
「終わりだ、ニンジャスレイヤー=サン! イイイヤアアアアアーッ!」ヴァーミリンガは自身を支点に高速回転! その手に握られたムチは、凶悪な螺旋軌道を描き、突発台風めいて空中のニンジャスレイヤーを襲う! 鉄の螺旋が彼を背後から捕らえんと迫る!
「グ……!」ニンジャスレイヤーは呻く。背後より鈍い金属が空を裂く音が、巻き起こされた旋風が迫る! 視界の両端が凶悪な逆棘の渦に覆われる! カエシを引き抜いた痛みがフラッシュバックする! 回避手段は……ない!「グワアアアアアーッ!!!」ニンジャスレイヤーの絶叫とともに、螺旋竜巻は赤く染め上げられた!
――――――――――
本社ビル4階。照明の消えた倉庫には、多様な電化製品がラックに積まれて綺麗に並んでいる。その内の一つからウノエは……否、タキは生体LANケーブルを引き抜いた。「終わったぜ」「アッ……ハイ」彼は立ちくらみ、よろけた。
「まあ、なんだ。全部終わりだ。分かってるだろうが、ニンジャスレイヤー=サンが野郎を殺したら警報が鳴る。そしたら港に逃げろ。船がある。運転手付きの専用だ」「ハイ」
「じゃ、オレは帰る。オタッシャデー」「エッ? あ、あの、ちょっと。タキ=サン!?」ウノエは引き留めようとした。だが、無駄だった。視界がブラックアウトし、ノイズが鳴った。既にログアウトされたのだ。「なんてこった」ウノエは呻いた。
タキは既にバックドアめいた侵入経路を構築しており、緊急時にはネオサイタマからの遠隔ハックを可能としていた。ここにいる意味は既に皆無。だがウノエにはそれを知る由もない。ハッカーのための肉体提供の役目を終え、ただ立ち尽くし、全てが終わるのを待つだけだ。だが……それでいいのか?
心の中がざわめき立ち、落ち着かない。この島で過ごした日々。忘れた夢。怒り。恐怖。悲哀。その全てが混ざり合い、混沌として沸き立っている。「邪魔になるよな」ウノエは口に出す。「死ぬかもしれない。実際無意味だ」動かない口実を並べ、合理性を以てざわめきを消そうとする。
だがそれは消そうとするほどに強まった。ウノエはウロウロとその場を歩き回り、理屈で補強しようとした。「俺が何をしたって変わらないんだ」それが正しい。だって俺には何も出来ない。相手はニンジャだ。途端に込み上がる恐怖。恐怖?
何を恐れる。恐れるのはおかしい。オレは間違ってない。堂々としろ。タキ=サンのように。思考がそこに至ったその時だった。(クソなもんはクソだろうが!)その言葉が蘇り、木霊めいてニューロンに反響した!
「クソだ」思わず口をつく。すると込み上がった。「クソだ」怒り。「クソだ」恐怖。「クソだ!」悲哀! 全てだ! ざわめきは何一つ消えていない!「クソだ!」何もかもが! 何故か!? その答えは初めから彼自身の中にある!「ウオオオオオーッ!」ウノエは衝動のままに走り出す!
#9
「グワーッ!」ニンジャスレイヤーは床に叩きつけられ、その体はバウンドし、壁面に叩きつけられた。「グ……ワ……」クレーターめいた衝突痕が、その衝撃の大きさを物語っていた。
「フゥーッ……!」ヴァーミリンガはザンシンした。ヒュオオオ……風が止み、舞っていた破砕粉塵がパラパラと落ちた。(ちと、やりすぎたか?)ムチを振って血を払い、腹に刺さったままの逆棘を慎重に引き抜く。当然その間も、ニンジャスレイヤーから目を離すことはない。最低限のカラテ警戒を維持し、彼はゆっくりと歩み寄り……ニタリと笑った。
「グ……」壁に張り付き、呻くニンジャスレイヤー。その出血はヴァーミリンガの想像より遥かに少ない。(なるほど)全身の傷を見れば分かる。螺旋に飲み込まれる瞬間、回転方向に従って表面を転がり、天井へと叩きつけられ続ける……それを繰り返し続けることで致命期間を短縮したのだ。なんたる状況判断力! 彼は舌を巻いた。
痛めつけられたニンジャスレイヤーを前にして、ヴァーミリンガがトドメを刺すことはない。もとより彼はニンジャスレイヤーを殺すつもりはなかった。叩きのめし、屈服させ、配下に迎え入れる。それこそがこのイクサの真の目的なのだ。若くしてこの戦闘経験。冷静な判断力。この男はサツガイを殺す牙とすらなりえるかもしれぬ!
だが……賢明なる読者諸氏は疑問に思われるかもしれない。あのニンジャスレイヤーを相手に、これほどまでの蹂躙を行えるほど……彼が対峙した数々の強敵より一段上のレイヤにいるほど……ヴァーミリンガは強力なニンジャなのだろうか?
その答えは否だ。確かにヴァーミリンガは相当な手練である。だが苦戦の最大の原因は、他ならぬニンジャスレイヤー自身にある……!
「グ……」ニンジャスレイヤーは呻く。視界がぼやけ、かすみ、死の運命を暗示する。「グ……、ン…………」(黙れ……!)殺意圧の緩みにより目覚めかけたブラックハチェットの意識を、彼は再び黙らせた。だが視界が戻った時、彼が目にしたのはヴァーミリンガの足だった。
「イヤーッ!」「グワーッ!?」サッカーボールめいて腹を蹴られ、悶絶!「意識はあるようだな。ならそのまま聞け」ヴァーミリンガは語気を弱め、諭すように続けた。「これが貴様だ。貴様のカラテだ。サツガイの遥か下にいるワシにすら勝てず、ブザマを晒すのが貴様の限界よ」
「……」死神は答えない。社長は勝ち誇るように続けた。「まさか、元の身体ならば勝てるとでも思うておらぬだろうな? 無駄なことよ。何故ワシがブラックハチェット=サンごときサンシタを島に置き、勝手をやらせていたと思う? 無意味なもう1台のUNIXなどを用意し、イクサの準備を整えさせてやったと思う!?」急激に語気を荒げる!
「全てはワシの想定内よ! サンシタの体を選び、用意された勝機を信じ込み、ワシにブザマにカラテで負けた! 貴様は全てにおいてワシに劣っているのだ!」ナムサン! 老獪なるこのニンジャの策は実際驚異であった。だがそれこそは、ヴァーミリンガの宿すダマシ・ニンジャクランの秘伝。タイジン・ジツの奥義である。
本来の肉体のニンジャスレイヤーとヴァーミリンガのカラテ、その結果を現時点で予測するなど誰にも出来ぬ。だが全身を痛めつけられ、敗北感に打ちひしがれる時に、さらに判断の過ちを指摘され、自信たっぷりに言い切られれば……!? その結論を受け入れたが最後、もはやニンジャスレイヤーは彼に打ち勝つ可能性すら認識できぬ奴隷と化す!
だがヴァーミリンガの言葉は、端からニンジャスレイヤーの耳には届いていなかった。「……スゥーッ……」彼は敵の弁舌の最中、可能な限り呼吸音を抑えながらも、独自の呼吸を続けていた。「フゥーッ……!」
今、彼の中に内なるナラクはいない。ゆえにその呼吸は、ただカラテを整え、調律するだけのものに過ぎない。それでも彼は呼吸し続けた。「スゥーッ……!」サツガイに至り、殺す! いかなる障害があろうとも!「フゥーッ……!」ならば己の弱さなど、一切の言い訳にならぬ!
「……貴様。その目……何かしておるな?」ヴァーミリンガが見下ろす。彼は冷淡に言った。「よもやまだワシに勝てるなど思うておらぬだろうな。遠吠えなど滑稽ぞ」誤魔化すのも限界か。ニンジャスレイヤーはもはや絶望的なカラテを……収めた。「勝機はある」彼はヴァーミリンガの目を真っ直ぐに見返し、言った。「忍耐だ」
「何……!?」タイジン・ジツに集中していたヴァーミリンガはここにして漸く、砂利を踏みしめる僅かな音を聞き取った。それはこの施設のドアに近づき、そして……「社長ーッ!」バタン! 大きな音を立て、室内に飛び込んできたのは、マシンガンを持ったウノエだった!
「ウノエ=サンだと?」ヴァーミリンガは首をかしげる。なぜ彼がここに? 増援にでも来たつもりか。「足手まといぞ。去れ」ヴァーミリンガは冷たく言った。その体にはすでに油断ならぬカラテがみなぎっている。ニンジャスレイヤーは手負い。だが侮れぬ相手だ。
「社長……お、俺は……」ウノエは無意識に恐れた。だが。それでも。「……退職しに来ました」「何?」ヴァーミリンガが睨めつける。ウノエは地下のクローンヤクザから回収したマシンガンを縋るように握り、叫んだ。「もううんざりなんだ。このクソリゾートも。延々と続くバカンスも。職場も! 人も! アンタもだ!」
「貴様! 誰に口を」「アンタはもう上司じゃない!」問答の最中、ニンジャスレイヤーの体がピクリと動く! ヴァーミリンガは即座に振り返り拳を叩き込む!「イヤーッ!」「グワーッ!?」「ウノエ=サン! 今は貴様に構っている暇などない! とっとと去れ! これは命令だ!」
(命令!?)退職意思を蔑ろにされ、瞬間的な憤激が膨れ上がった。だが堆積した恐怖の前に、それはあまりにも弱かった。ならばどうする? このまま怯えているか? 押し着せの理屈で自分を満たすか!?
(そんなものはクソだ!)だが恐怖は消えぬ! ならば!? ……過剰放出されたアドレナリンがウノエの時間間隔を鈍化させていた。彼の目には己がゆっくりと銃口を上げるのが見えていた。
彼はもはや恐怖することに恐怖しなかった。だからこそ、その口から吐き出されたのは勇壮な咆哮でも絶望の嘆きでもなかった! あまりにも弱く、惨めで、繕わぬ……恐怖の雄叫びであった!
「アイエーエエエエエエエ!」ウノエはトリガーを引いた! 銃弾が早雨めいて吐き出される!「グワーッ!? 血迷ったか、ウノエ=サンーッ!」脇腹を捉えた! だが一発だけだ。残りは全て拳で跳ね飛ばされる! ウノエにもそれは辛うじて見えていた。だが引き金は引き続ける! ヤバレカバレだ!
「この……ッ!?」「イヤーッ!」「グワーッ!」ニンジャスレイヤーの強烈な頭突きがヴァーミリンガを強制的に振り向かせた! 死神の両手が敵の両手と組み合った!「付き合ってもらうぞ。忍耐とやらにな」「貴様ーッ!」
「アイエエエエエエーッ!」ヴァーミリンガの背中に無数の銃弾が浴びせかけられる!「「イイイヤアアアーッ!」」ヒュン! ヒュン! 二人のニンジャはボクシングめいた動作で銃弾をかわし続ける! ニンジャ第六感、そして気流を読む確かなカラテあってこそ為せる技だ!
「アイエエエエ!?」あり得ない事態に、ウノエは恐怖した。だがもはやそれは彼に引き金に込める力を増させるだけだった! 銃弾が霰めいて襲う! 襲う! 襲う!
ドクン!(おのれ、ウノエ=サンめ……!)ヴァーミリンガのニューロンが火を噴き、思考が極限加速した。よもやこのような時に愛する社員に裏切られようとは!(ニンジャスレイヤー=サンは……諦めざるを得まい……!)
形勢は彼に大幅に不利だ。背後より飛来する銃弾を躱すには、彼ほどのニンジャとあれど集中せねばならぬ。だが正面のニンジャスレイヤーはそうではない。彼はただ、ヴァーミリンガの動きに合わせればいいだけだ。そしてその思考の簡略化こそが、絶対的な膂力差を持つ彼らを拮抗状態に持ち込んでいた!
銃弾を避け、両手に力を込めながらも、ヴァーミリンガは思考をフル回転させる。弾切れなどニンジャスレイヤーも想定していよう。座して待つにはリスクが大きい。攻勢に転じ、ケリをつけるべし! 今、奴への攻撃に使えるものは?(……この弾丸だ!)フーリンカザン! 動かせる肘を弾丸の腹に当て、軌道を逸らすことで、ニンジャスレイヤーに当てるのだ!
ヴァーミリンガにとってこれは大きな賭けであった。失敗すれば肘に弾丸が突き刺さり、拮抗状態は大幅不利で崩れ去る。だがやらねばならない。彼は社長だ。守るべきものがある。そして何より、道を誤ったウノエの命を奪い、救ってやらねばならぬ! 彼は覚悟を決める! 勝負はコンマゼロゼロ1秒以下の一瞬!
「「イイイ……」」「アイエエエエ!」「ヤアーッ!」ヴァーミリンガは腕の力を緩め、肘の位置をずらした! 肘に焼けつくような痛みが走り、消えた!「グワーッ!?」ニンジャスレイヤーが仰け反り、手の力を緩めた! ヴァーミリンガは手を「イヤーッ!」「グワーッ!?」
(……何が起きた?)白く吹き飛んだヴァーミリンガの視界は、絶望的な速度で復帰する。ニューロンが遅れて分析結果を伝える。ニンジャスレイヤーの仰け反りは弾丸の痛みによるものだった。だがそれは隙ではなかった。最速頭突き攻撃への予備動作!(ワシの先を読んだというのか!?)
視界は徐々に色づく。眼下にはニンジャスレイヤーの後頭部がある。それが引き上がっていく。お互いの視線が至近距離で交差する。けして濁ることのない、頑なな意思の光を宿す、ぬばたまめいた双眸が彼を見据えた。(この目)曇りなき瞳の中に、映り込んだ己自身の姿に、ヴァーミリンガは時を見た。
それは、まるで。――直後、視界が赤く吹き飛ばされる!
「アバーッ!?」ヴァーミリンガの絶叫に、ニンジャスレイヤーは舌打ちした。弾丸が喉を貫いた。それは耐えに耐えて行き着いた、待ち望んだ致命傷であった。だが早すぎる! まだ何も聞き出せてはいない!「アイエエエエ!」ウノエの銃弾が飛ぶ! ニンジャスレイヤーは即座に状況判断し、連続側転を打った!
(無駄骨か!)ニンジャスレイヤーは舌打ちした。その耳にヴァーミリンガの呻き声が届いた。「ゴボッ、……ラ、……ト……」それは一つの名を呼んだ。「ブラスハート」
直後、着弾!「アバババババーッ!」銃弾はこめかみに、そして二の矢、三の矢めいて、顔の側面に着弾。その体をコマめいて回転させた! 鮮血が空中に小さな薔薇めいて舞った! インガオホー!「サヨナラ!」ヴァーミリンガは爆発四散!
――――――――――
爆発四散した社長を見た瞬間、ウノエは腰を抜かしてへたり込んでいた。マシンガンは過剰排熱により焼け付き、銃口から煙を上げている。視線の先、爆発痕のすぐ側で、死神は厳かにザンシンしていた。それは闇のように静かで、均整の取れた、宗教画めいて荘厳な光景だった。
やがて死神はゆっくりとウノエに近づいた。「あ……あの」「立てるか」「社長は……」「お前が殺した」ニンジャスレイヤーは静かに言った。「……お前の、勝ちだ」「俺の……」その言葉の裏にある感情を、ウノエは読み取れない。
ウノエは己の手を見た。そこにはもう、焼けるような痛みと、引き金の重さしか残っていなかった。単純に割り切れるような感情など、湧いてすら来なかった。だからその全てを静かに受け入れた。(これは、俺のものだ)
「……ヌウ―ッ……」ニンジャスレイヤーがよろめく。「大丈夫ですか!」「……接続がもうじき切れる」彼は親指で己を指した。「コイツが目覚める前に港に逃げろ」「……いえ。まだです。まだやることが」「死ぬぞ」「死にません」ウノエは真っ直ぐに死神の瞳を見据え、言った。「俺には夢があります」
ほんの僅かな沈黙の後、ニンジャスレイヤーは言った。「思い出せたか」「いいえ」ウノエはかぶりを振った。「夢を思い出す、夢が出来たんです」それは具体性に欠ける、哲学めいて頼りない言葉だった。しかしマスラダはただ、静かに頷いた。「……そうか」
やがてその首がカクンと項垂れた。帰ったのだと、直感で分かった。(アリガトゴザイマス)ウノエは伝えられなかった感謝が彼に届くことを祈った。直後、ブラックハチェットが全身の激痛に悲鳴を上げた。
――――――――――
「ハァーッ、ハァーッ!」ヴァーミリンガの死。その緊急事態を自動アラートで受けたケコアは、廊下をひた走っていた。イクサの間、万一に備えて彼は高級ホテルのパニックルームへ避難していた。だが、それを知るやいなや飛び出したのだ。
「ヴァーミリンガ! あの役立たずめ! バカ!」口汚く罵りながら、走る。恐る恐る部屋から出てきた従業員が声をかけた。「支配人! 一体何が……」「黙れッ!」「アイエエエ!」従業員は引っ込んだ。
(どうして僕が! エドゥアルト=サンに続いてヴァーミリンガまで! こんなのおかしいぞ!)思考がぐるぐると渦を巻く。ナボタタの土地は全て彼の所有物だ。故に彼らはケコアを丁重に扱い、偽りの地位を与え、増長させるがままにしていた。
(僕がこの島にエドゥアルト=サンを呼んで……雲の上だった人たちと知り合って……成り上がった! 強くなったのに! オカシイ!)ロビーを飛び出し、港へとよろめきながら走る。その先に誰かいる。「あっち行ってろ! バカ!」ケコアは叫んだ。女は取り合わない。銃を抱えたまま、ゆっくりと振り返る。銃?
BLAM!「アイエエエ!」威嚇射撃だ! ケコアはブザマに転倒し、慌てて立ち上がる。「久しぶりね、ケコア=サン」「……カレナ=サン?」返答を聞くやいなや、カレナは再び引き金を引いた!「ンアーッ!」だが悲鳴を上げたのはカレナ自身だった!
「アイエエエ!?」ケコアは叫び、後ずさる! カレナの撃った弾丸が、彼女自身に……(そうか!)これはポータ「ポータブル防衛装置ね。アダナス社製」
カレナは再び照準を合わせ、引き金を引いた。それがケコアの側に飛んだ瞬間、不可解な音が鳴り、弾丸は反転した。今度は外れた。射撃反動により体勢がぶれ、反射角上にいなくなったからだ。「エメツの作用を使って、飛来物のベクトルを正反対に反転させる」「何を言って……」撃つ。反転。カレナの頬を掠め、血が流れる。再び撃つ。反転。壁にめり込む。
「オイッ! 何を……」「でもね、ケコア=サン。物事には限度ってものがある」BLAMBLAMBLAMBLAM! フルオートだ!「アイエエエ!」マズルフラッシュの光にケコアは慄いた。「な、何ッ……!」「……そのクソ装置とアタシの、どっちが先にくたばるかってことよ!」カレナは目を見開き、引き金を思い切り引き込んだ!
BLAMBLAMBLAMBLAMBLAMBLAMBLAMBLAMBLAMBLAMBLAMBLAMBLAMBLAM!「アイエエエ!」ケコアは怯える! 本来であれば、こうした事態が起きた際は緊急IRCが自動的になされ、ヴァーミリンガが駆け付けてくる手筈だった。ゆえにカレナは、殺害に時間を要するこの手段を取れなかった。だが彼は、もういない。
ケコアの脳は鈍く回転していた。未だ事態は半分も飲み込めていない。彼女は何を言っている? クソ装置? くたばる? それはつまり、僕が撃たれる。それはつまり。だから。「ンアーッ!」カレナは肩口に被弾! 血しぶきが跳ね、ケコアの方へと飛んだ。それは自動反射により彼の足元にピシャリと跳ねた。カレナは止まらない。何らかの薬物の影響下にあるのか、すぐに照準を直している!
発砲と反射が絶え間なく続く、眼前で繰り広げられる超自然的光景を前に、彼はぼんやりと呟いた。「……死ぬ?」その言葉を口に出した途端、彼は凍りついた。それは彼の愚行が、ナボタタに好き放題にもたらしていたものだった。「や……ヤメロ……」
「ンアーッ!」カレナは頭から流血しながらも、決して目を離さなかった。その眼光にケコアは恐怖した。「く、狂って……!」ケコアは後ずさる。背中が壁に当たる。逃げられない。逃げられない! ケコアの恐怖が爆発した!
「だ、誰かッ!」ケコアはIRC端末を縋り付くように握った。彼を強くし、全てを与えてくれたものを。彼は叫んだ。「助けてッ! 誰か助けてーッ! アイエエエエエエ!」
やがて、パリンと何かが砕けるような音が鳴った。「グワーッ!?」ケコアの左肩に着弾! IRC端末を取り落とす!「キャパシティオーバードスエ。キャパシティオーバードスエ。カラダニキヲツケテネ……」アダナスの反射装置は無慈悲な機械音声とともに機能を停止した。
満身創痍のカレナは、怨敵を見下ろした。彼は被弾箇所を必死に抑えてブザマに転げ回り、カレナのことなど目に入っていない。
BLAM!「グワーッ!?」右足! BLAMBLAM!「グワーッ!?」左腕! 左足! BLAM!「アバーッ!?」右腕! 四肢を撃ち抜かれ、ケコアは体を動かすことすらままならなかった。「あ、あ……ああ……」彼は乞うように見上げた。「た……」
その口が開かれた瞬間、カレナの脳裏にあの日の記憶が、歪みきったケコアの笑みが去来した。それは現実と重なった。『だからカレナ=サン。僕はもう、君に』「助けて……」幻影は一瞬で消えた。過去は陽炎めいておぼろで、とどまることはない。
カレナはもう、何も言わなかった。ただ機械的に額に照準を合わせ、引き金を引いた。銃声が鳴り、血しぶきが跳ね、断末魔。それで終わった。
彼女は言葉もなく腰を下ろした。出血が酷く、意識はやや朦朧としていた。でも、これで終わった。何の感慨も湧いてこなかったが、わかりきっていたことだ。彼女は胸元に手を入れ、小さなスキットルを取り出した。それは生き延びてしまった時のために用意していたものだった。
しかし小さなスキットルには穴が空き、中身がこぼれてしまっていた。……あるいは、それが……平時では致死量足り得る量のそれが、血で洗い流されながらも、彼女に成し遂げる力を与えていたのかもしれない。
その時、彼女の脳裏に過ったのは、死んだ両親でも、開発反対デモに参加し殺された友人でも、ましてやケコアでもなかった。『キタノ・スクエアビル』それは素性もロクに知らず、笑顔すら見たことのない、ほんの微かな期間だけともに在った少女の言葉だった。『会いに来てください』
「……ハァーッ……」カレナはスキットルを放り捨て、動き出す。景色が急に色づいたかのようだった。鈍い痛みが全身に走り、体の至るところが悲鳴を上げている。
「簡単に、言ってくれるわよね。みんな……」無理やり立ち上がろうとして、転ぶ。その動きを数回繰り返したところだった。「いました! 彼女です!」「任せろ!」誰かの声。それは目にも留まらぬ速さでカレナをピックアップし、抱きかかえた。
「……アンタ。ブラックハチェット=サン?」「お前! 俺に感謝しろよ!」ブラックハチェットは甲高い声で言った。「証言するんだぞ! 俺は被害者だって! 悪いのはニンジャスレイヤーとかいう野郎だ!」「その話はあとに! 危険です!」その背中越しにウノエの声。しがみついていたのだ。
ウノエは背中から離れ、カレナに話しかけた。「えーっと……何から話せばいいのか……とにかく彼女は味方なんです。港に逃げましょう!」「助けに、来た、ってこと?」カレナは咳き込んだ。ウノエはニンジャに命じ、彼女を丁重に運ばせた。
「……ナンデ?」移動中、カレナは呻きながら尋ねた。ウノエは答えた。「死んでほしくなかったんです」「理由は?」「ありません」彼は苦笑した。「浅いのね」カレナも笑った。それは非合理的で、何ら論理的でなかった。それでも何故か、嫌な気分はしなかった。
――――――――――
ナボタタの海に、日が昇り始めていた。
カレナが自覚していた通り、ヴァーミリンガを殺したとて何が変わるわけでもない。ナボタタはすでに市場価値を得て、一つの観光単位へと変わっている。出来合いの高級ホテルやリゾートホテルはいずれどこかの企業の目に留まり、居抜き物件として使われるだろう。リモート観光は永遠に不可能となったが、島民にとっては見る顔が変わるだけだ。
それは島全体の空気も同じだ。過激派、中立派が大勢死に、融和派が大多数を占めた。文明の恩恵を受け、不便で非合理的だった文化は徐々に忘れられ、漂白され始めている。ナボタタは生き残り、その心は死んだ。
汽笛が鳴り、錨が上げられると、船はゆっくりと動き始めた。デッキにいたウノエは、波しぶきに体を濡らされながらも、新鮮な気持ちでいた。朝焼けの光も、見下ろす形のナボタタの海も、何もかもが新しい景色だった。
「お二人はこれからどうします?」ウノエが問うと、包帯まみれのカレナが答える。「分からない。でも、そうね。いつかネオサイタマに」「ネオサイタマですか?」
「行きたい場所があるの。会いたい人も」「そうですか」ウノエは深く問わなかった。そのような好奇心でこの穏やかな微笑みを壊すのは、酷く野暮なことだと思えた。
「ブラックハチェット=サンはどうします?」返事はない。見れば彼女がいた場所には代わりにボロ布の塊が落ちていた。「ブラックハチェット=サン?」「アイエッ!? 話しかけるな!」
「雇い主を殺したんだぞ……スゴイ数の追手が来る。お尋ね者になっちまった……!」ボロをかぶり、ブルブルと震える金髪の小柄な少女ニンジャは、もはや威圧的な虚飾に彩られた暴君ではなく、かつてのウノエと同じ惨めな存在に見えた。
ニンジャスレイヤーが去った直後、ウノエはブラックハチェットに雇い主殺しのリスクを滑らかなセールス・トークで語り聞かせ、脅迫し、協力させた。その効果は覿面だったが……効きすぎたかもしれない。
実際、彼女が賞金首になどなることはない。賭けるものがいないからだ。悪評は広まり、傭兵としては生きられぬだろうが……命を狙われるようなことはあるまい。
最寄りの空港がある島へと、船は動き出す。タキ。コトブキ。彼らは僅かな期間、2人のニューロンの同居者としてともにあった。そしてニンジャスレイヤー。彼らとともに走り、戦い、いくつかの言葉を交わした。それは互いの人生にとって、ほんの僅かな一瞬の、浅い繋がりに過ぎない。
表情。声。振る舞い。彼らと対面すれば当たり前に分かることを、2人は何一つ知らない。彼らが何を追い、何と戦い、何を愛し、何を守っているのか。親しくなれば知りゆけることも、当然何一つ知らない。
それでも2人の心には、彼らと交わした言葉が残されていた。それは依るには頼りなく、曖昧なものだった。しかしそれをありのままに受け入れた時、彼らはもう、一人ではなくなっていた。それがきっと、立ち上がる力をくれたのだ。
(いつか直接会いましょう。その時はきっと、お礼の言葉を――)ウノエは陽光を手で遮りながら、空を見上げた。
果てのない青空には3羽のカモメが飛んでいた。それはクゥクゥと煩く声を交わしながらも、けして大きく離れることはなく、ともに水平線の向こうへと消えていった。彼らがともに飛び続けられることを、2人は静かに祈った。
【リモート・ボンド、リライアブル・ボット】終わり
それは誇りとなり、乾いた大地に穴を穿ち、泉に創作エネルギーとかが湧く……そんな言い伝えがあります。
