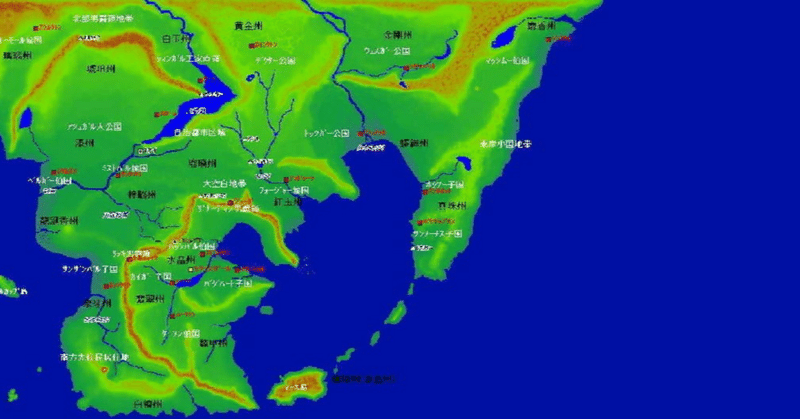
ティルドラス公は本日も多忙⑤ 嵐の年、国滅ぶ時(13)
第三章 シンネタイの変事(その3)
しかし、オドゥールに従っていた者たちの全てが彼らのように逃げ延びられたわけではない。突然のことに方針が定まらず逡巡する間に逃げる機会を逸した者、ディディアックの助言を拒んでミギル派と一戦交える道を選んだ者たちもいた。翌日からシンネタイの街中では そうしたオドゥール派の者たちと、ミギル派、そして彼らを支援するトッツガー兵との戦闘が散発的に行われる。
戦闘というより実態は一方的な掃討だった。ディディアックが察した通り、カフトは宮廷の掌握と並行して、計画が成功したあとにオドゥール派の者たちが反旗を翻すであろうことも計算に入れ、それに備えて万全の手を打っていたのである。抵抗か降伏か迷っている相手には最初に交渉に応じるような態度で接して油断したところを騙し討ちにかけ、準備が整わぬまま右往左往している相手は混乱から立ち直る間を与えず急襲して一気に制圧し、自邸に籠もって戦おうとする相手にはあらかじめ送り込んでおいた内応者に門を開けさせて邸内に突入する。こうしたカフトの素早い動きの前に、オドゥール派の面々は互いの連携が取れぬまま各個に撃破され次々に壊滅していった。
今、そうやってオドゥール派の屋敷の一つを攻め落とした寄せ手の中に一人の年若い武者の姿があった。彼の名はバークウィン=カークトン。エミザルの長男、つまりトゥーンの甥で、この年十五歳の少年である。若年ながらすでに数度の戦闘に参加して武勲を立てており、父や伯父にも劣らぬ武勇の士として将来を嘱望されている。この屋敷を攻めるに当たっても先陣を切って斬り込み、見事な戦いぶりを見せていた。
オドゥール派の一人だった屋敷の主は既に討ち取られおり、戦闘もあらかた終わっている。「まだ隠れておる敵がいないかよく確かめよ。」屋敷の母屋の廊下を大股に歩きながら、周囲の兵士たちに彼は指示を飛ばす。「伝令の者は戦果を取りまとめて本陣の伯父上と軍師どのに報告せよ。」
廊下の壁のあちこちには血の跡が残り、ところどころに死体も転がる。周囲に立ちこめる血と排泄物の臭い。しかしバークウィンは動じるそぶりさえ見せない。十代の初めから父に従って各地の戦場に身を置いてきた彼にとって、そんなものは見慣れた光景でしかないのだ。
そのとき廊下の向こうから、年の頃二十前後の若い女が悲鳴を上げながらこちらへと走ってきた。この家の娘か、息子の妻か、あるいは侍女か。その背後から、トッツガー家の軍装に身を包んだ数人の兵士が彼女を追いかけてくる。
「お助け下さい!」バークウィンの姿を認め、彼に駆け寄って跪きながら女は言う。「お願いいたします。何とぞ!」そこに追ってきた兵士たちが駆け寄ると、彼女の腕を乱暴に掴んで引き立てていこうとする。
「どうした。何事だ。」彼らに向かって尋ねるバークウィン。
「いや、大したことじゃございませんや。戦いも終わったことだし、ここは女でも捕まえて息抜きをしようやって話になりましてね。もちろん上官の方から略奪のお許しは得てます。」兵士たちの頭分らしい男がそう答える。
「そうか……。」トッツガー軍は略奪を禁じていない。むろん戦闘中に持ち場を離れて略奪を行えば任務放棄で重い罪に問われるが、戦闘が終わった後の略奪は兵士たちへの報償として正式に認められている。「ならば致し方あるまい。」少し哀しげな表情でバークウィンは言った。
「ひっ!」彼の言葉に女は息を呑む。
「何なら御曹司もお楽しみになりますかい? 順番は譲って差し上げますぜ。」下卑た笑いを浮かべながら兵士は尋ねる。
「いや、良い。まだ役目もある。」
「そうですかい。なら、俺たちだけで楽しませてもらいまさあ。さあ来い!」
そのまま兵士たちの手で近くの小部屋に引きずり込まれていく女の長い絶叫を背後に聞きながら、バークウィンは少し顔をゆがめる。
彼女を哀れに思わぬわけではない。おそらく昨日の朝までは彼女もこの屋敷で平穏に、大きな憂いもなく暮らしていたのだろう。それが突然起こった宮廷の変事で戦いに巻き込まれ、何が何やら分からぬうちに兵士たちに捕らえられて大勢で慰みものにされた挙げ句、殺されるか、運良く助かっても奴婢として売り飛ばされるか家も家族も失ってこの寒空の下に身一つで放り出されるかの運命が待っているのだ。
しかしだからといって彼女をどうしてやることもできない。そのまま屋敷の中の見回りを済ませ、撤収の命令とともに彼は手兵を率いて本陣に戻り、伯父であるトゥーンの前へと伺候する。傍らには父のエミザルの姿もあった。「伯父上、父上、ただいま戻りましてございます。」
「ご苦労。よくやった。」彼の言葉に頷くトゥーン。「天晴れな働きだったと報せを受けている。公爵もお喜びになろう」
「父上、お尋ねしたいことがあります。」少し考え込んだあと、エミザルに向かって口を開くバークウィン。
「何だ?」
「兵士たちの略奪ですが、控えさせることはできぬのでしょうか。今日のように国内の敵を相手にするような場合であれば、ことさらに略奪を行って敵を苦しめることもないのではないかと私は思うのです。」
「若いな。」かぶりを振りながらエミザルは言う。「良いか、そもそも略奪は戦場の作法、兵士たちへの褒美だ。戦いの後に褒美があることを知ればこそ、兵士どもは勇み立ち、死力を尽くして戦うのではないか。」
「それはその通りでございますが――」
「言うな。敵への無駄な情けなど戦場では無用のこと。それより戻って休んでおれ。明日も早いぞ。」
「はっ。では下がらせていただきます。」父の言葉に一礼してバークウィンはその場から退出する。そう、略奪は戦いに勝ためにはやむを得ぬこと、父の言う通りなのだ。
彼が去ったあと、傍らのトゥーンに向かってエミザルは言う。「困ったものですな、兄者。見事な武功とのことで褒め言葉の一つもかけてやろうと思っておれば、何に憶したのか突然にあのような軟弱なことを言い出すとは。あれでは先が思いやられます。」
「何を言うか。バークウィンこそ我が一族の千里の駒よ。俺の息子どもなど足元にも及ばぬわ。だからこそ公爵も、エヴドラさまの婿として見込まれたのであろう。」とトゥーン。
エヴドラ=アックディーラはイエーツの孫娘である。トッツガー家代々の家臣であるアックディーラ家に嫁いだイエーツの長女・トーティアの娘でこの年十二歳。以前からバークウィンとの間に縁談が持ち上がっており、近く正式に婚約する運びとなっている。
「お前は良い息子を持ったものだ。おそらく今から十五年、二十年のち、我ら亡きあとはバークウィンが我が一族、さらにトッツガー家を背負って立つことになるのだろう。大事にしてやれ。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
