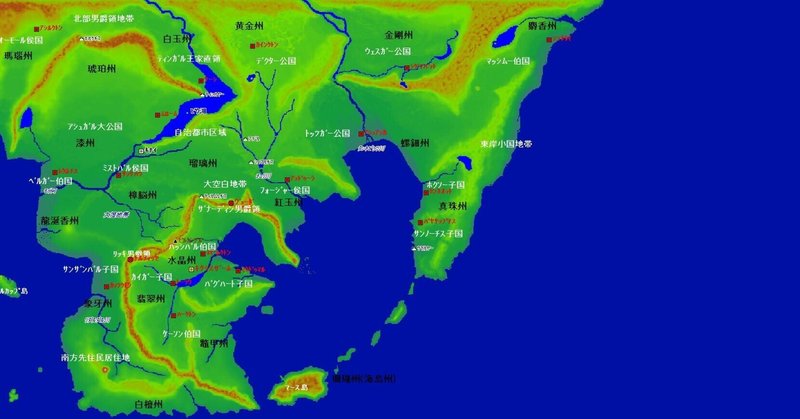
ティルドラス公は本日も多忙④ 都ケーシの宮廷で(30)
第六章 親族たち(その5)
ミッテルに案内されて通された奥の間では、この家の主・コンジュが威儀を正して待っていた。「伯父上、御挨拶申し上げます。」彼に向かって丁寧に一礼するティルドラス。
「よくぞ参られた。」型通りに挨拶を返すコンジュだが、その態度はエウロナに聞いた通り、どこかよそよそしい。
「父上、伯爵はこのたびの参朝で宮廷の勝手が分からずお困りとのことです。私が手助けをして差し上げようと存じますが。」傍らからミッテルが言う。
「良かろう。」どこか投げやりな調子でコンジュは頷いた。
そのあとティルドラスはミッテルの私室に通される。私室といっても二人が向かい合って座るとそれだけで身動きもままならなくなるような部屋で、その狭い空間の壁際に並んだ本棚には分厚い本が所狭しと置かれていた。
「どうした。伯爵さまには、こういうみすぼらしい家の狭い部屋は珍しいかな。」周囲をしげしげと見回すティルドラスに、何やら皮肉めいた口調でミッテルは尋ねる。
「いや、そうではない。」かぶりを振るティルドラス。「いい本が揃っているな。歴史、天文、地理、博物学、思想書……、これだけ選りすぐりの良書を手に入れるのは大変だったろう。」
「ほう、この本の価値が分かるのか。」ミッテルは少し意外そうな表情になる。「本はいい。何万里の距離と幾百年の時を超えてあらゆることを教えてくれる。いずれその話も心ゆくまで語り合いたいが――、まずは依頼だ。」そして彼は座り直し、口調を改めて言った。「正直に答えてくれ。今回の君の参朝には、王家のお声掛かりでトッツガー家の公女との結婚を成就させるという隠された目的がある……、そんな噂が水面下で流れているが、事実か?」
「――事実だ。本当のところ、それこそが目的と言っていい。」少し顔を伏せながらもティルドラスは言い切った。
「だとすると、手助けはできるが成功は請け合えない。むしろ失敗に終わる可能性の方が高いだろう。後から恨まれても困るのであらかじめ言っておく。何なら他の仲介者を探してくれてもいい。それでも僕に頼むか?」
「お願いする。」ティルドラスは頭を下げる。
「そうか。伯爵さまに頭まで下げられてはこちらも応えざるを得ない。全力でやってみよう。」ミッテルは頷いた。「まず手順を説明しよう。結婚への口添えを王に頼むには、少なくとも三回程度の謁見を許される必要がある。だがその前に、まず君がハッシバル家の家督を継ぐことを正式に認められ、朝廷内の官位も授けられて王宮に出入りできるようにせねばならない。併せてバグハート家の旧領をこのままハッシバル家が支配することの許しも得ねばならないだろう。一つずつ話を通していてはいつ謁見に漕ぎ着けられるか分からない。ここは朝廷の各所に根回しして、君の願い出が一度にまとめて聞き届けられるようにする。」
「そんなことが可能なのか。」
「金に糸目さえ付けなければな。単刀直入に聞こう。今、君が家臣たちから使途をとやかく言われず自由に使える金はどれくらいある。」
「黄金三百枚と銀二千両ほど。」
「ほう、それは大したものだ。ハッシバル家の内情は苦しいと聞いていたが。」驚いたように声を上げるミッテル。
「実際苦しい。ほとんどはアシュガル領滞在中にたまたま賭に勝って手に入れた金だ。」とティルドラス。
「であればなおさら好都合だ。しがらみのないあぶく銭なら、躊躇なく盛大にばら撒ける。」ミッテルは頷く。「ではそのうち黄金百枚、銀三百両を僕に預けてくれ。それだけあれば足りるだろう。それを各所にばら撒いて、他の話を後回しにしてでも君の願い出が聞き届けられるよう手を回す。残った金は報酬として僕がいただくことにするが、それでもいいか。」
「構わない。」
「君の官職だが、高い官位を得るには時間も金もかかる。どうせ宮廷に出入りするためだけの官職だ。今回は適当なところで我慢してくれ。」
「任せる。」
「よし、やる事が固まってきたな。少し待ってほしい。」そしてミッテルは机に向かい、何通かの書状を手早く書き上げると従僕を呼んでそれを手渡し、何やら事細かに指示を飛ばして送り出す。「手始めに、明日の朝一番であちこちを回って君に便宜を図ってもらえるよう頼んでくる。その時の手土産に使う黄金十枚と銀五十両、それから君の名刺を二十枚ほど、今日のうちに使いの者に届けさせてくれ。」
「分かった。」そしてティルドラスは大きくため息をつく。「しかし、想像以上に難儀なものだな。言っては何だが、そんな大金が公然とやりとりされていることにも驚いた。」
「ケーシとは、王宮とはそういう場所なんだよ。」何やら自嘲するような口調でミッテルは言う。「自身では何一つ生み出さず、ただ他人の働きを奪うことでかりそめの威厳を保ち、自身に何かの価値があるかのように見せかけているだけの場所――。宮廷そのものがそうして成り立っている以上、個々の官吏が地位を利用して他人からむしり取ることにやましさを感じるはずもない。僕の一族にしたところで偉そうなことを言える立場じゃない。取り次ぎ、仲立ちと言えば聞こえはいいが、要するに賄賂の上前をはねての口すぎだ。宮廷を一歩出れば何の役にも立たない人間さ。」
少し驚いたようにミッテルの顔を見るティルドラス。
「時に、君の義兄のロフトルザム親王をどう思う?」そんな彼の表情を見つめながら、何やら探るようにミッテルは尋ねてくる。
「……良いお方だと思う。」言葉を濁すようにティルドラスは答えた。
「良いお方、か。」ミッテルの言葉には、どこか嘲るような響きがあった。「なるほど、そういう言い方もできるか。だが、有り体に言ってしまえば馬鹿だ。単に親王という位の上にあぐらをかいて、天下のことも民のことも何一つ考えぬまま無為に日を送っている。君の甥のヨースタン公子の方は、親に似ず、子供ながら切れ者の素質十分なようだがな。」
「!」目を見張るティルドラス。
「もっとも、馬鹿は馬鹿なりにうまく利用する方法もある。」何やら独り言のような口調でミッテルは続ける。「馬鹿で操りやすい義兄を王位につけ、甥のヨースタン公子の代と二代に渡って王家の外戚として朝廷の権を握る――、そういう話に興味はあるか? もし興味があるならそれに向けて手を打とう。」
ティルドラスはしばらく押し黙っていたが、「いや、いい。興味など持てない。」とかぶりを振る。「君の言うようにして私が朝廷の権を握ったとして、それがいったい何になる? それで天下の民が少しでも幸福になるとは思えないのだ。」
「ほう、なるほどな。それが君の考えなわけか。なかなか面白い。」興味深げにティルドラスの顔を見つめるミッテル。
「私が何か面白がられるようなことを言ったかな。」少し気を悪くしたようにティルドラスは言う。
「少なくともここでは珍しいな。諸侯の地位にある人間で、そうした考えをはっきりと口にする人物には会ったことがない。――しかし気をつけろ。」ミッテルの口調が鋭くなる。「君が宮廷のせせこましい駆け引きなど超えた遠大な志を持っているのは分かった。だが、理想を追い求めて遠くばかりを見ているうちに、地べたを這いずり回る虫けらのような小人どもに足元を掬われることもある。そんな人間を何人も見てきた。悪いが君もそうなりかけている。」
「私が?」驚くティルドラス。
「ああ。」ミッテルは頷いた。「あるいはと思っていたが、君が自分でここにやって来たことで確信した。通常、諸侯がケーシに参朝する際には朝廷内の裏の駆け引きに通じた家臣が同行する。我々のような仲立ちをする人間への依頼も、本来はそうした家臣を通じて持ち込まれるものだ。ところが君は家臣からの助言を得られないまま自身の判断で僕に手助けを求めに来た。かつて天下に覇を唱えたハッシバル家に朝廷の裏に通じた者がいないはずがない。おそらく家臣たちが意図的に、そうした実情を君に教えずにいるのだろう。思い当たることはないか?」
「それは――」言いかけてティルドラスは口をつぐむ。そう、自分同様初めてケーシを訪れるチノーはともかく、朝廷の官位も持つフォンニタイがそうした裏事情を知らないはずがない。それを敢えて教えずにおき、自分が願い出を受け入れられぬままケーシで空しく日を送ることを望むのは――。
「おそらく君の叔母――摂政の差し金だろう。自分の親戚が摂政に阿る家臣たちにないがしろにされるのも業腹だ。そのあたりも折に触れて僕が指南することにしよう。」
翌日からミッテルは時々親王家に顔を出してはティルドラスと話し込むようになった。彼の年の離れた弟――この年十歳で名をグロリオという――も親王家を訪れ、こちらはナガン、ヨースタンと三人で遊ぶようになる。
周囲の様々な思惑が交錯する中、ティルドラスのケーシでの日々が始まる――。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
