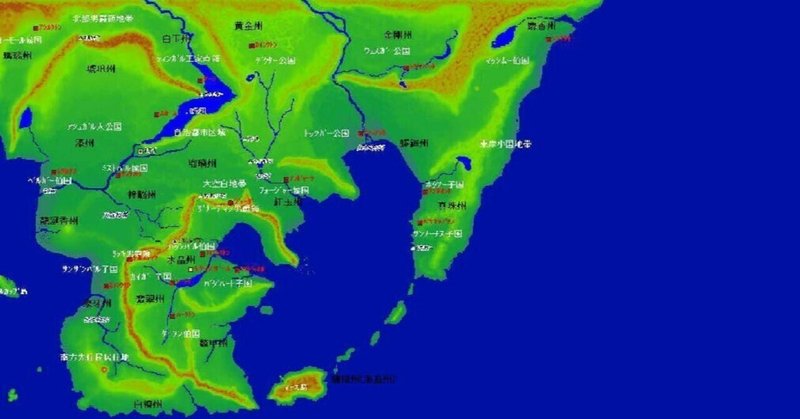
ティルドラス公は本日も多忙④ 都ケーシの宮廷で(58)
第十一章 饗宴(その6)
列席者たちが料理に箸を付ける間に、軽快な笛太鼓の囃子に乗って、流れを隔てた余興の舞台に芸人たちが入れ替わり立ち替わり現れては、ちょっとした軽業や寸劇などを披露してみせる。この余興の構成も、王や列席者たちを退屈させず、食事の邪魔にもならぬようホッホバルとドゥーカンが知恵を絞って考えたものだった。
前菜が終わり、羹(スープ)の椀が列席者の前に出される。毒味の手順が略されたので羹は出来たての熱いままで、いつもは冷めた食事しか食べられない猫舌の王は食べ終わるのに時間がかかるはずである。余興もそれを見越してのものだった。
突然激しい太鼓の音が鳴り響いたかと思うと、その拍子に合わせて剣を手にした二つの人影――サクトルバスとイスラハンが舞台に現れ、激しく舞い踊り始める。「おお!」慣れない熱い羹に手こずっていたゴディーザムだが、しばし手を止めて、目の前の勇壮な演舞に見入る。
互いを傷つけはせぬかと見る者がはらはらするほどの近い間合いで剣が翻り、時々激しく打ち合わせられて夕暮れの薄闇に火花が散る。ひとしきり舞ったあと、最後にひときわ強く打ち鳴らされた太鼓の音と共に二人は動きを止め、列席者たちに向かって恭しく一礼した。
「うむ、見事である。」ゴディーザムは大きく頷くと、少し離れて侍立するティルドラスに「あれはどのような者たちであるか。」と尋ねる。
「右の者の名はセルヴ=サクトルバス。臣の衛士にございます。身分こそ奴隷でございますが希に見る武勇かつ忠義の士で、臣は大いに信任しております。左の者はセギル=イスラハン。サクトルバスの友人でオーモール家の衛士を務めております。陛下の勘気を蒙りました主・ヒッサーフ侯爵へのお許しを請うため、御前で技を披露して王をお慰めしたいと申しておりました。」ティルドラスは答える。イスラハンを借りるに当たっての交換条件としてオーモール家から王への取りなしを依頼されており、それに合わせた答えだった。
「天晴れである。あれほどの者を奴隷の身分に止めておくのは惜しい。オーモール侯爵の衛士も、その武勇と忠誠を余は大いに嘉するものであると伝えておくように。」ゴディーザムは上機嫌で言うと、程よく食べ頃になった羹に手を付け始めた。
羹に続いて主菜と飯が供される。魚の蒸し物、炙り肉……。味付けは主にバーズモンが受け持ったもので、高価な香辛料を多用したケーシ風ではなく、材料そのものの味を引き出すことに主眼を置いていた。主菜が盛られる大皿はヘルツェンコの作、一切の装飾を廃して土の色と質感を前面に出した素朴な作りで、その上に蓮や葡萄の葉が敷かれて料理が盛り付けられ、品が変わるたびに葉が取り替えられて新たに盛り付けがなされる。「珍らかな趣向であるな。なかなか良い。」ゴディーザムが言った。
料理の合間に余興も続けられる。踊り、曲芸、奇術、そして宴も終わり近くなって舞台に歌い手と楽器を手にした者たちが並び、音楽が始まった。
指揮者の役割を担う打楽器の主席奏者はドゥーカンが務める。よく知られた合唱曲や合奏曲がいくつか奏され、最後の料理、果物と甘い菓子が列席者たちの前に並んだところでティルドラスがゴディーザムの前に進み出て言った。「次の曲は、おそらくケーシの宮廷の方々はご存じありますまいが、南方の民の恋歌でございます。」
「ほう、恋歌とな。」とゴディーザム。
ティルドラスの合図と共に曲が始まる。ラクナウの歌をドゥーカンが管弦楽の伴奏付きの合唱曲へと編曲した「楊柳の歌」だった。
――柳よ柳よ川辺の柳……――
Song of the willow 「楊柳の歌」|MURA Tadasi (村 正)|note
河原の楽士や歌い手、街娼の中で歌の上手い者たちまでもかき集めて作った急造の楽団ではあるが、ドゥーカンによる稽古のたまものか、周囲に朗々と響き渡るその曲に列席者たちはしばし箸を止めて聞き入る。少し離れた場所に座ったルシルヴィーネも熱心に耳を傾けているのがティルドラスの立つ位置からも見えた。
余韻を残して曲は終わり、舞台に並んだ者たちがゴディーザムに向かって一礼する。「おお、見事。」頷くゴディーザム。
この趣向は宮廷内で評判になり、ケーシではその後しばらく「田舎風」の名を冠した料理や調度が――我々の世界のロココ美術にも見られたような、現実とはかけ離れて美化された「田舎」ではあったが――貴人たちの間で流行したという。
宴が終わり片付けが始まる中、余興を演じた者たちや料理人たちを集めてねぎらうティルドラス。「王のお気に召したかどうかは分からぬが、十分に満足のいく出来だったと思う。よくやってくれた。感謝に堪えぬ。」
「お役に立てて何よりでさ。」彼の言葉にガルマが満足そうに頷いた。
そこに王宮の使いの者が姿を現し、ティルドラスに向かって声をかける。「籍田令ティルドラス=ハッシバル、参られませい。王よりお褒めの言葉が下される。併せて、先の願い出についてお聞き届けがあるとの仰せである。」
「成功だ。」他の者たちと共に裏方の役目を務めていたミッテルが囁く。「事は成ったぞ。さあ行け。」
胸を躍らせながら、ティルドラスは使いの者たちに先導されてゴディーザムの前へと伺候する。「今日は大儀である。」目の前に跪くティルドラスに向かって声をかけるゴディーザム。「なかなか興味深い趣向であった。誉めて取らすぞ。聞くところによれば籍田令としても熱心に勤めておるとのこと。その方の忠勤、しかと見届けた。」
「身に余るお言葉にございます。」
「先に願い出のあった旧バグハート領の差配であるが、願い出の通りその方に任せることとする。追って大鴻臚の府より沙汰があろう。慎んで受けるが良い。」
願い出とはそちらのことだったか。しかし旧バグハート領の件も重要であることに変わりはない。「ありがたき幸せ。」多少失望しながらも恭しく頭を下げるティルドラス。
「もう一つの願い出はその方の婚儀についてであったな。そちらについても良きように取り計らおう。」
はっと息を呑むティルドラス。「では――お聞き届けいただけるのでございますか?」
「王の言葉に座興・偽りはないぞ。心して待て。」ゴディーザムは鷹揚に言う。
「あ、ありがとうございます!」喜びのあまり大声を上げそうになるのを辛うじて抑えながら深々と低頭するティルドラス。
「とはいえ、事は王家の娘との婚儀である。一朝一夕には行かぬ。」ゴディーザムは続ける。「まずは我が娘か姪たちの中からその方に娶すのに相応しい者を選ばせることとする。その方も身を慎み、かりそめにも王家の婿として恥ずかしき振る舞いなどいたさぬよう、しかと申しつけておくぞ。」
「は?」思わず顔を上げるティルドラス。だがその時には、王はもうきびすを返して歩み去るところだった。「王家の娘との婚儀――?」その場に跪いた姿勢のまま、彼は呆然と目を見張る。
周囲にはまだ、宴の名残の笑いさんざめく声が響いていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
