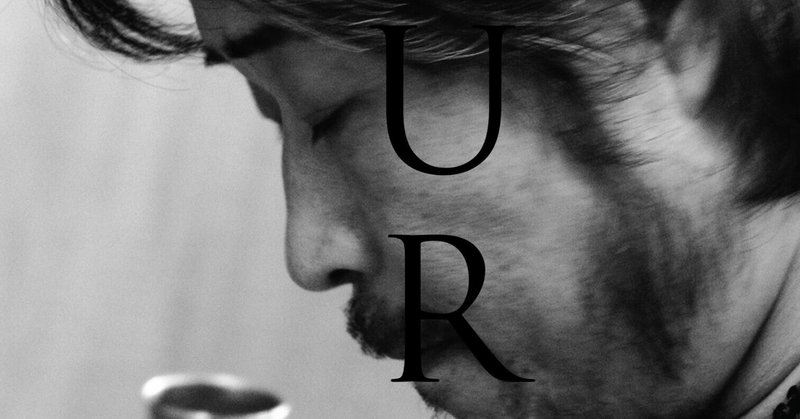
「作品には人生が表れる」伝統と機能を掛け合わせた唯一無二の漆塗りガラス
【インタビュイー】ガラス作家・藤井 嘉彦
和歌山県海南市の黒江で「塗り工房ふじい」を営む藤井嘉彦さん。
紀州・黒江は、山中塗り、会津塗りと共に漆塗りの三大生産地。そんな漆の街で生まれ育った藤井さんは、世界で初めてガラスと漆塗りを組み合わせた食器を開発。テーブルウエアの世界に革命をもたらした。
日本の伝統が持つ美しさと西洋の機能性を掛け合わせた食器は、藤井さんにしかできない唯一無二の作品として、国内外から高い評価を得ている。
流行にとらわれず、自身が心の底から作りたいと思ったものだけを作る。作品づくりにかける思いを伺った。
「家業を継ぐのは当たり前」紀州漆器の里、黒江で生まれて
ーーこの道に入ったきっかけは?
藤井嘉彦さん(以下、藤井):僕の家は、黒江で代々漆器業を営んでいました。
黒江は紀州漆器の里とも言われていて、漆器づくりがさかんな街。子どもの頃から、漆は当たり前にありました。
僕らのころは、家業がある家の子は自分の意志とは関係なく、学校を卒業したら継ぐのが当たり前の時代。伝統を守りたいとか引き継ぐとか、当時は深く考えていませんでした。
ただ子どもの頃から、なんとなく食器はすきでした。 昔は自営業の家の子は継ぐのが当然といった風潮でしたが、今はだいぶ変わりましたよ。僕には息子がいますが、継がなくていいと思っています。

ーー息子さんが継がなくてもいいと思っている理由を伺っても?
藤井:人から与えられたものではなく、自分自身の人生を生きてほしいんですよ。継ぎたいと言えば、これまで培ってきた技術は教えるし、工房にある機械なんかも渡しますが、僕と同じものは作れないし、作る必要もない。
ものは人なり、人となりで、どんな人生を過ごしてきたかが作品に表れます。自分の人生で作り上げたセンスは、永遠に通用するもの。だから唯一無二の作品が生まれると考えています。
ものづくりは苦しいことの連続。人よりも努力しているか、これで自分は許されるか、バチは当たらないかとか、そんなことをずっと自問自答し続ける修行みたいなもの。覚悟がなければ、続けられないですよ。
僕らの学生時代は家を継ぐのが当然のことだったけれど、今は選べる時代。僕好きなところも好きなところへ行って、好きなようにやっている。息子にもすきなことを存分にやってほしいと思っています。

「漆しかやっていない自分」海外で味わった栄光と挫折
ーー家業を継いだ頃、どんな生活をしていましたか?
藤井:高校を卒業して家業を継いだ頃から、漆器の海外輸出を主に僕がやっていました。年に数か月、中東やヨーロッパなどへ出掛けて行って、展示会に出て販売してきます。
当時の日本は世界の工場的な感じで、少し前の中国のような位置づけでした。景気のよいエリアでは、おもしろいように売れていきましたね。
ーー転機となったことは?
藤井:30歳の頃、バブルが弾けた時期ですかね。急速に円高が進んで、海外で日本のものが売れなくなりました。
ちょうどその頃、世界の工場が、日本から中国へと移っていった。奈落の底に叩き落されたような感じでした。 どん底でいろいろ考えましたよ。これまで流行りを追いかけて、帳尻を合わせてパーッと売れるものばかりを作ってきたけれど、本当にそれでよかったのか?
幸い僕は海外に行く機会が多かった。日本は集団やチームで成果をあげることがよしとされる社会。でも日本を出ると、個人でも評価される世界があることを知っていました。 時代の流行を追うことはやめて、これからは自分にしかできないものを作ろうと決めました。

ーーなぜガラスと漆器を組み合わせようと?
藤井:海外の展示会に行くと、「漆器は傷がつく」とよく言われていました。
日本を始めとするアジアでは、日常で食べる時に使うのは、箸。一方、ナイフとフォーク、陶器の食器を使う食文化の欧米では、当然のことですよね。 「漆の食器は傷つきやすい」というデメリットをなんとかできないかとずっと思っていました。それに漆器は熱や湿度にも弱くて、輸送中に壊れてしまうことが多々ありました。そこをクリアできれば、海外でももっと受け入れられる可能性があると。
趣味でガラスを塗っていたこともあって。ガラスの裏目から漆を塗ることができれば、ナイフやフォークでも傷つかないのでは?と思ったのがきっかけでした。
「レーザーを使って絵を描くガラス漆器」さらなる進化を目指して
ーー藤井さんの代表作品でもある、「レーザー蒔絵」の魅力を聞かせてください。
藤井:蒔絵は漆器の表面に漆で絵を描いて、金粉や銀粉を使う技法です。
漆器は、表面加工が弱点で傷がつきやすいこと。その弱点をガラスの裏目から漆を塗る方法でクリアしました。
漆器に絵を入れるとなると職人の手作業になるわけですが、うちはレーザーを使って絵や模様を描いています。レーザーを使ったことで、クオリティーも安定して、早くしかも量産ができるようになりました。
手描きの蒔絵は流動的で躍動感のある絵は難しいのですが、光の繊細な流れや柔らかい自然の曲線も描けるんですよ。ガラスに完全密着しているので傷が付かない。ガラスなのに、漆器独特の絵の感じや色合いが出ていることに、感動してくださる方が多いです。
ーーデザイナーの稲葉絵里さんとコラボした作品、「PERLA」や「FATA」はこれまでのイメージと少し違います。コラボした経緯は?
藤井:稲葉絵里さんとはもともと友達だったんです。彼女は、神戸に住んでいるごく普通の主婦。専門的にデザインを勉強したことはないと言っていました。 ですが、僕は彼女の中にある豊かな感性とセンスのよさを感じていて。自分の人生の意志表現を形に落とし込める方だと思っていたので、いっしょにやってみたいなと。
彼女が住んでいる神戸は真珠の街でもあるので、真珠をモチーフにした「PERLA」や「FATA」が生まれました。
ーー知っている漆器とは色合いが全く違って驚きました。どんな反響がありましたか?
藤井:ありがたいことに、各方面から高く評価されています。
とくに「PERLA」は、色目の美しさもあって、反響は大きかったですね。コラボしたことで、これまでの漆の世界とはまた違う世界観を表現できました。


「黒江の技術をもっと知ってもらいたい」死ぬまで挑戦し続ける
ーー藤井さんにとって「塗る」とは?
藤井:気が向いているからできることだと思っています。
実は僕自身、漆に対してそんなに強いこだわりがあるわけではないんです。 なんて言うと驚かれるかもしれません。漆にこだわりはないですが、品質と技術にはものすごくこだわっています。ガラスと漆が完全に密着しているのは、うちだけの技術と誇っていますし、最近の生活仕様に合わせて食洗器でも使えるようになっています。
僕がこれまでやってきたことは、先代たちが生き残るために継承してきた技術を活用しているにすぎない。ガラスと組み合わせたのも、伝統を残したい気持ちもあるけれど、生き残るためでもあります。
ーー今後の目標やビジョンを聞かせてください。
藤井:「知ってもらうこと」でしょうか。
漆塗りガラスの知名度は、日本国内でも1~2%といったところ。全世界に知ってほしいですね。 今は、主にレストランやホテルなどで使ってもらっているのですが、漆器自体、冠婚葬祭やお正月などのイベントごとでしか使われないですよね。漆器はもともと日常で使うための食器。何気ない毎日の生活が華やぐような、普段から使えるようなものを提案していけたらと思っています。
それから、黒江の漆器の技術をあらゆる分野に活用できるようになればいいですね。 これから大阪万博に向けて、関西エリアはどんどん盛り上がっていくでしょう。そこで2023年の8月には、漆建材を使ったギャラリーをオープンする予定です。漆をテーブルウエアとしてだけでなく、住む環境からもっと身近に感じてもらいたいですね。
僕は、苦労は幸せの種だと思っています。そんな幸せの種が、「人生」となって作品に表れるのではないでしょうか。
これからも僕にしか作れないものを表現するために、死ぬまで挑戦し続けたいですね。

藤井さんの作品はこちらからご覧いただけます!
日本橋アートうつわは、日本の文化を継承する陶磁器・漆器・ガラス販売サイトです。
つくりて様が1点1点こだわり抜いたうつわ作品を多数ご紹介、販売しております。日常にぜひ日本文化を取り入れてみてはいかがでしょうか?
会員の方々のインタビューも随時更新しています。
つくりて様それぞれの作品へのこだわりや、ものづくりへの思いが詰まったインタビュー記事も是非ご覧ください!
