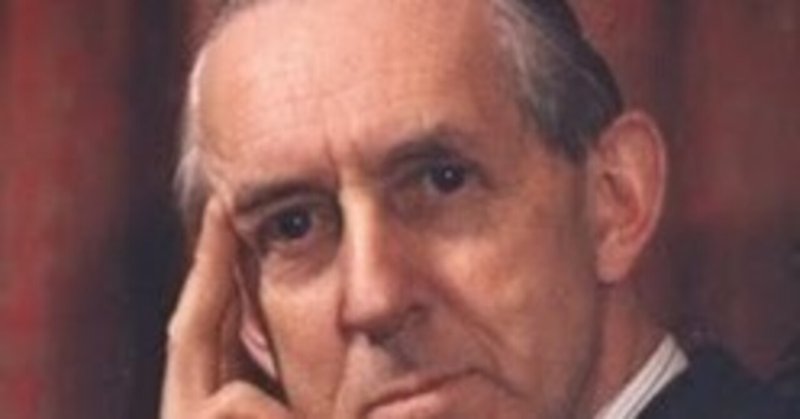
39 ひとつになった仏教世界(上) 仏教ルネッサンスの時代|第Ⅲ部 ランカーの獅子 ダルマパーラと日本|大アジア思想活劇
仏教ルネッサンスの時代
アナガーリカ・ダルマパーラの死の翌年、昭和九(一九三四)年、日本では高楠順次郎らの提唱で「仏誕二千五百年」を祝う盛大な行事が行われた。ただしこの年がブッダ釈迦牟尼の誕生より二千五百年といえるか否かは宗派によって異論が甚だしく、学問的にもいまだ確定していない。この高楠のキャンペーンは昭和五(一九三〇)年五月にハワイで開催された「第一回汎太平洋仏教青年会大会」での決議を踏まえたものではあったが、日本仏教界の大事業である『大正新脩大蔵経』が同年に完成したことを機に通仏教的記念行事を開くという、便宜的色彩も強かった。ゆえに田中智学はじめ日蓮仏教の関係者が強く批判したほか、西本願寺もこの年の末になって高楠の説を認めない通達を出すなど、日本仏教徒挙げての祝祭とはとても言いがたいものだった。
しかし、昭和九(一九三四)年はアジア仏教徒の国際交流という点では画期的な年になった。東京では「第二回汎太平洋仏教青年会大会」が盛大に開催された。同年七月十七日から十二日間までの大会に、外国代表十二カ国(中華民国、インド、マレー、シンガポール、タイ、ハワイ、カナダ、ビルマ、セイロン、ジャワ、満州、アメリカ合衆国)三百二十余名、日本代表三百名余り、その他含めて千人以上が集結したのである。

英領セイロンからはダルマパーラの後継者で大菩提会主事のデーヴァプリヤ・ヴァリシンハ、一九一五年セイロン暴動に際して獄死したダルマパーラの実弟エドムンドの未亡人らヘーワーウィターラナ家の関係者を中心に総勢六名の仏教徒が参加した。
大会では世界平和促進運動に関する決議、人種平等に関する決議、聖地ブッダガヤ復興に関する決議、仏教青年会の本尊を釈迦仏とし礼拝形式を三帰依とする決議、仏教の本質を「涅槃を理想として菩薩道の実践を期するもの」とする決議、汎太平洋仏教青年会連盟結成に関する決議など、世界仏教徒を貫く仏教の基本的な立場が確認された。
長く停滞を強いられていた仏教が、太平洋諸国にまたがる世界宗教として、新たな雄飛を図ることを堂々と宣言したのである*94。それにしても、汎太平洋仏教青年会大会の決議は、一八九一(明治二十四)年にオルコットが提唱した『十四々条の信仰条規』をわずかながら想起させる内容ではなかろうか。十九世紀の末、白い仏教徒によって端緒をつけられた「ユナイテッド・ブッディスト・ワールド」のビジョンは、二〇世紀半ばのひととき、おぼろげなリアリティをまとい始めていた。
この気運に乗じて、日本仏教の国際的活動機関として『国際仏教協会』が設立され、仏教の海外伝道や西欧・アジア各国など世界仏教徒との連絡を図った*95。『大正新脩大蔵経』(大乗経・小乗経という旧来の区分を廃止した)がこの年に完成したのに続き、同年から昭和十六(一九四一)年にかけて、高楠順次郎の監修のもと、パーリ語三蔵のほぼ完全な邦訳である『南伝大蔵経』が刊行された。
高楠はこの南伝大蔵経の翻訳にあたって次のように述べている。
仏説に南北の別があるわけでなく、初めから大小を分って説かれたわけでもない。仏所説の内容は同じ処から出発したもので、一切の法門はその水源を同じくしているわけである。一方には仏の人間性に重きを置いて、仏が教えられたり、行われたりしたことを、そのままに守ってゆこうとする人々もある、言わば世尊の正風を残そうとする形式派である。また一方には仏の如来性に重きを置き、同じ仏が教えたり、行われたりしたことをも、そのままでなく、その心持ちを失わぬように守ってゆこうとする人々もある。言わば世尊の正意を掴もうとする精神派である。……元来形式と精神とは別々のものではなく、形式を具した精神、精神を具した形式でなくてはならぬ。形式から精神も出で、精神から形式も出来るのであるから南北大小の経論もその内容から見るときには一脈通じたものがあるのである。そこで、真の研究の立場に立って見れば大小乗を区分すべきものではない。

いささか皮相的な見解ではあるが、高楠は従来の大乗仏教至上主義から脱却し、通仏教的な視点からパーリ仏教を日本へ紹介しようとしていた。
このような日本仏教の積極的な活動の背景には、釈宗演の遺志を継いだ鈴木大拙の努力による禅仏教の欧米での評価のほか、左翼勢力による激しい「反宗教運動」が一段落して「宗教復興」のムードが高まったこと、日本仏教運動の主体が在家のインテリ層に広まっていったことなどが挙げられるだろう。仏教研究家として岡本かの子がもてはやされ、新しい大衆メディア・ラジオで放送された友松圓諦の『法句経』講義、高神覚昇の『般若心経』講義が大反響を呼んだ。友松と高神は同年夏、宗派を超えた仏教啓蒙運動「全日本真理運動」を発足し(翌昭和十年一月には機関誌『真理』を創刊)、瞬く間に数万の会員を集めるに到る*97。昭和の初頭、日本では仏教ルネッサンスとも呼ばれる言論界の仏教バブルが起きていたのである。
『海外仏教事情』誌における南北仏教対話
この仏教ルネッサンスの時代にあって、日本仏教の外交窓口となった国際仏教協会の機関紙『海外仏教事情』(明治二十年代初頭刊行の同名誌とは別物)には欧米仏教徒との通信のほか、スリランカなど上座部仏教圏の僧侶による大乗仏教教理への批判や異議申し立てもそのまま掲載されていた。同誌上で世界の仏教徒の間での思想的な対話と相互理解を図ってゆく傾向が見られたことは、現在から振り返っても特筆すべきではなかろうか。
例えば、スリランカのナーラダ長老は『海外仏教事情』に寄せた「上座部と大乗」という論文のなかで、「仏陀の真面目な信奉者として、筆者が浄土教徒に切望する点はゴータマ仏陀をその正常の位地に置くことで、その理由は正法を発見して我々に仏陀への道を教示した人こそゴータマだからである。」と日本の阿弥陀信仰への率直な疑問をぶつけている。
また、ナーラダ長老は同論文のなかで南伝大蔵経の邦訳に触れ、「(これ)に依って日本仏教徒が今まで以上によく諒解するのは仏陀の根本教説だろう。なお筆者が欣快とする所は、日本仏教学者諸賢が小乗(Hinayana)という軽侮的名称を深甚なる考慮の結果削除して、パーリ聖典の翻訳に一層の友誼的かつ適切な言葉を採用したことである。」と積極的な評価をしている*98。
また同じく『海外仏教事情』誌上には、鈴木大拙夫人であるビアトリス女史の論文*99への反論という形で次のような投稿も寄せられた。筆者のシリワルダーナはいわゆる「小乗」仏教への無理解と蔑視観に基づく「南方仏教=小乗仏教=矮小な自利主義、日本仏教=大乗仏教=広い視野を持った利他主義」というレッテルを批判してこう語っている。
鈴木夫人及び夫人と同類の人々に一つ訊きたい事がある。即ち大乗仏教のために大いに主張しているがこれらの慈悲深かるべき同胞は過ぎ来し世紀中、法の恵みを他にも与えたか、彼等仏教の基調は利他であると容易に言われるが、この利他ということはパーリ語経典には無いかの如く言っている。彼等は仏陀が弟子達に要求した精神に則って振る舞ったか、……故ダンマパーラの強烈な活動の結果として、仏教インドに如何なる事が起こりつつあったを見知するのに近代日本は四十年も要した。

この時期、日本仏教はようやく、ダルマパーラが望んだごとく世界仏教の核としての自覚を持って働き始めたかに見える。それは大日本帝国がアジアの列強植民地の「解放」を大義名分として、帝国主義的な膨張を志向していたことと見事に足並みを揃えた動きでもあった。そして仏教が日本国家の勢力拡大に「追従」することは、ダルマパーラが生前まじめに望んでいた日本仏教の進路だったのだ。
大東亜共栄圏と日本仏教・ひとつの事例
いわゆる大東亜戦争と日本仏教との関わりについて、本格的な研究は少ない。以下は筆者が本書の調査過程で拾った事例のメモ書きである。
これはほとんど指摘されないことだが、大日本帝国がアメリカ・イギリスなどの連合国に戦端を開いた昭和十六(一九四一)年十二月八日は、北伝仏教の伝承では釈尊が悟りをひらいた「成道会」にあたった。また、緒戦の勝利を象徴するシンガポール陥落は翌年の二月十五日の「涅槃会」であった。大本営発表の華々しい戦果に浮かれた日本の仏教者は、これを大東亜共栄圈建設に仏教が果たすであろう聖なる役割を象徴する「慶事」として言祝いだ。
東南アジアのテーラワーダ仏教圈は、日本の大東亜共栄圈構想にすっぽりと組み入れられた地域であった。インド学者やパーリ仏教の研究者たちは薄暗い研究室から引っ張り出され、イラク戦争前後に中近東研究者がマスコミで引っ張りだこになったように、南方進出に伴う占領地経営のブレーンとしてもてはやされ、周囲の羨望と嫉妬の眼差しを浴びていた。
実際に大東亜戦争突入前後の南アジア情勢を概観すれば、インドではガンディー、ネールに率いられた国民会議の主流派が満州事変以来、日本に批判的な姿勢を取ってきた。しかし、ラス・ビハリ・ボーズ等、日本を拠点にして、反英インド独立運動を続ける勢力も隠然と存在していた。
また戦時中には国民会議左派のカリスマ、スバス・チャンドラ・ボーズが日本との同盟を結び、自由インド仮政府を樹立した。すでに敗色が濃厚になっていた昭和十九(一九四四)年三月、ボーズの指揮するインド国民軍は、無謀な作戦の代名詞たるインパール作戦発動に伴い、日本陸軍とともにインド本土への進撃を開始する。
一方、英領セイロンにおいても大東亜戦争の開戦後、『大菩提会』のデーヴァプリヤ・ヴァリシンハが一時英国当局に拘束された。大菩提会をはじめスリランカ仏教徒の一部には反英・親日の傾向が強く、潜在的な利敵組織として監視を受けていたのである。日本軍が破竹の進撃を続けていた昭和十七(一九四二)年四月五日には、コロンボとトリンコマリーのイギリス軍港が日本軍の爆撃を受け、航空母艦ハーミーズが撃沈された。スリランカ民衆の一部は、この攻撃にひそかに喝采したともいわれる。
前述の国際仏教協会は、大東亜戦争突入後も、『海外仏教事情』で共栄圈内各地の仏教国の実情を紹介し、南方上座部仏教に関する知識の啓蒙に努めた。東京において昭和十六(一九四一)年から毎年『南方仏陀祭(ウェーサーカ・プージャー)』の行事を執り行ったこともその一環である*101。
腹の底はともかくとして、偏狭な「大乗仏教優位論」を振りかざすことなく南方仏教を理解しようとした仏教者たちの姿勢は、価値相対主義の浸透した現代から見ても驚くほどに、徹底していた。昭和十九(一九四四)年六月には「釈興然追悼号」を発行して、日本仏教界で無視されてきた釈興然グナラタナ師の再評価を試みた。興然の弟子として、当時日本人ではただ一人、南方上座仏教の戒法を護持していた釈仁度はそのなかで曰く、
日本の仏教徒は今日までみずからの仏教を大乗仏教と称し、南方のそれを小乗仏教とさげずんでいた。しかし立場を変えて南方仏教徒をして日本の仏教徒を批評せしめたならば何というであろう。かれらが日本仏教を真正なる仏教として認めることは困難であるらしい。これが現状である。このまま放置しておくときにはこの対立は共栄圈建設の癌ともなる危険を孕んでおる。日本仏教徒は南方仏教をたとえ信奉するには至らぬまでも理解しようとの努力を一日もゆるがせにすることはできない。これなくしては共栄圈建設に対する仏教徒の協力という言葉は空辞にすぎない。

しかし、この時すでに日本の敗色は濃厚になっていた。負けが込んでくるとアジア仏教徒の連帯を説く「開かれた」言説は陰を潜め、紙の欠乏でやせ細るばかりの仏教ジャーナリズムの紙面ではひたすらに「皇道精神」の発揚が叫ばれた。日本仏教は自虐的なまでに時局への過剰適応を図り、もはや仏教という表象すらもかなぐり捨てて、ひたすら危機に瀕する「不朽の国体」への全面帰依と皇道精神への同化を叫び続けた。「鬼畜米英」「聖戦完遂」といった国家から下賜される愚劣な戦争スローガンをひたすらに内面化しようと励むことが仏教者の仕事となっていた*103。
アジア仏教徒の連帯を説き、日本人とは異なった仏教のあり方を「理解しようとの努力」にしても、それはあくまで外向きの「方便」に過ぎなかったともいえる。日本国内においては、「グット己れを死切つて、天皇に帰一し奉り、八紘一宇の大精神に生きる道理を教へるのが佛教であると思ふ」(「大東亜建設の経綸と佛教」)といった代物が仏教だと喧伝された。これは別に大戦末期のうわごとではない。大東亜戦争緒戦において、『大法輪』昭和十七年二月号に掲載された論説である。それも神道指導者によって皇道精神純化の名のもとに展開されたキリスト教や仏教への攻撃に「反論」したものだ。国家意志へのひたすらなる奉仕のみが、国家意志(大我)の前に無我たること(なんと悲惨な断章取義か!)のみが、大東亜戦争期の「日本仏教徒」に許され得る表向きの言説であった。
日本が釈興然を「再発見」してから約一年後、日本の敗戦によって大東亜共栄圈は崩壊した。「皇道仏教」の時代は終わり、さっさと忘れ去られた。良心的であれ、野心的であれ、日本仏教の海外活動も停止した。かつてダルマパーラが創設に関わった『日印協会』も、戦時中ラス・ビハリ・ボーズ、スバス・チャンドラ・ボーズらのインド独立運動を支援したかどで、GHQから政治文化面の活動を禁止された*104。
クリスマス・ハンフレーズと「仏教の十二原理」
未曽有の敗戦と連合国による占領統治下で、仏教徒たちもまた茫然自失としていた一九四六(昭和二十一)年二月、イギリスからひとりの仏教活動家が来日した。ロンドン仏教協会長 クリスマス・ハンフレーズである。彼(Trevers Christmas Humphreys 1901-1983)は、イギリスの法律家家系に生まれ、ケンブリッジを卒業後、法曹界に入った。若くして神智学協会の会員となり、のちに仏教へ傾倒していった(一九二八年に出版された『仏教とは何ぞや?』に、仏教本来の積極性を主張する教証としてブラヴァツキー夫人の言葉が引用されている)。弁護士資格を取った一九二四年、ロンドンに神智学協会の仏教ロッジを開設するが、これはのちにロンドン仏教協会(Buddhist Society, London)としてヨーロッパ仏教の拠点に成長していった。

前述のように一九四六年から来日して、「英国代表検事(Wikipediaの記述には副検事 assistant prosecutorとある)」として極東国際軍事裁判(東京裁判)に関わったというのだが、具体的にどのような仕事をしたのか、詳細は分かっていない。来日早々、ハンフレーズは「日本仏教の復興」に向けて精力的に動き始めた。
4月には総持寺で、6月には西本願寺で、東西別々に各宗の代表者を集めて、仏教の共通理念としての、所謂「仏教12原理」を提示し、東西の委員会にこれが承認を求めた。
彼は6月には妙心寺で、7月には知恩院に出講して日本各宗の代表者たちが、この12原理に一致点を見出したことに非常な満足の意を表明し、3ヶ月以内に全世界をおどろかすニュースとなるであろうと予言した。これは丸で明治10年頃(ママ)に来日したオルコット大佐の故事を思い出させるほどのものであった。
占領期の一九四九(昭和二十四)年にはハンフレーズの著書『新日本と仏教』が刊行されており、そこには彼が日本仏教復興のためにと持ち来った「仏教の十二原理」が披露されている。これは前年に、英国仏教徒を対象として策定されたものだが、上座部仏教をベースにした合理的で明快なオルコットの十四箇条に比べると、内容的には大乗仏教の教義にも配慮して「万有の根源的生命」やら「最高実在の顕現」といったヒンドゥー教の梵我一如論と共通した俗流「如来蔵思想」的言辞がちりばめられており、霊魂の実在を信じる神智学悩の人々にも親和性の高い文章になっている。その割には大乗仏教の根本教理たる空の思想や六波羅蜜には一切触れず、もっぱら四諦、中道すなわち八正道を宣揚しているあたり、チグハグ感は否めない。それでも、日本の僧侶にとっては、悩みの種である五戒(特に不飲酒戒)に触れないのはありがたかったのではないか*105。
一九四六年(昭和二十一年)二月私は日本へ来た。そして四月に、横浜の総持寺に私を尋ねられた著名なる仏教者に対して、私はこの十二原理を提示した。これ等の仏教学者達は、この種の原理を広く出版に附すことの必要を感じて、直ちに、文学博士長井真琴氏を委員長とする委員会を問う今日に組織して、この十二原理が日本仏教各宗の承認を得られるか否かを検討した。そして本原理の日本語訳を作製、熟慮の後、これを採用することに決定した。
彼は同年六月に京都に赴き、この十二原理を十七宗派の代表者の前に提出した。戦勝国から天下った白人仏教徒の前に並んだ各宗派の代表者は緒方宗博氏の日本語訳を読み、
即座に、この原理を一般的に承認し、尚詳細な検討を加える為に龍谷大学々長森川智徳氏を委員長とする委員会を組織した。そして後日この委員会も全面的に本原理を承認した。それ故に、日本歴史始まつて以来最初の出来事として、各宗派の同意した日本佛教が出来上つたと言つてもよいのである。
「私が日本滞在中、十七の主な仏教宗派の会議の席上で仏教十二原理を提案したとき、一番困難であろうと思ったのは、何人も結局は努力によって自らの救いを成就しなければならないという提案にたいして真宗および浄土宗の賛同を得ることであった。しかし真宗連合の長たる京都西本願寺法主が学究的な人であったおかげで、全面的な同意を得ることができた。その結果、詳細については拙著「東京を経由して」に述べたように、はじめて日本仏教に統一を与えることになった。というのも、真宗はオルコットの仏教信条を承認した日本の仏教宗派の名簿からはっきり脱落していたのだからである。」
ハンフレーズは自らのミッションをこう自画自賛している。日本側の反応はどうだったのだろうか? 結論からいえば、まもなくほぼ完全に忘却された、というのが正しいのだが、前述の『仏教大年鑑』には、
「素より事実は彼が夢見ているように簡単に行く問題ではなかったが,彼の投じた一石は決して無駄ではなかった。
各宗の代表的学者に全一仏教,国際仏教運動について考えねばならないという強い刺激を与えたことはたしかであった。」(十九頁)という比較的、肯定的な評価も記されている。ハンフレーズの奔走は、意気消沈した仏教徒の心に希望の灯をともしたのである。
一九五七(昭和三十二)年に訳出された『仏教』(緒方宗博訳、青山書院)序文で、中村元は「かつて戦争直後には日本へ来たこともあり、その事情を記憶している中年以上の若干の日本人は、複雑な気持を以て氏を見ていることだろう」というコメントを寄せた。ハンフレーズとの関わりは、日本仏教徒にとって、あまり思い出したくない過去になっていたようだ。

ハンフレーズは鈴木大拙に心酔しており、大拙から長年にわたり禅を学び、海外での出版エージェントを勤めたことでも知られる(大拙の著書の編者として名を連ねているものもある)。ただし大拙自身は、おそらく高額のエージェント料金を取るハンフレーズに対して苦々しい思いを抱いていたようで、「ハンフレーズは○にきたなく、又何でも自分のものにしたがる○○○○○○○○人物だ、但々英国の仏教会をもり立てて二十年もつゞけて居るところだけが感心、それ以外に何もなし」(昭和二十八(一九五三)年十二月十七日古田紹欽宛て書簡 『大拙全集』三十七巻、岩波書店、二〇〇二年、二六一頁〜二六二頁 ○は伏字)と斬って捨てている。

オルコットの再来とまではいえない(彼は明らかにオルコットの仕事を踏襲し、もっとうまく成功させたと思っていただろう)までも、日本仏教の未曽有の危機に際して、諸宗派の統一を促し、日本仏教の復興を図らんとしたヨーロッパ人仏教徒がいたことは、忘れ去ってしまうには惜しい興味深いエピソードだ。
ハンフレーズは、仏教が新生日本の精神的基盤となるべきことを強く訴えていた。
全日本の文化及び芸術の根源は仏教であり。日本が再び武力の上に立つことは許されないことであるが故に、東方に於ける日本の将来はその国民性に懸って居るのである。而してその国民性は、主として仏教から流れ出た哲学、宗教、文化、及び芸術の産物に外ならない。それ故に、日本に於て強力なる仏教復興が計画され、仏教が再び寺院の外に飛び出して、民衆の日常生活の中に深く喰い込んで行くことなくしては、東方に於ける精神力としての日本は死滅するであろう。
この日本人独特の美しさと言うものは、勿論それは仏教に依って養われたものであります。それで仏教精神こそ日本の心臓であります。若し仏教が日本で死滅したとすれば、心臓が止って四肢が動かなくなるが如く、日本全体が死滅する時であります。
戦勝国の占領者として、祖国に対する「事後法による裁き」に関わった英国人仏教徒からのエールを、日本の仏教徒たちは素直に受け入れることができただろうか。少なくともこの時、ハンフレーズと日本仏教徒の間に、対等の関係など成り立ちようがなかった。戦後日本を占領統治したGHQは、積極的に日本をキリスト教化しようとしていた(皇室のキリスト教化に関してはかなりの成功を収めた……)。マッカーサーが、キリスト教化されない限り日本の民主化は成功しないと、恐ろしいことを考えていたのはよく知られている。アメリカやヨーロッパからは大量のキリスト教宣教団が日本に押し寄せ、聖書ブームが起こり、一部では集団改宗も発生していた。そんななか、少数とはいえ「仏教国日本」復興のためにひと肌脱ごうとしたヨーロッパ人仏教徒がいたということは、やはり記憶に留めておくべきであろうか*106。
註釈
*94 第一回の大会は一九三〇年五月二十一日から六日間、ハワイ・ホノルルで開催されたが、総勢二百名ほど、日本・ハワイからの参加者がほとんどであった。第三回大会はアメリカ合衆国で開催されることとなっていたが、時局の緊迫から結局流産した(『仏教年鑑』昭和十年版 1935, P.58 参照)。ちなみにスリランカを支配していたイギリス当局は一九三四年の「第二回汎太平洋仏教青年会大会」を日本がアジア地域における主導的地位を確立する陰謀の一環とみなして警戒していた。帰国したスリランカ仏教徒の代表団は警察から尋問を受け、日本との関係について執拗に問いただされている(〝THEY TURNED THE TIDE〟Sinha Ratnatunga , Sri Lanka 1991 p124)。
*95 日本仏教徒の海外宣伝活動は、明治二十年代の高楠等による「海外宣教会」以来途絶えていたが、大正末年頃から鈴木大拙の主宰する〝The Eastern Buddhist〟と高楠順次郎・桜井義肇による〝The Young East〟が発行され、俄然活気づいた。『国際仏教協会』はその流れのなかで、仏教学と日本仏教の国際的な普及を目的として設立された。機関紙として邦文「海外仏教事情」英文の〝The Young East〟を発行し、欧米、アジアなど世界各国に支部を持った( 「国際仏教協会設立趣旨」『海外仏教事情』No.4-2, 1937.2, 「国際仏教協会会則」同No.2-5, 1935.5)。なお、日本仏教徒の海外活動の代表的なものとして、日蓮宗の藤井日達による日本山妙法寺教団が挙げられる。藤井らのインド布教はガンディーとの関係を含めて比較的よく知られている。日達の自伝『わが非暴力 藤井日達自伝』(山折哲雄・編、春秋社、一九七二年)でも回想されている中国大陸やビルマにおける日本軍部との緊張をはらんだ関係性などには興味が尽きないが、本書では触れることができなかった。
*96 『雪頂・高楠順次郎の研究』八十八頁
*97 『20世紀の仏教メディア発掘』安食文雄、鳥影社、二〇〇二年、一〇一頁以降参照のこと。同書には友松らの真理運動をめぐる顛末が詳しく紹介されていて面白い。
*98 『海外仏教事情』第四─三号、一九三七年四月
*99 「大乗仏教に於ける利他思想」国際仏教協会発行の英文誌〝The Young East〟に掲載された。未読。
*100 「大小乗優劣論 鈴木夫人に問ふ」(『海外仏教事情』第三─九号、一九三六年十月)
*101 釈尊正風会では興然がセイロンより帰国した明治二十六年以来、「伏舎佉月満月会」と呼びウェーサーカ・プージャーを伝えていた。昭和十六年七月、本来の暦からはずいぶんと遅れて日比谷公会堂で「南方仏陀祭」が挙行された。しかし法要の導師は興然の直弟子である釈仁度師ではなく、ベンガル人比丘のラーストラパーラ師が務めた。この南方仏陀際は戦況の悪化で『海外仏教事情』も停刊に追い込まれた昭和十九年まで毎年都内で開催された。全土への空襲が激化した昭和二十年においてもなお、五月二十五日に三会寺でウェーサーカ祭が営まれた。敗戦後の昭和二十一年五月のウェーサーカ祭は鶴見の総持寺で開かれ、東元慶喜と釈仁度師によって儀式が執り行われた。国際仏教協会はすでに大東亜省の補助を離れており、これを最後としてウェーサーカ祭(南方仏陀祭)は断絶した。以上、東元慶喜「わが国における上座部仏教研究の過去と将来」(『水野弘元博士米寿記念論集 パーリ文化学の世界』春秋社、一九九〇年収録)に拠った。
*102 「釈興然特集号」『海外仏教事情』第十─三号、一九四四年六月
*103 『禅と戦争 禅仏教は戦争に協力したか』ブラィアン・アンドルー・ヴィクトリア、光人社、二〇〇一年(ZEN AT WAR 1997の翻訳)では、明治初頭の廃仏毀釈(仏教排撃運動)に始まる日本仏教の近代史を時系列で辿りながら、日清・日露戦争から日中戦争、大東亜戦争(太平洋戦争)までの禅仏教のリーダーたちの戦争肯定・殺生礼賛の言説を詳細に分析し、禅の教学が戦争遂行に果たした役割が考察されている。類書としては『近代日本の仏教家と戦争 共生の論理との矛盾』栄沢幸二、専修大学出版局、二〇〇二年がある。
*104 「日印協会の生いたちと歩み」財団法人 日印協会より
*105 以下、『新日本と佛教』(大蔵出版 一九四九)に掲載された「佛教の十二原理」(緒方宗博訳)のさわりである。
佛教の十二原理
佛教の開祖釈迦牟尼佛陀は、西紀五六五年頃、一國の皇太子として北方印度に誕生した。生来内省的な性格を有して居た彼は、苦悩に充てる世間の生活に満足せずして、二十九歳の時出家沙門となりて、全人類の為に苦悩解脱の道を求めた。修行多年、遂に正覚を成就した彼は、佛陀即ち円覚者として知られる様になった。爾来四十五年間、彼は広く道を求むる人々の為に苦悩止息の道、中道の教えを説き、八十歳にして平和なる入滅を遂げた。彼の滅後其の教法は遠く八方に拡がり、今日では世界人類の三分の一近くが、佛陀は自ら正覚を成就し、且つ人々を解脱に導く一大先達なりとして讃仰して居る。
世界の佛教は今日大別して二派に分れて居る。一は小乗或は長老派として、セイロン・ビルマ・シャム及び印度(それは今日既に佛教國ではない。)の一部に行はれて居る南方佛教であり、他は大乗として、西蔵、南蒙古、支那及び日本の数億の住民の間に行はれて居る北方佛教である。而してこれ等の南北佛教は相互に寛容であり、寧ろ同一物の両面を現はして居るに過ぎない。
佛教は平和の宗教と呼ばれて居る。何となれば、未だ曾て佛教戦争なるものは行はれたことがなく、又何人と雖も、その信仰の為に佛教々團から虐待せられたことがないからである。以下十二ヶ條は全佛教に共通なる基本的原理又は眞理とする所である。
第一。自己救済は何人に取つても極めて緊要な即今の問題である。人若し毒箭に倒れば、その射手、その作者、その全長等の詮索に没頭して、これを抜き取ることを後廻しとするが如きことはあるまい。佛道の修行に於ても、修行しながら教義の理解をいよ〳〵深めて行くことも出来るのであるから、人生の如實相に直面し直接に身を以てする経験によつて即刻修道を開始せよ。
第二。萬有の根本事實は転変或は無常の法則である。一切の存在は、土も龍ぐらより大山に至るまで、一想念より天下國家に至るまで、存在の同一循環、即ち生成、發展、凋落及び死滅の道程を進行するものである。但だ萬有の根源的生命のみは永遠にして、萬物の間に自己を實現して行くものである。中國人曰く、『浮世は橋梁の如し、故にこの上に家宅を築く可からず。現世は流転の連続なり。故に壮美なりと雖もこれに執着する者は苦悩を招かん。』と。
第三。転変無常の法則は人間霊魂に就きても亦同様であり。人間霊魂と呼ばるゝものは不死不変ではない。但だ思議すべからざるもの、即ち最高の實在のみは流転を超越して居り、人間を始め一切の有情はこの最高實在の顕現に外ならない。何人と雖も、自身中に流動しつゝあるこの根源的生命を用意に捕捉し難きことは、恰かも彼の電球に光明を附與する電流の把握し難きが如くである。
もう充分だろう。もしハンフレーズがまともな師に就いていたならば、「妄想情解!」と一喝されて終わりではないか。
*106 ハンフレーズと同じく東京裁判に関わったイギリス人(アイルランド系)仏教徒としては、ジャック・ロナルド・ブリンクリー(Jack Ronald Brinkley 1887-1964)がいる。ジャックは父フランシス(ジャパン・メイル経営者兼主筆)と親子二代にわたって日本に滞在し、明治維新から戦後復興期まで、日本の英語教育、日本の再建に尽くした。大東亜戦争中は敵国人として国外追放されるが、終戦後はレンパン島の日本人捕虜の処遇改善のために奔走し、GHQの命令で一九四九(昭和二十四)年まで極東国際軍事裁判における検事団翻訳課長に就任した。一九四八(昭和二十三)年には、仏教宣揚に努めた功績により浅草寺にて天台宗権僧正の僧階を授与された。一九四九年七月に特別除隊すると、八月、教科書会社・英宝社を創設。一九五三(昭和二十八)年から没年まで立正大学文学部英文学科教授。日英文化交流、立正大学など仏教系大学における英語教育に尽力した。ブリンクリー親子の経歴については、長森清「ジャック・ロナルド・ブリンクリーの足跡 〜父フランシスの影響を受けて〜」(『異文化研究』3、国際異文化学会、二〇〇六年三月)に詳しい。
最後まで読んでくれて感謝です。よろしければ、 ・いいね(スキ) ・twitter等への共有 をお願いします。 記事は全文無料公開していますが、サポートが届くと励みになります。
