
ひとふで小説|レンガイケッコン(17)
これまでのお話:第1話/収録マガジン(前回まで)
(17)
蓮本に素性を知られる不快の理由には「親しくない相手に大事なことを把握されている」というのも、きっとある。それならば、せっかく近付きつつある“好意的な顔見知り”から“友達”に格上げされることを目指すのも一つの道だろうか。
友達は難しくとも、せめて顔見知りから“知人以上友人未満”程度の関係性に格上げしてもらえれば、蓮本が自分の身の上を知っていることにも納得がいくかもしれない。
順番が逆だとしても、結果的に納得のいく“親しみのある相手”に自分のことを教えただけ、というところに落ち着けるならば、きっとすっきりできる。
そのためには、東之から見た蓮本の好感度をどうにか“回復”し、蓮本が東之にとって身の上を話すに値する相手になる必要があるのだ。
(私、今、自分本位を極めたようなこと考えてる…。西関さんこんなバカを助手席に乗せてるって気付いてる?そこまで私の人格に興味ないか…)
何から何まで身勝手な発想だ。わかっている。
尤も、きっと蓮本は文化的にも経済的にも社会的な身分としても充実した交友関係を、読者や視聴者から見えない場所に時間が足りないほど持っているはずで、自分などが良き友人として選ばれることなど本来ないだろう。そういう冷静な慎ましさを東之が失うことはなかった。たとえ今自分が蓮本の助手席に乗っているとしても。蓮本が楽しそうに見えても。こんなのは偶然にすぎない。蓮本の部屋に、ゴキブリが出たから。殺虫剤を、切らしていたから。蓮本が市井の人に感じの悪い対応をしたとき、失うものはあっても、得るものはないはずだから。
それだけ。
勤め先のエントランスに、ドラマや映画で何度も見た俳優の女性がしゃくり上げる声を抑えながら入ってきた夜があったのも、アイドルグループに所属する若い女性が三人寄り固まって「ネエさんち、ここで合ってる?」と小声で話していた夜があったのも、知っているのだ。
いずれも勤務時間を終えて管理人室のカーテンをほとんど閉めた後のことだった。向こうから見れば人目の気配が無い、油断できるエントランスホールだったのだろう。見なかったふりをして誰にも口外したことはないが、階段に消えていった彼女たちはみんな、悩みでもあったのか、慕っているのか、蓮本を尋ねたに違いない。
彼女たちに蓮本が割いた時間を自分も割かれようとは、到底思えなかった。著名人とそれ以外の人間に存在価値の差があると感じることはないが、それでも著名であればあるほどそれ相応に顔を合わせる人々の分母も大きいはずで、分母が大きいところには人格的に成熟した人や性格の合う相手の選択肢というのが幅広く存在する確率が高い。
仕事で顔を合わせる相手だけがその全てではないだろう。蓮本の生きる世界には「蓮本さんに会いたい」「蓮本さんと仲良くなりたい」「蓮本さんを紹介して」という“ファン”が、お茶の間から芸能界から文壇まで様々な階層の中に散りばめられているはずで、そうなれば本人が望もうと望むまいと、蓮本は人間関係を“選べる側”に立つ。
(…蓮…………西関さんのことは「競争率が低かったとしても受かるか微妙な難関大を、競争率MAXの年に記念受験する」…みたいな認識が適切か。…それもそれで失礼かもしれないけど、そう思わずに友達を目指すのは、意図的に身の程を見誤らないとさすがに無理だわ…。出会える人の数も種類も桁が違いすぎるし…)
傲慢な願いであることは重々承知の上で、東之は蓮本が自身にとって、“自身の身の上を知っていてもおかしくない人”になることを明確に望んだ。
東之の思惑など知らぬ蓮本は車内に備え付けられた小さな時計を見た。マンション管理人室に規定された昼休みが何時から何時までかは知らないが、今しがた乗車した際に見た時計の長針は十二時四〇分頃を指していたと思う。十三時までだとして、普通に考えれば残り二〇分あるかないかだろう。
蓮本は些か寂しく思ったが、東之はあまり口を開かない。先ほど問われた整備士時代の話も、突然自分から語り始めるほど準備はできていない。
「管理人さん、どうしたの?」
「えっ?」
「なんだか口数が減ったから。酔った?運転荒かったかな、ごめんなさい」
「あ、いいえ…あの、あー…」
「何?悩み事?」
思わず口に出してしまった気軽な問い掛けだったが、蓮本は言い終える頃には既に悔やんでいた。
ここでもまた東之を試してしまったような気がして、浅はかな性分を恥じる。東之に悩み事があって欲しいわけではないのだ。ただ、悩みがあるならば、親しくなれる脈があるならば、打ち明けてもらえる可能性があると思ってしまっただけで。
何かをより多く聞き出すことができれば、仲良くなれたような錯覚。求婚計画は掘り返さないつもりだったのに、どこかに、より深く知り合う機会を探る自分が残っている。
「いや、…だ、大丈夫です。緊張しちゃって…。ははは…、だって」
スーパーのビニール袋の口を意味もなく結びながら、東之は答えた。
「蓮本チカ先生じゃないですか。棲む世界が違うのに、私と居るわけ、ないじゃないですか、みたいなことを、思ったりしてました」
蓮本との距離を縮めようと思った矢先に、口をついて出たのは卑屈でつまらない台詞だった。東之はつくづく、自分を嫌った。
「ええ?居るじゃない。どうしたの?」
「ごめんなさい、リアクションに困りますよねこんなこと言われても…あはは」
口数の少ない帰り道はあっという間だった。東之は外を眺め、蓮本は相変わらず注意深い運転を続けている。
マンションの外壁が見えて間も無く視界が暗くなったかと思うと、車は二階の床下にあたる位置に備えられた薄暗い駐車場に入庫した。
無駄な切り返しもなく綺麗な動線で所定の枠内に駐車した蓮本が左足を踏み込むと、ギッとパーキングブレーキの音がする。エンジンが切れて、電装が徐々に落ちる。ドライブが終わった。
「ほら、エンストしなかった!」
蓮本が唐突に元気な声で言った。
「え?」
東之は、何の話をされたのか分からない。
「…ええ?だってさっき管理人さん、作業着で乗ると車が拒否ってエンストするんじゃないかって仰ったじゃないですか。ふふふ、良かった。無事に帰って来れましたねー、ただいま」
シートベルトを外して、運転席を解錠すると全てのドアロックが音を立てて開いた。
「ああ!…あ、あはは…、すみません、自分で言ったのに、緊張して忘れてました。おかえりなさい。おかえりなさいで合ってるのかな?私も、ただいま、か」
「おかえりなさい。ご無事で何よりです」
東之もシートベルトを外し、ドアを半開きにしながら降りる支度をした。ふと思い立って、スーパーの袋から財布を取り出すと駐車料金の満額以上を満たす千円札をドリンクホルダーの脇にある小物用の凹みに差し入れた。蓮本は降車の支度をしていて気付いていない。
「ま、そんなわけで、どんなわけで?まあそんなわけで管理人さん、とにかく、作業着って凄くかっこいいから。私の一番好きな服だから、あんまり恥ずかしがらないでもらえると嬉しいです。って、行くときに駐車場で言おうとしたこと、思い出しました」
車を降りながら腰を屈めて喋っていた蓮本は、バン、と運転席のドアを思い切り閉めた。それから後部座席のドアを開けて、
「素敵な服なんですよ、作業着が一番」
と言いながら、スーパーの袋を指に引っ掛けて、今度は後部座席のドアを、やはり、バン、と思い切り閉めた。自分が座った助手席のドアを蓮本が閉めたときとは違う、遠慮のない音に、東之は蓮本の心遣いを知った。
東之も助手席から降りると、ドアを閉めた。半ドアにならない程度の力は加えたが、実家の車のように無遠慮な閉め方はしない。人の距離感というのはつまり、こういうことなのだと感じる。
美しい車は、ピッと鳴ってから、ガト!、ッ、と鍵を掛ける音を立てた。
それにしても服を褒められたのなんて、いつ以来だろう。以来というか、そんな経験、これまでにあっただろうか。
過去に付き合った彼氏だって、家族だって、こんなにまじまじと何かを褒めてくれたことはない。
「あ、ありがとうございます…人から褒められることなんてないから、ちょっと、照れますね。ははは…」
(…西関さんは言葉の仕事の人だから人を褒めるのが上手いんだろうけど…)
東之は僅かばかり照れながら、反面、自分が褒められたのではなく、蓮本の職能により褒め言葉が強く響くだけなのだと、冷めてかかった。
「そう?管理人さんは背も高くて作業着も似合ってかっこいいから、私がこのマンションに住んでる子供だったら、こんなお姉さん近くで働いてたら憧れちゃうな。それで、私も将来あれ着たい!ってなったと思う」
「すべてのマンションの管理人が作業着ってわけじゃないと思いますけどね、私は…あんまり働く気があるように見えない格好で出勤しちゃったら、住んでる方からクレームを頂いて。それでこれに落ち着いただけなので…」
「えっ?そうなの?やだぁ、服にいちゃもんつける人がいるの?ちょっと詳しく聞きたいけど、ここで立ち話してたら管理人さんのお昼休み終わっちゃうから残念。また聞かせて」
「面白い話じゃないですよ」
駐車場からエントランスに戻る百メートルほどの道は、どちらからともなくゆっくり歩いた。惜しむようにゆったりとした歩調に合わせるように、歩幅を狭め、狭めた歩幅に合わせるように、また歩調を落とす。
エントランスに入り、管理人室の前まで来ると、東之は蓮本にお辞儀した。
「それじゃあ、ここで。ありがとうございました」
蓮本も改まってお辞儀すると、
「こちらこそありがとうございました」
と言った。
そうして、一瞬東之の顔を真面目に見据えると、胸の前で小さく手を振って、
「じゃあ」
と小さく呟き、背を向けた。友達になることも上手に叶わないまま、結婚を考えたことのある相手に。
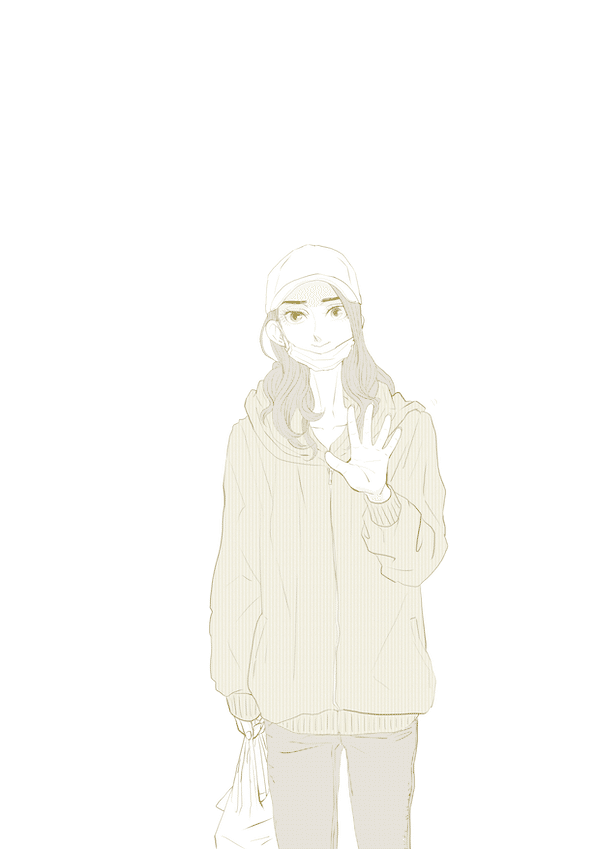
つづく
無料の理由:「ひとふで小説」は、何も考えずに思いつきで書き始め、強引に着地するまで、考えることも引き返すこともストーリーを直すことも設定を詰めることも無しに《一筆書き》で突き進む方法でおはなしを作っています。
元は具合悪くて寝込んでいた時に、調子が悪くても寝ながらでも物語作りの傍に居られないもんだろうか…みたいな気持ちでスマホのテキストアプリに書き始めました。ラストも何も決まっていないので、正直ちゃんと終わるかどうかも分かりません。敢えて先の展開を考えないライブ感優先でやっていて、人物たちが最後どうなるのかを私ですら知りません。挿絵もこまかい手の隙を活用して、ご飯を食べながらとか寝る前に、深追いせず、時にタブレットを抱えて寝転んだまま描いています。
他の無料記事が同じ理由で無料というわけではありませんし、そういう作り方の創作物がお金を得るべきではないという精神論を大切にしているわけでもありません。(「どんな心意気で作っているか/どんな姿勢で創作に臨んでいるか」と「料金を取っていいか/コストがかかっていないか」は関係ありませんから、まったく同じ姿勢で作られたものが有料で公開されることにも肯定的です。)
ただ、このコンテンツに関しては、どんな物語になるかが見えていないので、値段をどうつけていいか現段階では私自身もわからない、ということでなんとなく無料にしています。
(作・挿絵:中村珍/初出:本記事)
