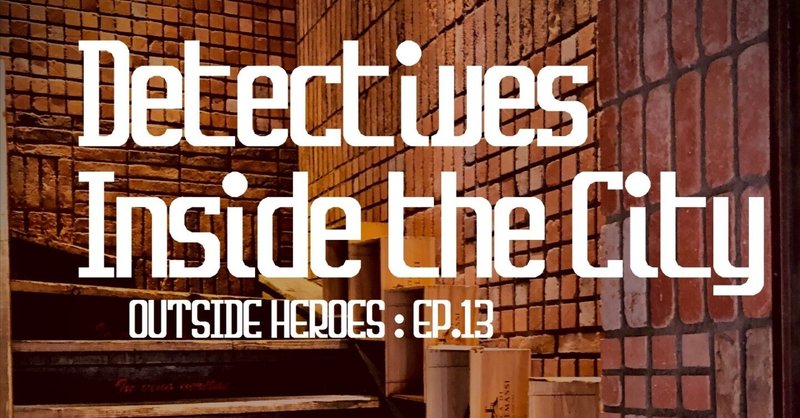
アウトサイド ヒーローズ:エピソード13-9
ディテクティブズ インサイド シティ「特効薬? “ミュータント風邪”の?」
キリシマは大仰な身振りで首をすくめながら、すっとぼけた調子で訊き返した。
「そんなものが、何の関係が……」
「この薬は、元々は野生のダガーリンクスを狩るためにつくられた鎮静剤だったそうです。ただ、オーサカではモンスターの被害が多くなかったので、倉庫に大量に保管されていた。一般に販売されることもなく……」
アマネは端末機をポケットに戻すと視線を逸らすキリシマに声を荒げることもなく、淡々と説明を続けた。
「そして、これは全くの偶然でしたが、変異を起こした動物を鎮圧させる成分が、“ミュータント風邪”の激しい症状を抑えるのにも効果があった。誰が気づいたのかわかりませんが、その何者かによってこの薬はカガミハラに持ち込まれた。お陰で“ミュータント風邪”の致死率が大幅に下がったそうです」
「それは結構なことじゃないですか! 通りで最近、“何人亡くなりました”、みたいなニュースを聞かないわけだ! なるほどな~、そうかそうか……」
へらへらしながら、なんとなく話を畳んでいこうとするキリシマ。
「しかし」
アマネの言葉が、間延びした相槌をぶった切った。キリシマの肩がびくりと震える。
「この薬は元々、ヒトが使うことを想定していませんでした。薬がターゲットにしている遺伝因子を持たないものが服用すると、激しい副作用を起こす。それが……」
「ミュータントの、狂暴化」
固い声でキリシマがつぶやくと、アマネがうなずく。
「そう。今連発しているミュータントの狂暴化事件は、全てこの薬が原因です。薬が病院や医者にコントロールされている分には、まだ問題は起きませんでした。ところが薬はいつの間にか、一般人に流通するようになった……」
「どうして、こんなことに……」
キリシマはアマネからの視線から逃れるように、カウンターテーブルの上に視線を落とした。
「薬の購入ルートについて、医師は黙秘を続けています。病院から盗まれた形跡はありませんでしたが……」
男はすっかり冷めたオムライスを口に入れ、もぐもぐと顎を動かしている。ごくりとのみこむ。味気のない重い塊が、喉を通り過ぎて落ちていった。
「恐らく、カガミハラに持ち込まれたルートは同じだろうと、私は思います」
「……それで、この話を俺にしたのは、何故です」
巡回判事の手元に視線を向けながら、キリシマはぼそりと言う。アマネは青い顔をした男をじっと見つめていた。
「キリシマ探偵にも、協力してほしいんです」
「きょう、りょく」
「町の裏事情にも詳しく、薬品の知識もあり、ブラックマーケットへのコネも持っているキリシマ探偵なら、何か知っているかと思いましたので」
絞り出されたような声を漏らした後、再び黙り込むキリシマ。アマネは言うだけ言うと、食器を持ってさっさと立ち上がった。
「さて、それじゃあ、私はそろそろ捜査に戻りますね。ごちそうさまでした!」
食器を返却口に置くと、カウンター席に振り返る。鋭い眼差しを探偵に向けて。
「事態を放置していれば、狂暴化するミュータントはまだまだ増えるでしょう。そうなれば、この町に暮らすミュータント皆の問題になる。だから私は、できることをやるだけです。……では」
アマネは大股で歩き去っていく。重い金属製のドアが閉じる音と、乾いたドアベルの音。
「……クソ」
静まり返ったホールの中でキリシマは一人、うめき声を吐き出した。
その日以来、カガミハラ・フォート・サイトにおけるミュータント狂暴化事件は目に見えて少なくなっていった。軍警察も対策チームを解散し、“イレギュラーズ”も通常業務に戻る。
そして、市内にひっそりと広まっていた“ミュータント風邪の特効薬”も、人知れず姿を消し始めていた。
「『コイツがヤバいモンだってのは、よくわかっただろう!』」
カガミハラ市内第6地区。廃ビル群と工事現場、そして急ごしらえのバラック長屋がモザイクを描く再開発区域。
路地裏の薄暗がりに響く、ひどくひずんだ声。ボイスチェンジャーを使っているようで、声の主は判然としなかった。
「『……ああ、俺も悪かったよ、そんなモン売りつけちまってよ! だからオトシマエをつけに来たんだ。全額返金するからよ、早くブツを返しな!』」
吼えるような怒鳴り声、女性の泣き叫ぶ声、ガラスが割れる音。傾げた戸口からフードを目深にかぶった目出し帽の男がスーツケースを抱えて転がり出た。
「『すまんかった、すまんかった! ……じゃあな!』」
家の中からは、尚も罵声が響いている。覆面の男は振り返らずに、一目散に走り去った。
「ひい、ひい……」
覆面男はうらぶれた通りを数区画走ると、息を整えながら覆面を脱いだ。目出し帽を丸めてスーツケースにねじ込んだ。
「ひでえ目にあった……」
額の汗をぬぐいながら愚痴をこぼす。しかし内心では、当然の報いだとも思う。売った薬を回収し、詰め込んだスーツケースはずしりと重かった。
「けど、これで全部だな……はあ」
謎の覆面商人となって、市内にばらまいた特効薬。キリシマは数日かけて、まだ使われていなかった薬を回収しつづけていた。“顧客名簿”と照らし合わせ、全ての薬品アンプルを集めたことを確認すると、男は深くため息をついた。
「ひとまず何とか、なったな」
キリシマは気を取り直すと息を整え、スーツケースを持って背筋を伸ばす。
あとは、集めたアンプルを処分するだけだ。
「……ん?」
目に飛び込んできたのは、道の端にある丸いモノ。近づいてみると、うずくまったミュータントの老女だった。ふさふさとした毛並みに長く垂れた耳……以前、仕事を失った息子の素行調査を頼んできた母親だと、キリシマはその時気付いた。
「おい、大丈夫か!」
肩を貸して助け起こす。老女は浅く、乱れた息をついていたが、キリシマに気づいて顔を上げた。
「ああ、探偵さん、ですか……ケホッ、ケホッ」
「どうしたんです、こんなところで」
支えられて立ち上がった老母はせき込みながら、何とか身体を支えようと足を踏ん張った。
「ごめんなさいね、急に、息がしんどくなって……身体も、動かなくなって……ケホッ、ゲホッ!」
急に起こる、風邪のような激しい症状……
「“ミュータント風邪”か!」
「探偵さん大丈夫ですよ、うつっちゃいますから、離れて……ゲホッ、ゲホッ!」
老女の状態は、瞬く間に悪化していった。これは話に聞く“重症化”の症状に間違いないだろう、とキリシマにも理解できた。
「こんなの、放っておけるわけないだろ!」
病院に連れていくか? けれども交通の便が悪いこの区域では、救急車両を呼ぶことにさえも時間がかかる……
「確か、家が近かったよな? とにかく、家まで送るから!」
屋根の端が少し崩れた、古ぼけた長屋の一室。板のようなフトン・マットレスに老女を横たえる。持っていた特効薬のビンを口に押し込むようにして飲ませると、血の気を失っていた顔色が少し和らいだようだった。
「ええ、と、頓服はこれでいいよな……」
俺の見立ては、間違っていなかった。キリシマはひとまず安心した。
客たちに薬と一緒に渡していたマニュアルを見ながら、薬を飲ませる手順を確認する。
「でも、あともう一回飲む必要があったんだっけか……ヤカン借りるぞ」
ワンルームの隅に置かれたケトルのスイッチを入れると、白い煙が一筋、染みのできた天井に向かって立ち昇った。マグカップに湯を注ぎ、少し水を足す。そこにアンプルの約液を垂らし入れて、よくかき回した。
「ばあさん、“ミュータント風邪”の症状が重いから、もう一回薬を飲まなきゃいけないんだ。湯で薄めておいたから、夕方あたりに飲みなよ」
マットレスの横に、白湯で薄めた薬のマグカップを置く。老女は僅かに首を動かし、薄目を開けて微笑んだ。
「ありがとうございます、探偵さん。もうダメかと思いましたが、お陰様で助かりました」
うずきだした胸に手を当て、キリシマは老女から視線を逸らした。
「これぐらい、別に……薬代はいらないから、しっかり休みなよ! 動けるようになったら病院に行くこと! いいな? ……それじゃあ!」
早口でまくし立てると、探偵はスーツケースを抱えて長屋を飛び出していった。
外からはトーンの低い雷鳴が、遠くから響いている。近いうちに、一雨ありそうな気配だった。
「あらあら……あら?」
長屋の扉を強く叩く音。老女が体を起こすと、扉が吹き飛びそうな勢いで開く。
「ババア!」
戸口から噛みつかんばかりの剣幕で吼えるのは鱗に覆われた、巨漢のミュータント。……仕事をクビになったことを隠し続けていた、老女の息子だった。
(続)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
