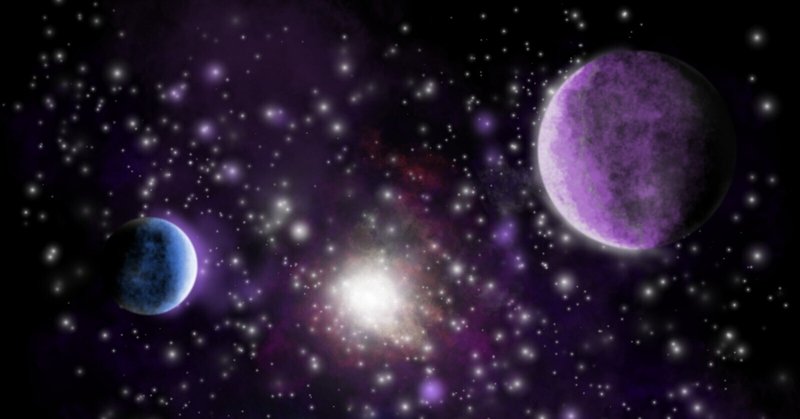
冨田勲さんのホルスト「惑星」からレナード・バーンスタインさんの「惑星」に
父が突然、冨田勲さんのシンセサイザー演奏によるホルスト作曲「惑星」のアルバムを買ってきました。たぶん1970年代半ば、私が小学生の頃です。
そのころ冨田勲さんと言えばNHKの「新日本紀行」のテーマ曲や「70年代われらの世界」のテーマ曲「青い地球は誰のもの」など、子供の私にも印象に残るような数々の名曲を手掛けられていて、子供の私でも名前を耳にしたことがありました。
冨田「惑星」のアルバムのジャケットはSFのような宇宙人の宇宙船のようなものが描かれていてとても印象的なものでした。
ジャケットの絵に引き込まれて、このアルバムを聞いてみると、それはまるで本当に太陽系の惑星を一つ一つ宇宙船で旅するような、そんな壮大な音楽でした。当時、テレビの「土曜映画劇場」か何かで使われていた「木星」の有名なメロディーも、遠くからかすかに聞こえ、だんだん近づいてくるような、そんなストーリーを感じるものでした。
本当に感銘を受けて、解説を読みながら何度も聴きました。
あまりに素晴らしかったので、祖父にも聴かせてあげようとアルバムを母の実家にもっていったこともあります。シンセサイザーの音を聞いた祖父は「こんな音楽が今は流行っているのかい?」とちょっと怪訝な顔をしていましたが、母がその素晴らしさを一生懸命説明していたのを妙に覚えています。
アルバムの解説には、当時ホルストの「惑星」は、編曲や楽団編成の変更禁止、部分演奏の禁止といった規則が設けられていたとのことで、関係者の努力によってこのアルバムのためにシンセサイザーによるアレンジが認可されたようなことが書いてあったと思います。
この話を読んだとき、私は、「ではホルストが守りたかった楽器編成など様々な制約の中で演奏される、ホルストが表現したかった「惑星」とはどんなものだったのだろう」と、非常に興味が湧いて、親に頼んでシンセサイザーではない、ホルストの「惑星」のアルバムを買ってもらいました。
それが、レナード・バーンスタインさんが指揮し、ニューヨーク・フィルハーモニックが演奏する「惑星」でした。
シンセサイザーの惑星には現代的なSF映画を見るような迫力とストーリー性を感じましたが、管弦楽器による演奏も、なんだか作曲者の思いと、指揮者と演奏者による躍動感や静寂感が生々しく伝わってくる本当に素晴らしいものでした。
ちなみに、このアルバムで初めてレナード・バーンスタインさんの名前を知った私ですが、当時、どこかの雑誌か何かでカラヤンやカール・ベームなどと比較して「若手」と書かれていたのを覚えています。それで、なんとなくバリバリに若い新進気鋭の指揮者をイメージしていたのですが、いま、あらためてその生まれ年を見てみると、1918年生(大正7年)生まれと書いてあってちょっと驚いています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
