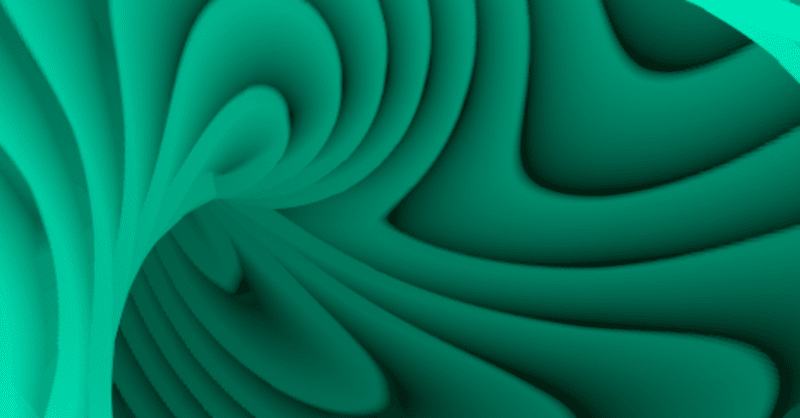
【創作】 錆びた背中(「雨の匂い」より)
シツレイしまーす、と太い声がした。引き戸を開けて病室に入ってきたのは、ナースウェアの男性だった。背丈があるスポーツマンらしい体格で、いかつい印象ながら、目は優しい。「具合はいかがですか?」
「きみ、看護師なのか」
西村というその看護師は自己紹介し、今日から私の担当になると言った。私の声にはやや当惑した様子が混じっていたようで、彼もそれに気づいたようだ。
「男性も、いまは看護師全体の1割くらいいるんですよ。珍しくもないです」
そう言って笑い、ベテランらしい手際よさで、ベッドに横たわった私のバイタルを取り始めた。点滴の薬剤を交換し、ひととおり終わって立ち去ろうとした彼を、私は呼び止めた。
「なあ、西村さん。男性だとこの仕事、なにかと困ることもあるんじゃないかな? たとえば、女性でないとだめだと言われたりしないか」
「そうですね、仕事は仕事なんですが。それを言っちゃえば、むしろ女性だと、かえって困ることもあるし……。じっさいに僕らもけっこう考えてやってますよ。性別もありますけど、結局は、人間どうし。おたがいの相性も大きいですからね」
西村看護師が立ち去ったあと、誰もいなくなった病室のベッドに、わたしはひとり残された。
窓の外は雨模様。昼過ぎから降り始め、午後になって本降りになった。この調子では、おそらく数日ほど降りつづくだろう。まるで、あの時のように。
そう、あの時も、雨だった。あの事故を起こした、半月前のあの日も。
見通しのよい直線道路だった。制限速度をオーバーしていた訳でもない。むしろ、雨が降っていたので速度は控えめだった。単車の整備もすませたばかりだったし、こちらに事故を起こす要素はほとんどなかった。
だがそれは起こった。
小さな交差点にさしかかり、そこで右折してくる乗用車を見たのを覚えている。ふつうにスピードを落とそうとしたそのとき、魔がさした。後輪がなぜかスリップし、私は単車に乗ったままスライドし、乗用車に突っ込んだのだった。
私の二輪車は大破したが、私自身は片足を骨折しただけで済んだ。手術は必要であったが、入院は二週間、リハビリ期間を含め全治三ヶ月の診断。この種の事故ではまれにみる幸運だったと言えよう。
しかし相手の乗用車は違った。回避しようとして、不運にもそのまま電柱に正面衝突した。運転席は大破し、運転手の男性は死亡した。さいわいながら、後部座席に乗っていたその妻は軽いむちうち程度の軽症だったという。
投与された鎮痛剤のせいだろうか、なにか、すべてが遠いことのように感じた。雨音を聞きながら私は目を閉じた。
その時。ふと、焦げ臭い匂いが感じられた。
神経が毛羽立つような感覚があった。火事ではない。忘れようもない、金属とタイヤがアスファルトにこすれ、断裂したマフラーからの排気が混じった、あの時のにおい。
眠気は消えていた。わたしは目を開き、病室の中を見回した。誰もいなかった。いないはずだった。それでも。
何かが動く気配がした。
病室のかたすみ、窓ぎわのくらい部分に、影のような何かがうごめいていた。影というよりも、けむりのような何か。わたしは息をのんで、それを見つめた。足がギブスで固定され、点滴につながってベッドに横たわった状態では、逃げ出すこともそれを確かめるため立ちあがることもできない。
何かは、少しずつ形を取りはじめていた。壁に向かって立っている人の姿、それも男性のようだった。ひょろっと背丈が高く、がっしりした背中の、どこかで見たような……いや、わたしには忘れようもない、その姿。
「……大沢、おまえなのか」
男の影は、うなづいたようにみえた。そしてうしろむきのまま、ゆっくりとベッドに近づいてきた。遊園地のアトラクションで等身大の人形がスライドするような、あきらかに人間ではない動きで。
「顔を、……顔をみせろ」
声をあげたつもりだったが、軋むようなかすれ声にしかならない。恐怖はなかった。むしろやりきれない焦燥感があった。なぜあいつはうしろを向いたままなんだ。なぜひとことも話さないんだ…… 影はわたしの視界いっぱいに広がり、顔を覆った。息ができない。声も出せず、私はもがいた。
「安藤さん、安藤さん」
女の声でわたしは目を覚ました。呼吸は荒く、汗をかいていた。ナースキャップをかぶった若いやせ顔の女性が心配そうにベッドをのぞき込んでいる。病室は明るく、隅々まで白く照らされていた。窓の外は、雨が降り続いており、夕闇がせまってくらかった。
あの影のようなものは消えていた。
「うなされてましたね。大丈夫でしたか? 保険のコーディネーターの方がいらっしゃいました。お話があるそうです」
辛かったらナースコールしてくださいね、と言って若い看護師は出て行った。入れ替わりに、眼鏡をかけ、書類ケースを持った地味なスーツ姿の中年女性が入ってきた。
赤木です、と中年女性は仏頂面で一礼し、説明をはじめた。過失は主としてわたしのほうにあると思われたが、事故現場には道路工事のミスがあり、それが原因であれば、ほぼ免責される可能性が高いという。責任問題では市当局もゴネるでしょうけど、それさえ通れば、まあ不幸中の幸いってやつですわね、と彼女は他人事のように語った。じっさい仕事でこそあれ、他人事なのだろう。
「被害者の奥さんも、不幸な事故ということで、あまり大げさにしたくないというご意向だそうで……。えと、亡くなられた大沢さんは、安藤さんのお知り合いだったんですね」
「大学の同級生でした」わたしはうなづいた。
「奥さま、いちどお見舞いしたいそうですが、来ていただきます? 当事者どうしで、ふつうはビミョウなところですけど、お知り合いということでしたら」
「……おちつくまで、しばらくは、ご遠慮いただきたいな」
「わかりました。あと、ご伝言ということで。『すまなかったと伝えてください』だそうです。まあ旦那様も亡くなったのに、お優しいこと。お知り合いだからでしょうかねえ。わたしもこの仕事長いですが、なんですか、自分側の過失割合が圧倒的に高いくせに、逆ぎれされるような方も多うございますからねえ」
病院の消灯時間は早かった。常夜灯の小さい光と、窓のレースカーテンの向こうの街灯の照り返しで、病室は薄暗かった。眠気が訪れてきた。しばらく前にのんだ睡眠導入剤が効いてきたのだろう。
あの焦げるようなにおいがした。今度は、覚悟ができていた。薬のせいで瞼は重く、すぐに閉じてしまうのだが、それでも目をしっかり開いて、あの影を見据えようとした。影は夕方とおなじ、窓際の部屋の角にぼうっと立っていた。
「大沢。怜子のほうにゆかず、こちらに来たということは、おまえは知っていたということなんだな、そうだろう」
影は後ろを向いたまま、何も反応しなかった。
すまなかったと伝えて下さい。わたしの脳裡にその伝言がひびいた。それはあの中年女性の他人事のような声ではなく、まるでそこにいるかのような怜子の若い美しい声だった。十年以上前のこと。たった一度だったが、夜が明けたとき、ベッドの中でわたしが聞いたあの声。
決して鈍感ではない大沢がそのことを知らない筈はなかった。だが彼は何も言わなかった。すべてを呑み込んだ上で、怜子と結婚したのだ。
そこに打算がなかったとは言えないだろう。怜子にとっても、あの時、あの大企業で、成功するコースに乗って邁進していた大沢は、フリーランサーふぜいであるわたしと比べてはるかに魅力的な相手であったに違いない。
ただ、大沢は怜子を愛していた。それはたしかだった。しかし。
「大沢。怜子は、おまえを愛していなかったんだ。知っていたのか」
呼んだが、影はぴくりとも動かなかった。
怜子とは、あのこと以来会わなかった。会うどころか、話すことすらなかった。あの電話があるまで。
そのころ、大沢の会社が大きな損失を計上してしまい、彼が詰め腹を切らされそうになっていると伝え聞いていた。大沢はその頃には昇進コースから外れていたようだし、私生活でも少なからぬ借金があったという。
また、会いたいの。お話をきかせて。わたしは、その声にひそむ媚びのような甘さを感じて戦慄した。それはまるで、腐りかけた果実のにおいだった。わたしはその場をごまかし、電話を切った。怜子にも、大沢にも、会わなかった。
そして単車であの道路をいつも走ることが、わたしの日課になった。わたしは知っていた。あの道路のあの交差点を数キロゆくと、大沢の自宅があることを。大沢は自家用車で市街地に出るときに、必ずあの交差点を通ることを。
——そして、あの雨の日、見知ったあのクラウンが二人を乗せて交差点を右折してくるのを見たとき、わたしの心の中の何かが弾けたのだ。
部屋の隅の影は動かなかった。こちらにやってくる様子もなかった。それどころか、少しずつ薄まって、消えてゆこうとしている。
わたしは焦った。
「行くな。本当は、おれが死ぬはずだったんだ」
怜子をみちづれにして死ぬ。そうすれば保険金も入って、おまえは助かったはずだ。だがわたしはミスった。失敗したのだ。
いや、あんなときにうまくできるなんて保証はだれにもない。せめて、わたしも死んでいれば……
いや、やはり、わたしはどうかしていたのだ。それとも、わたしは別のことを望んでいたのか。
影はどこかでみたようなシルエットになっていた。そう、あれは、大学の山岳部で撮ったスナップ写真。大沢の背中が妙に気にいって、卒業してからも持ち続けていた。あの背中だった。
幽霊などはいない。神経がみせる幻覚があるだけだ。わたしの目の前に現れるのは、わたしが望んだものなのだ。背負い続けるしかない、とわたしは感じた。薬のせいか、あきらめとも、希望ともとれない、無感情があった。結局は、人間どうし。おたがいの相性も大きいですからね。西村看護師の声がなぜかこだました。そして病室も、影もなくなり、わたしは睡眠導入剤が呼び起こす深い眠りに誘われていった。
(了)2020/05/29
付記:まつやさんの短編「雨の匂い」をベースに再アレンジしてみた習作です。保険のコーディネーターとか事故状況、治療経過はでっちあげ。社会状況は前半は平成風で後半は昭和風です。
