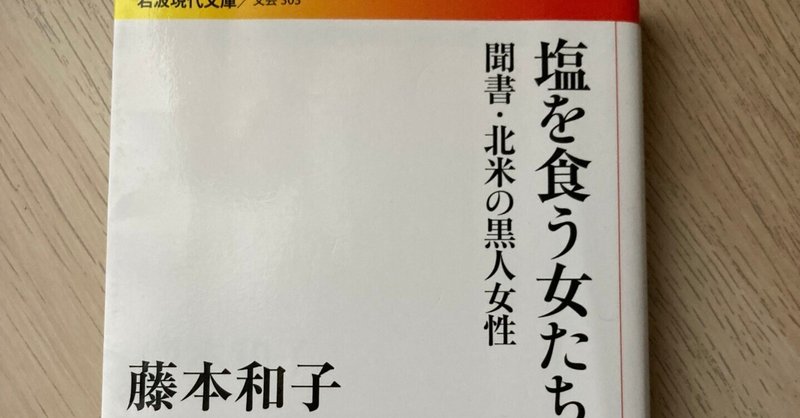
塩を食う女たち 聞書・北米の黒人女性 藤本和子 ~語る言葉を創る人~
塩を食う女たち
聞書・北米の黒人女性
藤本和子
(岩波現代文庫)
80年代に書かれた本です。7人の年齢も職業も違う米国の黒人女性の話を聞き書きしたもの。公民権運動が盛んだった50~60年代、ブラックパワー運動(暴力を伴う)が台頭してきた70年代を過ごしてきた女たちです。
作者の目的は、「黒人であること、女であることはどういうことなのか」という問いを通して、彼女たちの考えてる「存在の根」とは何かを知ることでした。
「存在の根」という言葉の意味、それは、彼女たちが人間としての尊厳を手放さずに生き続けることができた理由、その力の源泉のことです。平たく言えば、彼女たち黒人女性はどうやって生きのびてきたのだろう、という作者の素朴だけれどとてもつよい問いかけによって本書は成立しています。
7人の女たちそれぞれの「存在の根」は何だったか。
たとえば、西アフリカに旅したユーニス。現地の黒人の桁違いのたくましさに触れ、「アメリカの狂気を生きのびることができたのは、アフリカからやって来た彼らが特別にすぐれていたから。それならあたしもきっとすぐれているのだ」という信念を持つにいたります。
産婆のリジー。肉体や魂の治癒や再生にたずさわっていた女たちの力を思い起こさせるような、ヒーラー的な人生を歩んできました。
生の場に立ち会うリジーとは反対に葬儀社を運営するアーネスティン。毎日向き合う「ゲットー的な死(麻薬や事故での死)」。それは黒人のゲットー的生活を映す鏡。
『塩食う者たち』The Salt Eatersの作者トニ・ケイド・バンバーラ。「わたしたちがこの狂気を生き延びることができたわけは、わたしたちにはアメリカ社会の主流的な欲求(つまり病いのような物質主義と鬱病)とは異なるべつの何かがあったからだと思う」「わたしは判断の基準は自分の内面のそれでなければならないと考えるようになった。独立独歩であるために」
貧しいミシシッピー州で生まれ育ち、南部と東部で非常に異なる黒人と白人の関係性について思いを巡らすヴァージア。男性や家族をケアするために強くならなければならない、という黒人女性が持つ観念に窮屈さを覚えます。
住民の福祉のために立ち上がり活動を続けているアニー。貧しく苦しい生活のなかでも、住民の意識を変えようと社会生活の隅々まで目を配りながら、差別や黒人の無気力と闘う。彼女も、社会と家庭から同時に圧力をかけられている女性の立場をなんとかしたいと、まずは若い女性に自立する気概を与えたいと言います。
各章ごとに、聞き書きの文体・スタイル、またインタビューの雰囲気が異なっているところも特筆すべき点かと思います。友人同士の会話のようだったり、ドキュメンタリー風だったり、小説のようだったり。英語でインタビューした内容を日本語にしているわけですが、日本語にした女性たちの言葉のつよさと美しさに打たれます。作者はブローディガンの訳者としてたいへん高名な翻訳者。女たちの生い立ちや性格までも匂い立たせるように書き分けられており、あの時代に生きた黒人女性の話という通底したモチーフを持つ、一種の連作短篇集のようでもあります。そして共通の主人公たる存在は、作者をも含めた大文字での、有色人種の女、「彼女たち」なのです。
「黒人社会の中で生起することをうたいあげるには、言語がないのよ。英語では、共同体の文化も体験も暮らしも、半分も語れないのよ」と、語り手のひとり、トニは言いました。自分たちの姿を語る言葉がない絶望……しかし、藤本和子という稀有な作家/翻訳者/聞き手を通した彼女たちの声は、英語と日本語の世界を超越して、するどく重く、わたしたちに届いてきます。
#塩を食う女たち #藤本和子 #聞き書き #黒人女性 #アメリカ社会 #女性史
#読書記録 #読書感想 #読了
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
