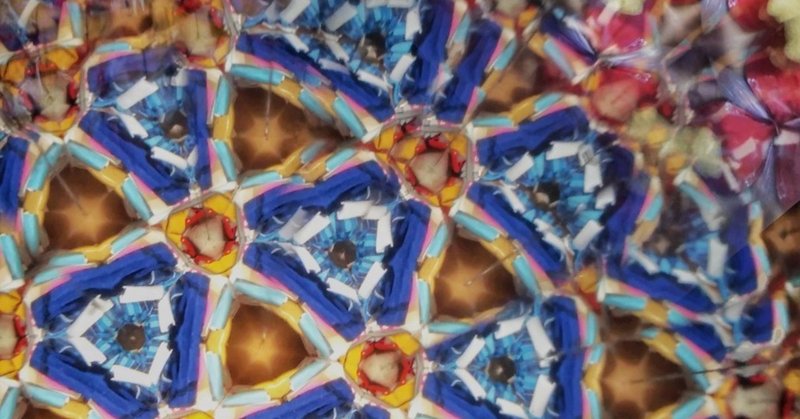
そのように見えるもの
Twitterを色々と遡って眺めていたら、自動生成でイラストを作り出す、人工知能を使用したウェブサイトの話題があった。
確かに、人間が描いたと言われたらわたしは信じてしまう。多少の不自然なところはあっても、人間が描いたものにも不自然さがないとは言えない。(勿論、練習を繰り返したプロならば精度は良いだろう。)
参照
https://www.thiswaifudoesnotexist.net/

身体の描写、特に服装は苦手のようだ。眼鏡は上下が逆さまになることがある。衣服を描き足して額や頬の不自然さを修正すると、それらしくなりそうだ。
実写版もあった。こちらが先のようだ。
参照
https://thispersondoesnotexist.com/

ニュース画像で出てきたら、どこかの国の政治家と思ってしまいそう。
でも実在しない。ただの画像だ。
既存のデータを解析して合成しているのだろう。アニメには詳しくないのだが、これの元となっているのは○○さんの絵柄かな、と思うような節は幾らかあった。
温かさがありそうでいながら、そこには温かさはない。それが人工知能なのだろう。開発者には温かみがあるとして、生成されたものには利便性と結果のみが残る。手間暇かけるコストは要らなくなるが、強い思いや動機、そうでなければならないという必然性は介在しない。
開発から実際の結果に至るプロセスのどこかで、温かさが使用者から見えなくなってしまう。
「そのように見える」けれど「実在しない」何か。
人工知能は人間の暮らしを変えていく。豊かになると思う。簡単な仕事から、やがては大変な仕事も、「置き換え」られていくのだろう。
でも、温かさはどこに行くのだろう。
それを求める気持ちも、どこに行くのだろう。
わたしたちが向かうのは、人工知能と人間が上手く良いところを補完しあえるような未来であるだろうか。
温かさから生まれて、温かいものと共にある。どうかそういうものであって欲しい。
◇ ◇ ◇
【多分どうでもよい補足】
絵画にはトローニーというジャンルがある。想像上の人物を描いたバストアップの作品である。
最も日本人に馴染み深いトローニー(とされる作品)はこれ、フェルメール作「真珠の耳飾りの少女」だろう。

だがトローニーにも、人物の表情や性格の表現を掴むための習作という制作動機があり、やはり人間の意思が強く働いているのだ。
なつめ がんサバイバー。2018年に手術。 複数の病を持つ患者の家族でもあり いわば「兼業患者」
