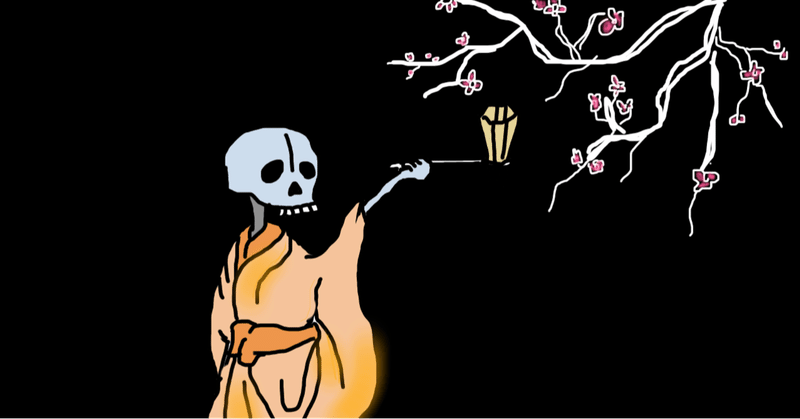
涎 / 2000字のホラー
本当にここに人が住んでいるのかと疑うくらいに傾いた古く小さな一軒家。黄ばんだ四角いボタンを押すとカチカチと感触はあるものの鳴っている様子はない。少し待って扉を叩く。
「留守ですか。」
誰も出ないのに留守ですかと問うのもおかしな話だと思ったが、
「はーい。」
という返事とパタパタと走る足音がした。扉を開けて顔を出したのは清楚な雰囲気の女性だった。二十歳くらいだろうか。化粧はしていないようだが白く滑らかな肌に大きな瞳とぷっくりとした桃色の唇。錆びて軋んだ扉が似合わない可愛らしさに驚き、つい見とれてしまう。
「どなたですか。」
「あ、えぇと、その…市のボランティアの方から来た者です。ここはお婆さんの一人暮らしと聞いていたのですが…ご家族の方ですか?」
まぁ、と微笑んだ顔も魅力的だ。
「ボランティアの方が来てくれるなんて知らなかったわ。若いのに偉いのね。」
「いやそんな。でもお孫さんが一緒に暮らしているのなら安心ですね。」
ふふ、と笑うと扉を大きく開いた。
「どうぞ。お婆さまは今は眠っているけれど。」
僕は慌てて手を横に振って断った。
「眠っているなら今日は帰ります。また後日改めて伺いますから。」
彼女は悪戯っぽく僕の手を掴んで引いた。滑らかで柔らかな手は意外と冷たかった。
「そんなこと言わないで。私も退屈していたの。お願い、少しだけ話しましょうよ。」
スカートをひらり翻しぐんぐん引っ張るものだから、僕が慌てて脱いだ靴は玄関に行儀悪く散らばった。
「待って、靴が。」
「そんなのいいから。」
所々抜けそうに揺らぐ木目の短い廊下を通り、日に焼けて変色した布の暖簾をくぐる。
「座って。お茶を入れるわ。」
片付いてはいるが狭い室内に古いテーブルと年代物のクッションを紐で結びつけた椅子。居間というよりダイニングだろう。まだ映るのかとブラウン管のテレビを見ながら腰掛けるとクッションはぺらぺらで尻が痛かった。テレビの横にはケースに入った日本人形。棚にはこけし、だるま、どこかの郷土品が並んでいる。あんな可愛らしい子がいなければ昭和初期で時間を止められたみたいだ。
彼女はお盆に蓋つきの湯飲みを乗せて持ってくると向かいではなく僕の隣に座った。身体を寄り添わせながらお茶をすすめる。玄関を入ってからずっと消毒薬みたいな匂いがしていたけれど彼女が隣に座るとお香みたいな匂いがした。
お茶をすすりテーブルの上に置いた僕の手をそっと撫でながらもう顔がくっつきそうなくらいに近づいて微笑む。
「ねぇ、本当はボランティアなんかじゃないんでしょ。」
どきり、とした。
僕は本当は受け子のバイトだ。この家の老人から現金が入った封筒を受け取る筈だった。
「隠さなくてもいいの。時々来るのよ。詐欺とか強盗とか。」
「強盗?」
うん、と頷きながら僕の指を一本づつ冷たい指先でなぞる。ゾクゾクする。
「け、警察を呼んだの?」
ううん、と首を振り僕の腕をぎゅっと抱きしめた。滑らかな布の向こうの柔らかな身体は見た目よりもふくよかで冷んやりとしていた。
ゆっくりと瞬きをして僕の頬に顔を近づける。吐息のような甘い声が耳元で響いた。
「食べちゃった。」
一瞬、何を言ったのか分からず身を引こうとしたが捕まれた腕はびくとも動かない。
「どういうこと…」
うふふふ、と笑う彼女の瞳は変わらず大きいものの白眼部分が無く全て真っ黒になっていた。
「ばっ」
化け物、と言おうとしたが声が出ない。舌が痺れてきた。先ほどのお茶に何か入っていたのか。
うふふふふ。
化け物は僕の頬や顎をゆっくりと指先で撫でる。美しい白い指は深い皺が刻まれ黒ずんだ爪が長く伸びていた。口元からは赤く長い舌をちろちろとのぞかせて僕を見つめる。
もう駄目だ。と思ったその時、電話が鳴った。化け物は僕から離れ電話に出た。
「もしもし。おや、誰だい。」
化け物は先程の可愛らしい声ではなく老婆の声を出している。
すぐに逃げ出したいのに身体が痺れてうまく動けない。せめて電話の相手に異常を知らせたいと必死に手足に力を込める。
ガタッと大きな音を立てて椅子から転げ落ちた。
「あんまり久しぶりだからねぇ。驚いて椅子を倒しちゃったよ。元気にしてたかい。」
化け物は動じることなく床に転がる僕を見ながら話し続ける。動けない僕の目に台所の隅に転がる手のような骨が見えた。
「おや、それならすぐにお金を用意してあげるからね。人目につかないように一人で取りにおいで。ふふふ。」
もう目も開けられない僕の頭に化け物の涎がだらりと滴り落ちた。
(1830字)
え!?サポートですか?いただけたなら家を建てたいです。
