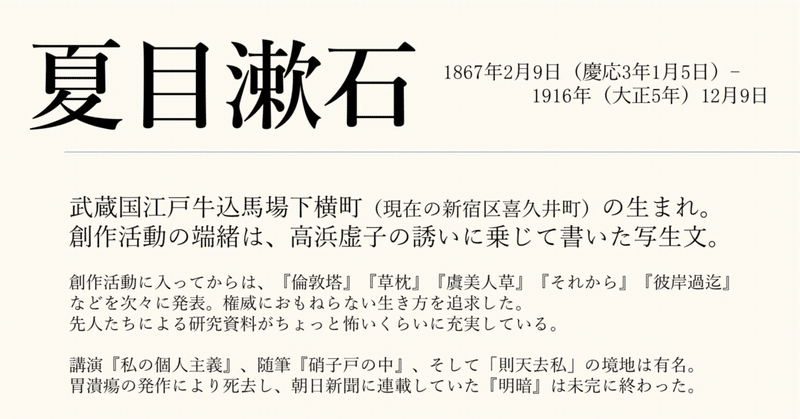
【PV】硝子戸の中 七【夏目漱石】
女の告白は聴いている私を息苦しくしたくらいに悲痛を極(きわ)めたものであった。彼女は私に向ってこんな質問をかけた。――
「もし先生が小説を御書きになる場合には、その女の始末をどうなさいますか」
私は返答に窮した。
「女の死ぬ方がいいと御思いになりますか、それとも生きているように御書きになりますか」
私はどちらにでも書けると答えて、暗(あん)に女の気色(けしき)をうかがった。女はもっと判然した挨拶(あいさつ)を私から要求するように見えた。私は仕方なしにこう答えた。――
「生きるという事を人間の中心点として考えれば、そのままにしていて差支(さしつかえ)ないでしょう。しかし美くしいものや気高(けだか)いものを一義において人間を評価すれば、問題が違って来るかも知れません」
「先生はどちらを御択(おえら)びになりますか」
私はまた躊躇(ちゅうちょ)した。黙って女のいう事を聞いているよりほかに仕方がなかった。
「私は今持っているこの美しい心持が、時間というもののためにだんだん薄れて行くのが怖(こわ)くってたまらないのです。この記憶が消えてしまって、ただ漫然と魂の抜殻(ぬけがら)のように生きている未来を想像すると、それが苦痛で苦痛で恐ろしくってたまらないのです」
私は女が今広い世間(せかい)の中にたった一人立って、一寸(いっすん)も身動きのできない位置にいる事を知っていた。そうしてそれが私の力でどうする訳にも行かないほどに、せっぱつまった境遇である事も知っていた。私は手のつけようのない人の苦痛を傍観する位置に立たせられてじっとしていた。
私は服薬の時間を計るため、客の前も憚(はば)からず常に袂時計(たもとどけい)を座蒲団(ざぶとん)の傍(わき)に置く癖(くせ)をもっていた。
「もう十一時だから御帰りなさい」と私はしまいに女に云った。女は厭(いや)な顔もせずに立ち上った。私はまた「夜が更(ふ)けたから送って行って上げましょう」と云って、女と共に沓脱(くつぬぎ)に下りた。
その時美くしい月が静かな夜(よ)を残る隈(くま)なく照らしていた。往来へ出ると、ひっそりした土の上にひびく下駄(げた)の音はまるで聞こえなかった。私は懐手(ふところで)をしたまま帽子も被(かぶ)らずに、女の後(あと)に跟(つ)いて行った。曲り角の所で女はちょっと会釈(えしゃく)して、「先生に送っていただいてはもったいのうございます」と云った。「もったいない訳がありません。同じ人間です」と私は答えた。
次の曲り角へ来たとき女は「先生に送っていただくのは光栄でございます」とまた云った。私は「本当に光栄と思いますか」と真面目(まじめ)に尋ねた。女は簡単に「思います」とはっきり答えた。私は「そんなら死なずに生きていらっしゃい」と云った。私は女がこの言葉をどう解釈したか知らない。私はそれから一丁ばかり行って、また宅(うち)の方へ引き返したのである。
むせっぽいような苦しい話を聞かされた私は、その夜かえって人間らしい好い心持を久しぶりに経験した。そうしてそれが尊(たっ)とい文芸上の作物(さくぶつ)を読んだあとの気分と同じものだという事に気がついた。有楽座や帝劇へ行って得意になっていた自分の過去の影法師が何となく浅ましく感ぜられた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
