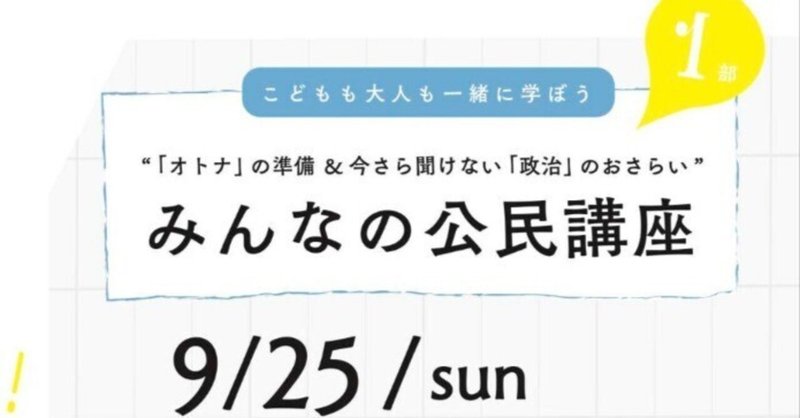
みんなの公民講座 開催しました。
今年度のまちづくり自主学校(第二期)の最初の講座、
「みんなの公民講座」をオンラインにて開催しました。
当日の参加者は小学4年生から中学生、大人までの総勢17名。
昨年のまちづくり自主学校でスピーカーをつとめた山田拓郎市長さんも顔を出し、最初に挨拶をいただきました。継続にむけてのエールと、さらには「フィールドワーク型」をやってもいいんじゃないかといった提案まで、熱のこもったお話でした。
今年のまちづくり自主学校の講師は、昨年のスピーカーの一人でもあった、大島もえさん。もえさんの昨年のレポートはこちら。
もえさんには今回の公民講座だけでなく、10月からはじまる立案ワークショップ(全4回)でも講師をつとめていただきます。
もえさんは元尾張旭市議会議員で、現在は政治と暮らしをつなぐ笑顔の研究所としてsmile lab m's主宰。smile lab m'sでは、不便、不自由を自己責任にしまい込むのではなく、背景にある仕組みやステレオタイプ、課題に向き合う術を伝え、政治を動かし解決するという選択肢を社会に広げる活動を行っています。
そこで生み出されたプログラムの一つである「オトナの公民講座」。
入門編から、声の届け方編まで、いくつかのプログラムがあります。
今回はこどもたちも含め、友達同士や家族でも気軽に話し合える機会になるようにと、「オトナ」には限定しない「みんな」の公民講座でと、提案させていただきました。
この「みんな」という言葉。口当たりがいいようで、実はとってもむずかしい。
私たちNPO法人にこっとの「みんなの社会部」は、今年、「男女共同参画部」から、この名前に改称しました。「男女共同参画」の元を辿ると「gender equality=ジェンダー平等」に行きつくのですが、ジェンダーって男女だけなわけではないですよね。それをより包摂的にと考えて、さらに、こどもも大人も、いろんな属性の人も、ということで考えた「みんなの社会部」。でも、この「みんな」という言葉の重み、考えれば考えるだけ途方もない気がしてきます。
たとえば、以前、耳が聞こえない方にお話を伺ったのですが、「みんな来てね」とうたっているイベントに行っても、耳が聞こえないと何を言っているのかさっぱりわからない、「みんな」って誰?と問いかけられました。
「みんな」って誰なんだろう。その問いに答えるのはとても難しいものですが、あえて、その言葉を掲げることで、この途方もなさを考え続けていければと思います。
そして、この「みんな」って誰?という考えは、政治にもダイレクトにつながってくる問題です。
政治とは、この社会に暮らす、まさに「みんな」を相手にしたもの。
この講座では、いろんな考えるヒントをもらいました。
もえさんの話のなかで印象的だった言葉があります。
チームや組織は辞められるけど、この「社会」を辞めることはできない。
政治はこの「世の中」で生きていく、世渡りの処方箋。
政治家とは、英語でlaw(法、ルール)maker(作る人)と呼ばれます。
多数派だけではない、少数派の意見をどうやってくみ取り、伝えていくか。多数決のシステムのなかで、自分だけでない、「みんな」の幸せのために、どうやって、どんなルールを作っていくことができるのかを考える立場にあるのが政治家です。
もえさんは社会と政治の関係についてこう説明します。
人は生まれた境遇によって、もって生まれたカードが違う。
社会はマジョリティ(多数派)を標準に作られていて、想定されていなかったマイノリティについてはそこに必要な物事がなかなか法制化されていません。法制化するということは、社会化するということ。
なかでも政治についてのこの言葉にはぐっときます。
政治の役割とは、なきものにされた人を社会の仕組みの中にいれる、
新しい価値の風呂敷をつくること。
「みんな」の生き方に世の中をあわせるのが政治の役割なのです。
だから、困ったこと、こうであったらいいなと思うことを、自分が我慢すればいいだけだと考えるのではなく、社会的なニーズとして、ルールを変える第一歩として伝えていくこと。それが、自分のためだけではなく、社会に生きる同じように困難を抱えている人を手助けする一歩になるかもしれない。
そんなことに気づかされます。
誰しもが、他者への影響力をもっている。
「政治参加」とは、政党や候補者選びのことではなく、
「わたしたち」が暮らしをつくっていく活動のことです。

もえさんの熱のこもった話をきいたあと、休憩をはさんで、後半の対話の時間では、こんな質問も出てきました。
Q こどもが学校の校則を変えたいと思っていたけど、先生に聞く耳をもってもらえずあきらめている。大人が思う以上にこどもは先生に意見を言えない。どうやったらこどもたちの力で前に進められるようになるのか。
講座のはじめにも「こどもの権利」についての説明がありましたが、こどもには「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」があります。(日本は1994年にこどもの権利条約に批准しています。)
近年では大分変化してきているとはいうものの、学校ではこの「参加する権利」がなかなか守られていないのが現状です。
もえさんは、この質問をまずは二つに細分してみます。
1)こどもに学校に声を届ける気持ちがある場合
2)こどもに届ける気持ちがなくなってしまっている場合
1)の場合。
伝えるアプローチを吟味すること。状況をさらに細分し、まずは、先生の意見が個人の考えか、学校の考えかを確認すること。そうして事実を時系列でまずは伝えてみる。そしてそれについての見解をもらい、どういう解決策があるかアイディアをもらうところまで持っていく。一回の話で解決するとは思わず、壁打ちのように、対話を重ねていくことを前提とした関係を作ることが大事です。
2)の場合。
大事なのは、こどもにも問題を手放す権利があることをまずは認めて、無理に何かをさせようとはしないこと。そして、選択肢を細かくしていく。親がついていけば話せるのか、親だけで話に行くのはいいのか。親がもし、自分事として、何かアプローチをしたくなったら、こどもの了解を取ったうえで、独自に話をしてみるということもありえる手段かもしれません。
物事には、「絶対正解」があるわけではなく、「最適解」をどう解釈していくかが重要になってきます。そのための絶え間ない試行錯誤と、交渉(ニゴーシエーション)とが必要になってくるんですね。それを具体的な例で考えることができる時間となりました。
終了間際には中学生さんから、衆議院議員の秘書ってどんな仕事? 市議会議員ってどんな仕事? 自分で政党は立ち上げないの? といった、なかなか普段接することの少ない職業の具体的な仕事内容についての質問が上がり、もえさんが駆け足で説明するという場面もありました。
もっともっと話したいことがたくさんあるなか、あっという間に2時間が過ぎていきます。
「みんな」で構成される社会で生きていく上での根っこの部分、政治の役割について、もえさんの4人のこどもの事例なども含めた具体的な話が盛沢山で、こどもから大人までが一緒に考えることができる、とてもわかりやすい内容でした。
はじめのクイズも好評でした。選挙権は18歳からですが、17歳でも投票できるレアなケースがあるのは知ってました?
さて、10月からはじまる立案ワークショップ「あったらいいな まち課題に向き合うはじめの一歩」では、それぞれの参加者が感じている課題や問題を、もえさんと一緒に解きほぐし、提案の形にまでもっていこうという、とても実践的で、贅沢な内容です。
どんな課題が出てくるか。どんな最適解を考えだすことができるのか。
今からとても楽しみにしております。
市内在住の方優先で、通し申し込みはあと1枠のみ!
申込はこちら。(定員に達し次第締切となります。)
講師のもえさん、ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!

顔を出せる人だけ出してもらいましたが、それまでオフにしていたこどもたちが続々と顔を出し。ずっと聞いていたんだなということがわかる一コマでした。
(みんなの社会部 ミナタニ アキ)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
