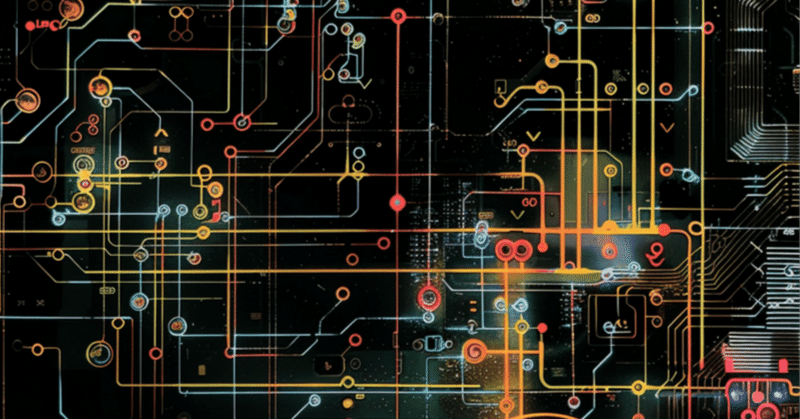
AIの時代に考える
AIの進歩が目覚ましいというニュースを見た。
映像を使った検索などができたり、ミーティングの要約をしてくれたりするそうだ。
AIを使って益々の効率化が望めるとのこと。
そこでふと思い出すのが、昔々、メールが出てきた頃の話。
インターネットが普及してメールができるようになった頃、これで仕事の効率化が進み、仕事がもっと楽になると期待されていたそうだ。
しかし実際には、効率的になって浮いた時間は別の仕事が入るようになって、結局は楽になるということにはならなかったという皮肉な話だ。
今や、仕事のメールもいつでもどこからでも確認できるし、メールよりも手軽なチャットも出てきて、更なる効率化がはかれている。
しかし逆に、できるいつでもどこからでもメールやチャットの返事をしなくてはいけなくなって、文字通り仕事に追われているのが現状というのが、ほとんどんの人が感じていることではないだろうか。
効率化によって物事がスピード上げて進み、それに自分がついていなくてはいけないという状態と言えるだろう。
スピードが上がるというのは仕事に限ったことではない。
日常生活でも物事がどんどん加速している。
例えば、YouTubeで動画を見ている時、ついつい1.25倍速やら1.5倍速で聞いてしまう。
ちょっとした情報であれば、ショート動画でまとめてあるものを見たりして分かった気にもなる。
話は変わるが、先日、日本舞踊の会を観に行った。
日本舞踊はこうした現代社会の対極にあるといってもいいくらいのもので、大半の踊りはまぁゆっくりである。
こう言っては申し訳ないが、中にはあまり上手ではない踊りもある。
踊り自体はどういう展開か見たいものの、こんなゆっくりなのは見ていられないな、1.75倍速で見たいななんて思ってしまった。
そう思った瞬間、そう思った自分に心底ぞっとした。
日本舞踊という娯楽になんで効率を求めているのだろうか。
つまらなくたって、「つまらないな」と思いながらも観る心のゆとりがなくなってしまっているのだろうか。
「つまらない」を排除した時間は果たして豊かな時間なのだろうか。
どうやらつまらない時間、あいまいな時間、もやもやした時間を排除しようとする力が強くなってきている気がする。
AI によって検索の速度が格段に上がると誇らしげにIT業界の人たちがプレゼンテーションしているのを見ると、つくづくそう感じる。
「これはなんだろう?」と疑問に思っている時間を最小限にしようとしているのだ。
でもその「これはなんだろう?」と思っている時間も重要なのではないだろうか。
哲学的な問いを考えるのは分かるが、そんな辞書に載っているような疑問は考えるのに値しない、そういうのは自分の頭ではなくてAIに委ねればいい、という考えもあるかもしれない。
でも、哲学的な問いをいきなり考えるのは非常に難しい。まずはそういう簡単な疑問から、想像し探索する練習をしていくのではないだろうか。
「空はなぜ青いのか」という疑問だって、AI に聞いたりネットで検索すればすぐに答えが出てくるが、自分で空を見上げながら考えてみたら、「空だけではなくて海も青いよな」「青といっても一色じゃないよな」「宇宙に飛び出せば暗いんだよな」などと発見や、更なる疑問が広がってくるだろう。
これを特に強く感じるのが美術館の中である。
美術館の中にいる時間が増えたので、つい美術館に繋げてしまいがちだが、例えば、風景画のタイトルが聞いたこともない場所だとする。
すると意外にも、結構多くの人が、その地名を検索し、どんな場所なのかを確認するのだ。
私は元来ものぐさなので、そういう人たちを見ると、マメだなぁと感心する。
それと同時に、そんなにも分からないことが気になるものだろうかとも思う。
自分であれば、知らない土地に対して絵画を通して想いを馳せ、こんなに美しい所なんだなと絵画の中に身を投じて想像する。
もちろん知っていた方が作品理解が深まるところもあるだろう。
でも日常生活が、こんなにも分からないことへの時間を減らそうとしている動きになっているのであれば、美術館の中では分からないこと、あいまいなこと、もやもやすることを楽しむようにしてもいいのではないかなと思うのだ。
そんな訳でこの頃は、まずはタイトルも解説もいっさい読まずに、ただ作品を堪能する時間を設けるようにしている。
あまりに分からなすぎてタイトルをすぐさま読みたくなる時もあるが、ぐっと抑えて分からないを楽しもうとしている。
そうすると、現代社会の観点から言うと「無駄な時間」なのかもしれないが、逆にとても贅沢な時間を過ごした気分になって、気持ちがいいのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
