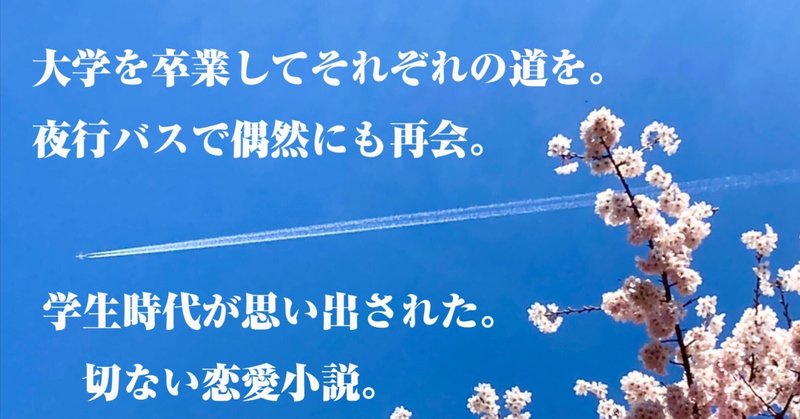
大きな玉ねぎの下で(13)
「あの時、並んで立つのに、たくちゃんは私の右がいいと何度も言って。写真を撮ってもらおうと頼んだ人が困ったこと覚えている?」
その時のことは、はっきりとは覚えていなかったが、亜紀の言葉で思い出の缶詰の奥からその瞬間のことが出て来た。
「だって、たくちゃんは私の右に立ちたいって、わがままいうんだもの。理由を聞いてもなかなか言わないし。それを思い出したの。それでくすって笑っちゃった」
そうだ、僕はあえてあの時、右を選んだのだ。本当の理由は結婚式の時、新郎は新婦の右だと思っていたからだ。だから亜紀の右に立って、この場所で写真を撮りたかった。
「ねぇ、どうしてそんなに私の右に立ちたかったの?」
「内緒だよ
「私、わかったの。大学を卒業して2年経った日に、どうしてたくちゃんが私の右に立ちたかったとうことがね」
「2年って?」
「なんでもないよ。でも理由がわかるのに2年もかかっちゃった」
「たくちゃん、その服なんとかならない?」
「え?どうして」
「だって、みんなが私たちを見ているけど、どうしてだかわかる?」
そうなんだ。通り過ぎる人の多くが僕たちを見ている。亜紀も気づいていたのだ。スーツ姿の僕とキャップをかぶってカジュアルな服を着ている亜紀。誰が見ても僕たち二人はアンバランスな服装。僕たちを見ている人にとっては、パジャマ姿で結婚式に出席しているのと同じくらいアンバランスに見えるのだろう。僕はスーツを入れて持ってきたガーメントバッグをずっと持っていた。
「亜紀、俺、着替えてくるからこのバッグ、持っていてくれるかな」
そう言いながら、亜紀に小説原稿を入れていたビジネスバッグを手渡した。少し亜紀の手に触れた。それだけでドキッとした。10年前は手を繋ぐのが普通だったのに、これも時の流れの中で変わってしまったのだろう。
学士会館のトイレでスーツからジーパン、トレーナ姿に着替えた。ちょっと寒さを感じた。持ってきていた薄手のダウンジャケットをトレーナーの上から着た。着なれないスーツから普段の姿になり、体が浮くほど軽く感じた。
「亜紀、着替えて着たよ」
「あ、夜行バスの時の衣装だ」
「衣装ってなんだよ。これなら二人で歩いていても誰にもジロジロと見られないだろう」
でも、この姿で小説原稿を入れていたビジネスバッグを持つと、やはりアンバランスだ。そのビジネスバッグを亜紀は見つめていた。どうして、スーツ姿でビジネスバッグを持って僕が東京に来ているのか、亜紀は聞きたそうだった。でも、それを飲み込むようにして話し出した。
「まぁ、いいんじゃない」
亜紀のこの言い方も学生の時と変わっていない。
「たくちゃん、お腹が空いてこない?」
「お腹がなりそうなほど空いているよ。昼飯を食べに行こう。どこに行きたい?」
僕は「何を食べたい?」と聞こうとしたのに「どこに行きたい?」と亜紀に聞いていた。心の奥で亜紀との思い出の場所に行きたかったのかもしれない。亜紀はそれに気づいたのか、行きたい場所を考えていた。本当は、この学士会館で亜紀の誕生日をした場所で食べたかった。でも、今はそれができるほどお財布が厚くない。
「たくちゃん、ブラブラ歩いて探そう」
亜紀の言葉は弾んでは聞こえなかった。何かを考えているようだった。
「駅の方に向かえば、いろいろあるから、歩きながら探そうか」
僕はそれしか言えなかった。学士会館から神保町駅の方へ二人で歩いた。目に見えるすべてのものが亜紀との思い出の景色だ。
「たくちゃんと地下道の出口を使って遊んだこと覚えている?」
「忘れないよ。亜紀が迷子になって泣きながら電話して来たこともね」
「そんなことを覚えているの?」
「実は、あの時、俺も迷子になっていたんだよ。亜紀は通っている大学の近くだからまさか迷子になるとは思わなかったからね」
「だって……、寂しかったから」
亜紀は小さな声で呟いた。
「この辺りに、さくら通りとか、すずらん通りっていう道がなかったかな?」
「そうそう、あの時、たくちゃんは聞いたよね。『さくら通りって桜があって、すずらん通りって鈴蘭が咲いているのかな?』って。行ってみようか。その通りに」
僕は左にいる亜紀と自然と手を繋いでいた。小走りですずらん通り方面へ向かった。
「私、行きたいお店あった」
「どこだよ」
「たくちゃんは限定品や発祥の地って弱かったよね」
クスッと笑いながら亜紀が言った。
「発祥のお店に行こう。どこだかわかる?」
僕はすぐに思い出した。そのお店に行った時、高級的な感じで緊張して入ったことを。入り口でどちらが先に入るかとか、入って高くて僕たちに食べられそうになかったらすぐに出てこようとか、でも僕が「発祥」という言葉に弱いことを知って亜紀はその店に入ろうとした。
今、起きていることが10年前と同じように感じた。いや、今起きていることは10年前に戻って起きていることなのかもしれない。
「わかった。中華だね。お店の名前は、えーと」
「思い出さなくても場所はちゃんと覚えているから大丈夫」
僕たちは少し早く走り出していた。握り合っていた手に汗をかいているのがわかった。
「あった。このお店だ」
(まるで二人は学生の時のように手を繋ぎ歩き出していた。すべての時がもどったように。 次回へ続く)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
