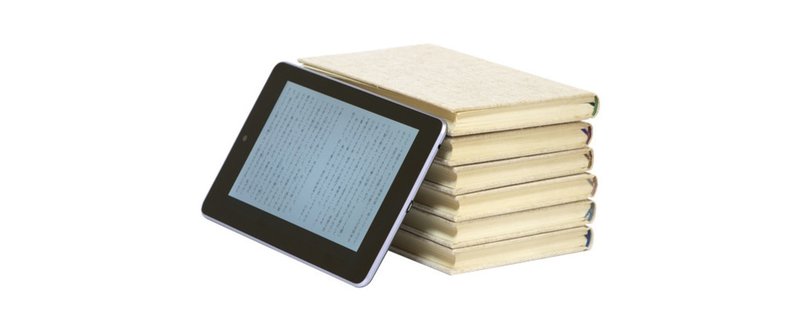
どのような〝家族〟であればいいのか、それはとりもなおさず私たちが新しい生を考えることなのです──下重暁子『家族という病』

この本を読んで二つのことがすぐに脳裏に浮かび上がりました。
一つは『〇〇という病』という本が実に数多く出版されていることです。例えば『意味という病』(柄谷行人さん)、『教育という病』(内田良さん)、『母という病』『父という病』(どちらも岡田尊司さん)、『女という病』『私という病』『愛という病』(すべて中村うさぎさん)、『経済成長という病』『株式会社という病』(どちらも平川克美さん)、『「あいつらは自分たちとは違う」という病』(後藤和智さん)、『ウツになりたいという病』(植木理恵さん)、『「意識高い系」という病』(常見陽平さん)……数え上げたらきりがないくらいです。不謹慎な言い方を許していただければ、日本中いたるところ病だらけみたいと思ってしまいます。
これらの本には、もちろん心身とわず〝病〟に苦しめられている人(家族)に向けて書かれているのもありますが、医学的な〝病〟というものについて書かれているわけではないものも数多くあります。
ではその医学的ではない〝病〟という言葉はなにを意味しているのでしょうか。
誤解をおそれずに言えば、〝気づかないうちに私たちをとらえているもの〟、常識化しているように思い、あるいは無意識化してしまい、なんの前提もなく、それらがあたかも当然であるかのように思っているということ・観念といったものをいっているように思えます。
私たち(日本や世界)が陥っている負のもの、それを〝病〟といっているように思えるのです。
このようないわゆる医学的な病ではないものであっても、それらが私たちにさまざまな制約を及ぼしてくるという意味ではやはり〝病〟といっていいと思います。この本もそのような意味で〝病〟という言葉を使っているのではないかと思います。
その上でいえば、この本にあるものは下重さんからの新しい家族観の提案なのではないかと思います。もちろんこの家族観に至るまでの下重さんの日々は〝病〟との闘いであったのは確かです。ですからこれはそれをくぐり抜け、自分なりに回復をとげた人間の闘病録・回復録とでも呼ぶべきものなのではないでしょうか。
「家族団欒の名の下に、お互いが、よく知ったふりをし、愛し合っていると思い込む。何でも許せる美しい空間……。そこでは個は埋没し、家族という巨大な生き物と化す。家族団欒という幻想ではなく、一人ひとりの個人をとり戻すことが、ほんとうの家族を知る近道ではないのか」
なぜ私たちは家族を盲信するのでしょうか。そこに付け込む「振り込め詐欺」のような犯罪がなぜあとをたたないのでしょうか。下重さんはそこに日本人の過剰なまでの家族信仰をみているのです。なぜ〝家族〟という言葉に〝幸せな〟という形容句、むしろ常套句が付けられてしまうのかと問いかけているのです。
一人暮らしの死についても
「都会で独居してそのまま亡くなるケースを人々は悲惨だというが、はたしてそうだろうか。(略)野たれ死にといわれようと、覚悟の上ならいいのではないか。心ない家族にみとられるよりは満ち足りているのかもしれない」
と記しています。
かつては家族という共同・共生体が社会という共同体が強いてくるものを時に緩衝し、時には社会に対抗する場になっていました。その家族像が浸食されてきているのかもしれません。とはいっても、私たちが〝家族〟というものに求めるものがなくなったわけではありません。〝家族的なもの〟への必要性がなくなったわけでもありません。
私たちは、〝家族〟というものになにを求めていたのでしょうか。それは、いまどこに求めればいいのでしょうか。どのような〝家族〟であればいいのか、それはとりもなおさず私たちが新しい生を考えることでもあります。この本はそれを私たちに突きつけているように思いました。
この本を読んだ時に浮かんだもう一つのことは「幸せな家族はどれもみな同じようにみえるが、不幸な家族にはそれぞれの不幸の形がある」というトルストイの一文でした。〝病〟は極めて個的なものであり、同じ病名だからといってそれへの立ち向かい方は、みなそれぞれが違っているという極めて当たり前のことでした。そこには安易な共鳴、共感を許さないものがあるのではないでしょうか。そしてこの本には下重さんの闘う相手がなんであったのかをもまた私たちに明らかにしているものでした。
書誌:
書 名 家族という病
著 者 下重暁子
出版社 幻冬舎
初 版 2015年3月25日
レビュアー近況:夏の高校野球、東西東京大会もいよいよ準々決勝。TV中継が始まりました。国士舘高校と東海大菅生高校の大熱戦から目が離せず、全く業務が進まない毎度の夏が野中にも到来しました。
[初出]講談社BOOK倶楽部|BOOK CAFE「ふくほん(福本)」2015.07.22
http://cafe.bookclub.kodansha.co.jp/fukuhon/?p=3790
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
