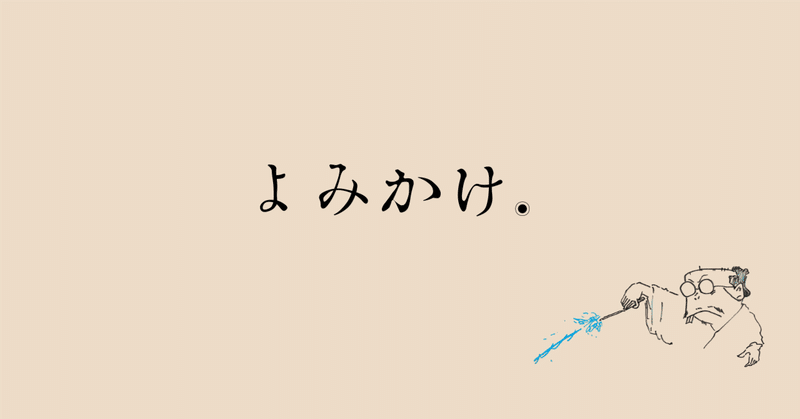
曽根崎心中EDM
2/11
近松門左衛門『曽根崎心中』を読んだ。
驚いた。あまりの衝撃にバイト先の食事会に遅れた。上司に叱られ席につき、会話をする間も私の頭に流れるのは曽根崎心中の音色である。
『曽根崎心中』は空疎であった。
私が驚いたのはその部分である。中身のない、空っぽの話なのだ。
何かの原型みたい。
と最初に抱いた感想はそれで、考えれば考えるほど、これは物語でなく、物語の枠の部分、形しかない。原型そのものである。
主人公徳兵衛の働く先も何をしているわけでもなく「職場」でしかなく、それはヒロインおはつにおいても同じである。
友人と思って金を貸した理由にも、なにかこの作品特有の流れがあるわけではなく友人だからで、その友人九平次が裏切るのだが、裏切る理由もない。裏切るから裏切るのである。果ては心中することになるが、それもフリがあるわけでなく、そう決まっているからそうしたとしか思えない。
『あなたの人生の物語』の異星人の生き方というのは、もしかするとこのときのおはつの動き方なのかもしれない。
物語は、構造と内容に分けられる。
これは小説に限らず音楽、映画、絵画などあらゆるものがそうだ。
『曽根崎心中』は構成のみがわれわれに迫ってくる。内容は必要ないとばかりに、物語ないの設定は、構成を成り立たせるためのもの以上に何も深い意味を持たされていない。
間違いなく、現代人でも『曽根崎心中』には感動する。
話を聞くと(読むと)心を打たれる。
それは、以上のあり方——この物語に内容はなく、ただ物語の盛り上がりという構造だけがあるからだ。
内容に関する共感も深みもない。否、必要ない。
そこに普遍性を得ているのである。
2/13
野口武彦『三人称の発見まで』に目を通す。
少し前、図書館で借りた本である。20日までに返さなくてはならないが、いい本だったので、後で買っても良い。
この本は「江戸時代は、三人称を知らなかった」というテーマ。
日本人がいかにして文章を書いてきたか、その工夫と出来上がりを確かめていくことで、そのテーマを浮き彫りにする。
日本人は明治時代に西洋の三人称文に出会うまで、三人称というものの存在を知らなかった。
このなかで、『曽根崎心中』が取り上げられていた。
世話物浄瑠璃の開祖として。
「『曽根崎心中』で近松門左衛門が成し遂げたのは超越的一人称の語りである」というこの章のテーマにここでは触れない。
私が気に入ったのは、『曽根崎心中』の構成について書いてある部分である。
筆者は『曽根崎心中』のうち「長すぎる」冒頭〈観音めぐり〉に注目する。
たしかに構成びいきのこの作品にして、この「長すぎる」冒頭は形式にしても長すぎる。不自然に思える。
ちなみに、武彦ちゃんは別にこの作品を構成的にどうこうは言ってない。ここに注視したのはのり子の勝手な引用である。
(この章は本来、この構成から古浄瑠璃(歴史に題材を取ったもの)からテーマの変更するさいに語り手の位置をどう定めたかという一人称のあり方を論じている)
この〈観音めぐり〉大阪の三十三ヶ所の寺を順番に巡る観光案内の解釈に今尾哲也の論文を用いている。
要約して言い切ってしまうと、この観音めぐり、観音はおはつである。
観音めぐりをしているのはおはつであり、そして巡られている観音も、ヒロインおはつである。
観音は変化仏として長く親しまれてきたが、ここではおはつに変化しているのである。
順を追って説明しよう。
まず、観音めぐりしているのはおはつである。
長いこの章があったのち、徳兵衛が登場し「コレおはつじやないか」と言ってはじめて、今まで読んでた観光案内がおはつの歩いていた描写だとわかる。
ではなぜ、ここで拝まれている観音がおはつだと言えるか。
それはこの物語のラストに示される。
徳兵衛とおはつは心中する。
苦しむ息も絶え果てるのを見届けたあと、近松はこうしめくくる。
「貴賤郡衆の回向の種 未来成仏疑いなき 恋の手本となりにけり」
おはつの成仏は疑いない、と。
徳兵衛でなくおはつを取り沙汰するのは一つの伝統のようなもので、遊女は観音に成仏するのである。
この世界で観音になったのはおはつであった。
これにより物語は発散せず円環状に閉じる。冒頭の観音めぐりへと。
おはつは死んだことによって、観音になる。
観音はおはつに拝まれる。
おはつは観音を拝む。
世話物は、市井一般の民を題材に採る。
普通に考えれば、歴史上の傑物でも神話の神でもない、我々とおなじ普通の人間の、しかも社会的に見れば小さな事件に過ぎない話である。
興味ないと言えば、興味ない。
ここに観音信仰の型を結びつける。
驚くべきことに、ジョイスが「ユリシーズ」で行ったことではないか。
事件から手を引いて、日常や精神に文学を題材を探した。まではいいが、これをどうやって読めたものにするかという問題に対し、神話の型を借りるという解答を出したジョイス。
近松も同じ手を使っていたということか。とはいえ、これは早合点かもしれない。この神話の型に嵌め込むのが、物語ることのある種の常套手段かもしれないし(意図せず反復してしまうこともあり得る)、第一、近松は事件を書いている。だからモダニズムにそれほど重なるわけでもない。
まあ、おいおい考えていけばいい。
2/15
ボルヘス『ボルヘス・エッセイ集』を読む。
ずっと家にあったやつで、だいぶん前に数ページ読んで面白かったが、以来存在を忘れていた。発掘したのでまた読む。
「城壁と書物」という章。短いエッセイ。
始皇帝の話である。
万里の長城と自分より前に存在していた書物を全て焼き払うことを指示したこの二つの事業を語る。
ボルヘスは城壁にを〈空間〉の上で取り上げ、書物を〈時間〉で、つまり焚書は始皇帝が時間を消し去るためにしたと指摘する。
面白いエッセイであったが、今回は見ないことにする。
これまで丹念に向き合っているとキリがない。ボルヘスのエッセイはどれを読んでも面白いのである。
私は見たいのは、野口武彦を読んだ時と同じく、本筋と全く関係のない箇所。
今回は最後の段落。まとめとしてボルヘスが書いたある芸術論である。
長城はひとりの支配者の影である。その支配者は最も敬虔な民族に過去を焼却するよう命じた。そのこと自体がさまざまな推測を呼び起こすが、それとかかわりなくものそのものが人を感動させる。(その美点は途方もないスケールの建設と破壊の対比のうちにある。)以上のことを一般化すれば、すべての形相はそれ自体のうちに美点を備えているのであって、推測される《内容》のうちにはないと考えられる。この考え方はベネデット・クローチェの理論にぴったり符号する。一八七七年の時点ですでにペイターは。あらゆる芸術は形式以外の何ものでもない音楽になりたいと願っていると断言している。
読書と執筆のカテにさせていただきます。 さすれば、noteで一番面白い記事を書きましょう。
