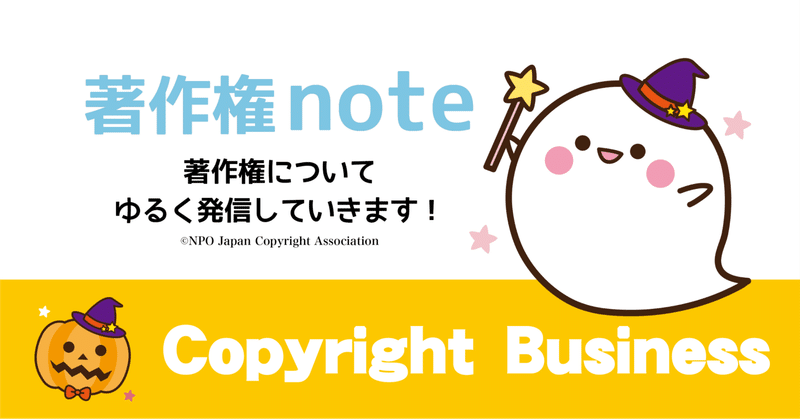
324.発想のヒント〈アイデア・名案にはコツがある〉タイトル変更版
【わくわく発想術】2.序章
※アイデアって、どんなに時代が変わっても色あせない。だ、大きく変化しているだけにすぎない。アイデアってすべてマネから始まる。ならば過去の素晴らしい、面白いアイデアだって、全てが宝物。過去には無限のアイデアのヒントが転がっている。そして、そのアイデアから新しいアイデアへと、大変貌し、大変化し続けている。過去の素晴らしいアイデアなき、新しいアイデアなんて生まれないかも知れないぐらい凄い潜在能力を持つている気がする。そう、過去から未来への創造するアイデアをヒントにして欲しい。
アイデア・名案のコツ教えます。お役に立つ実例満載。おもわず「わくわく」してしまう発想術をお楽しみ下さい。
1.発想のヒント〈アイデア・名案にはコツがある〉
はじめに。
今の世の中はどこを向いても不景気な世の中。なにか儲かる話はないかなア。なんか面白い話ないもんかなア。新聞記事を読めば戦争、事件、円安、物価高に倒産・合併、リストラとまるで嵐状態。そして、相変わらずの恐怖を煽り続けるメディアたち。
今の会社にいてもいつまで続けられるかとても不安。再就職するといっても就職先なんてまるでない。
また無事就職できたとしても3年、5年先はわからない。
(来年だってわからない)
人は誰もが年を取る。年金だって受け取れそうもない。先の見えない時代はいつもそんなもの。
これからは誰もが厳しい世界の中で、自分だけを頼りに一人で戦っていくことだ。でもどうすれば生き残れるのだろう。
そんなとき、やっぱり最後に頼りになるのはあなたのアタマ。
でもそのアタマをどうやって活用すればいいのと疑問も湧く。
まず、誰の目にも明らかなこの時代に、一人の人間の対応できる範囲には必ず限度があるということである。その意味では私も自分の限界を早く感じていた一人だ。一人でじっくりと考える知的生産法を否定するわけではないが、この方法はごく普通の人にとってはふさわしくない。つまり普通の人にはこの天才型、芸術家型は向いていないといえる。
また、プロといわれる専門化や技術者は、ときには革命的な発想を生むこともあるが、固定観念や独りよがり、時代錯誤という錯覚に陥りやすい。つまり、他人の言葉に耳を傾けることができなくなってしまうからだ。
まさにプロ不要の時代といえる。
それに一人の人間の能力などはたかが知れたもの。自分の限界を感じることは恥ではなく、自分の限界を知るものには自然とまわりに協力者ができるものだ。
そのためにはやはり人間関係は財産ともいえる。
人間関係の面白さは、単に人の力を借りるというのとは違うし、ましてやお金を払えば知恵を貸してくれるものではない。つまり、タダあっても知恵を貸してくれたり、自発的に、いっしょに何かをつくってくれたり、協力してくれる人達もいる。
これは、一緒に何かをつくり、生み出していく喜びを感じ合うことによって、いつのまにか協力者ができたり、義務でなく、面白がってやる雰囲気が必要だということだ。
こんなところに実は、財産という宝の山が隠されている。ヒントやアイデアは突然にあなたのアタマの中に自動的に生まれるものではない。こんなところに名案のコツがある。

2.批判は一切禁ずる。量を求める、自由奔放たれ
ブレーンストミング(Brain Storming)以下略記して「BS」は、アメリカのオズボーン氏の創案。オズボーン氏は著書の中で、人間の独創的なアイデアを高めるいろいろな実技的方法技術を唱えた人であまりにも有名な人。
このBSは、「一人の人間の対応できる範囲には必ず限度がある。」という前提がある。
つまり、解決しなければならないテーマを明記して、テーブルを囲んで数名または十数名の関係者が討論する場をつくる。その討論した発言やアイデアを担当者が記録し、アイデアの種がつきるまで行う。そして討論後にこれらのアイデアはひとつずつ批判的に検討評価して、よいアイデアがふるいに残され、絞る。
討論者と批判検討評価者とは別人に分ける場合がある。このBS法で最も注目に値するのは、一定のルールがあり、次の4原則がある。
⑴「批判を禁ずる。」
他人の出したアイデアについて決して批判的な評価をしてはならない。つまり、前向きに一生懸命考えたアイデアだが、人はすぐ批判したくなる習性がある。だからといってその批判者にそのアイデア以上のものがあるとは限らない。相手の欠点だけみて意見することはできるが、アイデアには必ず良いところもある。批判する、意見することによって、その人は二度とアイデアを提案しなくなる可能性も高い。人は褒められればうれしいが、けなされれば悔しい。こんな人間心理は誰にでもあることはわかる。まずは聞く、まずは良い点を見つける。
⑵「量を求める。」
できるだけ多量多様なアイデアを種が尽きるまでたくさん出すこと。
ひとつのアイデアは必ずしもひとつだけに終らない。アイデアは次々に改良され、修正され、変化できるものだ。あらゆる角度から、あらゆる見方から種が尽きるまで数多く出すこと。アイデアや発想は一点限りではない。何十点、何百点の中から素晴らしい宝がかくされている、そしてそれらを比較することによって深度を増す。
⑶「自由奔放たれ」
つまり、「こんなアイデアをいえばバカげたことだと笑われるじゃあないか」「なんとなく恥ずかしい」「馬鹿にされる」といった抑圧したいじけた気持を捨て、奇想天外なこと、突拍子もないこと、無理なことでも何でも発言してみることだ。
このことがなぜ大切なことかといえば、プロと呼ばれる専門家や技術者、理論家には、この自由奔放的発想が、できあがった固定観念によって消滅している場合が多い。
笑われてけっこう。馬鹿にされてけっこう。「あんたにこんな発想ができるかい」といなおれば良い。自由な発想、物事にとらわれない発想、自由な表現はこうして生まれる。
⑷「結合」
これは、他人のアイデアに触発されて、そのアイデアと結びつけて、さらに異なったアイデアを発想することだ。つまり、他人のアイデアを批判することではなく、そのアイデアに対して「こうしたらより、面白くなる」「ああしたら、こんな形になる」といった異なったアイデアの提案である。
これは「三人寄れば文殊の知恵」ということわざの通り、「一人の人間の対応できる範囲には必ず限界がある」といったことをルール化し、実際にやってみると、この4原則は実によくできた注意であると賞賛に値する。
このBS法は、アイデアや発想だけにこだわらず、自分たちが今感じている問題とか、悩みを吐き出しあう場合にも利用できる。またあるテーマについて情報を出し合う時、あるいは現状の底に潜む問題点を探り出すための討論にも利用できる。
そして特筆すべき点は、二、三人の少数でも十名、二十名のグループにも応用できる点である。
それでは注意点としては
BS法のテーマがあいまいになると、かならずしも生産の目的がひとつに絞られない場合がある。又、目的が示されないときもある。つまり、あまり狭い目的を示すことによって、自由でおもしろい発想が制約されてはいけない。
また、目的や役割りをあまり細かく決めすぎると、束縛間を与えてしまう恐れもある。だから大切なことは発想することによって、全員が自分に参加したいという満足感がなければダメ。すると一人一人が思わぬ力を出し、わずか3人だが3の発想ではなく、32も60にも発想力は増し相乗効果を発揮する。個人の力をはるかに超える力が生まれる。
又、BS法での討議の中で、当初予想だにしなかった生産物やアイデアが出てくるのは当然、日常茶飯事だ。このとき、目的と違うものであったとしても、決して否定しまってはいけない。こういうものこそ、次の何かに画期的な新機軸になりうる可能性がある。
そして、BS法には、自分の上・下だけではなく、アイデアの上・下もない。アイデアの勝負でもない。たとえば私達の経験や体験は十人十色。この十人十色の経験と体験はむしろ誰もマネのできない人生観ともいえる。そして、年齢も関係ない。若者には若者の目線があり、子供には子供の目線と体験や経験がある。私達は小さな子供達にも学び教わることもある。決して決めつける必要はない。
プロなればなるほど見失ってしまう感性やアイデア・発想。アイデアや発想は本来普通の素人と呼ばれる人達の考えや意見に聞く耳をもてる者が本来のプロフェッショナルだ。
続く~

※本内容は、発明、アイデア、著作権を中心とした「創作アイデア」のためのヒント集となっています。
どうか、みなさまの仕事や生活、趣味やさまざまな商品開発などのお役に立つことを主眼としています。ぜひ、楽しみながらお読みください。
私たち著作権協会では専門的なことはその方々にお任せして、さらに大切な「アイデア」「発想」などのヒントとなる内容にする予定です。
何度も言いますが「アイデア(内容)」は、著作権では保護できません。著作権が保護するものは「表現(創作したもの)」の世界です。
しかし、どちらもアイデア(ひらめき)があって、形になるものですから、著作権の世界でもこのアイデアという表現、創作の世界にもあるものです。
本内容は、全国の都道府県、市町村、学校、NPО団体、中小企業、noteの皆様、クリエイター、個人の方々を対象としているものです。また、全国の職員研修での講演先のみなさまにもおすすめしています。
特定非営利活動法人著作権協会
「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)
↓著作権noteマガジン
Production / copyright©NPО japan copyright Association
Character design©NPО japan copyright association Hikaru
著作権
著作物
創作
表現
クリエイター
note
ヒント
ひらめき
アイデア
発明
先使用
商品開発
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
