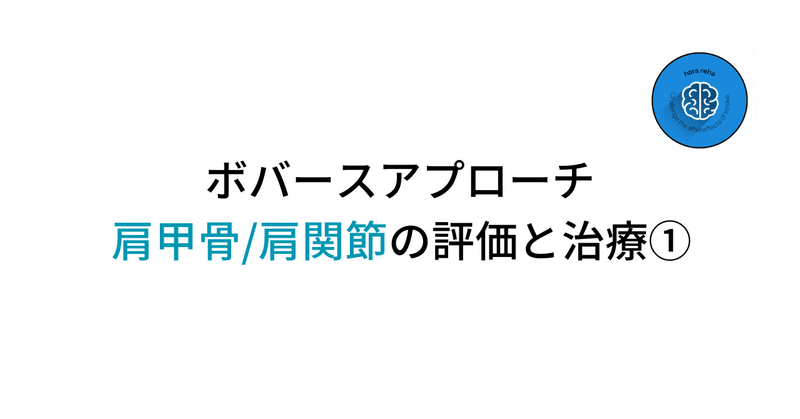
ボバースアプローチ編:肩甲骨/肩関節の評価と治療①
お疲れ様です。はらリハです。
本日は…
「ボバースアプローチから考える肩甲骨と肩関節の評価/治療」を題名にお話ししたいと思います!
はじめに
ボバースや環境適応など、徒手的な誘導から患者様の動きを改善させていく主義では、視診での動作分析、徒手的な誘導に伴う姿勢や筋活動の変化を捉えることから治療仮説を組み立て、治療場面を展開することが多いです。
一例をもとに…
1)視診での動作分析
2)徒手的な誘導から得られる評価
3)評価から得られる情報での仮説
4)訓練の組み立て
基本的にはこの流れで羅列していこうかなと、思います。
1)評価
上肢の挙上を課題として評価/訓練の組み立てを考えます。
両手バンザイに対して…
● 前額面
□ 右肘屈曲
□ 右指の屈曲
□ 左股関節外旋
□ 左足部が内側
→ 右上肢挙上の制限あり?
● 矢状面
□ 肩関節の挙上の可動性は差はない
□ 右肩甲骨挙上あり
placingから随意運動の反応
右肘近位から上方へ誘導、100°辺りから抵抗/重さあり、肩甲骨挙上で引き上げる反応、上肢からは足底の知覚が得られにくい、下ろす際はさらに重さを感じる
反対側は、120°辺りで抵抗あり、内旋の反応を引き出すとより上がりやすいが、下ろす際には体幹屈曲が出現しやすい
手首誘導から肩関節伸展誘導、伸展5°でやや外転あり、肩関節前上部に抵抗、内旋で抵抗緩和
反対側は、同様にやや外転を認めるが右よりは抵抗が遅い
後方からの視診
右肩甲骨前傾、下制、腋窩からやや外側から内旋傾向
左骨盤は後方に崩れあり
肩甲骨の動きを徒手的に評価
右腕の重さを取って肩甲骨の動きを見るため、腋窩の前壁と後壁を持ち肩甲骨の挙上で、初動から抵抗が強く、そこから上げようとすると反対方向に姿勢が移動する
反対派、肩甲骨の挙上で重さは強く、肩甲骨自体は動くが、肋骨下部辺りが挙上に伴い、連動して動いてしまう
2)仮説
→ 1つの仮説
左股関節の支持性低下から姿勢を保つために、左股関節屈曲、内転での固定、胸腰椎後部周囲の後面筋の緊張を高め、左側への姿勢の崩れに対して右上肢の下制の代償に伴い、右上肢の挙上時に抵抗、自重感、制限が出現していると仮説
3)治療編
次回へ続く…
おわりに
ここまで読んで頂きありがとうございます。
はらリハでは、自費リハビリを受けたいが、金銭的に難しい方に向けて、有料の自主トレメニューを販売しています。
そもそもの話をすると脳卒中後遺症の根本的な問題を解決するためには筋肉トレーニングだけでは不十分です。
なぜなら…
根本的な問題は『脳』にあるからです。
脳の問題を解決するには「脳と手足を繋ぐ神経」を回復させる必要があり、そのためには「脳の可塑性」が重要になります。
ここでは…
『脳の可塑性を考慮した自主トレーニングメニュー』を作成しています。
回復を諦めていない方、身体の動きが伸び悩んでいる方、新しいリハビリを体験したい方に向けた記事です。
興味のある方は、たった500円で体験できるので、ぜひご利用下さい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
