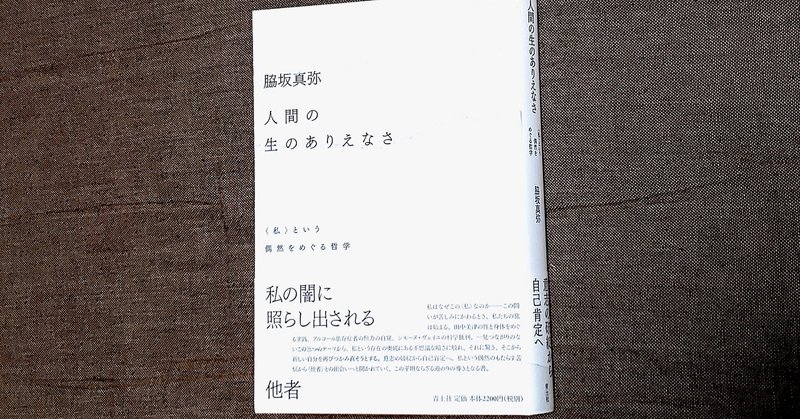
脇坂真弥 『人間の生のありえなさ/<私>という偶然をめぐる哲学』
☆mediopos-2368 2021.5.11
<私>と<他者>のあいだには
「深くて暗い河」がある
ほんとうは「河」どころではなく
決して渡れない深淵があるともいえる
深淵という表現よりも
それぞれの<私>が
ライプニッツ的なモナドである
といったほうがいいのかもしれない
つまり「モナドには窓がない」
その窓のないモナドであることから目を逸らし
ひとはじぶんのペルソナをつくり
そのペルソナどうしが演じることで
「窓」を通じて通じ合っていると思いこんでいる
しかしそうしたペルソナ的な自己認識が破れるとき
「私がこの私であること」の垂直的な深みから
<他者>と<共に>あることの不可能性に思い至る
「モナドには窓がない」のだ
<共に>あるためには「窓」がいるのだが
その「窓」がない
本書では
「私が<この私>であるという偶然」
と表現されているが
むしろそれは
<他者>を持たない絶対的な独自性という
「必然」であるともいえるのかもしれない
しかもそれこそが「自由」の絶対的根拠でもある
それは「決して触ってはならないその人の中心であり、
それを誰かが勝手に理解したり、
埋めたつもりになったり、
ましてや肩代わりすることは絶対にできない」のだ
<私>は苦しみ喜ぶが
それを<他者>と比べることも共有することもできない
けれども<私>はみずからの深みで
<他者>と<共に>あることを求めている
「共有しえないことを共有していく」ことを求めている
しかし<私>にも<他者>の<私>にも「窓」がない
「たとえそうだとしても、
ではいったいどうすればよいのか」
おそらくそれは答えのない問いである
本書では「黙って目を閉じたあてどもない
「祈り」よりほかにないのではないか」ともいわれる
しかし少なくともできることは
<私>においてと同様<他者>もまた
「<この私>であるという偶然」を
生きていることを認め
それぞれがモナドとモナドとして
<共に>照らしあっていると
想像してみることかもしれない
それはある意味で
華厳のような光の照らしあうような
世界像にも近いかもしれない
<共に>あることは
互いの<私>の「窓」を開かせることではない
それは<私>の絶対的自由において
<他者>の喜びや苦しみの「わからない」まま
ただ照らしあっていることなのだ
ことばをかえていえば
<他者>を「祈り」だすともいえるのかもしれないが
■脇坂真弥
『人間の生のありえなさ/<私>という偶然をめぐる哲学』
(青土社 2021.4)
「わずかな例外的状況をのぞいて、人は自分に関してごく普通の自己認識を持っている。自分の名前、生まれや育ち、性格や苦手なもの・好きなもの、今していることをいうのに、その私がひとつの偶然であるということまで知る必要はまったくない。」
「しかし、自分についてのこうしたごく普通の理解とはまったく別に、ある時、ある瞬間に、ハッと「私がこの私であること」を目の当たりにし、つかみ直すことはないだろうか。(…)こちらの自己認識はそれとはまったく違う垂直的な「深さ」をもつ。この「ハッと」は、その深さや意味に応じて、軽いため息であったり、一瞬視野が広がるような驚きであったり、時には底が抜けるような恐怖であったりするのである。
垂直的な深さを特徴とするこの自己認識はさまざまな現れ方をする。ある場合には、それまでの自己認識を一切変えることなく(…)、しかしその自己認識がより深いところからつかみ直され、ある種の「自覚」へと深まって、その人の行動を根本から変える。その時、その人はあらためて自分自身になると言っても過言ではない。あるいはまた、この把握によって従来の自己認識そのものが一変することもある。何かをきっかけにして思いもよらぬ自分の一面に気づき、それによってそれまでの自己認識がすっかり色合いを変えてしまう場合もある。自分でも信じられないほど恐ろしいことをしてしまった自分を目の当たりにして、「これは夢だろうか、これが本当に私なのか」と驚愕することも、時として人には起こる。
こちらの自己認識は(これは「自覚」と言い換えてもよいものだが)、このようにさまざまな形で現れる。だが、どんな現れ方をしようとも、その自己認識は自分で主導した能動的理解というよりは、むしろ思いもよらずそうわかってしまう、すでにそうであった/そうあってしまった自分自身に不意に気づかされてしまうという奇妙な性格を共通に持っている。この時、私は自分で自分をそのようにつかむと同時に、むしろ逆に自分が何かによってつかまれた、自分が自分でない底知れぬものからあらためてつかみ直された、そういう受動性を同時に経験している。先ほどの垂直的な「深さ」とは、この奥底からつかまれる体感にほかならない。この垂直的な深さが、戦術の平坦な「知識」ではなく、「本当はこうなのだ、これこそ本当だ」と思い知らされるような深くリアルな自己認識を生み出すのである。
さて、この不思議な受動の経験の根源にあるのは、何か決して私の自由にならないものによって、私というものが丸ごと、どのような支えもなくほしいままにされているような感覚である。私はこの感覚を、<私>という存在の偶然性と呼びたい。なぜなら、そこでは私という存在そのものが、自分にはどうにもならないひとつの根源的偶然の産物として自分自身に自覚されるということが起こっているからである。」
「「私が<この私>であるという偶然」は決して触ってはならないその人の中心であり、それを誰かが勝手に理解したり、埋めたつもりになったり、ましてや肩代わりすることは絶対にできない。それは私たちのあらゆる本物の苦しみと喜びの源だ。もしもこの偶然がすっかり消えてしまったらーーーーすべてが私たちのコントロールできるものになり、あらゆる出来事に合理的な理由や説明がつくようになり、あの不条理がもしすべて消えたらーーーーその時、私たちは本当に喜んだり、悲しんだりできるだろうか。私たちの本物の、まがいものではない心からの喜びや悲しみは、じつはこのどうにもならない偶然にこそ根ざしている。」
「これはつまり、今これを読んでいる一人一人が、互いに理解できない、誰に埋めてもらうことのできない、他人に肩代わりしてもらえない「私が<この私>であるという偶然」を、それぞれ別に背負って生きているということだ。だが、もしそうなら、私たちはやはりばらばらなのだろうか。私たちは完全に分断されているのか。(…)<共にいる>ということ、その<共に>ということが起こる奇跡のような場所は、やはりどこにもないのか。
もし、この<共に>ということが「あなたと私が同じ内容の経験をしている」という意味ならば、それはどこにもないだろう。私が経験している<この私>の具体的な内容は、あなたが経験している<そのあなた>の具体的な内容とは違う。(…)その意味では、私たちは簡単に理解し合えないところに置かれている。そして、互いをこの「経験内容」という次元で見ているかぎり、「あなたより私のほうが苦しい」と比べたり、あるいは自分よりも苦しそうな人に対して同情と同時に苛立たしさや奇妙な嫉妬さえ感じてしまう。そういう不幸比べのようなものが絶え間なく起こっているのが現代という時代であるように、私には思える。
だとしたら、真の<共に>が起こる場所は、各々が経験する具体的なそれぞれの<私>の経験内容とは無関係なところにあるはずだ。それはいったいどこか。
それは、おそらく次のようなただひとつの事実をおいてほかにないーーーー私に<この私>がたまたま降りかかってきているように、あなたにも<そのあなた>がたまたま降りかかってきている、つまりこの「偶然」は私に起こっているだけではなく、隣にいるあなたにも起こっているという、その事実である。私は<あなた>でもよかったのに、たまたま<私>を生きている。そしてこの偶然は、今この瞬間私を主語にして起こっているだけではなく、あなたを主語にしても起こっている。この事実に気づくということは、互いの苦しみの内容や程度がどれほど違おうとも、それぞれのまったく違う<私>を誰もがたまたま背負って生きているという事実を自覚することにほかならない。この自覚は、それぞれがまったく違う、決して<共に>することのできない<私>をたまたま抱えているという事実、その事実だけを<共に>する可能性を切り開く。
(…)
この「共有しえないことを共有していく」時にはじめて、私たちは隣に本当に誰かがいることに気づく。私とはまったく違う経験内容を生きる他人が、しかし私と同じようにそこにいるということに気づく。そうではないか。このことこそが、(…)あの<共にいる>という奇跡なのではないか。
現代という時代の大きな特徴は、この「偶然」から人が目を逸らし、できればそれをすべて消し去ってしまおうとするところにある。ひとつには科学が非常に発展し、ついにこの偶然の外皮に触れるところにまで進んできたからだろう。だが、そこにはもうひとつ大きな理由があり、それこそが科学の発展の隠れた原動力になっているのではないか。その理由とは、この偶然の恐ろしさだ。人間にとってこれ以上に恐ろしいものはない。大切なかけがえのないこの私の根幹が、自分にはどうにもならない偶然に支配されているーーーーこれほど恐ろしいことがほかにあるだろうか。」
「だが、たとえそうだとしても、ではいったいどうすればよいのか、とらえようのないこの偶然、それに触れてしまった人の「なぜ私なのだ」という声に、私たちはどうすれば関わることはできるのか。この「なぜ」に答えはない。この声は、たとえ聞こえてもどうしてやりようもない、その人に固有の----ヴェイユの科学論での言い方を借りるなた「その人とまさしく同じ大きさの苦しみ」にほかならないからだ。そこにはどれじょど触れて慰めたくとも、触れることができない/触れてはならない何かがある。
だが、それに触れないということは、この声を最初からなかったことにして忘れるということではなかったはずだ。それゆえ、この声を受けとった人々はこれまでこの声に「祈り」によって応じてきた。この声に答えられないことをわかったうえで、どうすることもできないままそこにじっと留まり、祈る。それは何の役にも立たない。まったく甲斐のない祈りだ。だが、この声に応答するものがもしあるとすれば、それは饒舌で便利な「言葉」ではなく、黙って目を閉じたあてどもない「祈り」よりほかにないのではないか。」
「しかし、今日、多くの人は(私も含めて)もう祈ることができない。私たちはこう、これほど甲斐のないものに耐えることができない。何もできないことにじっと耐えられるほど、辛抱強くない。それゆえ、私たちは「できること」で----正確に言えば「できること」だけで----「なぜ私なのだ」という声に答えようとし、それでよいのだと図太く居直る。たとえば、被害を被った人には手厚い補償をすればよい。加害者は死刑にして責任を取らせればよい。
(・・・)
私たちがしがみついているこの怠惰な「できる」とは何か。それと奇妙に一体になった苛立ちを見据えて、しかしもう一度「祈る」ためにはどうしたらよいのか。そもそもこの祈りとはいったい何だったのか。こうした問いにもまた、おそらく誰にも共通の簡単な答えなどないだろう。だが、私は「できる」とはちがうことを少ししてみたい。答えのない、一歩も進まぬ問いにとらえられ、そこに深く留まること(・・・)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
