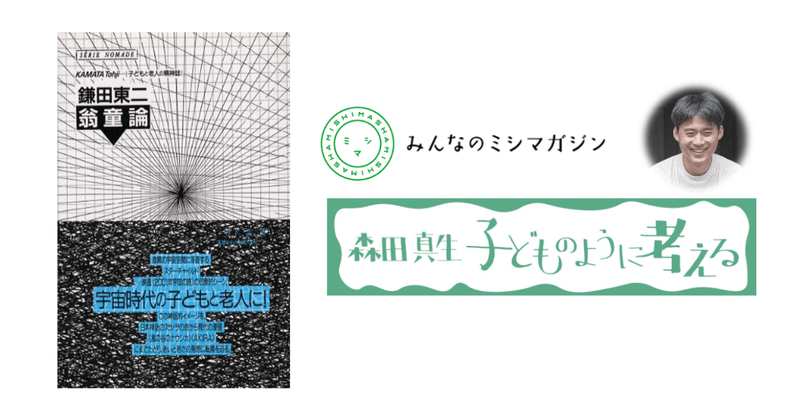
森田真生「子どものように考える 第1回」(「みんなのミシマガジン」連載)/鎌田東二『翁童論/子どもと老人の精神誌』(翁童論1)
☆mediopos-3134 2023.6.17
「みんなのミシマガジン」で
森田真生「子どものように考える」の
連載が始まっている(2023.06.16)
「子どもたちのいのちは新しい」とあるが
その新しさは古くから続くものに支えられ
「その来歴は、古く、懐かしい場所へと通じている」
そして「新しさと古さは本来、
矛盾し合うのではなく、支え合」っている
河合隼雄が『子どもの宇宙』のなかで述べているように
「老人と子どもとは不思議な親近性」があり
下西風澄も示唆しているように
「誰もがやがてふたたび回帰していく
「巨大な来歴のうねり」への近さという点で、
子どもと老人のあいだには、
「不思議な親近性」がある」のである
子どもたちのいのちが新しいのは
そうした「来歴のうねり」から
やってきたばかりだからだ
「子どものように考える」ということは
子どもに戻るというのではなく
そうした「巨大な来歴のうねり」を
近しく感じていくことでもある
それはたんに転生ということだけではなく
「ウイルスのように、細菌のように、太陽のように、
キノコのように、様々な自分でないもののように、、、、
感じ、考えることができる存在」として
「humankind」であるということである
この連載を読みながら
1988年〜2000年にかけて刊行された
鎌田東二『翁童論』(Ⅰ〜Ⅳ)を思いだした
「長老」や「翁」という言葉もあるように
かつて私たちは老人の知恵や成熟に対して畏敬をもち
「老いの中に若あるいは童に通じる
生命の循環を見」ていたが
いまでは老いに対する嫌悪や
やがて訪れる死に対する恐怖しかもたないようになっている
しかし「子どもと老人は、互いに相補的な背面存在」であり
「彼方の消息や異界の面影の共有者」でもある
そして「巨大な来歴のうねり」には
「個性以前の、いや個性以上の未知なる存在感覚」がある
「子どもたちのいのち」が「新しい」のは
そうした「父母未生以前の名状しがたい
「成りませる」存在感覚」をいまだ生きているからだろう
映画『2001年宇宙の旅』に登場するスターチャイルドは
老人と子供を具現した
神話的な存在として描かれているが
2023年を生きている私たちは
やがて「子どものように考え」
「老人」の知恵と成熟へと向かい
「目覚め」る時代を迎えることができるだろうか
■森田真生「子どものように考える 第1回」(2023.06.16)
(「みんなのミシマガジン」連載)
■鎌田東二『翁童論/子どもと老人の精神誌』(翁童論1)
(新曜社 1988/5)
(森田真生「子どものように考える 第1回」より)
「「新しい」とは、どういうことだろうか。それは、ただゼロから始めることではない。母から子が生まれ、古木から若い枝葉が芽吹いていくように、遠く、古くから続くものに支えられていてこそ、いのちは「新しく」あり続けることができる。
地下から湧き出す新鮮で清冽な水は、かつて地上に降った雨が、大地を通って浸み出したものだ。地上に降り注いだ雨が、地下に浸透して地下水となってから、湧き水などの形で流れ出していくまでの時間は、世界の地下水の平均で六百年超にもなるという(『見えない巨大水脈 地下水の科学』)。何年もかけて地中を経めぐり、ようやく地上に現れてきた水を、僕たちは「新しい」と感じる。新しさと古さは本来、矛盾し合うのではなく、支え合うものなのである。
子どもたちのいのちは新しい。
清冽な湧き水のように、力漲る芽吹きのように、若く、瑞々しく、そしてその来歴は、古く、懐かしい場所へと通じている。
河合隼雄は著書『子どもの宇宙』のなかで「老人と子どもとは不思議な親近性をもっている」と指摘している。
子どもはあちらの世界から来たばかりだし老人はもうすぐあちらに行くことになっている。両者ともあちらの世界に近い点が共通なのである。(河合隼雄『子どもの宇宙』)
新しいことは無から始めることではない。滅びることは、無へと消えていくことでもない。生成と消滅は連続している。その連続性を、哲学者で詩人の下西風澄は「精神史」という文脈で次のように美しく描写している。
消滅とは、無への抹消ではない。人間における心の消滅とは、別の再生のための潜水、巨大な来歴のうねりのなかへの回帰だ。生成とは無からの創造ではない。人間における心の生成とは、夥しい数の失われたものたちからの再生である。(下西風澄「生まれ消える心――傷・データ・過去」『新潮』5月号)
「夥しい数の失われたものたち」から、すべてのいのちは生まれ出てくる。誰もがやがてふたたび回帰していく「巨大な来歴のうねり」への近さという点で、子どもと老人のあいだには、「不思議な親近性」がある。
子どもとともに生きることは、この「巨大な来歴のうねり」を近くに感じ続けることである。彼らの言葉や声を通して、いのちの「新しさ」を支える「夥しい数の失われたものたち」を身近に思い続けることである。」
「哲学者のティモシー・モートンは、著書『Humankind』のなかで、「humankind」という言葉に意外な意味を吹き込んでいく。
僕たちはただ、「人間でないもの(nonhuman)」から切り離された「人間(human)」なのではない。「humankind」とは、自分を取り巻く無数の者たちのように、、、、なることができる存在のことなのである。
(・・・)
「自分らしく」あれるからではなく、自分でないもの「のように」なれるからこそ、僕たちはみな本来「human - kind」なのである。
自分がウイルスでもなく細菌でもなく、太陽でもなくキノコでもないということが「人間である」ということなのだすれば、人間であるという感覚を維持し続けることは、ますます難しくなってきている。何しろウイルスや細菌の一切の侵入をなくしてしまえば、僕たちは自分自身であり続けることすらできない。僕たちはただ「人間である」だけでなく、ウイルスのように、細菌のように、太陽のように、キノコのように、様々な自分でないもののように、、、、感じ、考えることができる存在なのだ。
カエルの近くでカエルのようになり、松の手入れをしながら松のようになる。子どもの近くにいれば大なり小なり、子どものように感じ、子どものように考えるようになる。それはhumankindの性なのである。
子どもは単に「若い」のではない。古く、懐かしい生命の「来歴のうねり」からやってきたばかりだからこそ、その感性は瑞々しく、その魂は新しい。子どものように感じ、子どものように考えること。そうすることでしか見えない風景がある。
それはただ、子どもに戻ることではない。子どものそばにいて、もう子どもではない自分が、それでもまるで子どものように感じ、子どものように考えてみる。そうして生まれてくる思考や感覚を、試みとしてここに記録してみたい。」
「「人間らしさ」や「自分らしさ」を支えるこの世界の地盤は揺らいでいる。しかしだからこそ、あらかじめ決められた「らしさ(identity)」にしがみつくだけでなく、「やさしさ(kindness)」が伝播していくような学びの場所を作りたい。そんな思いで、「みんなのミシマガジン」のこの場を借りて、新しい連載を始めてみたい。」
(鎌田東二『翁童論/子どもと老人の精神誌』〜「Ⅰ 翁童文化論/存在への畏怖」より)
「かつて人は、老いに対する畏れをもっていた。だが今日、多くの人は、老いに対する嫌悪と恐怖しかもってはいない。なぜなら人は、老いの醜悪と死による個体の断滅を恐れはじめたからであrる。
あるいはこう言うこともできる。
かつて人は、老いの中に若あるいは童に通じる生命の循環を見た。だが今日、多くの人は、老いの中に若さの消滅あるいは衰弱をしか見ない、と。生命の循環に対する直観はとだえ、人類自身の生態系は、老若あるいは翁童のフィードバック機構を失いつつある。さまざまなレベルでの自己組織系の破壊が進行しつつある。それが今日の私たちの直面している生と文明の局面である。」
「人間にとっての生の発端と終局を考えてみよう。この生の両極は、普通の人生を歩む人間にとって、子どもと老人という対照的な位相をもちながらも、その経験内容の質、あるいはその存在論的特質には思いのほか深い共通点が見いだせる。つまり、子どもと老人とは、人生の時間軸上の対極に位置しながらも、メビウスの輪のように構造的に循環しているのである。
このような、両極的統合体としての翁童的存在の消息を余すところなく物語ったのが、スタンリー・キューブリックの『二〇〇一年宇宙の旅』であった。
映画は、人類進化のテーマと、輪廻転生のテーマとを立体交差させながら、じつにスリリングに進行していく。人類にとって未曾有の宇宙体験と転生を体験する。ディスカヴァリー号の船長デヴィッド・ボーマンは、月面に突如出現した謎の飛行物体モノリスを追跡し、解明するための宇宙探検の過程で、神秘体験とも、変性意識状態ともいえる特異な意識体験をもち、急激に老化し、死に絶え、そしてスターチャイルド(星童、星の子ども)として転生する。
アーサー・C・クラークの小説版では、ボーマンは木星に向かう孤独な宇宙生活の中で、物質から意識の進化について次のような想念をめぐらす。
(・・・)
ボーマンは、意識の自己進化の究極が自己神化以外にないという生物学者のヴィジョンに想到する。そしてボーマンは、じっさいにこの自己神化に近い存在論上のジャンプを果たすのである。人間としての忘却、それが人間を超えてゆく者の目覚めなのであろうか。
この転生のプロセスは、興味深いことに、父母の性交、受精、出産による誕生なのではなく、あたかも蝶が、卵から幼虫、蛹を経て羽化し、成虫すなわち一匹の蝶となるような「変態(メタモルフォーゼ)」の過程として表現されていた。この存在性のメタモルフォーゼという点で、それは『古事記』に登場する「成りませる神」の出現を思い起こさせる。」
「子どもと老人は、互いに相補的な背面存在となり、彼方の消息や異界の面影の共有者となる。子どもと老人とが、個体差をもちながらも、それ以上に皆似かよった面影があるのはこのためなのだ。そこには、個性以前の、いや個性以上の未知なる存在感覚がある。ある種の、おぼろげで、頼りなく、それでいて愛おしく、懐かしい香りがあり、そこはかとない所在なさがある。それは、父母未生以前の名状しがたい「成りませる」存在感覚なのかもしれない。」
◎森田真生「子どものように考える 第1回」(2023.06.16)
(「みんなのミシマガジン」連載)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
