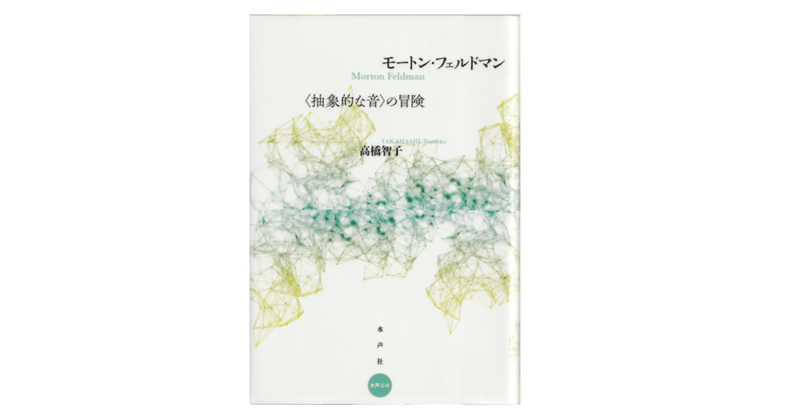
高橋智子『モートン・フェルドマン/〈抽象的な音〉の冒険』
☆mediopos-3071 2023.4.15
いわゆる「現代音楽」というのは
音楽そのもの
音そのものの芸術的形式への
あくなき問いかけだと理解しているが
そのなかでジョン・ケージとならんで
忘れることのできない作曲家が
モートン・フェルドマンである
フェルドマンは
図形楽譜を発明し
演奏時間四時間を超える長大な楽曲を書いたが
彼はどんな音楽を求めていたのだろう
ジョン・ケージをはじめ同時代の作曲家や
抽象表現主義の画家たちと深い関わりを持ち
ミニマル音楽やアンビエント音楽に少なからず影響を与え
ベケットなどとも協働した・・・
などそのフェルドマンに対するイメージは多彩であり
しかも時代とともに
一九五〇年代の図形楽譜から
一九六〇年代の自由な持続の記譜法へ
そして一九七〇年代前半の様々な変化の後
一九七〇年代前半後半には静かで長大な
フェルドマンの音楽のイメージを決定づけた作品など
その音楽はさまざまな変化とともにあった
その問いの一端を知るために本書を手に取った
副題に「〈抽象的な音〉の冒険」とあるが
これはフェルドマン自身が
「完全に抽象的な音の冒険」という言葉で
自身が目指す音楽の姿を描いていることから付されている
つまり「いかなる具体的な事柄やイメージも喚起しない音楽」
ということである
しかしながら著者が
「彼の音楽はわかりやすい説明や単純な宣伝文句を撥ねつけ、
さらには思考と言語の無力さを私たちに突きつける」
と本書の最後に吐露しているように
「静謐さや繊細さといった言葉で
語られることの多いフェルドマンの音楽だが、
実際に聴こえてくる音の数々は何とも表し難い」
またフェルドマンの音楽の独自性を説明するにあたっても
「従来の音楽理論の知識ではどうにも言語化しにくい」
というのである
音楽理論さえ全く疎いぼくには理解し得ないところだが
それでも「音楽を問う」ということにおいて
耳慣れた音楽聴取に埋もれがちななかで
こうした「現代音楽」の試みに
そしてその実際の「音」にふれる機会は欠かすことができない
著者は「あとがき」にこう記している
「フェルドマンの曲を聴いていると、
何もせず、何も期待しない時間の尊さに気付くと同時に、
合理性と効率を優位に置いて何事も急ぎすぎる風潮から
背を向けて生きていこうと、
筆者はそのつど決意を新たにしている」という
私たちは現代においては
音楽を聴くということにさえある種の効率性をもとめたり
「既存の音楽との類似点を探」ったりもしているが
そうしたありようから自由になることはできるだろうか
フェルドマンの音楽はたえざる
音楽および音そのものへの問いかけとなって
私たちの前にその姿を現してくれている
■高橋智子『モートン・フェルドマン/〈抽象的な音〉の冒険』(水声社 2022/12)
(「はじめに」より)
「静謐さや繊細さといった言葉で語られることの多いフェルドマンの音楽だが、実際に聴こえてくる音の数々は何とも表し難い。また、なぜこのような音楽になってしまったのか、その理由を想像するのも簡単ではない。たしかにフェルドマンの楽曲は類を見ない音楽かもしれないが、その独自性を裏付けているのは何なのか、どのような技法で、どのように記譜されているのか、従来の音楽理論の知識ではどうにも言語化しにくい。」
「図形楽譜の作曲家、ジョン・ケージの友人、抽象表現主義の画家と深い関わりを持った作曲家、極端に静かで長い曲を書いた作曲家、ミニマル音楽やアンビエント音楽に少なからず影響を与えた作曲家など、モートン・フェルドマンに対するイメージは様々だ。」
(「第一章 完全に抽象的な音の冒険————一九五〇年代の図形楽譜」より)
「完成され、なおかつ出版されている楽曲として、フェルドマンは一九五〇年から一九六七年までに一七曲の図形楽譜の楽曲を作曲した。作曲年代を見るとわかるように、その多くは一九五〇年、一九五一ー五三年、数年の中断を挟んで一九五八ー六四年に集中している。一九六七年の「イン・サーチ・オブ・アン・オーケストレーション(In Search of an Orchestration)」が彼にとって最後の図形楽譜の楽曲で、これ以降のフェルドマンの楽曲は全て五線譜で記譜されている。」
「フェルドマンが図形楽譜のアイディアに到達した背景の1つとして、まずは抽象表現主義絵画、特にジャクソン・ポロックが一九四七年頃に始めたアクション・ペインティング(・・・)に触れておかないわけにはいかない。フェルドマンは一九六二年に雑誌『カルチャー(Culture)』に寄稿した自作曲の解説の中で、「新しい絵画によって、これまで存在したものよりも直接的で、即時的で、身体的な音の世界を私は欲するようになった」と記している。この「新しい絵画」はポロックの創作と作品を指しており、フェルドマンが音楽よりも絵画に新しい創造の可能性を感じていたことを物語る。さらに彼はこう続ける。「ヴァレーズにはこの要素〔直接性、即時性、身体性〕があった。だが、彼はあまりにも『ヴァレーズ』だった。ヴェーベルンにもその一端が垣間見えたが、彼の作品は十二音技法システムの原理に関わりすぎていた。」(・・・)ここでフェルドマンはこの二人の音楽家よりも、「新しい絵画」に刺激を受けたと言っているのだ。」
(「第二章 「音それ自体」の探求————一九六〇年代の自由な持続の記譜法」より)
「一九五三年十一月二十二日に独奏チェロのための「インターセクション第四番(Intersection 4)」を完成させたのを最後に、フェルドマンは図形楽譜の休止期間に入る。(・・・)その理由の一つとして、図形楽譜による演奏が即興としばしば混同され、フェルドマンが意図した演奏に到達するのが難しかったことが考えられる。」
「図形楽譜を再開する傍らで一九六〇年代のフェルドマンの創作はさらに変化しようとしていた。彼は新たな概念「垂直な思考(Vertical Thoughts)」を打ち出し、この概念は主に五線譜による楽曲で試行錯誤されていた。」
「まず、フェルドマンは絵画における色にも「色それ自体」があるのではないかと考えた。「色それ自体」の主な要素はその色生来の「特定の大きさ」であり、色がそれを主張してきた場合、画家はその主張に従わざるを得ないだろうとフェルドマンは想像する。芸術作品の制作は、基本となる要素を作り手の創意のもとで構成して差異や特色を生み出す営為である。この場合、色は耳目を集める差異を生み出す材料の一つにすぎない。一方、色自らの訴えに耳を貸すことは、画家が色を「あるがまま」にしておくことを意味する。
「フェルドマンにとって、音楽を左から右への水平な流れとして扱うことも「音それ自体」の理念に反しているらしい。
(・・・)
音のあるがままを尊重したいフェルドマンは、こうした方法で作られた曲に本物の音は存在せず、それはまるで有名人そっくりに作られた(中には全く似ていないものも展示されているが)蝋人形をマダム・タッソーの蝋人形館で見るのと同じだと批判している。」
「フェルドマンにとっての喫緊の課題は理念としての、いかなる伝統やしがらみからも解放された「音それ自体」を見つけることだった。「音それ自体」や「音の存在ありき」を重視する傾向はフェルドマンに限ったことではなく、程度や内容の差はあれ、一九五〇年代から既に様々な作曲家に見られていた。トータル・セリーによって強固なシステムを構築したヨーロッパの前衛と、システムの構築を避けて別の道を模索したアメリカの実験に共通するのは、作り手の主観や自己表現から離れようと試みる態度だった。」
「「音それ自体」、「聴覚的な平面」。この二つは六〇年代のフェルドマンの音楽を知るうえでの重要な概念として自由な持続の記譜法に結実する。ちょうど一九六〇年に始まる自由な持続の記譜法は全五曲の「持続」シリーズから始まり、一九六三年にもう一つのシリーズ「垂直な思考」一−五が作曲される。この二つのシリーズのタイトル「持続」と「垂直な思考」は先に解説した「音それ自体」に対するフェルドマンの思索の結果を反映しているといえるだろう。」
(「第三章 カテゴリーの間————一九七〇年代前半の例外的な音楽」より)
「一九七〇年代になると、彼の音楽は記譜法だけでなく様々な点で再び変化する。一九七〇年代に見られる変化は、これまでの時代よりもはっきりと彼自身の生活環境の変化と連動している。」
「教師としての活動、ベルリン滞在によるヨーロッパの音楽界とのつながり、委嘱の増加、生まれ育ったニューヨーク市からバッファローへの転居などの様々な出来事は一九七〇年代のフェルドマンの音楽そのものにも大きな影響をもたらした。この時期の楽曲に特徴的な傾向として大まかに、五線譜での記譜、演奏時間三〇分以上の長い曲、オーケストラ曲、反復の要素をあげることができる。一九七〇年になると突如、記譜法が「普通の」五線譜に戻る。」
(「第四章 歪んだシンメトリー————晩年の長大な音楽」より)
「一九七〇年からの例外的な二年間を経て、フェルドマンの音楽は一九七〇年半ばから抽象的な作風に戻る。当然ながら、以前の作風へとそっくりそのまま回帰したわけではなく、作品の長さ、オーケストレーション、記譜法などにさらなる変化が見られる。」
「一九七〇年代後半から一九八〇年代のフェルドマンの音楽の最たる特徴を一つあげるなら、それはやはり曲の「長さ」だろう。演奏に最短でも五時間を要する一九八三年の「弦楽四重奏曲第二番」はフェルドマン=静かで長い曲のイメージを決定づけた。」
「楽章形式を時代遅れとみなし、複数楽章に異を唱えたフェルドマンは楽章形式に拠らない長い曲の作曲を試み始めた。明確な構成や区切りなしで長い時間を満たすには、音楽がとめどなく続いていく感覚が必要となる。彼はこの連続性の感覚に、従来の楽章形式の音楽とは違う「新しい形式」を見出そうとした。」
「フェルドマンの音楽もガストンの絵画も振り返ることによって実体が見えてくる点で共通している。「フィリップ・ガストンのために」は最終的に無に帰する音楽的な時間を私たちにもたらし、その無の中にこの曲の実体を刻印する。形と無形との境界を曖昧にした一九五〇年代、六〇年代のガストンの絵画は私たちが過ぎ去ってようやく姿を現す。どちらの場合も作品の全体像は「今ここ」の先にあるのかもしれない。」
「中東の絨毯への並々ならぬ熱意、フィリップ・ガストンとの永遠の別れの他にもうひとつ、フェルドマンの一九七〇年代後半以降の音楽に大きな影響を与えたのがサミュエル・ベケットの存在だ。」
(「終わりに」より)
「音と音との論理的な関係性を構築しない音楽は、フェルドマンの一九五〇年代の創作から一貫していた。特に、水平な時間の流れを断ち切るための図形楽譜と自由な持続の記譜法による楽曲にその傾向が顕著だ。彼は、音は音であり、音は他の何かを表象するものではないと考えた。彼にとっての「抽象的なもの」は他のものを参照することなく、それ自体で完結した存在でなくてはならない。彼のこのような態度は、音と音との連結とそれを司る音楽のさまざまな規則————機能和声、厳格対位法、音列などが挙げられる————の否定を意味するし、ともすると、音を構成する(composing)意味での作曲行為の否定にもつながりかねない。だが、彼はもちろんそんなことは承知のうえで「抽象的なもの」に身を賭していたのだろう。
音楽は決して芸術の形式になることはできないのではないかと嘆きつつも、フェルドマンは「芸術の形式」を次のように定義する。
芸術の形式とは、同定不可能なもの、あるいは、それを聴いたとき「いったいこれはなんなのか?」と口をついて出てしまうようなものである。
ここでの「形式」は「本質」に読み替えてもよいかもしれない。彼の考える「芸術の形式」は過去の記憶や歴史に依拠しない絶対的に唯一無二の存在を意味する。彼の考えに従うと、この「抽象的なもの」の境地に達した時、音楽はようやく芸術の形式になることができるはずだ。「音楽は芸術の形式なのか?」これは作り手だけに課されている問題ではない。聴き手である私たちが音楽を聴いているとき、ついつい自分の知っている既存の音楽との類似点を探ってはいないだろうか。」
「フェルドマンは、自分という人間が決して自分ひとりからできているわけではないのだとはっきり自覚している。もしかしたら。先にとりあげた壮大な問い「音楽は芸術の形式なのか?」は、彼の絶え間ない自己批判から生まれたのかもしれない。」
「結局のところフェルドマンの音楽はどんな音楽なのか? 本書は様々な角度から彼の音楽を考察したが。どんなに言葉を尽くしてこの音楽を描写しても、その核心部分になかなか辿り着けない。彼の音楽はわかりやすい説明や単純な宣伝文句を撥ねつけ、さらには思考と言語の無力さを私たちに突きつける。このような音楽としか言いようがない。」
(「あとがき」より)
「フェルドマンの曲を聴いていると、何もせず、何も期待しない時間の尊さに気付くと同時に、合理性と効率を優位に置いて何事も急ぎすぎる風潮から背を向けて生きていこうと、筆者はそのつど決意を新たにしている。
(・・・)
いかなる具体的な事柄やイメージも喚起しない音楽。これもフェルドマンの音楽の特徴であり、魅力の一つである。彼自身、「完全に抽象的な音の冒険」という言葉で自身が目指す音楽の姿を描いている。本書の副題もこの言葉からとった。」
◎高橋智子
1978年仙台市に生まれる。沖縄県立芸術大学中退。東京藝術大学大学院音楽研究科博士後期課程修了。博士(音楽学)。専門はアメリカ実験音楽。主な著書には、『イーノ入
門』(共著、P-VINE、2022年)、翻訳には、フィリップ・グラス『音楽のない言葉』(監訳、ヤマハミュージックエンタテイメントホールディングス、2016年)などがある。
◎Igor Levit - (TEASER) Morton Feldman - Palais de Mari(1986)
For piano
※全体の演奏時間は約29分
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
