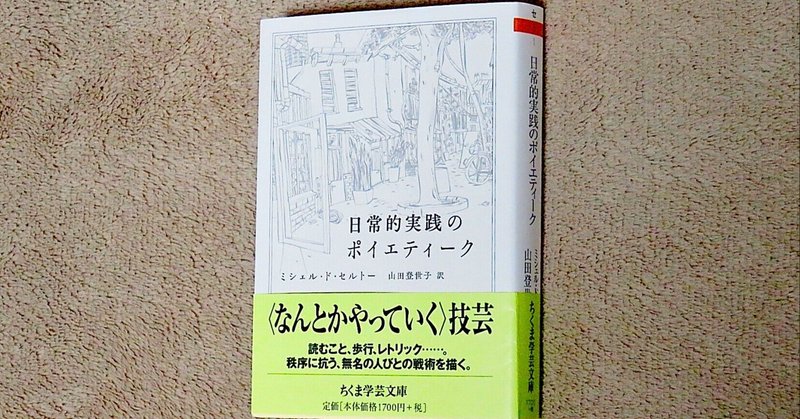
ミシェル・ド・セルトー『日常的実践のポイエティーク』
☆mediopos-2313 2021.3.17
科学(学問)には科学のやり方がある
しかしそれは計測できないものを計測できるとして
抽象化し一般化する方法論だ
科学はそれぞれの専門の世界を固有の場として
対象を定め合理的なものとして構築されるため
そこから日常は排除されることになる
そうしなければ科学は成立しない
大海を世界とすれば
海上に見える島を扱うのが科学であり
島を取り囲む海や海底は
科学的ではないということになり
世界は科学的世界と
それ以外の世界とに境界線で分断される
その意味で「日常的実践のポイエティーク」は
科学ではとらえられないもの
むしろ科学がほんらい依拠しているはずの領域を
科学とは異なった方法で捉えようとする
ちなみにポイエティーク(poïétique)は
制作であり発明であり詩的創造を意味している
ヴァレリーはか古代ギリシアのポーエーシス(poiēsis)を
美学(esthétique)と制作学(poïétique)とに
解体してとらえることを提唱したが
そのうちの制作学として位置づけることができる
そのポイエティークを日常的実践のなかに
見出そうとするのが本書の試みなのだろう
科学も日常の領域に分け入って
あらたな視点のもとで認識を深化させ
それを解明しようとは試みるだろうが
科学という「方法」に取り込まれたとき
それはすでに日常ではなくなってしまい
生きられた場はそこからすでに失われている
日常は抽象的な「場所」ではなく
また測ることのできない予測不可能性のもとにある
日常的実践は「からだ」と「こころ」をもって
いまここだけのかけがえのないものとしてあらわれている
それは思考においても言語においても
輻輳し重層化したメタファーとしての寓話としてしか
とらえることができない
しかし科学もまたそんな寓話の海から生まれたのだ
そのことを忘れた科学からは「生」は失われてしまう
生きることにはすべてがふくまれている
日々思うこと歩くこと話すこと笑うこと悲しむこと怒ること
それらを科学の言葉で名づけることはできない
科学が有効なのは
名づけられないことをふまえながら分かることなのだろう
そうすることではじめて「生」の海が
みずからのうちにあることを忘れないでいられる
■ミシェル・ド・セルトー(山田登世子 訳)
『日常的実践のポイエティーク』
(ちくま学芸文庫 2021.3)
「これからふむべき技術的段取りは、さしあたって、科学的な実践と言語をその出生の地に、everyday lifeに、日々の生活に帰してやることである。こうした科学の日常への回帰は、今日ますますその重要性が説かれていながら、およそ厳密であるにはきっちりと境界を規定しなければならないという専門科学の原則からすれば、科学からの追放でもあるという逆説的な性格をそなえている。学問(科学)というものは、みずからの固有の場をそなえ、その固有の場を所有するには、みずからのとるべき手続きをあきらかにし、明白に対象を定め、さらには反証の条件をも決定しうるような合理的な企図を有していなければならない。(・・・)それ以来というもの、学問は、全なるものをみずからの残りとしてしまったのであり、この残りが、文化とよばれるものになってしまったのである。
このような分裂が近代をつくりなしている。そのため近代には、さまざまな科学がたがいに孤立しながらそびえ立ち、そうした科学の島々が、底に横たわる実践の「抵抗」と、思考に還元できないもろもろの象徴系とをはるか下方に見おろすかっこうになってしまっている。「科学」の野望は、われわれの知の権力を行使しうる空間を足がかりに、この残りを征服しようとめざし、さらにこの帝国を完璧なものにしようと、さまざまな認識がよりつどってさっそく境界領域の目録作成にとりかかり、そうして明晰なものと曖昧なものを結びつけようとしている。(それが、「人文」科学といわれる混合科学の灰色のディスクールであり、暴力や迷信や他性からなる間をさぐりあて、それを----思考しうるとまではいかなくても----同化しようとめざして乗りだしてゆく遠征物語である。歴史しかり、人類学しかり、病理学、その他もろもろ、いずれもおなじ)。けれども、たとえそうしたところで、科学という制度がうみだした言語の分裂、調整可能な操作性をそなえた人工言語と、一社会の人びとが実際に話す言語とのあいだにある分裂は、あいかざらず、戦争か妥協かという葛藤の温床でなくなったためしはない。この分割線は、さまざまに変化しながらも、社会的実践に支配をおよぼす技術の権力をいっそう強化するか、それともこれに抵抗するかという闘争の要でありつづけている。この分割線によって、ある特定の知の手続きを分節化する人工言語と、だれにも共通な意味を形成する活動を組織化してゆく自然言語の二つが隔てられているのである。」
「テクノロジーの下で起こっていること、そしてその働きを乱しているものがいまわれわれの関心をひく。それはテクノロジーの限界であり、この限界はもう久しい以前からわかってはいるのだが、ゆきつく果てはノーマンズ・ランドだと決めつけるだけではなく、ちがった展望を見いだしてやることが必要なのだ。というのも、いま求められているのは、ひとりひとりがやってゆける実効性のある実践なのである。テクノロジーを担う技術者たちは、自分らが「抵抗」と名づけたもの、機能主義的計算(官僚主義機構の先端的形態)をかき乱すあの動きがいったい何であるのかよく承知している。かれらとて、現在の秩序が日常的な現実からすれば不自然であり、その不自然さがそこここで見え隠れしているのに気づかぬはずはない。だがそれらはそれを口にしてはならないのだ。オフィスのなかでこうした事態を話題に皮肉な口をきいたりするのは不敬罪であり、罪人はオフィスをクビになってしまうだろう。触っちゃいけない、芸術品に。というわけだから、こうした機能的合理性には、それらしい上品な言いまわしをさせておき、権力と行政のあるところいたるところにはびこっている婉曲語法を勝手に使わせておいてやろう。そうしてわれわれは、日常的な実践のざめきのほうにたちもどることにしよう。
日常的な実践は現在の経済社会のなかで小集団をなしてなどいない。やがては技術組織のなかに組み入れられてその記号表現になったり交換物になったりするような類の周縁性と日常的実践とは何のゆかりもない。現在、システムはさあまざまな操作の管理をひきうけると称しつつ、そうした操作と手を結ぼうと望んでいるが、そこにわけいってコード化不可能な差異をしのびこませるものこそ、日々営まれている実践なのである。こうした日常的実践は、ローカルな反乱、つまりは分類可能な反乱などではけっしてなく、だれにも共通した、この静かな、なかば羊のように黙々とした、ひとつの転覆であり----われわれひとりひとりのやり遂げる転覆なのである。そのような転覆の兆しを二つだけとりあげてみたいと思う。ひとつは、場所の「偏在性」であり、もうひとつは時間の破調ということである。この二つにふれてみれば、社会的空間というものは重層的なものであり、制御はきかぬまでも構築可能な表面などといったものに還元しつくせないものであるということ、そしてまた、不測の変化のあれこれは、計算化された時間のなかに考えられもしなかった情況をもちきたらすものだということを示唆することになるだろう。同じひとつの場所は厚みをなし、ひとの振る舞いには狡知がひそみ、そして歴史はさまざまな偶発事に満ちている。」
「ひとつひとつの場それぞれにそなわる差異は、併置されるような性質のものではなく、鱗状に幾重にも貼りあわされた層というかたちをとっている。」
「機能的計画が自己のあずかりしらぬもののほうへと運ばれてゆくもうひとつのかたち、それは、不測の事態である。過ぎゆく時間、途切れたりつながったりする時間(そしておそらく思考されたこともない時間)は、プログラム化された時間ではない。」
「理性の不調や破綻は、理性の盲点だが、まさにこの盲点をとおして理性はもうひとつの次元に、すなわち思考という次元に到達するのであり、思考は、みずからではどうすることもできない定めとして異なるものに結ばれあっている。象徴秩序は乱調というものときりはなすことができないものなのだ。日常的実践は、機会なくしては在りえない実践として、波乱の時と結ばれている。したがって日常的な実践は、時間の流れのいたるところに点々と散在するもの、思考という行為の状態に在るものといえるだろう。日常的実践は、絶えまない思考の身ぶりなのだ。
こうしてみれば、不測の出来事を排除したり、あってはならぬ事故とか、合理性の破壊者とかみなして、計算外に追いやってしまうのは、都市の生きた「神話的」実践の可能性を閉ざしてしまうことにひとしい。そうなれば都市に住む人びとに残されたものは、ただ、他者の権力によってつくられ、こしらえものの事件で捏造されたプログラミングのスクラップでしかなくなってしまうだろう。波乱の時、それは、都市を生きる実際の暮らしのディスクール(話)のなかで物語られるものである。言ってみればそれは、決定不能なひとつの寓話、機能主義的テクノクラシーの自明性の帝国ではなく、メタファー的な実践と幾重にも層を成した場所とにかたく結ばれあった、ひとつの寓話なのである。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
