
インド旅行記⑧(ガンガーを眺めただけの一日、旅をどう終えるのか)
2023インド旅行記:目次はこちら
今日も朝ごはんを食べに街に大通りに出ると、今日もまた日本語のうまい客引きのムケシュに声をかけられる。やはりお土産屋に来いとのこと。まぁ行かないのだが、しかし彼の日本語はほんとに上手い。ここまで習得するにはさぞ時間がかかっただろうと思う。今日は一日ゆっくりできる最後の日なので、落ち着いて朝食を食べられるレストランがないか聞いてみると、うってつけの場所がある、と教えてくれた。お土産屋には行かないが、もうここ何日も毎日話しているので、「お金は出すから一緒に朝食はどうか?」と誘うと、「私はそんな高級なの食べたらお腹壊しちゃうよ」と辞退する。ふーんそういうもんかなとレストランに入っていくと、彼もなんだかんだ店内までついてきて、ちゃっかり自分の向かいに座ってしまった。私が見ているメニューにも色々と解説を加えてきて、私がこれにしようかなと決めると、何事かをヒンディーで店員に言いつけている。何やかやとやってくれてはいるのだが、しかしやはり誘っても朝食は食べないと言う。現物支給ではなく、キャッシュがいいのだろうか。
注文した品を待っている間にも、フェイスブックのトーク履歴で色々な日本人と友達であることを見せてくる。まぁ安心だよというアピールなのだろうが、お土産は別にいらないからなぁ。

サーブされたチョーレ・バトゥーラ(揚げパンとカレー)を食べている間も、噛みタバコで口を唾液いっぱいにしながら、ずーっと喋っていた。何が目的かは分からないけど、こうやって何度も話していると、彼のことはそんなに嫌いじゃないな、という気持ちになってくる。
料理の方は、高級レストランだけあってお腹にどっしりとたまり、元気が出るような気がしてくる。最近チャウミンしか食べてなかったからな。それでもお会計は130rp(≒230円)だった。

店を出たすぐ裏手には古い寺院が隠れており、これもムケシュに教えてもらって初めて気付いた。これにはちょっとびっくりした。そもそもレストラン自体がなかなか歴史や由緒がありそうな建物の一画を使って営業していたのだが、その横手には中庭のようなエリアがあって、その中に更にもう一つ、小さめの寺院が建っていたのだ。横には牛が繋がれていてゆっくりと草を喰み、その隣で少女が一心に水仕事をしている。この光景は、いったい何世紀前から変わっていないのだろう。大通り沿いの建物の中に、こんなスペースがあるとは。一歩外に出ればリクシャワーラーや露天商達が激しく鎬を削っているというのに、なんと牧歌的な平和な空気だろう。

ムケシュがこのお寺の説明もしてくれた。彼が教えてくれなければ気づかなかったこの光景には素直に感動したし、これまで何日も話しかけてきた縁もある。きっと最後なのでお礼に幾ばくかのお金を渡すと、喜んで受け取ってくれた。ここで別れたら、もう彼と会うこともないだろう。こんなストリートの渡世をしていて、ここまで日本語をうまく使いこなすというのは本当に素晴らしいスキルだとと思う。インドの教育事情には疎いが、きちんと教育を受ける機会があれば、彼の人生も大きく変わっていたのではないか、と思わずには居られなかった。

朝食後あてもなくブラブラしていると、バザールの食材屋で小分けのスナックを売っていたので、お土産用に少し多めに買う。これを持って歩いていると、いつもはお金を求めてくる子供達がそのお菓子をくれ!と集まってくる。
これまでの滞在中にも「お金をくれ!」と寄ってくる子供に自分が渡せる額のお金を渡すと、大抵は「これじゃ足りない」と言われ、どこまでも「足りない足りない」と言われ続けることが多かった。彼らの切実性にも依るのだろうが、「今あげられるのはこれだけだよ」といくら説明してもそこに対話の余地は殆どなく、難しく思っていたところだった。
しかしこの一袋5ルピーのスナックを子供たちにあげると、一つ渡すだけでとても喜んでくれる。「弟や妹の分も頂戴」という子もいたが、多くても3つほどで嬉しそうに去っていった。いつも渡していた20ルピーの方が金額としては高いのに、安価なスナックの方を喜ぶ子供たちの無邪気さが悲しかった。もしかすると、お金だと大人に渡さないといけないが、スナック菓子であれば自分たちで食べられる、という事情もあったりするのかもしれない。結局30袋ほど買っていたスナックの小袋は、あらかた配りきってしまった。

またバザールをブラブラ歩いていると、今度は道端で蛇使いがコブラを籠に入れて、笛を吹いて操っている。どうやら笛の音色でコブラを魅惑している間に、コブラがとぐろを巻いている籠の中にお金を入れろということらしい。
面白がったお母さんに言われて小学生くらいの女の子も小銭を入れに来るが、怯え切っていて、手が震えて小銭を籠の手前に落としてしまう。それを見て母親がケラケラ笑っている。次は腰の曲がった労務者風のお爺さんが寄ってきて、10rpを籠に入れようとするも、しきりにコブラを小突付くなどして挑発している。そんなことして噛まれたら損でしかないし、何のメリットもなさそうなのに何でそんなことをするんだろう。ほら、蛇使いも若干迷惑そうにしているではないか。呆れるとともに、とても愛らしく思う。皆の生活の息遣いが肌身に感じられるようで、何故かとても懐かしい気持ちになる。

この日は一日中、とにかくガンガーを眺めて過ごした。
どの旅行客たちも、きっと一世一代の旅行のような感じでここを訪れたのだろう。大学生グループはやたらとはしゃいで大きな声を出し、友達にビデオ電話をしながらも時々「シヴァサイコー!!」みたいなことを叫んでいる。その後ろではお爺さんがガンガーの聖なる水に全身で浸かりたいようだが、なかなか上手くいかない。その辺りはとても浅いようで、試行錯誤の末、結局横になってゴロゴロ転がることで全身が浸かったことにしたようだ。もっと奥では、壮年の夫婦とその年老いた両親が、すぐそこの売店で買った「ガンガーの聖水入れボトル」を胸の前に掲げ、並んで生真面目な顔で記念写真を撮っている。

私はヒンズー教徒ではないので、この大河の有り難さを心から感じることはできないが、ここを訪れている人達が、それぞれに日々の生活で大切にしているものを抱いて、今ここに来ていることは分かる。ここには、途方もなく大きな人の営みがある。ガートに入り乱れる人達の織り成す光景は、いつまで見ていても飽きることがなかった。

辺りも何だか陽が翳ってきて、夕方のプージャの時間が近付いてきたようだ。これに伴って人も増えてきたので、一旦ゲストハウスに戻り、今度は屋上からガンガーを眺めることにする。ゲストハウスに戻るには狭い路地を入っていかないといけないのだが、その途中でその辺りをたむろしていた青年の一人とふと目が合い、「お前の眼は冷たい石のようだ」(Your eyes looks like icy stones.)と言われた。何だかひどく暗示的な言葉だった。

ゲストハウスの屋上からは綺麗にガンガーが見えるのだが、いつ行ってみてもあまり人が来る気配はなく、いつも朽ちた折りたたみ椅子が二脚寝かせてあるのみ。そのうち一つの椅子を立て、買ってきたミネラルウォーターを傍に置いて腰掛け、また飽くまでガンガーを眺める。さっきまでのミクロな人の営みとは対照的に、今度は雄大なガンガーの水面が、どこまでもどこまでも見渡せるような雄大な眺望。

何の鳥か分からないが、中くらいの大きさの鳥が群れになって、右へ左へと薄紫色の空を飛び回っている。近くの仏塔の頂上には、緑色のインコ達が休んでいる。道端にあのインコを籠に入れて売っている物売りがいたが、あそこから逃げ出したのだろうか。それとも、あの物売りがそこらで捕まえて売っていたのか。どちらにしても、すごく大きな有機的営みの中の、小さな愛すべき出来事だという気がする。

大きな木のそばにあるゲストハウスは、猿たちの溜まり場になっている。スタッフが相変わらず箒を振り回して追い払おうとしているが、猿は少し場所を変えるのみで、また座り込んでのんびりしている。果てしないほど広い流れを湛える大河には、豆粒ほどの舟がいくつか浮かんでいて、それぞれにそれぞれの思いを持った人々が一様に揺られている。遠くから微かにプージャの音楽が聞こえてくる。夕暮れの涼しい風が心地よい。
ふと、いつからこの景色はこうなのだろう、と思う。ホテルやガート周辺の建物の経年具合を見ても、自分が生まれるずっと前からこのままだったんじゃないだろうか、という気がする。これまでどれだけの人達がこうやってガンガーを見に来て、自分と同じようにこの光景を見て、そして自らの生活に還っていったのだろう。そしてその人達は、今何をして生きているんだろうか。そして、その中の幾人かは天寿を全うし、或いは納得のいかない気持ちの中で、死んでいったのだろう。

我々は一体何なのか?我々はどこから来たのか?一人一人に過大なほどの意識を抱えて、何をしようというのか?何を為し、どこへ向かうのか?
しかしどんな問いを立ててみたところで、眼前のガンガーはただただ滔々と流れるのみ。ここでこうして無為な思索に耽っていると、とても穏やかな気持ちでいられる。いつまでもいつまでも、こうやって人々の営みを静かに眺めていたい。

しかしそれは一方で、これまでの自分の人生を捨ててしまうのと同義だとも思う。私にはこれからも一緒に幸せに過ごす大切な奥さんが日本で待っているし、やはり日本での生活がある。どこかで区切りを付けないといけない。しかし、その弾みを自分で付けるのがとても難しい。ガンガーはいつまでも静かに、永遠とも見紛う穏やかさで流れ続けていて、どこにも切れ目というものが存在しない。

そうやってどうにも気持ちを決めかねていると、ふとどこからか一定のリズムで金属をぶつけるような音が聞こえているのに気付く。しかも、その音は近付いてきているようだ。訝っていると、隣接するビルから一人のおじさんが上がってきた。手には何かよく分からないが長めの金属の棒を持っていて、それを特に意味もなくコツコツいわせながら登ってきたらしい。おじさんも普段は人がいない屋上に人がいてびっくりしたのか、お互いにハローとだけ声をかけ、そのまま暫く二人とも黙ってガンガーを眺めていた。
どちらからともなくぽつりぽつりと話し始め、私が一週間ほどバラナシに滞在し明日出発してしまうこと、これが初めてのインド訪問であること、一方でおじさんがフジ・ガンガーホテルというところで働いていて、同じ系列のレストランもあったが最近は業績が奮わなくて閉まってしまったことなんかを話す。そしてこの会話の合間にも、何度も二人で無言でガンガーを眺めて過ごした。

「髪もバラナシで切ったのか?」と聞かれて、これはしめた、と思い、面白おかしく「どうもボラれてしまったようで、最初は150rpだって言ってたのに結局2000rpも取られた」と話すと(インド旅行記⑥参照)、意外にもおじさんは「俺の髪でも80rpだぞ?それで2000なんてそんな…」と言葉に詰まり、心から気の毒に思ってくれているようだ。私も失敗談として笑い話にでもと思ったのだが、予想外におじさんが親身になってくれたことでうまく気持ちの受け身が取れず、お互いに継ぐ言葉も見つからず、暫く黙って見つめ合ってしまう。
おじさんの気の毒そうな眼差しに向かい合っていると、自分は「良い話のネタができた」なんて強がってたけど、本当は悲しかったんだな、と思った。またそれと同時に、このおじさんがあの出来事を受け止められるようにしてくれたのだ、という感覚もあった。
この感覚も、結局私が勝手に思い込んでいるだけなのかもしれない。このおじさんも、もう少し話していると裏の意図が見えてくるのかもしれない。でも大切なのは、今眼の前のおじさんが自分のことを気の毒に思ってくれている、という、それを感じた自分の心を信じるしかないのではないか。人間と人間の関係で、それ以上のことが果たしてできるだろうか。トライ&エラーを繰り返して精度を上げていくことはできたとしても、人と人との関係の根本にあるのはこの永遠の断絶と、片側から他方を一方的に信じる気持ちなのではないか。信じていた相手が思ったとおりではなかったとしても、その時はまた傷つけばいいだけだ。そのことを恐れて信じることをやめてしまうのは、ひどく味気ない世界を生きることになってしまうように思う。

どこでこのガンガーを眺め続けることをやめるのか。ひいては、この旅を終えて自分の日常生活に還ってゆくのか。自分の中でも区切りを付けかねていたが、結局は絶対的な他者として、或る種の啓示のように現れたこのおじさんがこうやって親身に話を聞いて、心を寄り添わせてくれたことで、また自分と関わりのある人達の関係性の中へ帰っていこうと思うことができたように思う。
これでいいじゃないか。そろそろ、帰ることにしよう。私は(今後もしかするとそうでなくなるとしても、少なくとも今は)優しいおっちゃんに「それじゃ部屋に戻るよ、ありがとう」と告げ、日が暮れ出した夕闇の中、おっちゃんの気配と静かに広がる星空を背中に感じながら、急な階段を転ばないようにゆっくりと部屋に戻った。
(インド旅行記⑨に続く)





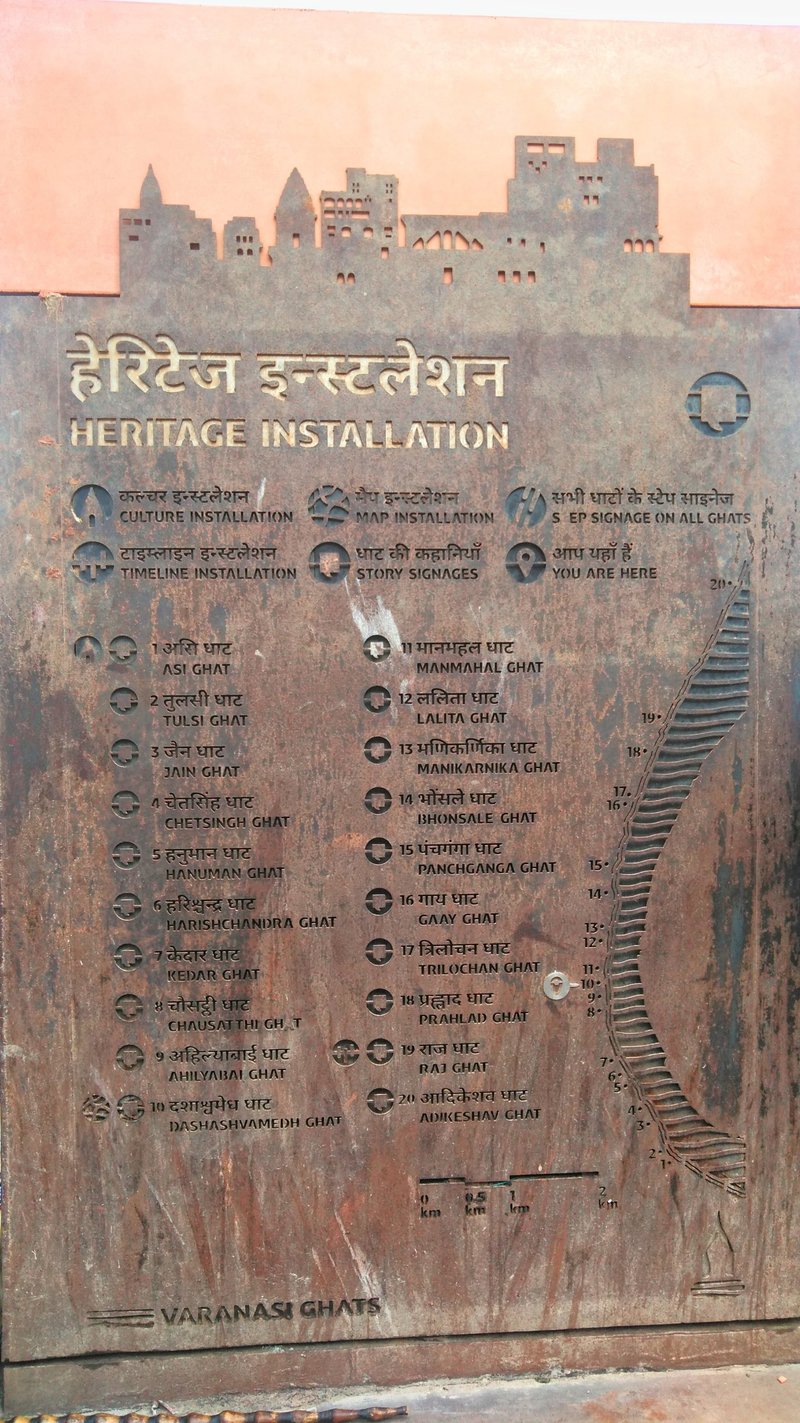
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
