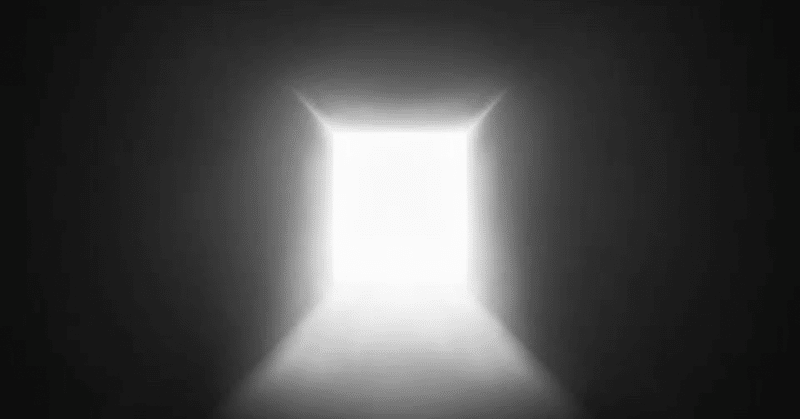
夢の中で
ここは、どこだろう。
暗い。もしかして夜だろうか?きっとそうだ。
冷たい。もしかして冬だろうか?わからない。
広い。もしかして外だろうか?どうだろう。
ふと、辺りを見回してみた。
どうやらここは、何か建物のようだ。
周りはコンクリート製の壁に覆われており、青白っぽいライトが微かに照らしている。
その、自然には無いような、人工の色合いがどうも、暗くて冷たく感じた。
ふと、あることに気づいた。
僕は、歩いている。いや、走っている。
僕が進むと、周りの壁たちは後ろへと流れていく。点々と間隔を空けて置かれた薄暗いライトが、一つ一つと通り過ぎていく。
それが僕に、白と黒を繰り返し見せる。それらが混ざる暇もないくらい、テキパキと。
そして、もうひとつ気づいた。
僕以外にも、人がいる。
4、5人と一緒に、僕は走っていた。
廊下のような場所を、僕らはひたすら前へと走っている。僕は後ろにいるため、顔はよく見えない。
どうやら男女どちらもいるようだ。知り合いだろうか?よく耳を澄ますと、何か喋っているのが聴こえる。
「間に合うかなぁ、?」
「多分大丈夫!」
「こっちであってる?」
「多分大丈夫!」
「なんだよ、多分って。笑」
みんなが喋っている。誰の声だ?
何を言っているのか、内容はハッキリとわかるのに、誰の声なのか見当もつかない。
おそらく友達だろう。何せ自分が、こうして一緒に走っているのだから。
それほど友達が多い方ではないので、候補はそこまで多くない。でも何故か、誰もわからない。
少しして、1人がこちらに話しかけてきた。
走りながら、顔だけ微かにこちらに向けて、
「もうすぐだよ!楽しみだね!」
明確にこちらに向けられた言葉に、僕は少しどきっとした。女の子の声だ。
しかしわかるのは、それがやっとだ。顔もハッキリ見えないし、姿もぼんやりしていてよく見えない。
僕は特に返事をした覚えもないが、彼女はニコッと笑い、また前を向いた。僕はこの人と、話したことがあるのだろうか。
少し、冷静になってきた。
だからこそ、少しずつ怖くなってきた。
ここは一体どこだろう?この暗くて、冷たくて、それなりの広さはあるのに、妙に圧迫感のあるこの空間。長い長い廊下のようだが、先は真っ暗で全く見えない。
天井のライトも頼りなく、ほのかにその場を白く染める程度だ。せめてもう少し、明るく照らしてくれれば良いのに。
そして、彼らは何者なんだろう?
本当に知り合いだろうか?顔を見ようとしても、あと少しのところでボヤけてしまい、よく見えない。顔が無いわけではない、ただ僕には全く、その顔が捉えられないのだ。
そして、こんなにわからないのに、この安心感は何だろう。
顔も声も、誰一人としてわからないのに、友達だろうかと思ったのは、一つにはこの安心感がある。
ずっと一緒に居たような、青春を分かち合ってきたような、そんな類のものだ。
僕は少しだけ、怖くなくなった。
それから、僕らはどこへ向かっているんだろう?
この真っ暗で冷たい廊下の先には、何か素敵なものがあるのだろうか?何故こんなに急いでいるのだろうか?
考えても、特に候補は思いつかなかった。
さっきのあの子は、楽しみだと言っていた。
一体何が待っているのだろうか。
そういえばさっきのあの子、何で僕に話しかけてきたんだろう。
他の人たちは走るのに夢中で、時折言葉をもらす程度だ。
でもあの子だけは、僕一人に向けて話しかけてきた。何故だ?
僕は彼女と、会ったことがあるのだろうか?
僕は大切な誰かを、忘れてしまっているのだろうか?ひょっとしてきm…
一人が大声で、叫んだ。
「あった!あそこだ!!」
僕らの進む先に、壁が現れた。そしてその下の方に、両開きの扉があった。
僕らはどうやら、あの扉の先を目指していたらしい。
みんなで一斉に扉へ駆け寄り、そして、鍵がかかっている可能性を全く考慮せずに、勢いよく突き破るようにして扉を開けた。
そこには、
外があった。
扉の向こうは外に通じており、屋上のようなだだっ広い場所があった。どうやら今は、夜らしい。
でも、そんな事はどうだって良かった。
どうだって良かったのだ。
それは、夜空を埋め尽くす、満点の星空だった。
屋上の様なその場所は開けていて、空が広々とよく見えた。
しかしそんな広い空を、余す事なく隅々まで埋め尽くすように、ビッシリと星たちがひしめき合っていた。
一つ一つが宝石のような、力強い輝きを放つのに、それがおびただしい数で空一面を覆い尽くしていた。端っこまで、しっかりと。
僕は生まれて初めて、空に吸い込まれた。
その星空はただそこにあるのではなく、僕に覆いかぶさるようにして圧倒的に存在していた。
どこまでも暗い深淵の中に、どこまでも明るい光たちが浮かぶ。僕はその闇にすっぽり包まれ、そしてその光にまっすぐ貫かれた。
手を伸ばせば、届きそうだった。しかし僕は、手を伸ばそうとは思わなかった。
僕は少し、恐ろしくなった。
すると、その星々の中にひっそりと、でも確かに、大きな青い月が浮かんでいることに気がついた。
他の星たちのような鋭い輝きはないが、ぼんやりとした幻想的な佇まいをしている。星の一つ一つを、そして僕ら一人一人を、淡い青でそっと包み込んだ。
空の闇を満たしたその青へ、僕は思わず手を伸ばしそうになった。
僕は少し、安心した。
しばらく呆然と立ち尽くしたあと、やっと誰かが声を出した。
「す、すげぇ!!すげぇよ!!」
「やったよ、、本当にみれたんだ!」
後を追うように次々と、みんなが歓声をあげた。どうやら僕と同じようにみんな、空に圧倒されて言葉を失っていたらしい。
さっきのあの子も空を見つめながら、思わず声を漏らす。
「きれい…」
その澄んだ横顔が、夜空の光に照らされて、ハッキリと見えた。
彼女は、泣いているようだった。
透き通った黒い瞳に、星たちが映り込む。
そしてあふれた涙に乱反射しながら、彼女の瞳の中で、まばゆく踊りだした。
僕は自分も、泣いている事に気付いた。
何故か、涙が止まらない。
どうしてだろう。溢れて止まらない。
自分の涙の滴で、彼女の姿が滲んで見えた。
嬉しいような、馬鹿馬鹿しいような気持ちで、思わず自分で笑ってしまった。
その様子に気づいた彼女も、ゆっくりとこちらに振り向き、そっと微笑んだ。
恐ろしいほどに、美しかった。
そして僕の方に近づいて、
「あのね、、」
彼女が何かを言いかけたその瞬間、何かが僕の背中を掴んだ。そして、ものすごい力でさっきの扉の中へと引きずり込む。
僕は為す術もなく、どんどんと元来た道を戻される。薄暗く、冷たいあのコンクリートの廊下へ逆戻りだ。
白と黒を繰り返しながら、あの扉はぐんぐんと遠くなっていく。
最後の一瞬、彼女が手を伸ばしているのが見えた。そして、驚きと悲しみを混ぜたような表情が見えた。
あぁお願いだ、そんな顔しないでくれ。
きっと大丈夫。僕は大丈夫だから。
僕らはきっとまた、どこかで会えるさ。
でも、一つだけ。
一つだけ、教えて欲しいんだ。
君は一体、、、
僕は、ハッとした。
そこは、自宅のベッドの上だった。窓の外には、都市のビル群とネオン街の明かりが見える。
見飽きた、いつもの景色だ。
僕は汗でびしょびしょのまま、ベッドへ倒れ込み、仰向けで天井を見つめた。
無機質な天井に、窓から月の光が差し込んでいた。
とても冷たい、青色だった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
