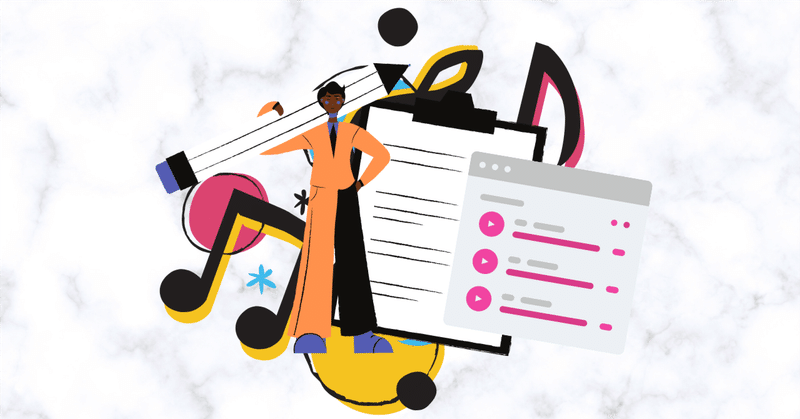
AIに人を感動させるような曲はかけないというミュージシャン
数ヶ月前だろうか、NHKラジオのマイ朝を聴いていたら、大貫妙子が出ていた。
多分土曜か日曜、
朝の7時前に、10分ほど、各界の様々な人が
エッセイを語る番組だ。
その彼女は、表題の
『#AIに人を感動させるような曲はかけない』
と言った。
多分70歳前後の彼女は、固くそう信じているのだろう。
同じ番組で、数日前、男性のミュージシャンが出ていた。
私は名前を知らなかったし、聞いたが覚えていない。
口振りからは、結構売れているミュージシャンのようだ。
彼は多分40代前後、(20代から50代だろう。)
彼は、パソコンソフトなどを補助に使って、
作曲や編曲、あるいは楽曲の分析などもするいう。
AIも使ってみたが、結論としては、
『#AIに人を感動させるような曲はかけない』
と、彼も言った。
私は、
『#AIに人を感動させるような曲を書けるようになるのは#時間の問題』
だと思う。
AIは瞬時に多くの曲が書ける。
あるいは書けるようになるはずだ。
人は、作曲の知識がなくても、AIで作曲させることができる。
それを作曲に興味がある多数の人が、
何度でも何度でも多数繰り返し、
AIに文句を言ったりアドバイスをして出てきた曲を
世間に公表すれば、その中に
人の感動を呼ぶものが出てくる確率は高まる。
それはフルオーケストラだろうが、
電子楽器だろうが、
アコースティックの楽器だろうが、
民族楽器だろうが
それらの組み合わせだろうが、
あらゆる編曲が可能だ。
ボーカルも、
ソロから、コーラス入り、男性、女性、混声、子供、デュエット、フルコーラス、
アカペラ、輪唱、・・・・。
思いのままだ。
作られる数とスピードが違う。
それを世に出す者には、
心理学や脳科学、社会行動学、データ解析など様々な学問分野や、
マーケティングやブランド構築、
人事や会社経営など、人や人の心を動かすプロなど
様々な才能が参入する
だけではない。
その音楽の消費者=ファンも参加する。
自分の好みの楽曲を世界に届けたい
P2Bの世界が出現するのだ。
これは生産者(メーカー)であるミュージシャンではない
「主役の消費者」が
市場にアプローチする
ことを意味する。
ビジネスが、
メーカー目線から、
消費者目線、消費者主導に変わった。
独りよがりなメーカーは退出させられた。
歴史は繰り返すだろう。
音楽や芸術に
消費者目線、消費者主導は
当然進出してくる。
それがAIの時代なのだ。
かれこれ4半世紀前、
チェスや将棋の世界最高峰の人たちが世界最高性能のコンピュータに敗れ去った。
それでもその頃、
囲碁は複雑だから、なかなかコンピュータには勝てないだろうと言っていた。
コンピュータが人間に勝てる時期は
今から10年ほど先だと言われていた気がする。
しかし、今から10年ほど前に、
パソコンソフトがプロ棋士に勝てるようになった。
そして、スーパーコンピューターではないパソコンにである。
2000年ごろは単独のコンピューターの能力で人間と勝負しようとしていた。
しかし、今はコンピューターの能力も桁違いだが、
何より、インターネットがあるし、世界中の情報にアクセスできる。
また、個人情報にもアクセスしていて、
個人単位で、音楽の好みも知っている。
大貫妙子が彼女のファンを一挙に大幅にAIに奪われることは
彼女が現役の間はないかもしれない。
しかし、前出の男性のミュージシャンの場合は
自分で手の内をAIに教えている。
彼が生き残るのに必要なことは、
1 AIをうまく使いこなすこと
2 AIが作った楽曲には識別CODEを義務付け、著作権は人が作ったもののみにする、世界を網羅する法律や条約の制定
の両方が必要だろう。
私は、かれこれ30年以上前、中国に農業視察に行った。
私は有機農業で生姜を生産していたが、
全国シェア40%以上の生産量を誇る高知県の生姜農家の未来を占うために中国に行った。
その時日本の生姜の年間消費量は4万トンだった。
そして中国、私が行った一つの村は地平線の彼方まで生姜畑だった。
当時の見た目重視の日本の一般市場での生姜の規格からは、
中国産はお話にならないと言って
農協関係者は笑っていた。
しかし、私の行った村の近隣を合わせただけで、
生姜の生産量は160万トンほどあった。
人口が十倍の中国人が生姜を日本人と同じだけ食べたとしても
その村の周辺には4年分の生姜があった。
日本で言えば、40年分だ。
そして、中国の人件費は、若い男の賃金で、百円/日だった(記憶なので不確か)。
当時、私の会社では、60代のパート女性に6−7千円/日払い、タクシーで送り迎えしていた。
二桁違う人件費だ。
160万トンの生姜から安い人件費で、人海戦術で選別すれば、
日本の見た目の品質に耐えるものは
1万トンぐらい直ぐに出る。
市場規模の何割単位で、中国産の生姜が日本市場に入れば価格破壊を起こす。
私は、有機栽培でやっていることの正しさを確信した。
さて、本題のAI、私の生姜の問題とは似た問題と違う問題がある。
20世紀は大勢の芸術家が生きている間に成功できた、
そして生活できた人類史上稀な
彼らにとって幸せな時代だった。
21世紀中盤以降はどうなるのだろう?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
