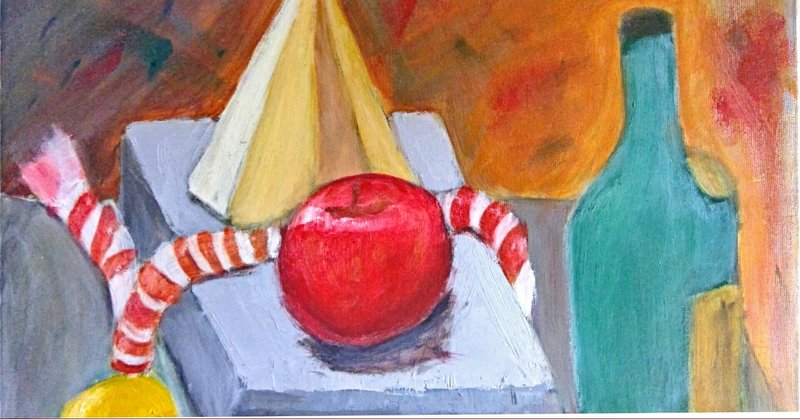
【断片小説】ア・ハーフ(12/24)・デイズ・ナイト ①
午後三時過ぎのこと、僕はベッドにうつ伏せで寝ていた。屈強なボクサーに強烈な左カウンターパンチを喰らってそのまま前に倒れたような格好だ。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のマーティ・マクフライの特徴的な寝相と似ている。入居したころより備え付けられていた堅いベッドをいつまでもスマホのバイブ機能が揺らしていた。アラームをセットした覚えもないのにどういうことだろうと思いつつ、寝ぼけまなこでスマホをとった。電話だった。
「もしもし」
「あ、もしもし。悪いな。寝てたのか、声でわかるよ。寝ていたのなら話も早い。君はきっと暇だってことだ。なぁ、今夜久しぶりに会わないか?」僕の寝起きの声は、味わい深いウィスキーをしこたま飲んだ後の砂漠の旅人の声のような深い低さがある。そう、誰かに言われたことがある。対して、この電話の主の声は、少し冷気を帯びて飄々とした印象を聞く者に与えるものの、そこにはどこかしら湿りを含む人間臭さのようなものも感じ取ることができる。
「今日がなんの日なのか分かって言っているのか?」、耳を澄ませば、下のコンビニの前で店員がケーキのセールを呼び掛けているのが聞こえてきそうだった。
「もちろん、イブだ。クリスマス・イブ」、いくぶん語気を強めて彼は言った。
「どうしてイブの夜に恋人でもないお前と会わなくちゃならないんだよ」
「なにを言ってんだ。イブの夜に恋人を置き去りにして友達と会っちゃいけないなんて法律はどこにもないさ。そして都合のいいことに君には恋人はいないだろう?」
「いない。五年はいない」
「それなら万事オッケーだ。ウチに来てくれ。場所は後で送っておく。映画でも見よう。見たいやつがあるんだ。安心してくれよ、さすがに恋愛映画をイブに一緒に見るようなセンスは持ってないさ」、そう言って彼がリクエストしたのは、数年前に劇場公開されたバイオレンスホラー邦画だった。15禁のレイティング付き。むしろこっちの方がセンスが悪いとも言える。
「悪いけど、ツタヤで借りてきてくれよ」
「俺が?」
「君が」
僕は頭の後ろに手をまわし、大げさに頭を掻いた。電話の向こうの彼に見えるわけでもないのに。返事をどう返そうか迷っている間に、彼はその沈黙を要請受諾と捉えたみたいだった。
「それから、コンビニでつまみを買ってきてくれよ。ポップコーンとかさ。やっぱり映画にはポップコーンだよな。普通の塩味でかまわないよ。あとはスモークチーズとかかな。安心してくれよ。酒はウチにたくさん揃っている。というか酒しかない。あぁだから安心してくれよ。金は出すよ」
「当然」そう言って僕は電話を切った。
おかしな姿勢で寝ていたために、ひどく首が痛かった。寝違えたのだ。スマホを持ったまま首のストレッチをしていると、彼の住む番地を告げるメッセージが届いた。
☃
街のどこの店でもイルミネーションが光り、どの店員もサンタやトナカイの仮装を着飾ってセールの呼びかけをしていた。誰一人としてキリストの誕生日を純粋に祝うものなどいないように思われた。
ツタヤでも例外なく、クリスマス特別セールをしていた。リクエストされた映画のタイトルの場所をサンタ帽を被った大学生くらいのバイトに訊ねた。彼女は僕の頭の五センチ上辺りを見て一瞬考えるふりを見せたあと、「少々お待ちください」と言って店の奥へと姿を消した。1分もかからないうちにDVDの入ったケースを持って戻ってきた。
少し切らした息を整え、僕にケースを手渡しながら、
「今、通常1週間のレンタル期間のところ、2週間に伸ばしてお貸しさせていただいています。こちらは旧作タイトルのみなのです。あ、別の割引としまして新作・準新作タイトルと合わせて5枚レンタルしていただくとお安くなりお得ですよ」と言った。
「いや、見たい映画はこれだけだし、それに明日返すから」、盤面を裏返し、目立った傷がないかを確かめながら言った。しかし、ケースが汚くて、うまく見極められなかった。
「そうですよね、旧作1枚だけでしたら1週間は長すぎますよね。私思うのですけど、レンタルしておいて1週間の終わりギリギリまで見ない人のこと、理解できないような気がします」彼女はサンタ帽を取り、果実をもぎるみたいにポンポンをいじっていた。
「世の中には色んな見方で映画を楽しむ人がいるものだよ。借りたその日には見ずに、しばらく日を置いてから、さて見てみようかとDVDをセットする人だっている。なにしろ他人の物語を受け入れたり、否定したりしなければならないからね。そして作品の出来によっては、それを自分自身の物語に組み込もうとする人だっている。そのためにはいくらか覚悟がいるものだし、相応の準備がいると思うんだ」
僕はケースを彼女に渡して、レジへと向かった。
「あなたもそうなの? 他人の人生を自分の物語に組み込むことについて」
これおつりです、1円玉2枚を手渡す。ふいに彼女の指の先が掌に触れた。堅く冷たい、陶器でできたような指先だった。まだサンタ帽は被っていなかった。
「僕に限って言えば」、会計の済んだ商品をリュックに入れる。
「覚悟する間もなく、いつも突然にやってくるんだ。誰も彼も突然に自分の人生を持ち寄ってくる。いつからか準備は無駄だと思った」
誰も彼も、僕のことなどお構いなしに自分の人生を語り始める。
☃ ☃
この街が碁盤の目のように都市開発されていて助かったと思った。住所は南北・数字と東西・数字の組み合わせで表されており、ここから北に何ブロック、東に何ブロック進めばいいのかわかりやすい。算数や数学を好きでもないのに習っていたのはこの時のためだったのだろうかと思う。昨夜から明け方にかけて降り積もった雪は、除雪車によって道路脇に寄せられ、土くれなどと混ざって薄汚い色の壁となり、ガードレールの役割を果たしていた。
僕は左手に約束通りにポップコーンとスモークチーズ、その他のつまみの入ったビニール袋を提げていた。どうせお金を出すのは彼だ。そう思うと、僕は多めに買うような人間だった。安心してくれよ、ポップコーンはバター醬油味にしておいたのだから。右手? 右手は上着のポケットに突っこんでいる。手袋が先月から見当たらないのだ。
リクエストされたDVDは大きなリュックサックの中に入れてある。その大きなリュックサックの中には他には財布とメガネケースしか入っていない。他に手頃な大きさのリュックを持っていなかったからだ。
白い壁の大きなアパート(むしろマンションと呼んだ方がいいのかもしれない)の前は綺麗に雪かきがされていた。エントランスの共用部扉の解錠のために部屋番号を震える指で押すと、彼は返事も待たずに解錠した。エレベーターで4階にあがり角部屋のインターフォンを押すと、しばらくしてからドアが十センチばかり開いた。
【②へつづく】
よろしければお願いします!本や音楽や映画、心を動かしてくれるもののために使います。
