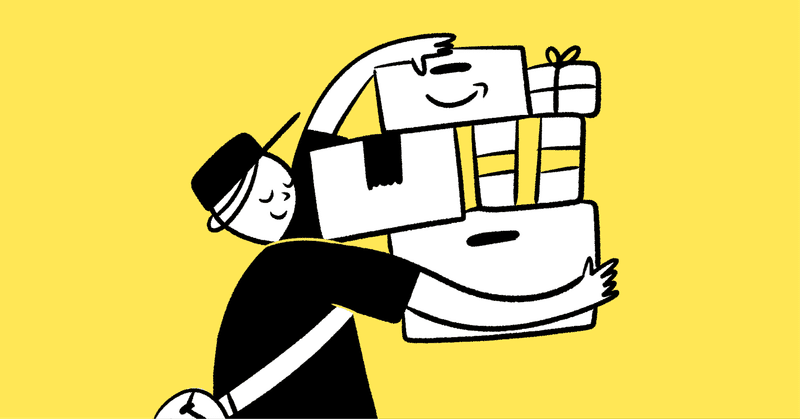
学部長の教科書⑩ リーダーシップ編 第5ステップ ビジョンの障害を放置せず、解決する
学部変革に向けたビジョンやミッション、コンセプトがかたまり、学部教員にもその内容は伝わりました。いよいよ学部変革を起こしていく段階です。
ただし、学部変革を進めていく上で、学部長が見落としてはならないものがあります。それは、コッター教授がいう「社員のビジョン実現へのサポート」という第5ステップです。わかりやすく言い換えれば「教員がビジョンを実行する上での障害を放置せず、解決する」ことです。
学部ビジョンやミッションが策定されると、その考え方にもとづいて、WGや現場の教員が新たな取組みを始めていくことになります。しかし、新たな取組みを進めていこうとすると、その前に立ちはだかるものが出てきます。それは「既成概念」や「慣習」、そして「既得権益」などです。
それらは、これまで長年にわたって行われてきた取組みだったり、学部・学内に存在する公式/非公式なルールです。あるいは改革に逆行する考えを持っている教員の存在かもしれません。いずれも変革に逆行する要素であり、改革を進めるうえで障害になるものです。それらを取り除こうとすることは、学部長にとっては特に心理的に大変な仕事になります。しかし、ここでもやはり学部長のリーダーシップが求められるのです。
「取り除き」、「減らし」たうえで、「増やし」、「創造する」
学部変革のためには、一人でも多くの教員がビジョンやミッションに理解を示し、フラットな人間関係のもとでチームとして教育改革に集中して取組む必要があります。しかし、実際には、先に述べたような様々な阻害要因があります。
では、改革を進めるにあたって、まずは阻害要因を取り除くことにエネルギーを注ぐべきなのでしょうか? それとも新たな改革に注力して、「まずは走る」ことに集中すればよいのでしょうか? どのような順番で学部変革に取り組めばよいでしょうか?
ここでは、W・チャン・キムとレネ・モボルニュによるビジネス本の名著、『ブルー・オーシャン戦略』を参考にしましょう(W・チャン・キム/レネ・モボルニュ『〔新版〕ブルー・オーシャン戦略』ダイヤモンド社,2015年)。「ブルー・オーシャン戦略」とは、ライバルがひしめく市場でコスト競争にあけくれる「レッドオーシャン市場」から、ライバルが存在しない「ブルーオーシャン市場」へとポジショニングを移すための差別化戦略のことです。ブルー・オーシャン戦略では、コスト優位なビジネスモデルやビジネス戦略を生み出すことに主眼にありますが、学部改革においても、限られた資源(予算、人、設備等)をいかに効果的・効率的に活用して大きな成果に転じられるかを考えていく必要があります。
ブルー・オーシャン戦略では、「4つのアクション(the four actions framework)」という枠組みが提唱されています。すなわち、次のような4つの問いを通して、これまでのビジネスモデルに挑む必要があると述べています(なお、このフレームワークは『次世代トップエリートを生み出す 最難関校 ミネルバ大学式思考習慣』を書かれた山本秀樹さんから教えていただきました)。

(出典:前掲77-80頁をもとに作成)
「4アクション・フレームワーク」では、まず「取り除く」ことからはじめ、次に「減らし」、そのうえで、「増やすこと」や「創造する」という順序が重要であることが示されています。新しい取り組みがどんなに優れたものだったとしても、「取り除く」ことと「減らす」ことなしに進めてしまえば、人や予算といった資源を分散的に投入することになってしまい、一般の教員から見れば「ただやるべきことが増えただけ」になります。学部長に対する信頼感は確実に低下するでしょう。したがって、「取り除き」「減らす」ところから改革を進めていく必要があるのです。
もちろん、「何かをやめる」こと、特に「改革を妨げる要因を除去する」ことは、学部長にとってストレスフルな仕事です。存続を願う人との対立は避けられません。「このプログラムをやめることを納得してほしい」と相手を直接説得することも必要になるかもしれません。あるいは、教育プログラムの担当者や責任者を変更するような権力の発動が必要になるかもしれません。学部長は矢面に立つことになり、つらい気分を味わうでしょう。しかしこれこそが学部長という権限を持った人しかできないことなのです。
こうしたことは、改革ビジョンを共有した後の早い時期に手を付ける必要があります。それは、その後の改革をスピーディーに進めるためでもあり、学部長への信頼感を獲得するためでもあります。
Q1.取り除く
①学生を分断する考え方やプログラムを「取り除く」
新しい改革ビジョンや学部コンセプトに逆行する考え方や要因は、最初に「取り除く」べきです。もはや「ほとんど無価値」であるにも関わらず、あるいは「ない方がよい」にも関わらず、変革を阻むものにはどのようなものがあるでしょうか?
私の前任校では、2学科を1学科に再編するところから学部改革がスタートしました。それまで2学科の違いを打ち出せず、共倒れの状態になっていたからです。これは私の前任の学部長が手掛けた仕事ですが、私が学部長として改革をスタートさせるうえで大きな「お土産」でした。
学部長として改革を進める中で気づいたのは、「出身高校や教科学力、GPAだけで“できる”学生と“できない”学生を区別する考え方」から決別することの大切さです。
大学の教職員は、結構学生の能力を見誤りがちです。愛想がよく、反抗的なところがなく従順で、外見も奇抜なところがない学生を「優秀な」学生とみなしがちです。しかし、教員が注目してこなかった学生が就活で意外な成果を出して驚くことは珍しくないはずです。また、多くの学生は、教員に対して「ペルソナ」を見せているに過ぎません。「優等生」に見えても、学生一人ひとりは教員が想像する以上に複雑で、悩み多き青年期を生きているのです。「できる学生」とか「できない学生」といった単純な二分法で学生を見ることはなくすべき考え方です。
また、多くの文系学部では、GPAは学生の能力のごく一部を評価するものでしかありません。GPAが低くとも、主体性や課題解決力、コミュニケーション能力といった非認知能力が高い学生はたくさんいます。1年生の時から常にGPAが高い学生よりも、最初はGPAが低くとも4年間で伸びた学生の方がガッツのある学生だと感じることもあります。極端なことを言えば、科目数が多くしかも自由に履修できる余地が大きいカリキュラムであれば、GPAは楽勝科目に関する情報を入手できるかどうかの要素が大きくなります。
結局のところ、「できる」「できない」は相対的な話でしかありません。「能力の低い学生を別にする」という考え方にもとづく教育プログラムは、すぐさま「やめる」べきです。学部変革は、「すべての学生が成長する潜在能力を持っている」という価値観を持って取り組むべきです。学内で「できる」と思われる学生だけに手をかけていくのではなく、「できない」と思った学生が伸びる仕組みこそが、高校生や高校の先生のニーズであることに気づく必要があるでしょう。こうした意図は、学部変革のビジョンと関連させながら、一般教員には何度も伝えるべきです。
前任校では、この点から、初年次基礎ゼミナールを入試別やプレイスメントテストの能力順に編成するようなやり方をやめました。これは現任校でも踏襲しました。その結果、多様性の中で学生同士がお互いの良さや強みを学び合うような雰囲気が醸成されていきました。退学率も一気に下がりました。
もちろん、能力別クラスや習熟度クラスは、語学科目に関しては一定の合理性はあるかもしれません。また、海外の大学で多くみられる「honors program(オナーズプログラム)」のような、トップ層の学生を選別して、さらに引き上げる特別プログラムがあってもよいとは思います。ただし、それは「すべての学生の能力をきちんと引き上げる教育プログラム」があることが前提です。一部の学生だけを伸ばそうと考えている学位プログラムで学ぼうと思う学生がいるわけはないのです。
② “できない”学生を軽視する考え方を「取り除く」
「学生をできる・できないで区別しない」考え方にもとづいた改革を進めるためには、「“できない”学生を軽視する」考え方を持つ教員を、学部長を補佐する役職や教務委員、初年次科目の主任などに任命しないことも必要です。これは当たり前のようですが、大変重要なことです。いくら仕事ができる教員であっても、いくら学部内で影響力の強い教員であっても、「“できない”学生を軽視する」考え方が強かったり、「“できない”学生に対して組織的に対応する」ことの重要性を認めない教員であれば、改革を推進するポジションにつけるべきではないと、私は考えています。
私も、かつて「考え方の違う教員を変えてこそ」と思い、ある意味で保守的な教員に学部長を補佐する役職についてもらったことがありました。案の定、本人は学部改革を積極的に推進しようとせず、また、周囲の教員も私の意図が理解されず、冷ややかな見方が学部内に蔓延していったことがありました。最終的に、「泣いて馬謖を斬る」ことになったのは言うまでもありません。
学部長は総じて権限が弱く、自分を補佐する教員の任命すら自分の意見が通らない大学もあるでしょう。しかし、改革を推進するポジションに、反改革的な考え方を持つ教員を置くべきではありません。それは他の多くの教員からの信頼を失うことにつながります。もちろん、考え方の異なる教員をいかに説得し、巻き込んでいくかということも重要ですが、それはまた別の話です。
Q2.減らす
①正課授業以外の取組みを「減らす」
教育の質保証を支えているものは、本来であれば、3つのポリシーとカリキュラム、そしてカリキュラムと連動した質の高い授業です。しかし、カリキュラムの整備や授業改善には時間がかかります。教員の考え方もバラバラであり、コンセンサスをとりながら授業改善を進めることは一朝一夕にできることではありません。
こうした結果、授業改善以外の様々な“改善策”が五月雨式に導入され、それが相互関連性を持たないままアドオンされていくことが起こりがちです。また、大学はえてして他大学や競合校に負けまいと、他大学や競合校の取組みを五月雨式に盛り込みがちです。
現任校に着任して印象的だったのは、授業改善への取組みが弱い一方で、授業外・正課外の取組みが多いということでした。退学防止を目的とした担任制、学生面談とそれに伴う膨大な書類作成、○○コンテストや○○コンクール、○○講座のような授業外で行われるイベント、学部のDPと関連性の薄い留学プログラムなど、様々な取り組みが導入され、教員が様々な形で関わる取組みが目立っていました。
組織的な教育改革や授業改善という根本のところに手を入れず、効果の薄い取組をあれこれ取り入れてしまうと、教員がやるべきことが分散してしまい、教育改革にパワーを集中することができない状況にあります。特に、授業以外の業務量を増やすと、授業改善や授業準備にかける時間は減少し、授業の質は確実に低下していきます。この点は、多くの大学経営陣に意識してもらいたい点です。
私は、授業外の取組およびそれに関する教員の負担を「減らす」ことにつとめてきました。それは、自分が教員だからという理由ではなく、教員にはもっと授業改善や授業準備、学部として組織的に取組む教育改革に時間を割くための余力を持ってほしかったからです。
現任校では、以前は年度当初に1年から4年のゼミに配属された学生の面談を必ず行い、担任による所見を1人ずつ作成し、その内容にもとづいた担任報告書を保護者に送付するようになっていました。1つのゼミの定員は20名です。3学年にわたってゼミを担当している教員は、60名の報告書を作成することになります。あまりに教員の時間を圧迫していたので、書面の8割を学年共通の内容を学部として作成し、担任教員の所見は極めて短い内容に変更することにしました。また、その所見も前年度のゼミ担当教員の総合所見をもとに作成できるようにしました。この変更によって、学部として保護者に伝える情報は一貫性を持ったものとなり、むしろ学部と保護者とのつながりは強まったと感じています。
その他、授業外に教員が動員されることもできるだけ減らすように務めました。高校への出前講座などはその一例です。「こんな業務に時間をかけるくらいだったら、授業改善に時間を当ててほしい」と教員に伝えるようにしました。任期期間中の4年間を通じて、教員の業務はかなり効率化を進められたと思います。
②教員個人が学生の責任を追う仕組みを「減らす」
多くの大学では、今述べたような「担任制」が導入されています。大学に「担任制」があることはさほど知られておらず、「大学で担任とはレベルが落ちた」という人がいます。しかし、実は大学における担任制には長い歴史があります。私の大学時代でも、教養部の語学クラス担当の教員が「担任」ということになっていました。ただし、担任の先生と個人的に話をすることは一度もありませんでしたが。
現在では、成績不振問題、人間関係の問題、中退問題、就職問題等、多くの学生が様々な問題を抱えるようになりました。それとともに、担任が個々の学生の実情を把握し、適切な支援を行うことで、問題を解決しようと考える大学は増えています。すなわち「担任によるパーソナル支援」を厚くしていけば問題は解決するだろうということです。
しかし、「一人の学生を一人の教員が面倒を見ることが良い取組」というのは思い込みです。私は、担任制そのものの存在を否定はしません。ただし、一人の教員が一人の学生に対して働きかけても限界はあります。
大学教員には、学生支援の経験や知見にかなり差があります。学生支援に関心が薄い教員がいくら面談を形式的に行ったところでからこぼれ落ちる学生は簡単にこぼれ落ちていきます。一方で、面倒見の良い教員は、自分の研究時間や授業準備時間を犠牲にして面談に取り組むのですが、学部内で歩調が合ってなければ、成果にはほとんどつながりません。
そもそも、学生が成績不振に陥ったり退学したりするのは、教育プログラムに問題があるためであり、個々の教員の支援不足のせいではありません。個々の教員がいくら学生に対して丁寧なパーソナル支援を行ったところで、退学率はさほど変化しません。「面談による退学防止策」とは、学部全体の組織的な教育改善に手を付けない一方で、その責任を担任に「押し付け」ているだけなのです。
退学問題や成績不振問題を教員の面談というパーソナル支援によって解決しようという取組みは「減らす」べきです。
③ その他減らすもの
もちろん、「減らす」べきものは他にもたくさんあります。その筆頭が「カリキュラムの科目数」です。ただし、カリキュラム改革は学部長になってすぐさま手掛けられるようなものではなく、少なくとも1年以上は時間がかかります。カリキュラム改革については、noteの過去記事に詳しく説明していますので、御覧ください。今後、「カリキュラムのマネジメント」の項目でも改めて論じる予定です。
3.「増やす」と「創造する」
では、学部で何を増やし、何を創造すればよいのでしょうか。学部によって必要なことは異なると思いますが、私は、何よりも「教員が学ぶ時間(FD)」と「教育面に関する教授会のコンセンサス」を増やし、「教員協働で進める授業」を加えるべきだと考えています。
私が知る限りでも、FD(Faculty Development;大学教員の能力開発)を形式的に行う大学・学部が多いと感じています。90分間の中で、前後の挨拶があわせて10分ほどあり、70分で講演を行い、あとの10分ほどが質疑応答となるようなFDセミナーがほとんどではないでしょうか。そんな「一方的講義」を年数回行ったくらいで、教員の能力開発に資すると考えるのは無理があります。
現任校では、学部のFDには時間をかけました。年始の日は授業が入っていなかったので、年始FDを3時間かけて行うことが恒例でした。授業コマでいえば2コマです。テーマは「カリキュラム改革について」とか「カリキュラム・マネジメントについて」とか「教学マネジメントについて」といった内容で、その趣旨に沿った講演を講師の方に行っていただきました。講演と質疑応答で1コマ、あとの1コマはワークショップです。「学系ごとに複数科目を並べ、シラバスのねらいを共同で作成してみる」とか「担当する教育プログラムごとにPDCAをどう回すか考えてみる」といったグループワークに教員が取り組むのです。
年始FD以外にも、少なくとも2時間は時間を取ったFDワークショップも必ず実施していました。「経済経営学部はFDが長い」とよく言われましたが、一方で、教員の負担を減らしていったことを知っている教員からは、特に不満は出ませんでした。また、ワークショップを通して教員同士がコミュニケーションを取る機会ともなり、多くの教員にとって意義のある時間になったと思います。
「教員協働で進める授業の導入」については、すでにこのセクションの文字数が多くなってきたので、別の項目で説明します。これまでも、「学部マネジメントと学部長の役割」『大学マネジメント』JUN 2018 Vol.14, No.3や、大森昭生・成田秀夫・山本啓一・吉村充功(2018)『今選ぶなら、地方小規模私立大学!〜偏差値による進路選択からの脱却』レゾンクリエイト、などをお読みいただければと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
