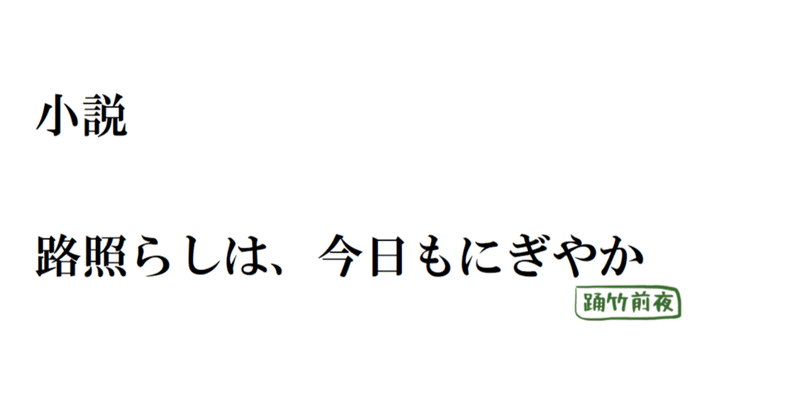
短編小説 路照らしは、今日もにぎやか
路照らしは、街灯に似た生物だ。
路を照らすことを生業としている。
今日も積雪は照らされ、青白く光っている。
辺りに人気はなく、路照らしたちは何のために路を照らしているのか分からなくなっていたが、今まで路照らしとして路を照らすうちに自然と生まれたプライドと責任感が、彼らの原動力だった。
突然、猫が横切った。
どうやら必死に寝床を探しているようだ。
汗が飛沫となるほどに素早く駆け、もふもふの毛は湿り、ぐったりとしている。
そんな都合も知らない路照らしたちは「あ、ねこだ。」「かわいい。」
「うらやましい。」と次々に呟いた。
深夜の路照らしに一番必要なのは、そういうささやかな癒しだった。
朝になって光が世界を満たすと、路照らしの灯は消えてしまう。
だけあって、路照らしにとって夜の時間は貴重だった。
自己の存在を満たす時間でもあり、視界で何かが動くのを見て小さな幸福を感じる時間でもあった。
生まれた場所から一切動くことのできない路照らしにとって、
「動くもの」を見るのは何よりの贅沢だった。
とりわけ、食べ物を取り合って喧嘩する猫なんかは大好物だった。
(喧嘩が好きなのではなく、たくさん動いている様子が好きなのだ)
その一方で、路照らしたちは静かな空間も好んだ。
「静」があるからこそ「動」が映えるのだ、とさえ思っていた。
動くものが見えない時は、暗い路をじっくりと観察して、気が付いたことを仲間とこっそり共有した。
路照らしごとに違った視点があり、全員にとって全員が個性的な感性の持ち主だった。
ある者の視界では不思議な文字の印字された茶色い金属板が見えた。路照らしは必死に解読を試みたが、どうやらモグラの家の玄関らしい、という結論に落ち着いた。
またある者の視界では雨の日、光の反射具合で小さな虹がよく見えた。色とりどりに瞬く虹を見た路照らしは、「ここに世界の全部が詰まっているに違いない。」とじっくり虹を観察した。
見れば見るほど、いろんな色があって、輝いていて、奇麗だ、ということしか分からなかったが、観察した以上は何か深いことを言わなければならないような気がしたので、「なるほど。世界とは、そんなものなのだなあ。」と達観したふうを装った。
路照らしたちは個々の世界に在るものを描写し、解釈し、論評し合い、「素敵だね。」「素敵だね。」と言い合った。
今日は雪についての議論が白熱した。
ある路照らしが言った。
「雪はてらてら光って、それでいてふかふかだ。」
「ああ。その通り。そして月の光が反射して青白くなるのも素敵だ。」
「確かに。」
「やあ、ちょっといいかい。月と雪ってなんだか言い方が似ていないか?」
「ううむ。すごい。これは発見だ。」
「そういえば、聞いたことがある。実は月は黄色くなくて、本当は青白くてさらさらしているらしい。」
「おお、それは知らなかった。」
「すごい。」
「ということは、月もモフモフしているのだろうか。」
「雪みたいに?」
「そう、雪みたいに。」
「ならきっと、雪は月から降ってくるに違いない。」
「そうだ。きっとそうだ。」
「すごい。」
「大発見だ。」
「じゃあ、お雪様って呼ばないといけないね。」
「うん。今日はお雪様がきれいだ。」
「最近、お雪様がよく降るね。」
「きっと、最近の月は大きいからだ」
「うーむ、まさにその通り。」
……そんな議論がえんえん続き、夜が明けた。
太陽が顔をのぞかせて、それから電気の、文明の光がそこかしこで灯った。
日光を浴びた積雪はじりじりと溶け、小さな水たまりをつくった。猫がちゃぷちゃぷと走る。口にはどこからか調達してきた焼き魚をくわえている。
「いってきます!」と家を出た人間の子供は、家を出るなり「猫さん、おはよう!」と声をかけた。
猫は無視して、太陽の方向へ駆けると急カーブして路地に入った。
路照らしは、とうに眠りについていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
