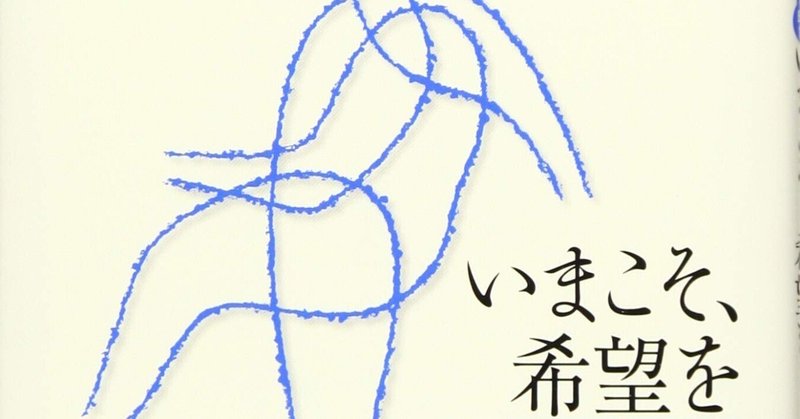
1968年以後という文脈における暴力──サルトル×レヴィ『いまこそ、希望を』
ジャン=ポール・サルトルとベニー・レヴィの『いまこそ、希望を』は、1970年代を通してフランスの左翼が暴力にたいする知覚を大きく変えざるをえなかったことについての、貴重なドキュメントである。
ベニー・レヴィは1968年5月の学生叛乱の闘士の一人で、当時はピエール・ヴィクトールの名を名乗っていた。中国の文化大革命が1966年に毛沢東の扇動のもとに生じたとき、フランスでは毛に共感する学生たちがマオイスト組織を結成し、ヴィクトールはそれ以来73年に転向するまでフランスの新左翼、通称ゴシスム(gauchisme)の中心的な人物であり続けた。1970年には彼が結成した「プロレタリア左派(Gauche prolétarienne)」が非合法化され、GPが発行する『人民の大義』は印刷中の全部数を押収、指導者らが逮捕されていった。ヴィクトールがサルトルと接触したのはこのときである。若きマオイストはそれまでサルトルのヒューマニズムに辛辣な態度をとってきたのだが、戦略的な理由から手を結ぶことにしたのだった。サルトルに『人民の大義』の名義上の編集発行人になってくれないかともちかけ、サルトルはそれを快く受けた。警察は、それまでの理を通すなら、サルトルを逮捕しなければならないはずだった。当時の内務大臣レイモン・マルスランはわざとらしく極左の学生たちを投獄することで勝ち誇っていたが、マオイストの「子供たち」を投獄するのと世界でもっとも尊敬されている知識人を投獄するのとでは、わけがちがった。サルトルはボーヴォワールとともに発禁処分となった機関誌をパリの大通りで配る挑発行為に出た。「マルスランは麻痺状態に陥り、指一本上げることができなかった」(WfE 207)。この上ない宣伝活動だった。結果として、この事件の前後にフランスでマオイスト(彼らは少数精鋭の過激派にすぎなかった)の世評が高まることとなり、ヴィクトールとサルトルの友好関係は、1980年にサルトルが亡くなるまで続いた。
ヴィクトールは1972年くらいまでは「残虐を好む男」(PMF 213)として知られていた。革命的暴力の正当性を信じ、「人民裁判」をマオイストが中心となって開くことを熱心に主張した。1972年4月、ブリュエ=アン=ナルトワの小さな鉱山町で労働者階級の両親をもつ16歳の少女ブリジット・ドゥワヴルが惨殺されたとき、ヴィクトールは「われわれにとって、階級の憎しみは創造的なものだ」(WfE 37)と、起訴を免れた容疑者を人民裁判にかけることを強く訴えた。そこには、ひとの意表を突く暴力的なニュアンスがあった。
「ブルジョワ階級の権威を覆そうとして、屈辱をなめた住民が短期間の恐怖政治を施行し、軽蔑すべき憎い少数の連中に危害を加えようとする、これは当然だろう。ある階級の権威を攻撃するとなると、必ずや、この階級のうちの数人の首は槍先に突き刺されて引き回されるのだ」(PMF 241)。
この発言には、ヴィクトールがその数か月前にフーコーとのあいだで交わした人民裁判をめぐる討論のこだまが聞きとれた。フーコーは人民裁判というヴィクトールの発想に反対して、「人民の正義」の例として、フランス革命下のパリでの凄惨な「九月虐殺」をはじめとする、民衆暴動のさいの反司法的かつ前司法的な残虐行為をあげた。
たとえば、私戦の最中、規則どおりに、「法に則って」殺された敵の首をさらすため、それを杭の上部に突き刺すというのは、ゲルマン式の古いやり方であった。また、家屋を取り壊す、あるいは最低でもその木造部分を焼き払い、動産を略奪するというやり方は、今でいう法益の剥奪に相当する旧来のしきたりであった。そして、司法的なるものの確立以前に遡るこうした行動が、のちの民主暴動のなかに定期的に蘇ってくるのだ。攻略後のバスティーユの周囲で、人々はドゥ・ローネー〔バスティーユの監獄司令官〕の首を振りかざして歩く。抑圧装置を象徴するこの建物の周囲で、司法審級などとは所詮肌の合わない民衆の実践が、祖先の古いしきたりをかつぎ回るのだ。
このときのフーコーはヴィクトールよりもさらに過激で、どんなブルジョア的規範にも囚われていないようにみえた。討論に居あわせたアンドレ・グリュックスマンは後にこう回想している。「言っておかなければなりませんが、フーコーが語ったとき、彼はテロ行為をしようという気でいる者たちに話していたのです」(PMF 212)。暴力の可能性は机上の空論ではなかった。
ブリュエ=アン=ナルトワの事件でリンチを露骨に扇動するような『人民の大義』の血腥い論調に激しく反対したのがサルトルだった。サルトルの申し立ては、暴徒によるリンチは左翼が見習うべきモデルではないという至極真っ当なものだったが、「ヴィクトール率いるマオイストらは、相変わらず動じなかった」(WfE 38)のである。
1972年はいずれにしろ転機の年となった。ヴィクトールとの討論ではテロルを擁護する側に廻ったフーコーだったが、ブリュエで一発触発の状況を目の当たりにすると「自分が見たことに反感を覚えた」(WfE 40)。ブリュエに集結したマオイストの集団のなかには、ヴィクトールの指導に従わなくなる者がしだいに増えていった。それに、「フランスの政治ムードは、はっきり知覚できるほどに変化していた」。社会は68年5月の熱から冷めて、すでに正常化の季節を迎えていたのである。「これみよがしの暴力行為に対する公衆の許容度は、無きに等しかった。お隣のイタリアやドイツで左翼テロの結果がどうなったかを見てきており、完全に唾棄すべきものだとわかっていたのだ」(WfE 37)。
さらに1972年は、イスラエルのテルアビブ空港でパレスチナの解放闘争を支持する日本の極左が無差別乱射事件を起こした年である。5月のことだった。さらに4か月後の9月5日には、オリンピック開催中のミュンヘンで「黒い九月」を名乗るパレスチナ解放運動の過激派がイスラエルの選手団を襲撃し、11名を殺害する事件が起きた。これが決定的だった。ヴィクトール自身がユダヤ人だったし、フランスの新左翼世代にはユダヤ人も多く、パレスチナ解放運動へのコミットにしだいに違和感を覚え、反ユダヤ主義的な傾向を疑っていった。フランスのゴシストはイタリア、ドイツ、日本の極左とは異なる道を歩んだ。彼らはテロリストとなる代わりに人権派となり、その一部は「新哲学者(nouveaux philosophes)」としてマスメディアを席巻し、社会主義の暴力を告発する反マルクス主義の急先鋒として活躍したのである。ヴィクトールもまた例外ではなかった。彼は1973年にプロレタリア左派を解散し、サルトルの個人秘書となり、ベニー・レヴィを名乗るようになった。
こうした文脈のなかで『いまこそ、希望を』を読むと、かつてのヴィクトールの変貌ぶりに驚かされる。彼は極左運動が社会の支持をえられないまま行き着く先の暴力を否定しただけでなく、マルクス主義の理想そのものが結局は暴力へと行き着くものと考えるようになったらしい。
レヴィ マルクスもまた、人間は最後には本当に全体的になるだろう、と言っていた。こうした理屈で、人間以下の存在は、総体的かつ全体的な新しい人間を建設するための原料とみなされた。(EM 47-48)
「人間以下の存在」とは、解放を求めて闘う人間のこと、しかしまだ人間扱いされていない人間のことである。サルトルはかつて、フランツ・ファノン『地に呪われたる者』の序文のなかで、熱狂的に、植民地の原住民を人間扱いしないヨーロッパ人のおかげで、「彼らは人間となるのだ」(DT 17)と書いていた。「反乱の初期においては相手を殺さねばならないが、一人のヨーロッパ人をほうむることは一石二鳥であり、圧迫者と被圧迫者とを同時に抹殺することであるからだ。こうして一人の人間が死に、自由な一人の人間が生まれることになる」(DT 22)。
レヴィはサルトルにたいして、暴力の創設的な機能を今でも信じているのかと問いかける。サルトルは、当時のアルジェリアの文脈においては暴力だけが唯一可能な解決策だった答えた。フランス人はアルジェリア人が受け容れることができるようなただ一つの解決策も検討することはなかったからである。暴力の贖罪的な機能を讃える論調については、レヴィに問い詰められて、「もうその意見をとらない」(EM 94)といっている。レヴィはサルトルを鼠のように、あたかもかつての自分自身を説得しようとするかのように、部屋の隅へと追い詰めようとする。彼らの対話の前に広がっている時間──70年代──は、どのような経験だったのだろうか。68年5月の熱狂は、さまざまに分岐し、抑えられ、引き継がれていった。この対話にはその分岐のひとつの帰結があらわれている。それは袋小路であった。レヴィはいう。「反乱とは、人間の統合の長い企ての一契機、友愛の経験の一面にすぎないのだ」(EM 104)。
参考資料
サルトル/レヴィ『いまこそ、希望を』海老坂武訳、光文社古典新訳文庫、2019年(略記→EM)。
リチャード・ウォーリン『1968パリに吹いた「東風」──フランス知識人と文化大革命』福岡愛子訳、岩波書店、2014年(略記→WfE)。
ジェイムズ・ミラー『ミシェル・フーコー──情熱と受苦』田村俶ほか訳、筑摩書房、1998年(略記→PMF)。
フランツ・ファノン『地に呪われたる者』鈴木道彦/浦野衣子訳、みすず書房、1996年(略記→DT)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
