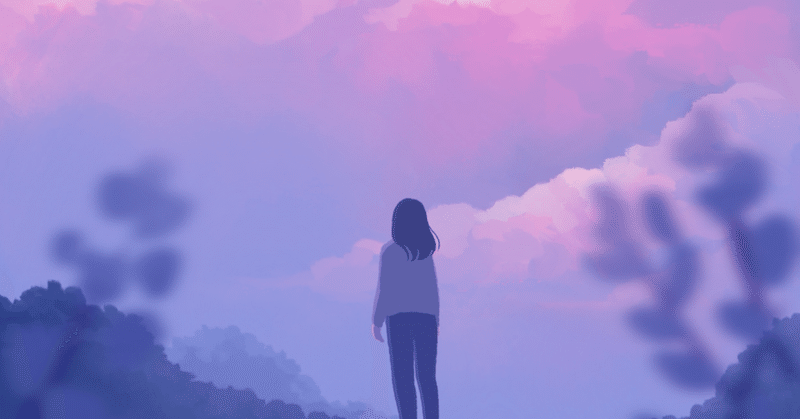
手を合わせること
時に思念は奇跡を起こすことがある。
生死を超えて。
目には見えないけれど、それは在る。
酸素は見えなくても呼吸するためには欠かせない。
無意識に1日何万回と吸って吐いて。
生きてはいても酸素のことを考えたりはしない。それでも無いことには生きられない。
もうかれこれ20年以上も前の話になる。
息子が小学校に行き、娘を幼稚園に送り届けた後の静かな時間がなにより大切だった。
ゆっくりとコーヒーを飲み、新聞に目を通すことがわずかな憩いのひととき。
なんとなく気配を感じ、顔を上げた。
ああ、気のせいかとすぐに新聞に目を落とす。
今度は音がした。
足音だ。床の上を踏みしめる音。
後ろを振り返るがもちろん誰もいない。
また気のせいかと思い、新聞の方に向き直る。
するとはっきり人の体温というか、身体の厚み、存在感がすぐうしろに立った。
ばっと振り向くがもちろん誰もいない。
部屋は静かだ。
時計の針の音だけが聞こえてくる。
振り向いたまま、足音がしたリビングのドアを透かすようにじっと見つめるが、もう何の音もしない。
もちろん誰もいない。
みしっ。
ある日、リビングの上から足音が聞こえてくる。
息子の部屋からだ。
息子は学校に行っている。彼の足音がするはずはない。
音はする。
誰かいる。
耳を澄まし、天井を睨みつけてみる。
するとまた背後に人の気配がし、慌てて振り返ってみるが何もない。
こんなことが1週間ほど続いた。
その間、音はだんだん頻繁にしかも大きくなっていた。
見えない者が自由におおっぴらに家の中を徘徊しているように。
2階の物音と人が歩くその気配に、これは本当に泥棒でも入ったんじゃないかとわたしは台所から一本包丁を持ち出し、そっと階段を上った。
廊下の突き当たりに息子の部屋がある。
息を殺しドアの前に立ち、怖い気持ちを押し隠し思いきって開けてみた。
誰もいなかった。
明るい陽射しがレースのカーテン越しに入る部屋に変わったところはなかった。
特に荒らされた様子もない。
包丁を持つ手を見やるとバカみたいに思えた。あれはなんだったんだろうと首を傾げて階下に降りた。
音はわたしには聞こえるが、家人には聞こえない。こんなことがあって、と言っても気のせいだと一笑されて終わった。
ある晩、下の娘に絵本を読み聞かせ、寝かしつけてさあ寝ようかという時だった。
身体の左半身に激痛が走った。
それは突然のことで声も出ない程の痛みだった。もちろんぶつけたのでもなく、急に火をつけられたようない痛みが覆い被さってきた。
トイレに行きたくなったのだが起き上がれない。
痛みで動けない。立つこともできない。
不思議なことにそれは左半身だけだ。
わたしは匍匐前進でトイレまでの床を張っていった。混乱する頭の中で、わたしの身体の中で悪いものが首をもたげてきた、病院に行かなくては、という思いがぐるぐるしていた。
脂汗と涙が滲んだ。
どうしてこんなことに。
わからないまま、朝を迎えた。
翌日、わたしは発熱した。
大した熱ではなかった。
半身に痛みはあるが昨夜のように歩けないほどではない。病院には行かず、冷えピタをおでこに貼って寝ていることにした。
息子が学校から帰ってきて、わたしが休んでいる寝室にひょこっと顔を出して言った。
ママ、オレ友達と遊んでくる!
あのね、ママ熱があって寝ていなきゃならないから、あなたが事故にあってもすぐに行けないの。だからくれぐれも気をつけてね。
息子ははーい、と元気よく飛び出していった。
その直後、息子は事故に遭った。
向かい側の道路に友達を見つけて、停まっていたトラックの後ろからぱっと車道に駆け出してしまったのだ。
驚くことに息子は左半身を下に倒れたらしい。
オレ、その時にスローモーションになって、ゆっくりふわあって身体が持ち上がったんだよ。
それで気がついたら道路に寝てたの。
あとから息子にその状況を聞いて驚いた。
あれは父だったのか。
気をつけろ、気をつけろ。
大変なことになるぞ、注意してやれ。
わたしの周りを散々ウロウロして音を立てたり、近づいたりしても忠告に気づかない娘のことをどんなにヤキモキしながら見ていただろうか。
そしていよいよ前日、父は荒療治に出たのだ。
いいか、あの子にこんなに苦しい痛い怖い思いをさせるなよ。
そしてあの時、どうして事故に遭ってもすぐに駆けつけることができないよ、気をつけなさいよと息子に言ったのか自分でもわからない。
父がわたしの口を借りて言わせた忠告だったのだろうか。
息子は車とぶつかる瞬間、誰かが身体を支えてくれたように感じたと言っていた。
孫を守りたい一心で父がとっさに抱き抱えてくれたのだろうかと思うと頭が下がる。
酸素が見えなくても呼吸をして生かされているように、亡くなっても思念は在り続けて残された者たちを守ろうとする。
小難しい理論はわからない。
ただそういうこともあるのだとわたしは思っている。
そんなわたしができる唯一のことは手を合わせることだ。
いつもありがとうございます。
守ってくださってありがとうございます。
死ぬその瞬間まで耳は聞こえているというから、そのお礼の言葉も今もきっと届いているはずだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
