
【発酵】ビールの泡の正体とは?
二十歳になり、お酒が飲めるようになり、ちょっとだけ楽しみが増えた。はじめは苦いだけと思っていたビール。それも「とりあえずビールで!」という言葉を覚えてからは、やっぱり舌は慣れてくる。ピーマンと同じ。年を重ねるごとに美味しく感じる。苦いビールは香るビールへ。
ということで、今回はビールの発酵についてお話していきたいと思います。
ビールの製法
そもそも、ビールがどのようにして作られるか知っていますか?
ビールを作るために必要な材料は、大麦(麦芽)・ホップ・米・トウモロコシです。これらを使って、アルコールとあの独特な苦味と泡を作り出します。
さて、ビールの製法を簡単に説明すると、
①大麦に水分を含ませて発芽させる(麦芽)
②麦芽を乾燥させてから米やトウモロコシと煮る
③煮た液体をろ過し、ホップを加える
④ホップを加えた液体を冷却し、ビール酵母を加えて発酵させる
⑤発酵・熟成後、再度ろ過し、瓶詰めする
という感じです。
まずは、大麦に水分を含ませて発芽させます。この発芽したものが麦芽です。その麦芽を乾燥・粉砕し、米やトウモロコシなどと一緒に煮ます。煮ていくことで、麦芽に含まれる酵素が米やトウモロコシのデンプンを分解します(加水分解)。これにより、デンプンはブドウ糖に分解されます(糖化)。
このブドウ糖がこれから添加されるビール酵母のエサになります。ちなみに「デンプン」ではなく「ブドウ糖」には理由があります。それは、デンプンはブドウ糖に比べてサイズが大きく、ビール酵母では分解することができないからです。ビール酵母が糖を分解するためには、あらかじめ糖をブドウ糖のサイズまで小さくしてやる必要があります。なので、麦芽の酵素による分解はビール作りに必須なのです。ちなみに、デンプンはいくつものブドウ糖が鎖のようにつながった構造です。
製造工程に戻ります。麦芽の酵素によって糖化された液体、これをろ過し、ホップを加えていきます。このホップがビールの苦味のもとです。ホップを加えた液体(麦汁)を冷却し、ビール酵母を加えて発酵・熟成させます。発酵・熟成後、アルコールが生成され、ホップにより苦味も生まれ、若ビールができあがります。
あとは、この若ビールをろ過し、不純物を取り除くことで、ビールの完成です。なお、この後の工程で、火入れを行うのが通常のビールで、火入れを行わないのが生ビールとなります。
おおざっぱな説明ですが、ビール製造はだいたいこんな感じです。もちろん国や地域、製造業者によって、その工程に違いがあり、それが多くの種類のビールが存在する理由です。
ビールの発酵
麦汁にビール酵母を添加することでアルコールが生成されますが、科学的には以下のような発酵が行われています。そんなに難しい化学式ではないので、科学が苦手な方も大丈夫です。
【アルコール発酵】
C₆H₁₂O₆ → 2C₂H₅O + 2CO₂+ 2ATP
※ATPは生命が生きていくために必要なエネルギーのことです。
C₆H₁₂O₆がグルコース(ブドウ糖)、C₂H₅Oがアルコール、CO₂が二酸化炭素です。この化学式は、ビール酵母が麦汁に含まれるブドウ糖をごはんにして、有機物であるアルコールと二酸化炭素を生成することを表しています。
このアルコール発酵は日本酒やワインなど、すべてのお酒に行われる発酵であり、お酒造りに必要な発酵となります。
ビールの泡の正体とは?

ビールの泡の正体。それはアルコール発酵を知れば、おのずとわかります。そうです。ビールの泡の正体は「二酸化炭素」です。
先に説明したように、アルコール発酵は、アルコールだけでなく、二酸化炭素も生成してくれます。つまり、酵母の「おなら」がビールの泡を作っているのです。人を幸せにしてくれるおならです。
さて、ビールの泡の正体はわかりましたが、一つ疑問が。それは、
なぜ、ビールの泡は消えないのか?
ということ。
ビールをグラスに注ぐと、泡が生まれます。その泡は口ひげになるほど強い泡になり、なかなか消えません。同じように、シャンパンなどもアルコール発酵によって二酸化炭素の泡を作りますが、この泡はすぐに消えてなくなります。ではなぜビールの泡は残り続けるのか。それは、ホップに含まれる「イソフムロン」によるものだと考えられます。
イソフムロンは、ホップの苦味成分のもとでもありますが、この成分が麦芽のタンパク質と結びつき、あの消えない泡を作り出していたのです。シャンパンの泡がすぐに消えてしまう理由は、ホップを含んでいないからということです。消えない泡は、ビールだからこそ生まれる泡ということです。
偉大なホップはIPAを生んだ
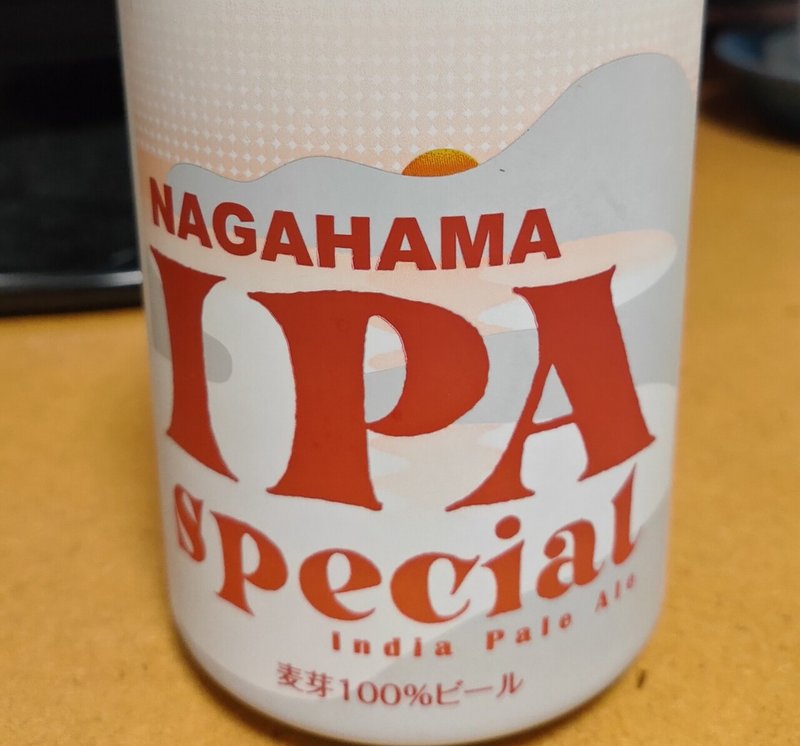
やはり、ホップは偉大です。ビールの、あのさわやかな苦味と消えない泡を作り出すのですから。しかし、ホップの役割はその2つだけではありません。もう一つ重要な役割が残っています。そして、それはあの「IPA」を生むきっかけとなりました。
IPAとは、インディア・ペール・エール(India Pale Ale)の略称で、インドで生まれたビールです。と言っても、作ったのはイギリス人で、しかも、"たまたま"できたビールなのです。
18世紀末、イギリスはインドを植民市としていました。そのため、インド在住のイギリス人も多かったのですが、彼らにはどうしても忘れることのできない飲み物がありました。それがイギリスの伝統的なビール、ペールエールです。彼らはどうしても、ペールエールを飲みたかったのです。
その要望に応え、イギリスからインドへ、ペールエールを送ることになります。しかし、そこで問題になるのがビールの腐敗。この時代には冷蔵完備した輸送船もないため、そのままビールを送ってしまえば、インドへ到着するころには腐敗してしまいます。
そこで活躍したのがホップ。なんと、ホップには防腐剤としての効果があったのです。これを知ったイギリス人は、ペールエールに普段よりも多めにホップを加えてビールを作りました。これにより、腐らせることなく、インドへビールを送り届けることができ、さらに苦味の強いIPAが生まれたのです。
ホップの偉大さには頭が上がりません。
いつもありがとうございます。
最後に
ここまで、ビールの発酵や泡の正体などをお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか。
普段からお世話になっているビールも、発酵の観点、微生物の観点から見ると、もっと好きになるはず。発酵に終わりはありません。いつまでも"発酵中"です。これからも発酵について、コラムを書いていきますので、よかったら寄り道していってください。
では。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
