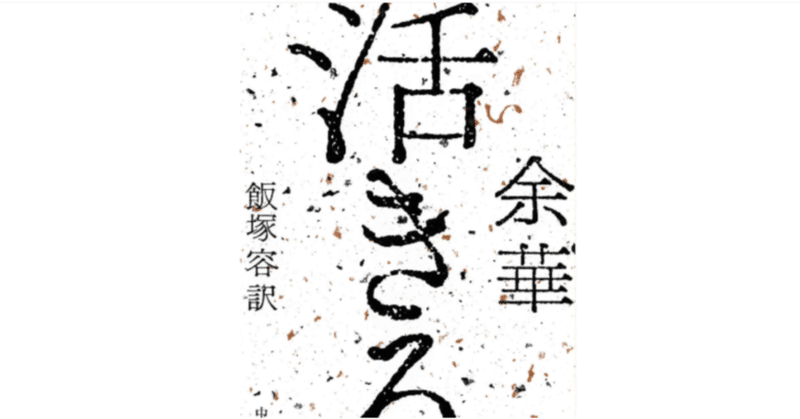
あるようにあった人生に号泣する:余華『活きる』
小説を読んで涙が止まらなくなることはもちろんある。しかし、慟哭するように声をだして泣いてしまったのは重松清の『ゼツメツ少年』以来だ。そして久しぶりに一気に読んだ。
あまりに一気に読んだので、Kindleのマーカーはどこにも付けられていない。何かを書こうとしても、自分がどこで心を大きく揺さぶられたのかすぐには見つけることができない。
歳を取るのは悲しいことだ。一歩一歩、柱に小さな傷を付けながら進むようにしないと細かなことが思い出せない。以前は本は見るだけで意味が取れたのに、いまは一行ごとに指さすように追わないと文字が頭の中をすべっていく。かつての記憶もどこか夢のようだ
主人公の福貴はなぜあんなに克明にいろいろなことを覚えているのだろう。小説だから? 作者の創作物だから?
もちろんそうなのだろう。
けれども、私には、単に小説という以上に、福貴も家珍も風霞も有慶も、実在の人物のように生々しく感じられた。有慶が羊を買ってもらって本当に嬉しそうな様子も、風霞の笑顔も、まるで私もそこにいて目の前で見ていたかのようだ。
福貴が好んで過去を思い出し、好んで自らを語り、まるでそれによって、人生をもう一度経験できるかのようだったのはなぜなのだろう。
深い後悔? そうかもしれない。彼は何度も何度も自分の人生を牛のように反芻していたのかもしれない。しかし、そんな言葉は物語のどこにも見当たらない。
福貴は、はっきり言えばダメな奴だ。人生にもそれほど真剣に向き合わず、教育があるわけでも、知恵があるわけでもなく、家族に対しても殊更に愛情深い訳でもなく、時代に抗うでもなく、悟るでもなく、前向きな人生ともいえず、コントロールできない理不尽さの中で懸命に生きるエネルギーに満ちあふれていたというわけでもない。
家珍が実家の父によって去ったあと、福貴の母親はいつも部屋のそっと涙を流していた。福貴は「いまいましい、いまいましい」とベッドの中で自分の過去を思うだけで、特に何かを積極的にするわけでもない。そしてやっとのことで龍二のところへでかけ、五畝の畑を借り受け、小作人に身を落としていく。
妻の家珍の家珍の気持ちもよくわからない。これは福貴の語る物語だ。福貴がしたこと、福貴が見たこと、聞いたことしかわからない。戻ってきた家珍に福貴がいたわる言葉をかけると、家珍はうれしそうに笑って「大丈夫よ」と言ったと、福貴は語る。その後、息つく暇もないほど忙しかったが、笑みも絶えなかったとも。一部はきっと本当のことだったのだろう。
「活きる」という物語はコントロールできない不幸に溢れている。福貴はダメな奴だ。しかし、時代も決して幸せな時代ではない。
福貴は「おれは度胸がすわった。自分で自分を脅かすことはない。すべては運命なのだ。苦あれば楽ありといういうではないか。おれの後半生はますます好転するだろう」と考える。そしてそれを家珍に話す。
福貴の人生がこの先、彼が思うほどには好転しそうには思えません。ダメな福貴ならではの考えのように思える。
妻の家珍は「わたしは多くを望まないわ。毎年あなたに新しい靴を作ってあげられれば、それでいいの」と答える。家珍は普通でよいというだ。家珍が殊更に美化されているかといえばそれほどのこともないのだろう。普通を望むことは多くの人が願っていることなのだから。むしろ普通でない特別さを望むことの方が自然の摂理に反している。福貴も納得し「家珍の言うとおりだ。家族が毎日一緒にいられたら、それ以上何も望むことはない」と思う。
そして、多くのことが起き、家珍はいう。「あなたにやさしくしてもらって、わたしは幸せだったわ。子供を二人産んだのが、せめてものお返しよ。来世でも、また一緒に暮らしたい」。
福貴と一緒になったことは家珍の不幸なのだ。福貴もそれはわかっている。わかっているが仕方がなかったと思っている。不幸もあった、よいこともあったと思っている。
福貴の生き方を「たくましい」という言葉で表現することは不適切だと私は思う。福貴は、理不尽ともいえることのすべてに対して、「あるようにあった」というしかない生き方をしている。そしてこの点が、家珍や風霞の生き方に次ぐ、この小説の最大の良さなのかもしれません。
私は福貴はダメな奴だと思う。克明にいろいろなことを覚えているのは、福貴に後悔があるからだとも思っている。
何を小説の登場人物にむきになってと言われるかもしれない。後悔すらも「あるようにあった」と思う福貴も、その物語を読んだ私も、いずれも「あるようにあった」というしかない存在だと、私は感じるからだ。
訪問していただきありがとうございます。これからもどうかよろしくお願い申し上げます。
