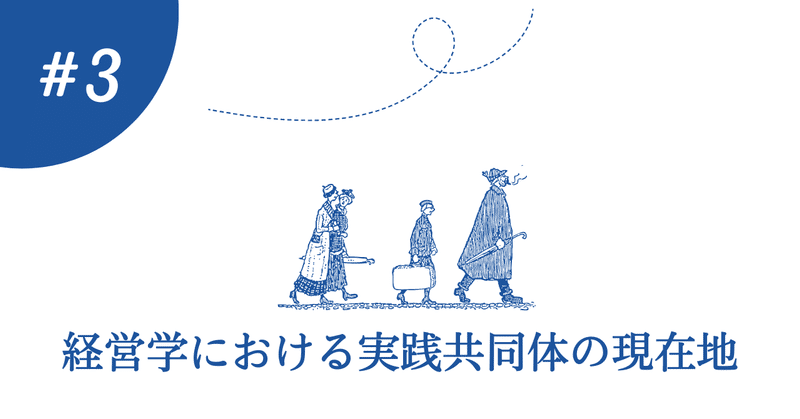
経営学における実践共同体の現在地③
前回からの続きです。今回は残りの2つのタイプについて解説し、経営学における実践共同体の定義まで行きたいと思います。
外部連携実践共同体
これは組織的な実践(記事を跨いだので改めて書いておくと、1.組織目的の達成のために、2.組織的にルール化、あるいは暗黙的に慣例化された実践に、3.否応なく(つまり状況によって必然的に)従事している)だけれども、社外の人々が集まる実践共同体です。業界団体や企業間の越境学習プログラムなどが該当します。日本でこの分野の研究として有名なものと言えば石山先生のNPO2枚目の名刺さんの越境プログラムの事例(石山, 2018)や、中西先生の航空業界の飛行経路計画者達の事例(中西, 2018)があります。特徴的なのはどちらの事例も、その実践を組織に持ち帰る事が前提となっている事、そして、それでいて組織から一定程度離れることで実践者本人がより個人的アイデンティティを内省しやすいという事です。これは越境学習の特徴がよく表れているといえる点です。
企業間の寄り合いのようなものは多数あると思いますが、それ即ち外部連携実践共同体というわけではありません。あくまでそこで学ばれる具体的なテーマがあり、それについて参加者が相互に関わり合って実践が発展していることが重要です。これはこのグループに限ったことではありませんが、学術的に正確に現象を捉えるならば「人が集まっていればとにかく実践共同体」と安易に見なさないことが重要です。
独立実践共同体
独立実践共同体はある職業や地域の人々が、特定の目的や関心によって結びついています。概念が提唱された際に着目されたものに近いという意味で、非常にプリミティブ(原始的、根源的)な実践共同体です。組織との関係性を考える上では一見組織とは関係ありませんが、なぜここまでを射程に入れているかというと、やはりそこにいる人々は組織の一員でもあるからです。例えばマネージャーやデザイナーの実践共同体にいる人々は、一義的にはそこで自身の技能について研鑽を深め、アイデンティティを強固にします。そしてその経験は必然的に職場に赴くその時も切り離せない物ですから、職場外での学習として組織と緩やかに関わっているのです。
実際にこの象限ではキャリアやレジリエンスなど、近年の経営環境で重要な課題となっている話題が多数登場します。どの象限よりも個人の内的発達を取り扱う研究群と言えます。
各研究が明らかにしたいものは何か
ここまで組織と実践共同体の関係性という視点で4つの象限に分類した結果を解説してきました。これらの研究は実践共同体の研究とは言っても、視点が全く異なります。これを表にすると次のようになります。

こうしてみてみると、概念の提唱当初に着目された要素が大きく分かれて研究が展開していることに気づきます。一つはなんといっても新たな学習形態として、知を創出するという期待です。これは分類上組織内を対象にしたものの内、特に潜在的実践共同体の研究に色濃く表れているのですが、しかし、長年の議論で実践共同体ありきの研究が増えた結果、当初の期待はそのままに制度的実践共同体の研究が多くなっていきました。つまり、社命で作ったプロジェクトや業務の延長にある人々の集まりにまで創造性を求めるような状況ができてしまったのです。そこでは重要だった非公式性や自発性といった側面は置き去りになりがちでした*1。置き去りになったのは、二つめの要素であるアイデンティティ形成についても同じことが言えます。知の創出に先鋭化した議論になるため、個々人の内的発達についてはあまり議論が及びません。これを知識創出の議論と呼びましょう。
アイデンティティ形成の議論を色濃く受け継いだのは、組織外の実践共同体研究でした。組織から距離を置いた個人に焦点が当たるので、必然的にそうなると言えるでしょう。特に経営学的なトピックとしてはアイデンティティだけでなく、そこから派生してレジリエンスやキャリア、自己肯定感や心理的安全性など多数の話題が登場するようになりました。また、越境学習の議論の盛り上がりもあって、個人的な活動をどう仕事活かすかという事が社会的にも重要視されるようになってきました。非常に重要なトピックですが、この点はまさに現在進行形で議論が行われている最中であり、まだまだこれから研究と実践の両方が必要な領域です。こちらは従業員の内的心理発達の議論と呼びましょう。
近年の実践共同体研究を大きく二つにわけたところで、知識創出の議論=①、従業員の内的心理発達の議論=②として元々の4象限の図に重ねると次のようになります。

経営学における実践共同体の定義
全ての議論がこの図のようにきれいに分かれるわけではありませんが、このような物の見方を通して実際の現象を捉えることで、概念が提唱された当初重要であった論点―つまり状況への依拠性やアイデンティティの形成など―を含めて包括的に人々の集まりを整理することができると考えました。
これを踏まえて私なりに置いた概念としての実践共同の定義は次の通りです。
ある状況に置かれた人々が共通の目的、関心のために諸力を提供して関わり合うことによって、特定技能の向上や知識の創出、そしてアイデンティティの形成を行う集団
これにより明確に状況の依拠性やアイデンティティ形成の議論を改めて定義の中に取り戻すことを企図しています。しかし実践共同体自体そのものは文化人類学的、教育学的研究から生まれたものですから非常に広範な現象を含めてしまいます。また、経営学においては議論の射程が広がってきていることからもこの定義を部分的に限定し、拡張せねばなりません。そこで経営学における議論では以下のように具体化することが必要ではないかと考えました。
実践共同体の中でも組織的、個人的なビジネス上の目的達成のために技能熟練や知識創出、そして自身の内的心理発達を促進する集団であり、その成果が何らかの形で組織に還元されるもの
ここでは目的をビジネス上の物に限定し、最終的な成果が間接的ではあったとしても組織に還元されることを明記しました。また、アイデンティティの発達についてはキャリア論の広がりやウェルビーイングなどの議論の登場なども踏まえ、内的心理発達として少し大きな言葉で捉えようとしています。
(状況の依拠性については「実践共同体の中でも」とすることで言及済みという扱いです)
ジャーナル別にみる国際的な実践共同体への関心
今回上げた研究は、ジャーナル単位で見ると214に及びます(ちょっと細かいところまで挙げすぎたかもしれません)。そのうち10年の間に5件以上の掲載があったのは9つのジャーナルのみでした。さらに10件を超えるのはJournal of Knowledge Management のみという結果でした。もちろんジャーナル名だけで研究の中身まで判断するわけにはいきませんが、経営学においては知の創出に議論が傾倒しているだろうことは察せられます。また、ここまで分散が広がるという事は、実践共同体はそれ自体が大きな研究トピックとして発展しているというよりは、主となる研究を補強するために引用されたり、分析フレームとして援用されたりしているのでしょう。実際に個別の研究を見ていると、概ねこの推察は間違っていないと感じます。
今回も長くなってきたので、この図の使い方やこれからの研究の方向性、補足などは次回に譲りたいと思います。
*1.この自発性に関する議論も次回に譲ろうと思いますが、ここで少し補足しておくと全く無視されたわけではなく、もともとの意味とは異なる形で自発性が使われるようになってしまったというのが実態です。Bardon & Borzillo(2016)はこれを「陰湿なコントロールの一形態」と表現し、組織が実践共同体に限定的な裁量を与えることで、実質的に組織が実践共同体をコントロールする様子を報告しています。
Bardon, T., & Borzillo, S. (2016). Communities of practice: control or autonomy? Journal of Business Strategy, 37(1), 11–18.
石山恒貴. (2018). 『越境的学習のメカニズム―実践共同体を往還しキャリアを構築するナレッジ・ブローカーの実像』. 福村出版.
中西善信. (2018). 『知識移転のダイナミズム: 実践コミュニティは国境を越えて』. 白桃書房
