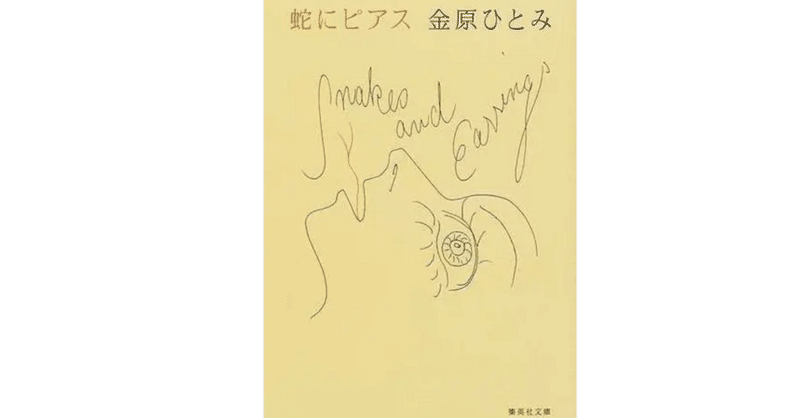
蛇にピアス 金原ひとみ 感想
いつも聞いているポッドキャスト番組が取り上げていたので初めて読んだ。深い感銘を受けたと同時に、芥川賞を同時受賞した『蹴りたい背中』同様、今の視点で読んでその価値がより深まる作品だと思った。
それにも増して、この小説は筋の読み方が複数存在し、どの筋を採用するかによって全く違う小説として感じられることも面白い。感じ方は人それぞれという域を超えた変容を見せる。
その大きな理由は、作品の発表スタイルによるバージョン違いのせいだろう。Wikiによると、まず、初出の文芸誌と単行本の結末が異なっていて、映画版のラストシーンもまた違う。結末が変わるとどのように解釈が変わるか、この点については最後に述べたい。以下の私の感想は、単行本バージョンのものである。
私はこの小説は、ルイの内省と成長の物語であり、青春小説の範疇に入ると思った。青春小説とは、主人公が自我の成立過程において外部の障害に立ち向かい、困難を乗り越えて人間的に成長するという一連の物語である。通過儀礼を挟んだ物語の前後で主人公が変化し、それによって何かを得たり、失ったりする。
オーソドックスな青春小説では、主人公は思春期の若者であり、自我が芽生えつつある成長段階にある。しかしこの小説の主人公ルイはそれよりも精神面でより幼く感じるところがある。物語の前半でルイが抱えているのは、今のこの世界に留まりたい、でも身体改造をすれば思うような自分になれるという単純な欲求である。低い自己肯定感からくる自傷行為に似て見える。
この身体改造がタイトルにある『蛇にピアス』つまり舌にピアス、からのスプリットタンであり、また、背中に龍と麒麟の刺青を彫る、ということもあるのだが、この二つのモチーフはそれぞれ別のアイデンティティを指し示していると分析できる。それは社会的なものと、身体的なものである。
背中に入れる刺青としてルイが選んだのは龍と麒麟であり、それぞれ恋人のアマと彫り師のシバが持つ絵柄であることから、それはルイにとっての男=社会との関わりを象徴している。それは所有や依存による支配関係である。龍と麒麟から自由を奪うために瞳を描かなかったことが、ルイの心身の絶不調となって表れた描写には、文学的なリアリティがある。瞳を欠いた龍と麒麟は、同時に、世界から目を閉ざそうとするルイ自身の姿でもあったのだ。
スプリットタンも同様に、自我の確立のメタファーとして使われているが、こちらはルイ自身の身体的な意識を象徴していると思う。この読み方は、性自認のような、精神と肉体に焦点を当てた文学的なテーマとして近年に多く扱われるようになった。
終盤で、ルイが舌の先端を切り離すことを止めて、そのために入れていたピアスも外し、「無様に空いた穴」を流れる水を、「私の中に川ができた」と語ったことが印象的だ。女性器の隠喩である「穴」と、生命の象徴である「水」を含むこの表現は瑞々しく、肯定的な響きがある。ルイは身体的アイデンティティを得て、ありのままの自分と向き合えるようになったのだと思う。
そのほかのモチーフとして、アマから贈られた「歯」があるが、これは複数のテーマの複合として感じられた。アマとルイとの関係性や、アマの暴力性、所有という概念、ルイの体との一体化。そして何よりエピソードとしてのインパクトが強く、読後感に影響を与えている。
結末部分のバージョン違いについて。文藝春秋に発表されたものを読むことはできなかったが、ネット検索をしたところによると、ルイがシバと生きていく意志を仄めかすものであったようだ。また、映画版では、渋谷のスクランブル交差点で腹を押さえてしゃがみ込むルイのシーンで終わっているらしい。この二者は表現としては共通している。これらの結末はルイとシバの未来を予感させるもので、アマを殺したのもシバだろうと想像させ、シバの人間性への興味が増すことになるだろう。
そうなると、ルイを中心にした三人の人間関係のドラマという要素が強まってくる。青春小説においては、成人としての通過儀礼を乗り越えられず、若いままで死んでしまう登場人物もよく描かれるが、アマはそれに相当し、ルイは喪失を抱えながら成人してシバと結ばれる、という筋立てになる。
私が読んだような、ルイ主観のアイデンティティ獲得と自立の物語という観点で見ると、シバは社会制度を代表するキャラクターで、子どもから見た憧れの人物、しかし成熟した目で見ると普通の範疇の常識人という造形になる。
刺青師という職業柄、筋の悪い客に舐められないようにカリスマ的なセルフプロデュースをしていて、アマやルイのような若者にハッタリを効かせるのもたやすい。前半のシバとルイとのセックスシーンにおいては、ルイは、シバの本気度を推し量ることができず、そのことがシバのサドをエスカレートさせていた。逆にシバはルイの心理を冷静に読んでいたとも言える。SMというのは形式に則ったロールプレイであって、それを理解しているのがシバという人間だ。
芸術面では秀でているが実は真っ当な社会人、というのが私のシバのイメージで、単行本のラストでルイが心ここに在らずになったのも、そうした彼の洗練された退屈さを感じ取ったからだと思った。
(単行本のラストシーンについての説明部分)
