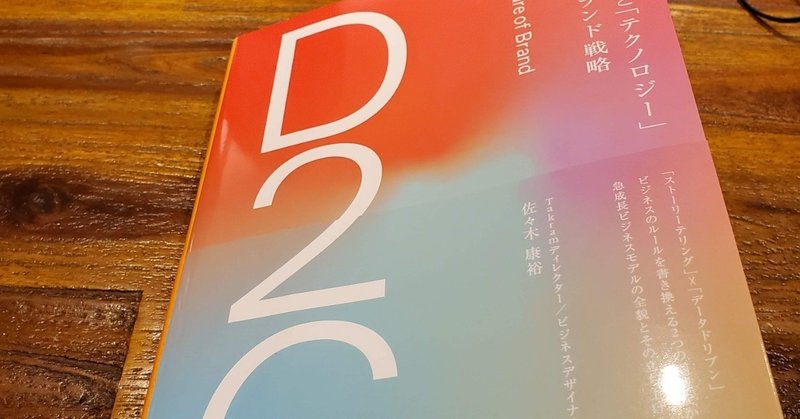
2020年1月読んだ本
今年のテーマはインプットした内容をできるだけ、アウトプットにつなげて転用いくというアウトプットスキルを磨くことなので、できる限り月末に読んだ本の振り返りをしていきたいと思います。(皆さんが本を選ぶときの参考になれば幸いです。)
今月読んだ本はこちら。正月があったのもあり、今月少し読んだ量が多かったので、来月は絞りたい。
1.手ぶらで生きる。見栄と財布を捨てて、自由になる50の方法
ミニマリストしぶさんが書いた、生活をMinimalにしていくコツを50個まとめた本です。僕自身ものを捨てて選んでいくという行為によって、より自分自身の理想的な生活に近づけることができると考えているのですが、なかなか実践することは難しいと感じています。そんな中でも以下のような言葉が胸に響きました。
本当に大切な1%のために、99%を削ぎ落とす
必要なものはそう多くない。人生にとって必要なもの以外は排除する
大事なものを見失わないように、そうではないものリストを作成するなどをして、仕分けしていく。情報やモノで溢れている社会だからこそ、実践したい生き方だなと思いました。
2.AI時代対応 大人の知的習慣 「複合力」こそが究極の効率化である [Kindle]
時間をもっと効率的に使って、2020のやりたいことをやる時間を増やそうと思い、読んでみました。
この本では、物事を複数同時に進めることで、知的生産性がアップして、効率がアップするよーって話がされています。ただ、紹介されている事例に関してはすでにやっているものが多い。実践するとしたら、掃除とか家事をしながら、オーディオブックで読書かと。
ただ、読書中のメモができない問題があるので、どうにか解決したい。
3.漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
古くから伝えられているお金の法則を漫画でまとめた本。
・欲望には限界がない。だからこそ、欲望に優先順位をつけろ
=自分のビジョンを明確にして、それ以外を優先度下げていく。ただし、ビジョンに縛られすぎると自由度が減る
・借金は人を過去に縛り付ける
・自分がわかる商売をしろ・わかるものに投資しろ
・金よりも知恵。知恵を使いこなせ
とかの考え方は響いた。今後の参考にする。あと普通に漫画としてストーリがよく面白かった。
1のしぶさんの本にも共通するけど、時間もお金も有限だから欲望に優先度をつけて、本当に集中するべき一部にリソースをさくべきだなと。今年のやりたいことを叶える上でのキーワードです。
4.反応しない練習 あらゆる悩みが消えていくブッダの超・合理的な「考え方」
僕らたちが普段感じている悩みやストレスはすべて、自分自身が周りに抱く「判断」の結果から来ているという。
日常の中の不要な「判断」を取り除くには、
判断している自分に気づき、判断をやめ、感情で反応するのではなく正しく物事にあたる。自分のやるべき物事に集中してただただ、取り組む。
このような考え方がまだできないときがあるので、「判断している自分に気づく」「手放す・事実のまま受け止める」の二段構えで反応しない練習をしていきたいです。あと、これを紙に書くとよいらしいので最初は寝る前に紙で実践します。
5.Think Smart 間違った思い込みを避けて、賢く生き抜くための思考法
幸福になる方法は人それぞれだけど、不幸になる方法は共通している。正解はないけど、不正解はある。
といった幸福へのアプローチから不幸になる方法を科学研究を元にまとめた本。
①自分の考えには批判的になる(無意識に自分の意見が正しいと思いがち)
②自分の得意分野とは離れた分野の考え方を身につける(自分の分野の考え方に固執してしまう)
などの点が響いた。②に関しては、事業を立ち上げ組織を作る際、それぞれの人の得意分野で組織をつくっていこうとする力が働くことを他人をみて感じでいた。だから、自分がその罠に陥らないためにも複数の専門分野の観点は持っていたいなと思う。
時期によって響くパートが異なると思うので、ぜひまた読んで不幸な行動、思考を避けたい。
6.危機と人類(上/下)
『銃・病原菌・鉄』などを書いたジャレット・ダイヤモンドの新刊。今回は、国家の危機を乗り越える要因を12項目あげ、それを実際に危機を乗り越えた国がどのように要因を使っているかをまとめた本。
この危機の要因は個人の危機(離婚、解雇、転職、離別など)を乗り越える際にも活用でき、トラブルに直面したときにもう一度眺めたいと思う。
(日本に対して解釈するパートもあるが、その認識はいかがなものかと思う。ただ、国際社会の流れからは島国だからかちょっと外れているのは認めないといけないなと感じた。)
7.21Lessons
基本的なスタンとしては、21世紀の人類にとって重要なテーマになりそうな21のテーマを取り扱いながら、それらが将来・今人類にどういう影響を与えるかを述べている。
絶望的な話ばかりも多いが、その中にも少しは希望のある話を織り交ぜながら今後の人類史を述べているのが印象的。そしてあくまでハラリは、将来おきうる未来に対して良い・悪いといった評価は本書の中では示していなくて、あくまでこの事実をどう捉えるかは読者に委ねられている。あくまで人類史を記録する学者としての立場を貫いている。
明日から活かせることとしては
・瞑想で自分の心を見つめ直し、ただしく感情を理解しようとすること。言語化する作業をすること
・世の中、事実たる事実はほとんどなくなってきているから無遠慮にメディアの情報を信じるのではなく、できるだけ第一リソースに触れるようにする
・情報がたくさんありすぎて、知っていることがたくさん増えたように感じるが実際そんなことはない。知的謙虚さをもって何事にも完璧には知らないという姿勢で挑む
8.これからの会社員の教科書 社内外のあらゆる人から今すぐ評価されるプロの仕事マインド71
現在新卒2年目で、まだまだ基礎力が足りないなあと痛感しています。早く基礎を身につけて、活躍できるようになりたいと思い読んでみました。
特に印象に残っていることは
・社内調整を面倒がるな、
・最低限のリスク管理としてのマナー
・無駄な敵を作るな、積極的に相談
・ビジネスの本質は「人と人」。人へのリスペクトを絶対に忘れるな
・正解はない。だから正解を自分でつくっていけ
とかの部分。自分の人に対する向き合い方を変えてGIVERよりな向き合い方に変えていかないといけないと痛感した。信頼されたいではなく、自分から信頼する。与えてほしいではなく、自分から与える。その姿勢がビジネスの基本だよなと。
09.言語化力
サービスLPで使うコピーライティングを考えるヒントになればと思い読んでみた本。言葉で人を動かすために、どんな手順でどういう点に気をつけて言葉をつくっていくといかをまとめていて、本自体おもしろくてすぐ読める。
ここで響いたのは、
自分が働く理由とは何か。自分にとっての幸せとは何か。生きるとは何か。それを言葉にすることで、行動に迷いがなくなり、実力以上のパワーを発揮することができる
たしかに、自分があまり仕事で成果を出せてないとき、アイデアが出ないときは、自分の中で仕事への迷いが生まれているときだ。その迷いは、結局、「自分が言語化して、決めきる」ということに対して逃げていた自分がいたからだと思う。言語化はかんたんではなく、力のいる作業だけど、そこから逃げずに向き合っていきたいなと思った一冊でした。
10.きちんと伝わるセンスのよい文章の書き方
文章がきれいな先輩に文章力の本ないですかと質問されておすすめされた本。この本の中で響いたのは、
①読み手に対する圧倒的な想像力不足が読みづらい文章を生み出す
②何を書くかよりもなにを書かないかが重要
③自分の`常識`は相手の'非常識'
④あなた以外が書ける文章では相手には響かない。
など自分がまだまだだなと思う点が多かった。メールもそうだし、企画書を書くときなどに、上の点は意識しながら、文章を作成したい。
11.D2C「世界観」と「テクノロジー」で勝つブランド戦略
自分が今やっているプロダクト開発に活かせるものはないか・D2C型のビジネスモデルの製品を自分も多く活用していて、純粋にどんな仕組みで成り立っているのかを知りたい!という思いで読んでみた。
・モノとコトを掛け合わせて、ユーザーにプロダクトの世界観を体験してもらう。
・データ活用による「優しいデジタル」の実現。
・顧客にとってのユニークなポジション獲得することで継続的な関係性を構築していく。
など、知れば知るほどよい世界観でした。山口周さんが、世の中の売れているビジネスには「意味のある」モノと「役に立つもの」の2種類に分かれるという話をしていたのですが、D2Cは完全に「意味のあるもの」を作るために今後学んでいく必要があるモデルだと思いました。
12.なぜ人と組織は変われないか― ハーバード流 自己変革の理論と実践
大学3年生のときに読んだ本を再読。
人がなにかに挑戦するときに足かせとなっている習慣・恐怖などがあり、その恐怖は自分にとってメリットのある裏目標を達成するためにある。つまり、足かせはある状況下だと自分を守る固定概念になる。
だから、人間は挑戦するときに足かせとなってしまう習慣や考え方をやりたくないと思っていてもしてしまうのだ,
という本書の分析は数年後の今読んでも気をつけないといけないなと思う。同じ方法に固執してしまうと、なにか大きなことを成し遂げることは困難なので、常に自分の考え方をアップデートしていきたいなと思った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
