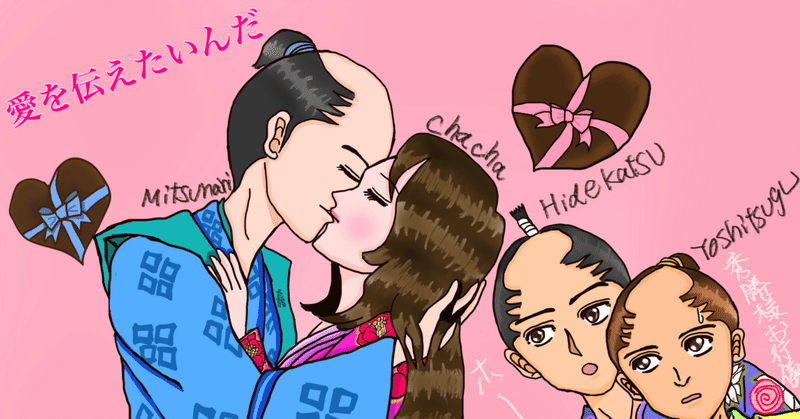
愛を伝えたいんだ
あと少しで立春を迎えるという天正十三年(1585年)一月末。しかし…外の空気はまだややひんやりと冷たく、朝の空もまだ心なしか青が深いように見えた。
「さみーなぁ…これでも春は来るんだよなぁ三成」
羽柴秀吉の近習である大谷吉継は同僚で親友の石田三成に両腕で自分を抱え込みながら問いかけた。
「来るさ。少なくとも暦の上では…体感で春が感じられるのはいつかなんて分からないけど、人は永遠とも思える時間の中で同じような季節の移り変わりを繰り返してきたんだからね。俺たちが死んでもきっと季節は同じようにうつろうのだろう」
と三成が感傷的な答えで吉継に答えていると後ろからドタドタドタっと誰かが走ってくる音が聞こえたので、三成と吉継は慌てて後ろを振り向いた。
「三成、吉継、みーつけた!」
大声で叫んだ人物ははたして彼らの予想通り、主君である今天下人に最も近いと言われる羽柴秀吉の後継者、羽柴秀勝であった。25歳の三成、26歳の吉継から見れば17歳の秀勝は弟のようなものだが、秀勝は主君である上にマイペースでやや強引なリーダーシップの持ち主であり、また何かイベントを思いついたのかな…と三成と吉継は思った。
「三成、吉継、もうすぐすっごい大事なお祭りがあるんだけど知ってる?」
秀勝は目を輝かせるように生き生きとして言った。
「…まだ正月が終わったばかりですが、思いつくか、なぁ三成?」
「…いやー不勉強で思いつきませぬな。秀勝様それは南蛮の祭りでしょうか?」
「さすが三成は冴えてるねえ、そう南蛮のお祭りだよ。愛し合うもの同士が贈り物を贈り合う日なんだって。茶々も憶えていれば知ってるはずだよ。君たちもさぁ、愛する妻がいる身なんだからそう言う流行は欠かさずチェックしなくちゃ!」
秀勝が力説していると後ろから何やら面白からぬ声が聞こえた。
「南蛮の祭りじゃそうじゃ…徳川との戦いも終わっておらぬのに呑気じゃのう、近江衆は」
吐き捨てるように言ったのは尾張衆の筆頭で秀吉とはいとこの関係にある福島正則。
「まったくよ正則、この戦の厳しき世に愛だの恋だのぬかしておられるのは、とんだ呑気ものじゃ」
正則に呼応したのは同じく秀吉のまたいとこにあたる加藤清正であった。彼らは三成のことは勿論、織田家という主筋ではあるが羽柴家の外部から秀吉の跡継ぎになった秀勝のことも面白く思っていなかった。三成は主君の前で無礼であろう、と言おうとしたがその前に主君である秀勝の方が怒声をあげた。
「呑気ものとは何事か!お前たちのように戦、戦と戦のことしか頭にない奴は無粋で困るの!そんなんだから女子にもモテぬのじゃ!天下が統一されればいずれ戦は終わる。その時戦しか脳のないお前らはどうやって生きていくのじゃ!バレンタインは俺の昔の父上と母上との大切な思い出なんだ」
秀勝の怒りが収まりそうにないのを見て、正則と清正はほうほうのていで逃げていった。三成と吉継はいつも陽気で元気一杯の秀勝が抱える淋しさを一瞬垣間見たような気持ちで複雑になった。そう言えば秀勝は9歳で実子石松丸を亡くした秀吉に秀吉の主君である織田信長から与えられた養子であった。信長は嫡男の信忠以外は息子たちをいずれも他家の養子にしていたが、秀勝は正室である濃姫が生んだ唯一の子供であり、濃姫と信長の秘蔵っ子であった。だが母である濃姫は、南蛮から来た占い師の「この子は織田家に残ると争いの種になる。他家に出ればもっと輝ける未来がある」という言葉に養子に出す決心をし、父信長も「猿(秀吉)ならば実子同様於次(秀勝の幼名)を可愛がってくれるだろう」と思い、羽柴家の養嗣子としたのであった。信長の思惑通り秀吉とその正室おねは於次丸こと秀勝を実子同様に可愛がって育てたし、本能寺の変で信長と濃姫が横死した後も秀勝が羽柴家の後継者であることに変わりはない。秀吉の子飼いである尾張衆の中には秀勝よりも秀吉と血のつながりのある甥の秀次に心寄せるものもあるが、「秀勝がいる限り後継者は秀勝」と秀吉は言っている。でも秀勝はまだ17歳の多感な少年である。9歳で親元から引き離されたことや14歳で実の両親を亡くしたことに悲しみがないわけがない。それなのに秀勝は人前で泣いたことはおろか淋しそうな顔をしたのは見たことがない。三成は初めて見た秀勝の悲しそうな怒りに魂を揺さぶられる想いがして彼に問うた。
「秀勝様、バレンタインとはどのようなお祭りでございましたか?」
「え?えっとねあれはこの家に養子にくる一年前の話だから…」
秀勝は少年時代に戻ったような懐かしそうな眼差しになって語り出した。
天正六年(1576年) 2月14日
「於次、於次…もう起きなさい。父上がお客様を連れていらっしゃいますよ」
濃姫はいつのまにか我が膝で眠ってしまった愛くるしい一人息子に優しく声をかけた。この子はいずれ養子に行く、あまり甘えさせてはいけないのだけど…と思いながら。於次は顔は母の濃姫に似ていたが、性格は無邪気でマイペースで自分の思い通りにしないと気が済まない父親の信長に一番息子たちの中でよく似ていた。
「まあ於次ったらお母様のお膝でお昼寝なんてまだまだ甘えんぼさんなのね!」
そう言い放って奥の部屋に入ってきたのはこの日のために岐阜城に来ていた、於次丸の従姉で信長の妹お市の方の長女である茶々であった。
「これお茶々!生意気な口を叩くのではありません。私たちは居候の身で養っていただいているのですから、すみません義姉上」
娘の後を追って入ってきたお市の方が濃姫に謝罪した。濃姫はフフフと笑うと「お茶々殿はもう立派なレディーですものね。今日は許婚の佐吉殿(後の石田三成)ともっと仲良くなれる方法を宣教師の方が伝授してくれるそうですよ」と言った。
「まあ本当ですか?!」
茶々は目を輝かしてピョンピョン飛んだので、母の膝で昼寝を貪っていた於次も起きざる得なかった。
「うるさいなぁお茶々は。もう、せっかくいい夢見てたのに。そんなにじゃじゃ馬じゃ佐吉にも嫌われちゃうぞ」
「そんなことないもん、佐吉は於次みたいにワガママな甘えん坊じゃないもん」
「ふんっじゃあいつか佐吉を見つけてもお茶々には教えてあげないっ。佐吉もお茶々なんかより大人しく慎ましいお嫁さんをもらった方が幸せだね!」
「なんでそうなるのよー、於次のバカっ」
「これこれ二人とも。いい加減にせんか。南蛮の客人に日の本の子供は節操がないと思われるではないか」
於次と茶々が振り向くとそこには南蛮の宣教師を引き連れた現在天下一統に邁進中の織田信長がいた。家臣には手厳しい要求を出す信長も於次と茶々の前ではごく平凡な父親であり伯父であった。
「ちっ父上っ」
「伯父上!」
「ホウ、コチラガノブナガサマノオコサマデスカ?」
「いや茶々は姪じゃ。於次がわしとお濃の息子じゃ。」
「それはそうと宣教師様、今日はそちらの国では特別な日と夫からうかがいましたが、具体的にはどのような日なのですか?」
「ソウデスネ、恋人ヤ家族ナドノ大切ナ人同士で贈リモノヲ贈リアイマス。ローマ帝国ノ時代ニ愛シ合ウ恋人同士ヲ帝国ノ掟ヲ破ッテ結婚サセテイタ聖人ヴァレンティヌスサマノ殉教ノヒデス」
「まあヴァレンティヌス様って良い人ね!わらわと佐吉も結んでもらえないかしら!」
「お茶々、タダでお願いを聞いてもらおうなんて図々しいよ。お茶々がまずキリシタンにならなきゃ。宣教師様はキリシタンの教えを広めるために日の本に来ているのであって、お茶々の恋を叶えるために来ているんじゃないんだからね」
「うるさいわね於次!」
「これこれ二人ともやめよ。喧嘩は犬でも食わんと言うぞ…それでそのわしが所望したものは持って来てくれたのであろうな、セバスティアン殿」
「ハイ。コロンビア鉱山ノエメラルドデゴザイマス」
「まあ殿ったらそのような高価なものをどこの女性に贈られるのでございます?濃は正室
ではございますけど、少し恨めしゅうございますわ」
濃姫が艶やかな視線を夫の信長に送ると信長は慌てて照れながら弁明した。
「わしがこのように高価なものを送るのはお濃そなた以外に居らぬであろう。わしはわしなりにわしの夢を支えてくれているそなたに感謝しているのじゃ」
濃姫はそんな夫にクスクス笑うと、打ち掛けの袂から見事な錦袋に入れられた金平糖を取り出して夫に差し出した。
「では濃からはこれを。これほどの数の金平糖は滅多に集まりませぬよ、本当は於次やお茶々殿と食べようかしらと思っていたのだけど、今のわらわにそのエメラルドなるものの対価は支払えませんのでこれで許してくださいませ」
「よいよい対価などいらぬ。わしは濃にエメラルド以上に感謝の心を送りたかったのじゃ。金平糖は子供たちにやるが良い。わしには濃の気持ちだけじゃ十分じゃ」
「あらまあその気持ちの十分の一だけでも家臣たちにかけてやってくださいませ。皆、殿のために命懸けに汗水垂らして戦っているのですよ」
そんな濃姫と信長の掛け合いを観ながら侍女たちとセバスティアン殿が去り、お市の方が娘の茶々を引っ張って連れて行ったので、奥の部屋には信長と濃姫、於次の一家水入らずの状態となった。
「わぁー嬉しい。ととさまとかかさまとこうして居られるなんて。於次にはどれほど嬉しいことでしょう!」
「於次…」
濃姫と信長の顔が一瞬複雑に歪んだ。この子はこの子でこれから自分が父や母と別れ歩んで行くであろう道を思い描いているのであろうか、と。信長は普段は見せない優しい眼差しで「ここにこい於次…」と最愛の息子を呼ぶと息子を懐に抱きしめてつぶやいた。
「於次…お前はこれから父とも母とも別れ別の道を生きることになるかもしれんが、決して泣くんじゃないぞ。たとえお前のそばに居なくても父と母はお前を常に思っている。もしも父と母が非業に倒れることがあったとしても魂はそのそばに居る。だから強くたくましく生きておくれ於次」
「そうですわね、母も同じですよ。於次。あっそうですわ、もう夕刻の時間ですし、久しぶりに三人水入らずで食事をしませんこと?」
「そうじゃな、たまには良かろう」
それが於次こと秀勝にとって父と母と三人で過ごした最後の晩餐であった。
「て言うわけでさ、バレンタインは大切にして欲しいわけだよ。分かった三成に吉継…って何泣いてるの三成、吉継もしけた顔しちゃってさ」
「だって今までは気が強くてマイペースで、ちょっとおせっかいかなって思っていたけど、そうですよね、秀勝様は幼くして両親とお別れになってあんな形で実の父上と母上を亡くされて、辛くないわけないですよね」
三成は涙を流して語り吉継もうないづいている。
「あのさー、戦国の世で戦で親を亡くすなんていくらでもあるんだよ。母上だって俺にはおじいちゃんにあたる父君(斎藤道三)を亡くされていたし…って言うか三成それを言ったら茶々だって可哀想だよ。2度の戦で父親と母親を奪われたんだから。ちゃんと慰めてあげなよ、ああ見えて中身は繊細な子だからさ。今は茶々にとって一番大切な人は三成しかいないんだよ」
俺はあなたの涙を知らない。どんな時もあなたは春の太陽の陽射しのような温かい笑顔で俺や父上そしてみんなのことを照らしてくれた。三成は俺のおせっかいで茶々を娶ることになったと思っているのかもしれないけど、茶々を戦国の武家の娘に嵌められた枷である政略結婚から解き放ち、自由意志による恋愛結婚に希望を見出せたのはあなただった。それは茶々が一番よく分かっているはずだ。だから茶々は時々「濃姫様だったらきっと賛成してくださった」とあなたの名前を自然と口にするんだ。あなたは人の痛みや苦しみに誰よりも寄り添える人だった。だから父上もあなたを大切にしたし、頼りにしていたんだね…あなたが本能寺に滞在していたのは多分父上が不安そうだったからでしょう、俺は正直言って父上が羨ましいな、だって俺には母上あなたのような存在はいないから。
於次、くじけないのですよ、母はいつでもあなたの背中を見ていますよ。
本能寺から逃れてきた男が運んできたあなたの手紙にはたった一行そう書かれていた。俺はしばらく部下たちに一人にさせてくれと持ち場を離れてたった一人で号泣した。戦国の世の習いとして、父上はいつか戦場に命を落とすことはあるかもしれないと思っていたけど
…母上はずっと安全な場所で長生きしてくれると思っていたんだ。二人とも不安が少しでもあるなら丸腰で本能寺になんていかないでよ、お母さん、お母さん、お母さん…
「また亡き母上の夢でございますか?秀勝様はいつまで経ってもねんねですのね。これでは人の親になどなれないのではございませぬか」
羽柴秀勝の正室である千代姫は呆れたように早朝の寝所でため息を吐いた。千代姫は加賀の領主前田利家の娘で、秀勝の養父秀吉の直々の願いで秀勝に輿入れした。秀吉も利家も秀勝と千代姫の間に早く嫡男が授かることを願っている…ということは千代姫も秀勝も重々承知していたが、いかんせん秀勝の寝所での振る舞いは未だ少年という感じで大人の男とは程遠いと千代姫は思っていた。秀勝の父信長が中国出陣を前に家臣の明智光秀に討たれたのは確かに致し方ない面はあるが、秀勝の母でもある正室の濃姫こと斎藤帰蝶まで巻き添えで亡くなったのは息子の秀勝だけでなく世間的にも大きな衝撃を与えた。濃姫は織田政権の柔を象徴する華であったからだ。もう三年も経つけれど秀勝の負った心の傷は癒えていない。葬儀の時も法要の時も一切涙を見せず、それこそ養父の秀吉や養母のおねも心配するほどなのだが、千代姫は知っている。秀勝は時折「お母さん、お母さん、お母さん…」と叫ぶ夢にうなされてはしょげているのだ。千代姫はいっそのこと秀勝が父上や母上の死を忘れられないと目の前で慟哭してくれたら楽なのに、と思うがそれを言うと秀勝がまた頑なに心を閉じてしまう気がして言えなかった。
「あーよく寝た。さーて今日はどうしようかな、三成と茶々をおちょくりにでも行こうかなぁ…」
そう秀勝があくびをして起き上がったところ、バタバタと侍女が走ってきて「秀勝様、秀勝様、お客人でございます!」と叫んだ。
「客人?また官兵衛とか尾張衆の脳筋連中じゃないだろうな、こんな朝っぱらから無礼だと追い返してしまえ!」
「それがその女性の方でして…」
秀勝はその言葉を聞くとゔぇっとした顔をしたが、「そうかでは客間に通せ。俺もすぐ行くと伝えよ」と言うなりさっさと寝巻きの小袖を着替え、いつもの羽織袴姿で急いで寝所を出て行った。
果たして秀勝が邸宅の客間を恐る恐る覗いて見るとなんのことはないそれは従姉妹で幼馴染みの茶々だった。だがひどくご立腹の様子である。
「なんだ茶々かー。ビックリするじゃないか、でも一人でくるなんてどうしたのさ。三成とケンカでもした?あの三成を怒らすなんて茶々も相当なワガママを言ったのだろうねw」
そう言って秀勝がゲラゲラ笑うと茶々はますますいきり立ち怒鳴り出した。
「秀勝!あんたまた余計なこと三成に吹き込んだわね!おかげさまで三成は夜になっても寝所に来ないじゃない!一人書斎に籠ってコソコソと何かしてるわ」
「えー?!三成には茶々だって両親を戦乱で亡くしてるから慰めてあげなよ、って言ったのになぁ。茶々、三成は本当に何も言ってないの?何も言わなかったとは思えないんだけど」
秀勝は解せぬと言う顔で腕組みをした。
「…そっそうね先月憂いげな目で屋敷に帰ってきた時は、急にわらわを抱きしめて珍しく自分から求めてきたわ『大丈夫、ずっとそばに居るから…』ってそれはしっぽりと愛し合ったのよ。だから余計に分からないんだわ、その日以来三成はろくに会話してくれないのよ、一体どうなってるの?」
茶々は頬を紅潮させ口をとんがらせた。そんな茶々の様子を見て秀勝は「ああ、そうか」と深刻そうなため息をついてみせた。
「なっ何なのよ秀勝。勿体ぶっていないで教えてちょうだい!」
「まあまあそんなに怒らないでよ茶々、男には甲斐性ってものがあってさ、三成も茶々だけじゃなんて言うの満足できないって言うか、きっとそういう事情があるんだよ」
すると茶々は激昂して秀勝を怒鳴りつけた。
「ふざけんじゃないわよ、秀勝と茶々の三成を一緒にしないで!あんたはそうかもしれないけど、三成は一度も浮気したことないし、結婚した時も茶々が初めての女だったんだから!いい加減なこと言わないで」
「三成や吉継は奇特なだけだよ。普通は妾の三人や五人はいるもんだよ、でもさぁコソコソとやってるということは浮気じゃなくて本気なのかなぁ…茶々捨てられちゃうかもねぇ」
秀勝が意地悪そうに畳み掛けると茶々は一転泣き出した。
「へっ変なこと言わないで!今の茶々には三成しかいないのよ。三成が居なくなったら茶々はどうすればいいのっ」
わんわん泣く茶々を見て秀勝は少しからかい過ぎたかな、と反省した。ただ、秀勝には秀勝で茶々には懲らしめてやりたいと思うことがあった。茶々は昔の癖なのか未だに自分を秀勝とか於次と呼び捨てにしているが、秀勝は次期天下人の後継者であり茶々の夫である三成の主君なのである。そろそろその生意気な態度を改めてもらいたいと思い意地悪を言っただけなのだが…でもこうなっては仕方ない、それは次回に説き伏せてやるかと秀勝は観念した。
「茶々…そんなに三成が大好きなら三成を信じてあげなよ。俺の母上は…母上は父上には沢山側女がいたけど決して怒ったり泣いたりしないで、父上を待っていたよ」
秀勝は再び遠い眼差しで”あの日のこと“を語った。
秀勝こと於次が南蛮の祭りバレンタインを知った日、於次は父信長と母濃姫と共に夕食を共にした。バレンタインは愛するもの同士が贈り物を贈り合う日で、信長は濃姫に南蛮で珍重されていると言う美しい緑色の石エメラルドを贈った。それは母濃姫が正室だからと言うのもあるだろう、しかし父には母の他にも多くの側室がいる。彼女たちにも父は何かしら贈り物をするのだろうか、母は許すかもしれないけど於次には面白いことではなかった。
「父上…父上は母上以外の女性にも何か贈るのですか?」
「…どうじゃろうのう。それは考えておらなかった、やはり皆に贈った方が公平か。エメラルドは贈れぬけどな」
「そうですねえ、それが公平でしょうね、彼女たちが沢山お子を産んでくれるから織田家は成り立っているのですし…」
濃姫は少し寂しそうに笑った。それを於次は見逃さなかった。
「父上!バレンタインを贈るのは母上だけにしてくださいまし。特別な日なのですから特別な母上だけにしてください!」
「これこれ於次、ワガママは言ってはなりません。父上も困るでしょう?」
「だって父上には奥さんが一杯いるかもしれないけど、於次にとっては母上は一人だけなのです。於次は於次の母を大切にしてほしいのです」
信長はやれやれと言うふうに微笑むと於次の頭を撫でた。
「分かった、分かった。バレンタインを贈るのは濃だけにしよう。けれどもそなたの母は剛の女よ、わしがいくら子を儲けるために側女を置こうとも必ず夫は自分の元に帰ってくると信じておるからの」
「あら、それは少し心外でございますわ。わらわは殿を信じているという以上に、殿に愛され必要とされる自分を信じているのでございます。自分の評価を外に託したらその瞬間人は人に軽く見られるのでございます」
「だそうじゃ。於次、そなたもいつか妻を持つのだからお濃のような女子を娶ると良いぞ」
父上…母上のような女人なんていないよ。母上は唯一無二の人だもの。
そしてバレンタイン前日。秀勝はある決意をして三成を呼んだ。
「秀勝様、御用とは何のことでございましょう?」
「三成、茶々がうちにまで怒鳴り込んで来たぞ。三成が茶々を可愛がってあげないからーすんげえ怒って、三成が一人で書斎でコソコソしてるってさ。何してんだよ」
「書斎で絵を描いていただけでございます。ただ、バレンタインに茶々に渡したい絵だったので茶々に見られたくなかったのです」
「だよね、三成に俺みたいな度胸はないもんねぇ。茶々はまだ怒ってるの?」
「それが茶々はまた懐妊したみたいでそれが故に情緒が不安定なのでございましょう」
「へぇー、なんだかんだ言って茶々と三成はラブラブなんだねぇ…そうだ、その祝いといっては変だけど、これを茶々に渡してくれる?」
秀勝は深紅のビロードの布に包まれたものを三成に渡した。
「秀勝様これは?」
「母上の遺品なんだ…父上がバレンタインに母上に贈ったエメラルド。綺麗でしょ、男の俺が持っているのもアレだから、母上のようになろうと意識している茶々に持っていて欲しいんだ」
「でも母上の遺品なんですよね…良いんですか?」
「俺には母上が最後に書いた手紙だけで十分だよ…それにそろそろ俺も巣立ちしなくちゃね」
「秀勝様…あなたの母上とて決して泣かなかったわけではないと思いますよ。秀勝様が長浜城に来られた日、母君は一緒についていらっしゃったじゃないですか、そして秀勝様を秀吉公とおね様にお渡しになる時、目が痛いわって笑っていらっしゃった。でもそれは涙を誤魔化すための芝居だと思います。俺も親になったから分かるんです、あの時の濃姫様のお気持ちが。まして秀勝様は濃姫様にとって唯一人のお子様ですから。お淋しかったろうなと思います」
「…養子の話は母上と父上が積極的に進めた話なのに?」
「それでもです」
バレンタイン当日。秀勝は南蛮の商人から買い上げた百本の赤いバラを持って千代姫のもとを訪れた。
「千代姫、君のために百本の異国の花を買い上げて来たぞ。これからも両家の繁栄のため仲良くしようぜ」
「両家の繁栄のためでございますか。それはそうでございましょうね、私たちはそのために結びつけられた夫婦ですもの、お茶々様やお美代殿(お美代は大谷吉継の妻)のように扱ってもらえるなどとは到底思ってなどおりませんわ」
「あれ…何か怒ってます?」
「秀勝様、お妾の中将の君が男児をお産みあそばしたとか。おめでとうございます。寝屋でのなさりようはわらわではそそられないということでございましたか。まことに不甲斐ない妻で申し訳なく思っております」
「……あの吉継のところに行ってきます」
「あーなんで俺は三成や吉継みたいにはできないのかなぁ。千代姫が母上みたいだったら俺も大事にできるのかなぁ…ってダメだ。これじゃ母上から巣立てない」
そう、俺は巣立たないといけないんだ。母上が亡くなってもう三年になるのだもの。
「というわけでさ、頼むよ吉継。うちの太郎くんを貰ってくれよ、君んとこ子供いないでしょう。ね、この通り」
よりによって夜のバレンタインに大谷邸を訪れた秀勝は親友で部下でもある吉継に頭を下げた。
「詰めが甘すぎですよ、秀勝様。正室より先に妾が息子を産むなんて千代姫様からしてみれば面目丸潰れじゃないですか。まだ結婚して一年も経っていないんですよ、男どもはそれでも仕方ないと言うかもしれませんけど、女はいたたまれないんだと思いますよ」
愛を伝えたいんだ 完
