
◆読書日記.《ジャン=ポール・サルトル『嘔吐』》
※本稿は某SNSに2022年1月14日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。
ジャン=ポール・サルトルの処女長編小説『嘔吐』読了。
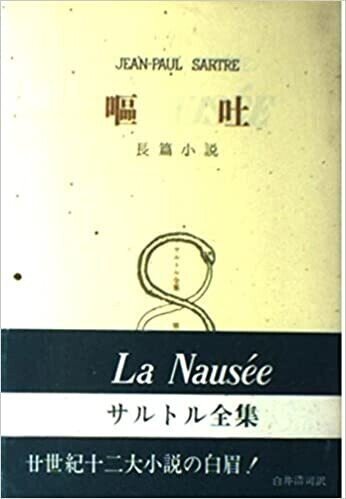
執筆年は1938年という、第一世界大戦と第二次大戦の間の時期に書かれた小説。
「神は死んだ」の時代であり、新しい時代の信仰対象であった「科学」でさえ大量殺戮兵器の誕生によってその価値が揺らいでいた。人々の実存不安の時期に受け入れられた小説。
<あらすじ>
歴史研究者のアントワーヌ・ロカンタンは長期の旅行ののち、18世紀のド・ロルボン侯爵に関する研究をまとめるべくフランスの港町ブーヴィルで図書館に通う日々を暮らしていた。
昔からの知り合いがいるわけでもなく、カフェに行っては顔見知りの女給なんかに声をかけて一晩を共にしたり、通っている図書館で顔見知りの「独学者」と軽い挨拶を交わしたりする程度の孤独な毎日である。
そんな何事も起こらない平々凡々として日々の中で、ロカンタンはふいに変化が生じた事を知る。
それはどんな変化なのか、どこにあるとは言えない抽象的な変化が起こったのだ。自分の周囲のものが変わったのか、それとも自分が変わったのか。
ロカンタンは「変わったのは自分だ」と悟るようになる。
依然としてロカンタンの周囲には何事も起こってはいない。
だが、手に掴んだパイプや、握ったフォーク、あるいは扉を開こうとして握ったドアノブ――そんな何気ないものから、理由の分からない<吐き気>が呼び起こされるのだった……というお話。
<感想>
……と、いったようにこの小説はラストの辺りまでは基本的に劇的な事件は起こらない。淡々とした、30歳の研究者の日常を一人称で描写しているだけである。
だが、これがサルトルの無神論的実存主義思想の「小説化作品」であるというだけあって、劇的なのは常に主人公の内面にある「吐き気」の謎にあると言えるだろう。
主題は非常にハイデガー的だと言えるだろう。そして、所々の描写がフッサールの超越論的現象学的な記述になっている所が面白い。
現象学は前期サルトル思想に大きく影響を与えた思想だし、ハイデガーも(当時は)フッサールの現象学を継ぐ学者として既に主著『存在と時間』が有名になっていた時期であった。
ロカンタンの内面の変化はサルトル的主題としてはお馴染みの「実存主義的変化」であったと言えるだろう。
彼は日常の中で彼の周囲を取り巻いていた細々とした日常品から、ふいに「意味」が欠落するのである。
ふと、自分の掌の内に硬くて冷たいものが触れられている事に気が付いて、それを見てみる。手を開いてみると――そこには扉のノブが握られていた。
「私はただ単にノブを握っていたにすぎない」
日々通っている図書館で挨拶をする「独学者」についても、ふとある朝、「彼がだれであるかを思いだすまでに、十秒ほどかかった」という。
幾つかの穴が開いた肉塊の上に糸の房がわさっとかかっているそれを「顔だ」と思うのに時間がかかったのであろう。
何しろ、握手をした時でさえも「大きな白い蛆のような彼の手が私の手の中にあった」というくらいであるから。
現象学的に言えば、われわれはそういった「顔」や「手」や「ドアノブ」というものを「それが何であるか?」という事をいちいち分析して理解しながら生活しているわけではない。それらを直観的に「顔」や「ノブ」だと自動認識しているわけである。
我々が認識している「世界」というものは、そういった自動認識によって理解され、理解されたものの中で生活しているのである。
我々は、扉の表面から突き出た物体を詳細に確認してから「ノブだ」と認識して、それを利用しているわけではない。
逆に言えば、その「扉の表面から突き出た物体」を「ノブ」以外のものだと認識するほうが難しい。
つまり、我々の身近にある物事というものには、すべからく「意味」が張り付いているのである。
しかし、そういった物事に決まった「意味」など本当にあるのだろうか?
サルトルの実存主義には「実存は本質に先立つ」という考え方がある。
ドアノブやフォークのような人間が作り出したものであるならば、「ドアノブ」というその物体の「本質」に合わせて作り出すから、ドアノブが出来上がる前にドアノブは「本質」が出来上がっているものだと言えるだろう。
だが、人間は、「私」という存在は、「何者であるのか」というその人の本質が何であるかというのは、生まれながらに決まっているわけではない。
「私が何者か」という事が決定される前に、「私」はこの世界に投げ出され、否も応もなく生きている事を強いられている。それが「実存は本質に先立つ」という事である。
つまり、人間は生まれたままの状態では何の意味も本質もなく、自ら行動して何者かにならなければ、何物にもならない、というのがサルトルの実存主義的な考え方である。
しかし、物事に「意味」を張り付けているのは人間に他ならず、そもそも「物事の意味」等というものは我々人間にとってしか「意味」を持たないものだ。
そもそも自然界のものに「意味」や「名前」などはなく、木や草や川に名前を付け、それらを分類して意味付けしているのは人間だけに外ならない。
「意味」等というものは、人間に限ってしか意味を持たないものなのだ。それがハイデガー的な存在論的問題でもあった。
「マロニエの根」等というのは人間にとってしか意味を持たない言葉だ。
ロカンタンは自分の<吐き気>の正体に気が付く。
「ことばは消え失せ、ことばとともに事物の意味もその使用法も、また事物の上に人間が記した弱い符号もみな消え去った(P.146より引用)」
存在というものには、単にそこに<ある>だけであって、本質的な意味などはない。それは人間だって同じ事なのだ。
ロカンタンは、何かの理由があって生まれてきたわけではない。
何かしらの宿命があって自らの生を生きているわけではない。
「存在に意味はない」――ゆえに私という存在にも意味はない。
「それぞれ存在するものは、当惑し、なんとなく不安で、互いに他のものとの関係において余計なものである(P.148より引用)」
それはロカンタンの実存的不安感、孤独感と同一のものであったのだ。
このようなプロセスを経てサルトル的実存主義思想はハイデガーの存在論的問題から"人生論"的な問題系へとスライドする。
西洋は長らくキリスト教の「神」の懐に抱かれ、われわれの「人間が生きている意味」は充実していたのであろう。
人生は何のためにあるのか? 生きる意味とは? 私は何のためにここにいるのか?――こういった問題は、教会の神父様が懇切丁寧に教え、どのような心構えでどのように生活し、死んだ先でもその幸福は保証されていたと言えるだろう。
だが、「神は死んだ」のである。
ロカンタンと顔見知りの図書館の「独学者」も「ぼくは神を信じてはおりません。神の存在は科学によって否定されています(P.132より引用)」と漏らす。
長らく西洋人が伝統的に頼ってきた「人生の指針」たる「神」はもういない。
彼らはそんな「信頼できる意味=神の教え」の喪失した時代に「投げ出されて」生きているのである。
だからこそ実存主義は「人生論」的な側面が見え、だからこそ第二次大戦後の西洋人らに受け入れられたのであろう。
周囲に物は溢れ、年金生活者として強制的な労働に従事せずとも生きていけるロカンタンに、そのような実存的不安が訪れるのは、この時代特有の病理であったのかもしれない。
そう考えれば、これはある種「実存的不安」を抱える時代の人間には普遍的に当てはまるテーマを扱った小説だったのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
