
◆読書日記.《中根千枝『タテ社会の人間関係 単一社会の理論』》
<2022年12月30日>
中根千枝『タテ社会の人間関係 単一社会の理論』読了。
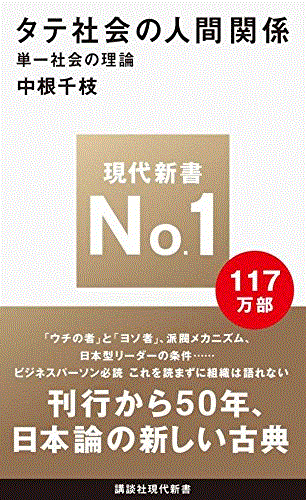
2022年末からYoutubeでホロライブのVtuberちゃん達にドハマリしてその動画を貪るように見ていたので、しばらく頭のネジが緩んでいた(今もばっちり緩んでいる)。
あれは初期のAKB48グループの売り方のリモート版だな、と思っていて、知れば知るほどその沼にハマっていってしまう。
……という事で年末に読み終わった本書もついついレビューを後回しにしてしまっていたのである。ってなわけでぼくにも色々と事情があるのだ。読者諸兄、ご容赦を。
◆◆◆
さて、本書は東大名誉教授、女性初の日本学士院会員、学術系としては女性初の文化勲章受章者、という日本では著名な社会人類学者による日本論にして日本の社会組織論である。
ムダのない引き締まった評論で読んでいて非常に楽しかった。
社会人類学が専門の著者が日本社会の社会構造を分析して日本型組織の特徴を挙げた古典的著作なのだそうだ。
初版が1968年だからもう半世紀以上前の著書なのだが、未だに「日本組織あるある」な内容なのは、さすが古典と呼ぶべきか。
ぼくもサラリーマンとして過去何社もの企業さんとお仕事をした事があり、また大鹿靖明『東芝の悲劇』、今沢真『東芝 終わりなき危機』、森功『腐った翼―JAL消滅への60年』等といった企業の内幕を描いたルポ等を読んできた身としては、本書の記述には確かにそういった企業の性格を説明できていると思わせられるような説得力があった。
現在までに120万部以上を売り上げるロングセラーであり、イギリスでは英語版も出版されているので、海外にもそこそこ知られている様子である。
本書が日本論として特徴的なのは、社会人類学を用いた分析を行っている点にあると言えよう。
もともと人類学は未開社会の実態調査を元に発展してきたが、社会人類学はそういった人類学の方法論をもっと大きな社会に適用させた比較社会論といったようなものになる。
社会人類学については、著者の説明が簡にして要を得ているので引用しよう。
一定の社会を、一定の方法論に基づいた実態調査によるデータを解釈、綜合することによって、その社会の基本的と思われる原理を抽出し、理論化し――このようにしてとらえられるものを、「社会構造(ソーシャル・ストラクチュア)」という基準用語(key-term)によって表現している――そのレベルにおいて他の社会との比較を行う、という研究方法をとるのである。
この社会構造分析によって、本書では日本の組織の多くが「タテ」の性格が強いと説明するわけである。
そもそも、本署が「古典」と呼ばれる理由の一つには、タイトルにもなっている「タテ型組織」や「タテ社会」といったような、組織構造の類型として「タテ」という概念を出して、これがきっかけで一般にも「タテ」という考え方が広まった点にもあるようだ。
しかし、本書で扱っている「タテ」というのは所謂「場」の論理を前提にしているので、一般的に知られているような「タテ」という考え方とは若干の違いがある。
この考え方の混乱は未だに一般的な「タテ社会」「タテ組織」という考え方にも残されているようなので、ここで少し本書から敷衍しておこう。
一定の個人からなる社会集団の構成の要因を、きわめて抽象的にとらえると、二つの異なる原理――資格と場――が設定できる。すなわち、集団構成の第一条件が、それを構成する個人の「資格」の共通性にあるものと、「場」の共有によるものである。
社会集団の構造の特徴である「タテ」や「ヨコ」という分類の考え方というのは、この「資格」と「場」という構成要因が第一条件になっている、というわけである。その前提条件の元に、「タテ」や「ヨコ」という分類が出てくるのだ。
この「場」というのは、地域が一緒の集団であったり所属機関が一緒の集団であったり、といったように、それぞれ所属している構成員の性質によって集まっている集団ではなくて、一定の「枠」によって集まっている集団と言う意味である。
それに対して「資格」というのは、個人の「属性」によって集まっている集団という意味となる。
属性というのは、例えば氏や素性や人種といった生まれながらに備わっている属性であったり、学位や職種といったように個人の意思で取得する属性もある。著者によれば老若男女といった属性の差や、貴族と庶民、労働者と資本家、地主と小作人といった経済的な属性の差なども、ここでは「資格」という事になる。
例えば、会社員がビジネス・シーンで自己紹介をする時に何と言うかという事でも、このような「資格」と「場」に関する個人の意識の差がはっきりと表れる。
A:「はじめまして。エンジニアの田中と申します」
B:「はじめまして。ABC株式会社の田中と申します」
「A」のタイプの自己紹介を行っている人は、仕事をしている上で自分の「資格」の属性の意識が強いタイプという事ができる。
それに対して「B」の場合は、仕事をしている上で自分の「場」の属性の意識が強いタイプという事ができるだろう。
日本では圧倒的に「B」のタイプが多いという事を考えても、日本人が基本的に「場」の属性意識が強いという事がわかる。
日本人が外に向かって(他人に対して)自分を社会的に位置づける場合、好んでするのは、資格よりも場を優先することである。記者であるとか、エンジニアであるということよりも、まず、A社、B社、S社の者ということである。また他人がより知りたいことも、A社、S社ということがまず第一であり、それから記者であるか、印刷工であるか、またエンジニアであるか、事務員であるか、ということである。
実際、××テレビの者です、というので、プロデューサーか、カメラマンであると思っていたら、運転手だったりしたなどということがある(このごろの日本では、みんな背広を着ているので、一見しただけではちょっとわからない場合が多い)。
例えば日本では、同じ職業の人たちで横のつながりを作ろうという職能組合の結束よりも、企業の中の結束のほうがよっぽど強いという特徴があるというのも、この「場」の属性意識が強いという事の証左の一つと言っても良いだろう。
日本の労働組合の性格というのが、企業と企業との垣根を超えたヨコのつながりの組合ではなく、しばしば「組織内で、上層部と労働者との間の意見調整を行う御用機関」でしかないのも、日本の組織が「場」の属性意識が強い性格の表れであるとも言えるだろう。
◆◆◆
著者はロンドン大学で研究を積み、インドに数年滞在して調査をしていたという経験もあり、イギリス、インドなどの事情にも精通しているそうで、しばしば本書で日本とヨーロッパとインドの社会組織の比較を行っている。
それによれば、日本とインドではこの「資格」と「場」の意識が大きく違っていて、インドのほうはカースト制度(基本的に職業・身分による社会集団なのだそうだ)があるように「資格」による分類意識のほうが強いのだそうだ。
だから、本書でも日本とインドでの集団意識、組織感覚の違いについては、非常に好対照の例として何度も紹介している。
日本人の「場」の意識というものは、「知らない者はヨソ者」という意識が強い。これは、同じ「場」という枠組みの中にいなかった者は自分と同一集団の人間ではない、と認識してしまう考え方だ。
それに対してインド人や中国人などは、違う組織の中にあっても違う国の中にあっても、常にその中に自分と同じ属性の人たちがいて、その人たちと「見えないネットワーク」によって繋がっている、という意識があるのだそうだ。
だから、海外に行っても中国人は自然と中国人ネットワークを作り易い。
外国に滞在しているインド人・中国人・ヨーロッパ人たちが現地において、ゆうゆうとして仕事をし、落ち着いた生活をしているのは、実にこのネットワークの存在にあるのである。
こういう「海外の常識」を知らされると、蒙を啓かれたような気分になる。
自分が常識だと思っている事が、海外の全く違う文化の人たちとどれほど共通しているのか、という事は海外の事情を知らなければ、理解する事が出来ない。
そもそも自分の考え方や意識は、どの程度「全人類に共通する普遍的な事」なのか、という疑問が人類学を発展させてきたと言ってもいいだろう。
◆◆◆
日本のように「場」の意識が強いと、集団はどのような特徴を帯びる事となるのか、著者は様々な例を挙げて説明している。以下などはその一例である。
日本の企業の社会集団としての特色は、それ自体が「家族的」であることと、従業員の私生活に及ぶ(家族が外延的にはいってくる)という二点にある。
この特色は、ぼくも実際に会社員として経験したあらゆる企業に当てはめて考える事ができる「あるある」的な特色であった。
特に、会社の人間関係と言うのは、何故ああも個人のプライベートに侵食してくるのか、というのは以前から何度も疑問に思っていた事であった。
どの会社でも経験したのは、誰も顔見知りのいない新しい職場に配属された時、「オロカメンさん、お昼いっしょにどうですか?」とか「今日おヒマでしたら、歓迎会がわりに呑みに行きませんか?」といったように「職場のコミュニケーションとして食事時間を共有する」という意識がどの職場にもどの会社にもあったという事である。
本書を読んで気が付いたのは、そう言えば「食事の時間」というのは、全く仕事とは関係のない「プライヴェートな時間」であって、それを断る事に何ら論理的にも倫理的にも非難される事はないはずだ、という事であった。
しかし、実際にはこういった「職場のコミュニケーションとして食事時間を共有する」という事は日本の組織ではイニシエーションじみていて、この誘いを完全に断り続けると職場関係は悪くなる傾向にある、という事だ。
ぼくが一時期、社員教育のお仕事をさせてもらっていた時、特定派遣の事業をやっていた部署の営業さんが相談にやってきた事があった。
他社にアウトソーシング事業として派遣されていた自社の社員が、お客さんである派遣先の社員さんにお昼を誘われても呑みに誘われても全て断っていたそうで、お客さんから「何か、あの人に嫌われてるんですかねぇ」と愚痴っぽく言われたというのである。
相談しに来た営業さんが言うには、今回の件はクレームというわけではないが、お客様ウケは良くないので、今後お客様に対してこういう態度をとらないように、特に新人社員にはそういったコミュニケーション意識をつけてほしい、というのだ。
派遣事業の営業さんのお話を聞いていると、けっこう仕事をする上では、その人の技術や知識が優れているかどうかではなく、「その人と一緒に仕事をしていてストレスにならないか」「その人が職場にいて悪い空気にならないか」――といった人間関係のほうがよっぽど重要なんだという事がわかる(ここでも「資格」ではなく「場」が重視されている事がわかるだろう)。
で、その「職場の人間関係」を築き上げるのに馬鹿にならないのは、お昼をいっしょにするだとか、呑みのお誘いを断らないだとか――そういう自分のプライヴェート時間をどれだけ職場の人と共有するか、どれだけ職場関係が自分のプライヴェートへ侵食してくる事を許容するのか、という事なのである。
今その職場から離れて客観的に見られるようになると、改めて何でこんな馬鹿馬鹿しい事が問題になるんだと半ば呆れてしまうが、これが著者が言っているように「日本の企業の社会集団としての特色」にバッチリ当てはまっているという事がわかる。
日本企業の内部の人間関係は「それ自体が『家族的』であることと、従業員の私生活に及ぶ(家族が外延的にはいってくる)という二点」だという事である。
こういった傾向があるのは何が原因なのか?
著者はその原因を日本の「家」制度に見ている。
この日本社会に根強く潜在する特殊な集団認識のあり方は、伝統的な、そして日本の社会の津々浦々まで浸透している普遍的な「イエ」(家)の概念に明確に代表されている。
(略)
筆者の立場からすれば、「家」を構成する最も基本的な要素は、家をついだ長男の夫婦が老夫婦とともに居住するという形式、あるいは家長権の存在云々という権力構造ではなく、「家」というものは、生活共同体であり、農業の場合などをとれば経営体であって、それを構成する「家成員」(多くの場合、家長の家族成員からなるが、家族成員以外の者を含みうる)によってできている、明確な社会集団の単位であるということである。すなわち、居住(共同生活)あるいは(そして)経営体という枠の設定によって構成される社会集団の一つである。
ここで重要なことは、この「家」集団内における人間関係というのが、他のあらゆる人間関係に優先して、認識されているということである。
日本の集団は、昔からある「家」制度のように「場」という枠によって結束してきたという習慣によってなりたっている。
「場」という枠組みは、何かしらの属性を同じくした者が集まっているわけではないので、自然とその構成員の間でスムーズに話が通じるという訳ではない。
属性がバラバラの者同士が集まって集団を作らねばならないので、わざわざ「チームワークを強くする」、「絆を強くする」、「結束を強くする」……といった何かしらの施策が必要になってくるのである。
そのための「家族的な感覚(資格ではなく「場」を共有する者たちの感覚)」であり、だからこその「私生活にまで及んでくる」という事なのだ。だから、「「家」集団内における人間関係というのが、他のあらゆる人間関係に優先」される事となる。
故に、飲み会をしたがったり、雑談をする時でも家族の話をしたり、タバコ休憩の時間に仕事の話を進める、といった私的時間を共有し、仕事とプライヴェートがごっちゃになってしまう。
属性が違っている者たちが集まっているのだから、何かしらの共有感を得なければ、安心しないという事なのだろう。
それが日本の「場」にかかっているロジックだったのである。
◆◆◆
上にも述べたように、社会集団の構造の特徴である「タテ」や「ヨコ」というのは、この「資格」と「場」という構成要因が第一条件になっている、というのがミソなのである。
著者も書いているが、例えば「この会社は同期会が非常に絆が強いので、この会社はヨコのつながりも大切にしているのだ」とか「現代では親子関係(タテ)よりも夫婦関係(ヨコ)のほうが強いから、必ずしも日本はタテ型の強い社会というわけではない」といった反駁は、本書に上げている「タテ」「ヨコ」の考え方にはあたらないのである。
そういった「同期会」だとか「夫婦関係」とかいったヨコの関係は、あくまで「場」による集団の内部に限定されたヨコの繋がりでしかないので、本書における「ヨコ」の意味での組織構造には当てはまらないのだ。
本書で言う日本型の社会集団の構造の特徴は、上に説明したように強固な「場」の中に存在してる「タテ」型の組織構造なのである。
本書ではこの【「場」の中の「タテ」型の組織】といった形で導き出した公式を、様々な日本の組織に当てはめ、次々に日本型組織の性格を明らかにしていく。
この【「場」の中の「タテ」型の組織】という公式が、あまりに様々な日本の組織の特徴や問題点の原因を鮮やかに暴き出していくので、この部分が本書の中でもとてもエキサイティングなのである。
わざわざ長々と引用もしないが、例えば「なぜ日本では同じような作品や同じような商品が一時期に爆発的に流行し、どこもかしこも同じものを作ってしまうのか?」という問題は、本書P.106の「並立競争の長所とその国家的損失」の一節を見れば説明されているし、「なぜ日本は縁故主義(ネポティズム)的な傾向が強いのか?」というのも本書P.116の「「タテ」集団は底辺のない三角関係」を読めば、それが日本の組織の性格によるものだったという説明がなされている。
また、「タテ」型の組織と「ヨコ」型の組織では、おのずとその「リーダー」というものの意味さえも違ってしまうという事も本書P.121の「開放的な「タテ」組織、排他的な「ヨコ」組織」を読むと、その理由も良く分かる。
つまり、本書の主張というものは、この【「場」の中の「タテ」型の組織】という組織構造が、日本の組織の特徴やその問題や行動の傾向などといった様々な部分に影響を与えているという事を指摘する事にあるのだ。
これは著者の主張からすれば日本の「家」制度的な慣習の影響が大きいからこそ、古くからある組織――例えば官僚組織や長く存続している日本の大企業といった組織――ほど、この特徴が当てはまり易いと言えるのではないだろうか。
本書の中で最も感銘を受けた指摘は、「日本は「人」に従う伝統はあるものの、「ルール」に従う伝統を持っていない社会だ」という点である。
とにかく、痛感することは、「権威主義」が悪の源でもなく、「民主主義」が混乱を生むのでもなく、それよりも、もっと根底にある日本人の習性である、「人」には従ったり(人を従えたり)、影響され(影響を与え)ても、「ルール」を設定したり、それに従う、という伝統がない社会であるということが、最も大きなガンになっているようである。
なるほど、確かにそうかもしれない。
会社の組織ぐるみで粉飾決算をしていたり、上司の命令で職場全体で不正を働いていたり……といった事件が日本の組織で発生するのも、会社員が「ルール」に従う意識よりも「人」に従う意識のほうが強いからだ、と考えれば納得がいく。
そして、ぼくが日本の会社組織にすっかり嫌気がさしてしまったのも、半ばこういった「人」中心主義といった非論理的な部分にあったように思う。
「株式会社」というのは、西洋式に作られた組織形態であるから、基本的には会社はルールに従うし、その構成員も決められたルールに従わなければならない。
だが実情、しばしば社内では労働法が無視されたり、就業規則さえも無視されたり、といった独自ルールが幅を利かせる事がある。
日本の企業の内部で行われる不正の数々といったものは、西洋式の組織に合わせて作られたルールを、そのまま日本式の組織に輸入して組み込んでしまったための歪みが出ているのではないかとも思わせられる。
休憩時間にも仕事をしなければ顰蹙を買ったり、職場の掃除は就業時間前までに持ち回りで担当になった人が済ませなければならなかったり、就業時間外でも仕事に関するメールに返信しなければ上司から叱られたり、制服を着替えている時間は勤務時間に入らなかったり、就業時間前までに仕事の準備を全て整えて職場にいなければならず、その準備時間は勤務時間にはあたらなかったり……といった、就業規則に書いてない、労働法に抵触しそうな職場の独自ルールは、日本ではどの職場でも多かれ少なかれ存在しているのではないだろうか。
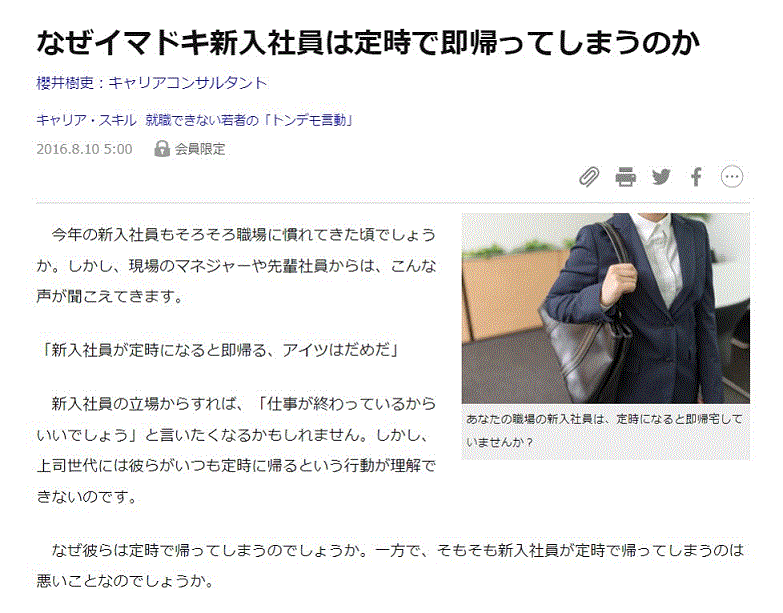
こういった事は、やはり「ルール」に従う感覚よりも強く、職場の人間関係の原理が強く働いている、という日本型の組織の特性があらわれているという事なのかもしれない。
日本においては、どんなに一定の主義・思想を錦の御旗にしている集団でも、その集団の生命は「その主義(思想)事態に個人が忠実である」ことではなく、むしろお互いの人間関係自体にあるといえよう。
ここでも宗教と同様、主義・思想は、日本社会にあっては後退を余儀なくさせられている。堂々と世界に誇りうるような、また、他の社会の人々に大きな影響を与えるような偉大な宗教家・哲学者が、いまだに日本(堂々たる文明国でありながら)から一人も出ていないという事実は、この日本的社会構造と無関係ではなさそうである。
このように考察してくると、日本人の価値観の根底には、"絶対"を設定する思考、あるいは論理的探究、といったものが存在しないか、あるいは、あってもきわめて低調で、その代わりに直接的、感情的人間関係を前提とする"相対性原理"が強く存在しているといえよう。
このことは、前に述べた、リーダーと部下の力関係における接点としてのルールの不在、人と人との関係における契約によって表現される約束の不在ということによっても、遺憾なくあらわれているところである。
会社の重要な施策を決める会議において「部長、それは今までのデータからいってもありえません。この施策はやめるべきです」といった意見よりも、しばしば「部長、このままでは自分のメンツがたちません!ここは私の顔を立てて、今一度自分に任せてください!責任はすべて自分が負いますので!!!」……などといった意見が通ってしまう馬鹿馬鹿しさにも、日本の組織構造にその原因の一端が隠れていたのだ、と分かっただけでも気分が少し晴れた気がする。
◆◆◆
……さて、といった所でけっこう真面目に、とってもためになるお話が書けたようなので、ここは自分へのご褒美としてまたホロライブのVtuberちゃん達の動画を見て、存分に頭のネジを緩ませていただこうと思う。←
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
