
◆読書日記.《尾崎まゆみ『レダの靴を履いて 塚本邦雄の歌と歩く』》
※本稿は某SNSに2021年10月14日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。
現代短歌の歌聖・塚本邦雄の短歌を分かりやすく解説した尾崎まゆみの随筆集『レダの靴を履いて 塚本邦雄の歌と歩く』読了。

ああ……遂に読み終わってしまった。
本書は塚本に師事した歌人の著者が、ブログで塚本邦雄の短歌を一首一首取り上げてその解説を掲載していたものをまとめた随筆集となっている。
塚本邦雄の短歌というのは、語彙の選び方についてもその技法についても、なかなか簡単には分かりにくい部分があり、かなりとっつきにくい。
その点、本書はブログに掲載されていた記事が元になっているという事もあって表現は平易であり、ひとつひとつの記事も短く、スパっと簡潔な解説が潔い。
しかも想定読者はおそらく短歌も読んだ事がない初心者を基準としている。
それでもあの難解な塚本短歌を理解させ、その魅力と共に楽しむ術を解説するという、超親切な「塚本邦雄短歌入門書」としても優れた本である。
塚本の短歌の難しさというのは、まず一つに拘りぬいた「語彙」の重さと言うのがあるだろう。
短歌と言うのは、五七五七七というたった三十一音に己の独自の個性的な世界と文体を詰め込もうという文学である。
あらゆる膨大なボキャブラリーの中から選ばれた単語は、様々な思惑が含まれる。
それは歴史的な意味であり、美術史的な意味であり、人類学的な意味であり、時に漢文の含意があり、哲学的な意味がある。
あるいは古典文学の本歌取りである場合もあり、季語や伝統文化の知識が入り込んでいる場合もある。
そういった様々な教養が試された上で、更にはポエムとしての一義的な解釈を拒む「深み」を持たせられているのが短歌というものだ。
塚本邦雄の作品というものは、その教養の深さと美学の深みが他作品とは異質なのだ。
更に塚本は前衛短歌運動を牽引しただけあって伝統的な短歌の定形を様々な手法で崩し、新たなルールを立ち上げているのである。
それは例えば初七調であり、五割れ句跨りであり、いろは歌であり、アポリネールの『カリグラム』を模した多行形式であった。
塚本を鑑賞するのには、これだけのハードルがある。
ぼくが塚本の歌集を初めて買ったときも、その内容は全く分からず、解釈の仕方もサッパリ分からなかった。
しかし、塚本は中井英夫の友人であり竹本健治も読んでいるという事もあって以前から興味があり、サッパリ分からないながらも、その奇妙な修辞に何とも言えぬざわざわとした胸騒ぎを覚えたものであった。
ぼくの経験上、前衛芸術のようなものについては「意味は全く分からないのだが、何故だか心がざわざわと粟立つ、分からないが惹かれる」というものについては、何かしら「掴んでいる」事が多い。塚本の作品についても、その勘が当たったわけだ。
塚本邦雄の短歌がやっとわかり始めたのは、彼が自らの歌集『緑色研究』に掲載されている一首一首について、それぞれに散文「自歌自賛」を付した随筆集『緑珠玲瓏館』を読んだ事で、塚本なりの感覚を散文によって掴んだ事が大きかった。
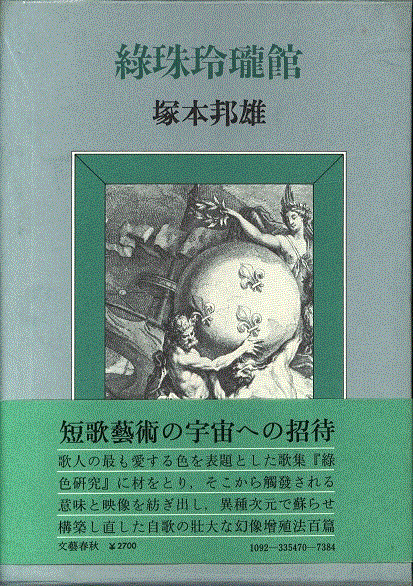
その後、様々な作家の書いた塚本論を集めた磯田光一/編の『塚本邦雄論』や塚本邦雄の短歌論集によってだいたいの感覚は解るようになってきた(気がする、くらいのレベルだが)。
そんなぼくでも本書の尾崎まゆみさんの解説は、また自分の「塚本邦雄感覚」の手がかりを得る上で非常に役に立ったと思っている。
以前も紹介したが、まず本書に惹かれたのは、冒頭に紹介されており、本書のタイトルの発端ともなった一首である。
「ゆきたくて誰もゆけない夏の野のソーダ・ファウンテンにあるレダの靴」
たまたま本書を手に取った時期――夏の季節を幻想的に彩る一首であった。
「ゆきたくて誰もゆけない夏の野」という修辞が、「非現実派」である塚本の美学を表していて非常に心惹かれるものがあった。
短歌の言葉に寄り添った解釈には、この歌を読んだときの魂を素手で掴まれたような感覚は反映されていません。というよりもその感覚の源は「言葉の意味に沿った正しい解釈」の中にはないといっても良いでしょう。
――と、本書の著者は言う。確かに、だからポエムの解説は難しいのだ。
例えば、読んでも全く意味の分からない短歌を、分かりやすく平易な言葉でパラフレーズしたら理解できるようになったとしよう。それならば、最初から平易な言葉で書けばよかったのか?――そうではない。
例えば、難解な長編小説を分かりやすく要約した"あらすじ"を読んで本編よりも感動する人間が、いったいどこにいるのか?
小説というものは「あらすじ」を長くしたものではないし、それと同じように、短歌は様々な思いの詰まった詩を三十一音に圧縮したものでもないのである。
短歌という形式に縛られる事によってはじめて表現する事のできる美――それを感じてこその短歌なのである。
また、引用した尾崎まゆみの言葉にもある通り、その三十一音を言葉通りに解釈しても、その後に更に「ポエム」としての解釈が必要になるというもう一つのハードルが控えている。
短歌はポエムであるからこそ、様々な解釈が許される芸術なのである。
ぼくからすると、本書の著者である尾崎さんの解釈の仕方は、とても柔らかくて優しい。
本書に現れているその繊細さが、尾崎さんご自身の感性も反映されていてまた好ましいのである。ブック・デザインの優しさも相まって、本書はなかなかの一冊であった。
「百年後のわれはそよかぜ地球儀の南極に風邪の息吹かけて」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
