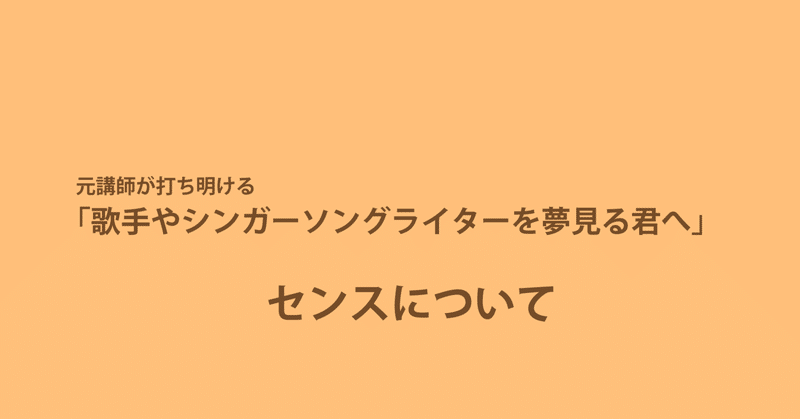
元講師が打ち明ける「歌手やシンガーソングライターを夢見る君へ」:センスについて
「センスがある・ない」ってよくいうけど・・・
スポーツ、芸術、技術まで、センスがある、ないという表現は
昔から、そして今もよく使われる。
君は、誰かと一緒にはじめて何かをやるというタイミングで、
「自分は全然できないのに、他の誰かはすぐにできてしまった」という経験はないだろうか。
そういう人は「センスがあるね」などと言われる。
講師としての強みになった「センスの乏しさ」
ちなみに、私は子どもの頃から今まで、何かをはじめてやってみたとして、一度でできるようになったという経験が全くない。
本当に、最初からうまくできたことなど一度もない。
この不器用さには自分でもイヤになる。
音楽も音楽以外のどんなことでも、
少しできるようになるだけで、3日くらいかかってしまう。
だからもちろん、過去にいろいろと初回チャレンジしたその時に、
センスがあるね、などと言われたこともない。
それなのに、なぜ音楽の仕事なんかしていたのかというと、
一番の理由は「ただ好きだった」からだ。
私の場合、音痴とかリズム感ゼロとか、そこまででもなかったが、
いわゆる凡人の、それも不器用なほうで、どんな分野にも「得意」というのが見当たらなかった。
ただそれが、講師としては非常に役に立っていた。
私が今までに挑戦してきたことは、「なんとなくやる」ことでは、どんなこともうまくできなかった。
だから、いちいちどういう理屈でできるようになるのか、調べたり考えたり試行錯誤したりしないと先に進めなかった。
しかし、その結果、「〇〇とはこういう仕組みだったのか」と、
苦労しながら理屈として理解してきたため、他人である自分の生徒さんにも
その仕組みを伝え、その仕組みを適用してもらうことで、
「できない人でもできるようにする」ということが可能になったのだ。
「センス」は育てられる
唐突だが、君はセンスあるほう?
ない? じゃあ私の仲間だ。
もしセンスがないとしても、何より君が本気なら、そして努力と運さえあれば、飯を食えるくらいにはなれるかもしれない。
センスはある程度育てることができるからだ。
もちろん生まれつきのセンスの程度というのもあるので、
センスがあまりない人が世界一とか日本一とかになるのは、
はっきり言って無理だ。
だからと言って、プロになるのに日本一レベルになる必要もない。
そして趣味であっても、センスを伸ばすことで、よりいいプレイができるし、自分も楽しめる。
今回の記事では歌手やシンガーソングライターを目指す人のために特化した視点から「センス」について取り上げる。
基本:センスとは「思いやり」
音楽以外のことも含め、センスとは究極的には「思いやり」だ。
その時に、その場で、求められているものを察知し提供できることが
「思いやり」であり、センスなのだ。
つまり、「相手の欲しているものに気づける能力」がセンスなのだ。
だから、他人の気持ちを思いやれる能力が育たないと、
いつまでたってもセンスは育たない。
「思いやり」は技術
これは、残念ながら必ずしも善人であるという意味ではない。
悪人も「思いやり」を使う。
誰かをダマして悪いことをするためには、
「相手はこう思うだろう、こうするだろう」
という予測をしなければならない。
「相手の欲しているもの」に気づいたうえで、
それを裏切って相手に害を与えることもできてしまうのだ。
悲しいことではあるが、そういう悲しいことを憎むためにも、
「思いやり」については冷静に意味を理解してほしいのだ。
つまり「思いやり」は技術であり、道具だ。
包丁が料理の便利な道具であると同時に人を傷つけることもできるように、
良いことにも悪いことにも使える。
歌手やシンガーソングライターを夢見る君には、
善人として「思いやり」、つまりセンスを養っていってほしい。
音楽とは、有形無形の「何か」を伝えるものだ。
君が善としての思いやり=センスを発揮することで、
よいものが世界中に伝わり、世の中がよくなる。
音楽の美しい使い方のひとつだ。
少し話がそれたが、「思いやり」が技術である以上、
工夫や練習によって伸ばすことができる。
「思いやり」の力を伸ばすと、センスが育つ。
ちょっと考えてみてほしい。
愛する人の誕生日が近づいているとして、あなたはどうするだろうか?
プレゼントは?
ケーキは?
夕食は?
いろいろと考え、準備すると思う。
実は、愛情(思いやり)からいろいろと考えたり行動したりする時に、
その人間の能力が最も高くなる。
愛情から考え、行動する時、精神面と理性の足並みが揃うからだ。
この心理を、歌手やシンガーソングライターという職業に置き換えて考えてみよう。
「愛する人」が「お客さん」で、「誕生日」が「ライブ」だとする。
聴いてくれる相手にどうなってほしい?
どう歌ったら喜んでくれるだろうか?
どういう順番でどんな曲をどれくらいの曲数歌う?
どういう場所で歌ったらより楽しんでもらえるだろうか?
どんな服やメイクで歌ったらいいかな?
それがセンスアップのスタートとなる。
センスとは生まれつきの部分も少しはあるが、大部分は後から自分で知識や工夫、技術を追加していくものだ。
相手の喜んでくれそうな歌を歌うとして、
思いやりを発揮したいと思っても、
歌を1曲しか知らないのと、100曲知っているのとでは、
どちらが相手に喜んでもらえる可能性が高いだろうか?
センスを育てるためには、「思いやり」のうちの、「精神的な部分」だけを意識してはいけない。「思いやりを形にするための引き出し」を増やす必要がある。
いろんな歌を聴く、しかも深く味わって聴いいたり、いろんなライブを見たりして、「思いやりを形にするための引き出し」を増やしておくと、よりセンスが発揮できる。
さらに、音楽以外にも、いろいろな思いやりの形を知ったり、君自身が実際に受け手として体験したりするのもよいだろう。
いわゆる偉い人よりも、
君の近くにいる、目立たないけど、思いやりにあふれた普通の人たち。
そんな人たちが、君のセンスを育ててくれる尊敬すべき先生たちなのだ。
基本はこのくらいにして、歌に関するセンスについて解説していこう。
歌についてのセンスは3種類
歌についてのセンスは3種類ある。
「体のセンス」と「心のセンス」、「意思のセンス」だ。
体のセンスは技術や体力として必要なことがこなせるかというセンス。
心のセンスは歌そのもので感情を相手に伝わるように表現できるかというセンス。
意思のセンスは創意工夫、アイディア、思いやりや配慮を求められる内容に合う形にできるかというセンス。
3つのセンスは、それぞれ質が違うので、伸ばし方・会得の仕方も変わってくる。
逆に言えば、3つのうち1つのセンスばかり伸ばしても、残りの2つのセンスはあまり伸びていないというケースもありうる。
普通の人がセンスと言ってるのは、大抵は体のセンスのことを指していると思うが、例えば耳が良くても、リズム感があっても、人を心底楽しませたり、感動させられる歌が歌えるわけではない。
絶対音感って知ってる?
何の音でも、音階として感知できる能力だけど、実はこれ、歌や楽器の上手さとはあまり関係ない。
実際、私の知人で、絶対音感を持ってるのに楽器があまり上手でない人もいた。
歌や楽器で必要なのは「相対音感」のほうなんだよね・・・。
また脱線しちゃった。
3つのセンスについて、以降、ひとつずつ解説していこう。
体のセンス
体のセンスとは、歌の技術、発声、音程、リズム、演奏技術などに関するセンスだ。
体のセンスは「継続的な練習」で育てる。
一回の練習で体得できることは少なく、大部分は練習にとって少しずつ伸びるセンスだ。
技術向上はもちろん、長時間・長期間、こなしていける体力もこの範疇。
体のセンスであるだけに、生まれ持つ量も個人差が大きく、その日の体調や年齢による衰えに対しても一番影響を受けるセンスである。
体であり、練習で育てられるセンスのため、方法論・理論が最も通用しやすい。
やり方が正しいほど効率よくセンスを伸ばせるし、間違ったやり方だと変なクセがついてしまい、かえってセンスを損ねてしまう。
心のセンス
心のセンスは、継続的な基礎練習ではなく、トライ&エラーで体験・経験をしていくことで身につける。
つまり、毎日コツコツというよりも、体験して一発で身につくという度合が強いのだ。
心のセンスの代表的なものと言えば、感情を作る、とか、感情を解放する、ということだろう。
言い方を変えると、「スイッチが入る」といえばわかるだろうか。
例えば、君は、今その場で、いきなり深い悲しみを感じて泣けるだろうか。
普通の人は、悲しくもないのにすぐには泣けない。
でも、歌や演技では、自分が絶望するくらい悲しくて、嗚咽しながら泣くということもありうる。
反対方向のベクトルで言えば、君が暗い気持ちの時でも、君がコメディソングみたいなものを歌うのが仕事なら、思いっきり楽しい笑顔で歌うことも求められるだろう。
歌の中で、その歌が表現しようとする感情を解放させる、歌が伝えようとする感情を表現できるようになるということが心のセンスだ。
心のセンスがある程度以上育っている場合、歌う前は笑顔で冗談を言っていたとしても、歌うとなった瞬間に、一瞬でその歌の心の状態になることができる。
心のセンスを発揮するには、つまり、歌や演技で感情を乗せる、込める、爆発させるというのは、とにかくやってみて、自分で感情が出せた、という経験をするしかない。
練習するんじゃなくて、やってみるんじゃなくて、やるのだ。
スターウォーズのヨーダが言っていたことだね。
だから歌を志す人は、まずとにかく少しでも歌の中で感情を出せるようになることからスタートになる。
もちろん、歌で感情を出すのが苦手な人もいる。
もし君がそうなら、どういうジャンルの音楽をやるのか、一度しっかりと考えてみてもいいと思う。
失恋ソングのような、感情ありきの歌もあれば、ダンス系やコミックソングなど、重々しい感情表現を必要としないジャンルもある。
これについてもいろいろな音楽を聴くことが効果的だ。
私が生徒さんに実施していた「心のセンス」を伸ばす方法
私が現役講師だった頃は、「生徒に少女マンガを読ませ、その吹き出しのセリフを思いっきり感情を込めてセリフとして言ってもらう」という練習をよくさせていた。
演技をする人は台本でやるんだけど、そんなの素人にいきなりはできない。
台本は文章だけなので、文章以外が全て役者が想像で補わないといけないのだ。
役者の想像力ってすごいと思う。
そんなわけでマンガだと、状況や登場人物の心情が、我々のような演技素人でも想像しやすいのだ。
始めはほとんどの人が棒読みになる。
少年マンガは戦ってばっかりなので、感情が偏りがちな気がしている。その点、少女マンガだと恋愛ものが多い上、しかもちょくちょく修羅場になったりどん底になったりするので、教材としてはうってつけなのだ。
「あなたって○○なのよ!」とか「あなたが好き!だーい好き!」みたいなセリフを、もし周囲に人がいたら一斉に振り向かれる勢いでやらなければいけない。
もし君が実家の自分の部屋でマンガ読みをしたとしたら、
母親がどうしたの?みたいな感じで駆けつけてくるくらいの勢いでやることになる。
くれぐれもいうが、お母さんを心配させろっていう意味じゃない。
そんなのやっちゃだめだぞ。
思いっきりやっても周囲の人を心配させない環境でやること。
まあそんな感じで、めげずにこういうことに挑戦(練習ではない)していくうちに、とりあえずは少しずーつ、感情を出せるようになっていく。
現役講師の最後のほうは声優志望の生徒さんに教えることも多かったが、声優志望の子は最初からなかなか上手にできる人もいて、さすがだなと思ったこともあった。
このマンガ読みでヒントを得たとして、「感情を歌で出せるようになる」には、さらなる挑戦が必要になるわけだ。
さらに、試行錯誤の末に歌で感情を出すことを何回か経験できたとして、次のハードルとしては、「自分の歌で伝えた感情が実際に相手に伝わる」というのがある。
このハードルも高い。これなんてまさに練習ではどうにもならない。
本番で、相手のために真剣に歌って、どれくらい伝わったか、究極それしかない。
知り合いとか親族とか君を肯定してくれる人たちではなく、赤の他人のお客の前で何回も歌い、君の表現したいこと、伝えたいことをぶつけ、それが伝わっているのかを聴いてくれた人から感じとらないと「伝わる歌」を歌う能力は育っていかない。
まあ「伝わる歌」はある意味、歌手やシンガーソングライター、音楽をする人すべての永遠のテーマとも言えるんだけどね。
そして、そういう体験・経験を積んでいくと、ようやく「歌手の卵」と言えるくらいにはなってくるんだけど、それでも最初のうちは自分の気持ちを作るのに時間がかかる。
私も初めて自主制作のCDをレコーディングしていた時期は、
悲しい歌を歌う日だったら、朝起きた時から自分の悲しい思い出をいろいろと思い出しはじめ、
スタジオに向かう電車の中でもずーっと悲しい気持ちを深めて、
午後のレコーディングでようやっと感情を込めた歌をレコーディングする、
という感じだった。
もちろん、歌う直前にすっとその気持ちになれればよいだけなのだが、力不足だったため、できなかったのだ。
しかし、聴いてくれる人々と、そして自分自身と、逃げずに向き合って「伝わる歌」を歌えるように挑戦し続けることで、すっと気持ちを作れる、つまりスイッチが入れられるようになっていくのだ。
スタジオ代やハコ代(ライブハウスを借りるお金やチケットノルマ)だって高いので、気持ちを作るのに毎回時間がかかるようじゃ、と仕事としては厳しいんだよね。
だから、心のセンスとは、逃げずに自分から、高いハードルに挑んでいくことで、自然と身につくセンスともいえる。
また、心のセンスを育てるには、つまり体験・経験するということは、
例えば恋心を理解するには恋をするのが一番ということになる。
別れの感情も、別れを体験することで、それがどういうことかわかる。
もちろん、一人でできる経験には限界があり、全ての人間の経験は直接できないので、名優の演技を見るとか、多くの物語を読むとか、いろいろな普通の人々の話を聞いたり、よく観察したりするということも大切だ。
歌での感情は「使うもの」。溺れてはいけない。
ただ、心のセンスは、根本的に「使うもの」だ。
ある程度、歌で感情を出せるようになってくると、人によっては、
今度は感情が最優先になって、感情に溺れる、というダークサイドに落ちる危険性が出てくる。
だから、感情に溺れてはいけない。
感情によって歌の良し悪しが決まるように勘違いしてはいけない。
良い歌を聴きてと分かち合うために、歌に感情をのせるのだ。
感情に溺れ、なんでも感情まかせにして、感情に自分が支配されていたら仕事にならない。
君が感情の起伏が激しくなって繊細になりすぎ、何かあると歌えません、みたいになったら、一緒に仕事するほうはいい迷惑だ。
感情は感傷だ。
歌う時は、
「感情豊かな自分」とともに、
「感傷は感傷として冷静に客観的に認識できる自分」も、
常に両方の自分を心の中に存在させていなければいけない。
聴いている人の前で歌っているのに、自分だけの感情が独り歩きするなんて、観客が置いてきぼりになるなんて、まさにただの自己満足だ。
趣味で一人だけで歌っているのなら、それでもいいけど。
ちなみに私は現役の頃、聴く人を涙させる歌をよく歌っていたが、歌っている時の本人としては全く普通の感情だったりする。
もちろん歌いながら気持ちが高まって歌声が涙声に近くなることすらあるわけだが、それでも悲しさで冷静さを失うわけではない。技術だからだ。
一曲のどの部分で、どの音でどのくらい「泣く」のか、全て制御する。
そうでなければ聴く人を泣かせられない。
私の師匠はこういうのを「お涙ちょうだい」と言っていた。
音楽で表現する感情の種類の中で、「泣ける歌」つまり「お涙ちょうだい」は、一番簡単なほうなのだ。
大体、「泣ける歌」で泣く人は、多くの場合、歌を聴くうちに、自分自身の悲しい思い出がよみがえってきて泣くのだ。本人は自覚していないことがほとんどだけどね。
もし君が苦労の末、歌で感情を出せるようになり、「泣ける歌」が歌えるようになったら、そこで満足しないようにしよう。
歌で表現できることは「お涙ちょうだい」だけではなく、それはそれは広く、深い。
そうじゃなきゃ、ねえ。
意思のセンス
意思のセンスは、「思いやり」を根本とした基本的なセンスで、相手を思いやることで生まれる創意工夫とその行動、そして正解を形にするための引き出しを増やすことなどになる。
せっかく思いやりがあっても、正解を知らなければ間違えてしまい、結果的に相手の望んでいないものを提供してしまうことになる。
意思のセンスはとにかく仕事としてやってみることが一番身につく。
本来は仕事でなくても、相手(客)のためにベストを尽くすことで身につくことだと思う。
しかし、友人や親族が相手だと受け取る側も優しいので、
どうしても甘えてしまい、実際はあまり意思のセンスは育たないと思う。
仕事としてやってみるというのは、
赤の他人からお金をもらい、仕事をして、評価を受けるということ。
お金が絡んでくるので、仕事でしか得られない厳しさ・辛さがある。
そのかわり、相手に貢献できた時は、
仕事でしか得られない喜びや、やり遂げた自負心も生まれる。
同じ音楽でも、ジャンルによって正解が全部、全く違う。
音楽の中で、歌だけで言っても、子供向け、ポップス、JAZZ、演歌、民謡など、正解は全部違ってくる。
今まで歌ものばっかり作ってきた人が、いきなりゲーム音楽で100点を取るのは不可能だと思う。そんなに甘くはない。
たとえサウンドクリエイターとして十分な技術を持っていて、同時に廃人クラスのゲーマーだとしても、歌ものをやっていた人が、未経験でゲーム音楽を作って納品したとして、60点取れればいいと思う。それくらい違うのだ。
その業界をよく知り、求められている正解を知り、そしてそれを提供できる技術とセンスを身につけて初めて、お金をもらえるレベルの音楽を提供できるようになるのだ。
そういうジャンルの話もいつか記事として取り上げられるといいと思う。
これは何の職業でも共通のものかも知れない。
相手の期待越えを目指そう。
相手の欲しいものを提供する。それに成功すれば次も仕事が来る。
具体的に言えば、相手がお金を出して発注してきた場合、
相手の心の中には一定の期待値みたいなものがある。
プロはその期待値ぴったりの仕事ができても、褒められない。
プロが仕事ができるのは当たり前なのだ。
相手の期待値を超える内容を提供できるた場合にのみ、
次の仕事がもらえるようになる。
相手は何を求めているのか?
そもそも「相手」とは誰なのか?
高級レストランが正解の時もあれば、
煙草の煙モワモワの汚い立ち飲み居酒屋が正解の場合もある。
そして押し付けは嫌がられる。
「思いやり」と「賢さ」を研ぎ澄ませ
ここで私の子どもの頃の話。
君はどう思うかな。
私は子どものこと、サッカーボールを親にねだった。
1か月後くらい待っていると、買ってきてくれた。
ただ、今は詳しく思い出せないが、そのサッカーボールは公式球ではなかった。
サッカーボールではあったが、公式球に似ている安物のボールだった。
私は「ちぇっ」と思った。
親の愛情も思いやれない子どもの私ももちろんセンスはないのだが、
つまり、センスというのは、思いやりの気持ちはもちろんとして、
本当に欲しがっているものを間違えずに探せる知識や、実現できる技量や資金も必要なのだ。
自分の親は、おそらく「なんとなくコレかな?」というのを選んだか、店員に公式球を教えてもらった上で、「うちの子はこれで充分だろう」と思ったか、ともかくそんな感じで廉価なボールを買ったのだろう。
家庭の話としてはよくある話で、ともかく探して買ってきた親の愛情に感謝するべきだろうし、微笑ましいというか、経済的というか、まあそんな話であるし、それでいい。
しかし、これが仕事だとすると、やっぱり
「思いやりで行動しました。でもハズしました」では、
プロとして生き残っていくための、真の「思いやり=センス」とは言えないのだ。
意思のセンス、つまり相手が本音で求めている、つまりお金を払ってもらえる音を提供できるようになるには、相手のことを思いやるのは当たり前として、さらにいろいろと勉強して知識と技術をつけていくことでしか、その正解には近づけない。
君は普段からそのことを考えて、やることひとつひとつに、
思いやりと賢さを研ぎ澄ませていこう。
意志のセンスの育て方
音楽の仕事をもらう前の君の場合、どうやって意志のセンスを育てればいいのか。
まず、自分でライブをやるにしろ、自主制作盤を作るにしろ、必ずお金をもらおう。
それも100円とかではなく、最低でも1000円か1500円はもらおう。
そうすることで相手も、この金額でこの音、というふうに本気度を上げて聴いてくれる。
そしてお金を払ってライブに来てもらっても1回目はノーカウントだ。
そのあと同じお客を何回呼べるか、そして、2回目以降でも飽きさせずにどれだけお客を楽しませられるか、
そこに主眼を置いて挑戦することで、意志のセンスが研ぎ澄まされるだろう。
もう一つの方法としては、ライブを設定したら、そのライブの当日、路上で知らない人を誘って、その人にお金を払ってライブを見てもらおう。
大変だと思う?
うん大変だよ。
その場で軽く演奏する必要だってあるかもしれない。
でもさ、聴いていただけるように売り込んで、お客様にお金を払ってもらって、しかも相手の時間を少しもらって歌を聴かせるって、
それは音楽の仕事そのものなんだよね。
こういう「生身の人間どうしがぶつからないと育たない部分」は、
配信ではなかなか実感できないかもしれない。
視聴者は基本的にお金払わないし。
見方を変えると、配信をメインでやっている人も、センスを高めるために、ライブでも活動するとか、あくまでもゴールはライブハウスに客を呼ぶという目標は具体的に設定しての配信というのも有効かもしれない。
で、運よく仕事がもらえそうなら、ダマシに注意しつつ積極的に挑戦し、評価されたり忘れられたりしていこう。
心をこめるということ
最後に、センスを高めるヒントとして
「心をこめる」とは何かについて取り上げよう。
想像してみよう。
定食屋に入ってカレーを注文する。
定食屋で働く女性がカレーを持ってきた。
君だったら、以下のどちらがより美味しく感じるだろうか?
①笑顔で「はーいカレーね。お待ちどうさまでした。どうぞ。」と言って差し出してくれる。
②不機嫌な顔で何も言わずに机の上にドン!と乱暴に置かれる。
カレー自体が変わらないのなら、味は同じはず。
でも明らかに①のほうが美味しく感じる。
これをさせているのが、「心」だ。
相手のことを思いやって、少しでも美味しく食べてほしいという心。
心は、材料としては料理に入れられない。
しかし、そういう心をずっと持ちながら料理をし、盛り付け、お客の前に持っていき、ひと声かける。
心をこめるというのはそういうことだ。
お客としても、カレーの味と、その店員さんの心とをそれぞれに感じ、両方を合わせて味わう。
そんなに大げさなことではない。
むしろとても小さいことで、誰にでもできる。
そういうとても小さいことを積み重ねる、と言ったほうが正しい。
以下に参考としてマザー・テレサの言葉を引用する。
小さなことを大きな愛をもって行うのです。
大事なのはどれだけたくさん行うかではなく、
行うときにどれだけ愛を注ぐかです。
どれだけ与えるかではなく、
与えるときにどれだけ愛を注ぐかです。
歌で言えば、一曲入魂、いや一音入魂というところか。
心をこめようとすると、歌の一瞬の表情を、空気を、言葉の扱いを、ほんの少し変える。
それが丁寧に積み重なると、波となって相手に伝わり浸透していく。
定食屋さんなら笑顔で「お待ちどうさま」、
寿司屋はハキハキと「あいお待ち!!」、
お化け屋敷なら不審な感じで「どうなっても知らないよ~」ということになる。
あなたの取り組む作品ではどうなるだろうか?
非効率の中にヒントがあるかも
こんなことをあれこれ考えてやっていたら、効率が悪い。
カレーを配膳するのに、言葉がけなんて、する必要はないはずなのだ。
でも、心をこめる、思いやりを発揮するというのは、時に非効率な場合もある。
音楽は自分が作るので、経費の多くは人件費だ。
短い時間で使ったほうが儲かるのだ。
しかし、この非効率の中に、楽しさや人生の喜び、生きる甲斐があるのだ。
音楽業界って、そんな非効率を愛しているバカどもが集まった業界という側面もあるのかもしれない。
この儲けの少ないタフな業界の中に、
君が少しでも仕事を楽しめる「何か」を見つけるためのヒントにしてもらえると嬉しい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
