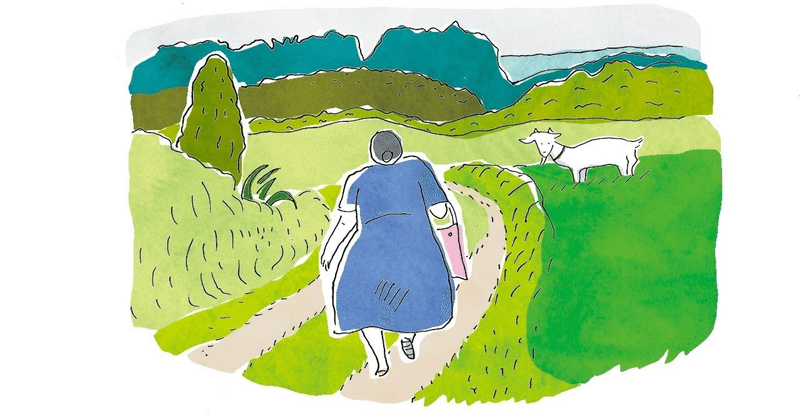
おばあちゃんたちが視ているものは。
僕はいま石川県の田舎に帰って、祖父母の家で生活している。
祖父が93歳で、祖母が87歳だった。
祖父の方は聴覚が仕事をサボったり、認知機能が白昼夢をみはじめたりすることがあるが、歳のことを考えれば二人ともまだまだ元気だった。
彼はしばしば『デイサービス』という謎の機関に連れ去られることがあった。
夕飯時に解放されるときもあれば、半月も帰ってこないときもあった。
おまんじゅうを食べるので忙しいのだと思う。たぶん。
そういうとき僕と祖母は家の片付けをしたり、適当に出かけたりするのだった。
祖父母は二ヶ月もの間、住み慣れた自分たちの土地へ帰ることができず、土地勘のない、知り合いもいない金沢での避難生活を余儀なくされていた。
そういう状況だったので、僕を連れて家に帰ってきた二人の活き活きとした姿がとても印象的だった。
まさに水を得た魚という感じだった。
祖母という年老いた魚は、そのまま家の外の住み慣れたサンゴ礁を泳ぎ回り、知った顔を捕まえては旧交を温めていた。
同行しているとき、僕は金魚のフンのようについていき、彼女たちの世間話に耳を傾けていることしかできなかった。
状況が状況だけに、その世間話ひとつとっても悲痛な色を帯びていた。
しかし僕が不思議なのは、彼女たちのネットワークだった。
例えば近所のスーパーに買い物に行くのでも、最低二人くらいは祖母の知り合いに出くわす。
ほとんどが老齢のおばあちゃんだった。
そしてほとんどのおばあちゃんが、マスクと帽子を被っていた。
北陸の冬は厳しいので無理もない。それは祖母とて例外じゃなかった。
孫の僕ですら、彼女の着ている服を覚えておかなくては、はぐれたときに見分けがつかないくらいだった。
ただ彼女たちには、いくら顔が隠れていようとお互いが知り合いだということがわかるようなのだ。
迷いなく近づいていっては、肩をたたき、言葉を交わす。
明らかに僕の視えていないものを認識しあっているのだった。
例えばそれは、達人同士が対面したときの空気に近いのかもしれない。
体の重心、僅かな挙動、視線、息づかい。
そういった些細な情報で相手の力量を判断する境地。
一般人には、彼らはただ向き合っているだけに見える。
しかし、そこには知られざる彼らだけの闘いがあるのだった。
隣にいる、なにやら訳知り顔の老人がささやくのだった。
『もう始まっておる……』
だとしたら期限付きとはいえ、これから田舎で暮らしていこうとする僕のような身であれば、そのスキルをいち早く身に着けなければいけない。
さもなくば、僕だけが彼女らに情報を抜き取られ、身分を明かし、技の起こりを見透かされ、乙川さんちの夕食を知られることになる。
それはあまりにも一方的すぎるのだった。
ほら、また祖母が声をかけた。
「あら、あんた!」
お互いの視線がぶつかる。
まばたきの間の情報戦。
僕のまだ見ぬ境地。
喉から染み出したひとつぶの汗の粒が、僕の体を下っていった。
『もう始まっておる……』
その場を制したのは。
「誰や?」
相手のおばあちゃんは、祖母の姿をまじまじとみつめた。
「ありゃ、ごめん。知り合いに似とったもんで」
祖母は恥ずかしそうにそう言った。
達人、敗北。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
