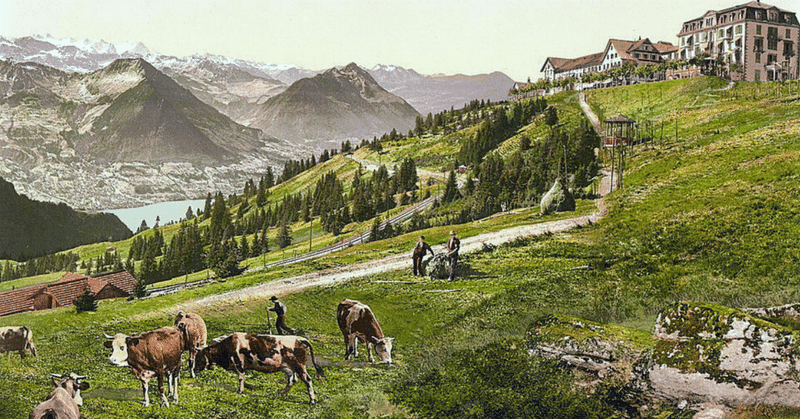
ハートランドの遙かなる日々 第二章 牧場の家
この日の帰り道はエルハルトの予想の通りに雨が降って来た。
四人の兄弟達は雨に降られてびしょ濡れになって家に辿り着いた。
「あーあ。大事なお洋服に泥が……」
アフラは自慢の衣装が泥に汚れてすっかり悄気てしまった。
「ほら、四人とも早く服を着替えて」
母のカリーナはマリウスを着替えさせた後、一人しょぼくれて刺繍のベストの汚れを洗っているアフラを見つけた。
「春祭りの大事な衣装なのに……」
「山に洗濯してもらったと思えばいいのよ。あとでお母さんが洗ってあげるから」
「うん。でもまたすぐ着て行かなきゃいけないの」
アフラは着替えながら、今日会ったイサベラ達のことを母に話した。そして、お詫びに貰ったフルーツの篭を母に渡した。
「こんなに! そんなことがあったの。でも羊が見付かって何よりだわ」
母はアフラの髪を拭きながら言った。
「アル兄なんてイサベラさん達にすごい剣幕で怒り出しちゃったんだから」
「へえ。それは意外ね。何か言われたのかしら」
「それがね。今度お城へ来てって言われたって言ったら怒り出しちゃったの。あたしが連れて行かれると思ったのね。少しお友達になっただけなのに。ねえ。いいでしょう? こんどお城へ行っても」
母のカリーナはアルノルトの行動の意味がようやくわかった。
「お城へ呼ばれて行った女の子は殆ど帰って来ないのよ」
「どうして?」
「お城の使用人になってしまうの。生活は見違える程豊かで、その方が楽だから仕方ないのかも知れないわ」
「あたしはまだ使用人になんてなれないわ……」
「お姫さまのお話相手も立派な使用人なのよ」
「そんな。決して連れ去ったりしないって天に誓って言ったのよ」
「お前はどうなの? お城の暮らしよりここがいいって言える?」
「わからない……けど」
「でしょう? お城はとてもきらびやかで、身分も高くなるし、俸禄も貰えるわ。だから正しい判断が出来なくなってしまうのよ。残された家族は辛いわ。村の敵の家に嫁ぐようなものだから……。それにお城にいられるのも若いうちだけ。年を取ると里に帰されて、その頃には行き遅れたおばさんよ」
「そんな。あたしは使用人になんてならないもん。あくまでもお友達としてよ。イサベラさんはとてもいい人なの。私をお友達って言ってくれたのよ。ここにも見学に来たいって言うの。だからお返しに約束をしたの」
「お父さんはきっと反対するわね」
「あたしもその時そう思ったの………だからお母さんから上手く言ってくれない?」
「お城の暮らしに憧れて、風習に染まってしまったりしない?」
「誓ってしない」
「どんなに良くして貰って引き留められても、必ず帰って来れる?」
「もちろん帰ってくる。だからお願い」
カリーナはアフラの意思の堅い目を見て、止めることを諦めた。
「じゃあそうお父さんに話してみるわ」
「ありがとう。お母さん。お母さんは話がわかるから大好き」
アフラは母の肩に抱きついた。アフラの手に触れた母は、異変に気が付き、
「手が熱いわ。あなた熱があるんじゃない?」と手や顔に手を当てた。
「きっと、山でびしょ濡れになったからだわ。すごく寒かったの」
手を当てたアフラの額はやはり少し熱を帯びていた。
「大変。今日はもう早くお休みなさい。後で食事は届けるから」
「はい。お母さん。少し疲れたと思ってたの」
アフラは早速ベッドに入って横になった。
カリーナが広間へ戻ると、他の家族達は夕食を待ち構えていた。
父親のブルクハルト・シュッペルはテーブルに着いて言った。
「もう夕食というのに、アフラはどうしたんだ?」
「少し熱があるようなの。今日はもう早めに休ませたわ」
「アフラが熱?」とアルノルトは少し驚いて言った。
エルハルトも心配そうに頷いた。
「そう言えば、帰りは歩くのが少し遅かった」
「そうか。じゃあ仕方ない。アフラにはあとで食事を届けてやってくれ。先にお祈りを始めよう」
ブルクハルトのその声で一同は手を合わせ、食事前の祈りが始まった。
ブルクハルトはビュルグレン村の管区長、ラントアーマンの地位にあり、それは大半の土地を修道院領としているこのウーリ州の教会管区の事務長であり、村の判事でもあった。アーマンは司法廷吏であるために自由民でも貴族に列せられ、地位は村長より高かったが、教会に属し、自治の州であるウーリでは管区長は面目上のものでしかなく、平和な村には事件が起こることも少なく、村の共有財産である共同牧場の管理者としての仕事が主なものとなっていた。
夕食を食べながら、アルノルトは父のブルクハルトに今日のことを話した。
ブルクハルトはアルノルトの話に感心深げに頷いて言った。
「そんなことがあったのか。アルノルト。お前も一人前になったな。よく羊を見付けて来てくれた」
「羊を見付けたのはアフラだよ」
そう言うアルノルトにエルハルトも言った。
「羊を逃がしたのもな」
「そうだったか。貴族の娘にもよくぞ言ってくれた。アフラをよく守ってくれたな」
「でもアフラはお城に招かれて浮かれていたよ」
「あんな非情な奴らのところに誰が好んで行くものか。そうだろう」
カリーナは夫のブルクハルトにわざと明るく言った。
「子供は大人の垣根を簡単に越えるものね。アフラはその貴族の子とお友達になったそうよ。お城にお招きを受けて行く約束をしたそうなの」
「約束したって、アフラは行くって言っているのか?」
「ええ。衣装を見せに行くそうよ。いけないかしら」
「ううむ。どこの貴族だそれは……それにもよる。帰って来れないなんてことになったら大変だからな」
「そうね。さっきどんな優遇を受けても帰って来れる?って聞いたら、友達として行くだけだから必ず帰って来るだって」
「そんなこと気まぐれな貴族のすることだ。判らないじゃないか。アフラを呼んで来い」
「あの子は熱を出して寝てるの。起こさないであげて」
アルノルトは父に言った。
「その貴族の子は今度の件で、神にかけてこの村の何ものをも奪わないって誓ったんだ。アフラを家族から連れ去らないとも言っていた。この村が好きだそうだから悪い人ではないよ」
「そうか。しかし、どこの娘なんだその子は……」
ブルクハルトは貰った篭をしげしげと見つめ、その篭に付いていた飾りを見て、唸った。
「赤い獅子! この紋章はまさか………ハプスブルク家……」
「ハプスブルクって?」
カリーナは聞き慣れない言葉に首を傾げた。
「知らないのか? 神聖ローマ帝国の新しい王家だ。ルードルフ王の紋章だ」
「王様ですって!」
アルノルトは気品のあるイサベラの姿を思い浮かべて言った。
「じゃあ、あの子は………王家の子?」
「王位に就いて、ルードルフ王はこの辺りを買い漁っている。山向こうの州のオプヴァルデンはハプスブルク王家に買い取られ、高い税を取られるようになって、ザールネンに大きな城まで出来た。だからハプスブルク関係者がよく来るようになって、皆騒ぎ出してな。村のゲマインデでも問題に上がっているんだ」
ゲマインデとは村の自治のために自由民が集まる青空会議の事を言う。村のことは全てこのゲマインデの上で決められた。ウーリが自治州を標榜するのは、このゲマインデでの直接民主主義の体制があるからでもあった。
エルハルトは驚いて言った。
「じゃあルードルフ王はこのウーリも買おうとしてるの?」
「ウーリは前王以来の特許状を頂いている自治州だ。領主権も殆どを修道院に置いている。だから誰も手を出せなかった。でもルードルフ王は今までの王とは違う。オプヴァルデンやニートヴァルデンではそうした土地にも目を付けて、修道院の権利を集めているらしい」
「ウーリも危ないって言うことだね。父さん」
「そうだ。我々にとってハプスブルクの王は危険な人物だ。そんなところにのこのこ出ていったら、目を付けられるのが落ちだ。絶対アフラを城へ行かすわけにはいかんぞ」
「そうですね。アフラには私から言って聞かせます」
カリーナは複雑な笑顔でそう言った。
アフラの熱は次の日になっても、またその次の日になっても引くことはなく、次第に熱は高くなっていった。そんな妹を心配しながらも、エルハルトとアルノルトは今日も早朝から羊の放牧に出かけ、父もまた牛の世話に出かけた。
母のカリーナは残って看病していたが、夕食の買い出しに行く仕事があった。
「マリウスー。マリウス。少しアフラの看病をしていておくれ」
「僕どうすればいいの?」
「額のおしぼりが熱くなったら水に浸して替えてあげてね。あとはちょうど果物があるから、アフラが欲しがったら食べさせてあげて」
「わかった」
「じゃあお留守番をお願いね」
母が家を出て行くと、マリウスはアフラの額のおしぼりを替えたり、汗を拭いたりして、付きっきりで看病をした。
マリウスはアフラの額に時々触ってみた。
「お姉ちゃんの頭、熱いなあ」
おしぼりは思ったよりもすぐに熱くなってしまうので、頻繁に替えなくてはならなかった。
そうしていると、外に立派な白亜の馬車がやって来て玄関先に止まった。そしてそこから降りてきた御者が玄関のドアを叩いた。
マリウスはドアを開けて訪れた客に言った。
「誰?」
「ここはアフラ・シュッペルさんのお宅ですかな?」
「そうだよ」
「アフラさんはご在宅かな?」
「いるよ。でも熱を出して寝てる。僕、看病してるの」
「そうですか。それは大変お労しいことです。では、ユッテ様とイサベラ・アニエス・ド・カペー様からご招待があったことだけお伝え下さい」
「アニさんどっかへ? お兄ちゃんは今いないよ」
「ゆっくり言います。イサベラ・アニエス・ド・カペーです」
「イサベラ・アニさんー・どカッぺー? ど田舎者! まあこんな山じゃあしょうがないね」
「違います! 唯一イサベラという名前だけは合ってますので、その名前だけお伝え下さい」
「イサベラ?」
「そう! もう一つ言うと、イサベラ様を呼び捨てにしてはいけません」
「イサベラ様?」
「そうです。そうです。その名を確とお伝え下さい。それともう一つ、ユッテ様とイサベラ様は明日ビュルグレンの教会へご来臨になります。それも併せてアフラ様にお伝え願います。では失礼致します」
御者は馬車に戻って、勢いよく駆け出した。
マリウスはこの事を伝えようと、姉のいる寝室へと走って行った。伝言の言葉を反芻してふと首を捻った。
(ごらいりんって何だろう?)
アフラはまだ熱にうなされて眠っている。
「お姉ちゃん、お姉ちゃん!」
マリウスは額から落ちていたおしぼりを取り替えて、顔に滲む汗を拭いてあげた。
しばらくして、アフラは目を覚ました。目を覚ましたアフラは寝ぼけ声で言った。
「マリウス……頭が痛いわ……水を頂戴」
「うん。リンゴも食べる?」
「うん………」
水を持って来ようとして、マリウスは振り向いた。
「あのね。さっき見たこともない馬車が来たよ」
「馬車………」
「えーと何て言ったっけ。アニさんじゃなくて、エイサラべーじゃなくて」
「イサベラさん………」
「そう! その人からご招待だって」
「やっぱり来たのね………それで何て?」
「兄ちゃん田舎者だって。熱で寝てるって言ったらすぐ帰っちゃった」
「そう。悪いことしたわ………」
「あとねえ。明日教会の鐘が鳴るんだって」
「教会?」
「うん。ごらりんごらりんって」
「ごらりん?」
すると玄関から再びノックの音がする。
「あっ。またお客だ。僕、行ってくる」
玄関に訪れたのは、シュウィーツに住むブルクハルトの友人、コンラート・シュタウファッハだった。シュタウファッハはシュウィーツでアーマンの地位にあった。
「シュタウファッハさん。こんにちは」
「こんにちは。マリウス。元気そうだね」
「でも、お姉ちゃんは病気で寝てるの。僕、看病してるの」
「そうか。それは大変だな。こちらも少し大変なんだ。お父さんはいるかな?」
「お父さんは共同牧場の方だよ」
「そうか。行ってみるよ。有難う」
マリウスは出て行く客を見送ると、水を汲んでアフラの所へ戻った。
「お姉ちゃん。水だよ」
その時アフラはもう深く眠っていた。
「もう。せっかく水とリンゴ持って来たのに。リンゴ食べちゃうぞー。知らないぞー」
マリウスはそう言って、林檎を剥きにかかった。
共同牧場へ行ったシュタウファッハは、そこでカリーナに会ってブルクハルトの居場所を聞いた。
「主人は干し草を集めに行きました。きっとあの丘の辺りですわ」
シュタウファッハは牛を避けながら牧草地を歩いて行った。丘の近くまでくると、木の陰の岩に腰掛けるブルクハルトを見つけた。
「おーい。ブルクハルト!」
シュタウファッハはブルクハルトに手を振った。
「おお! これはシュタウファッハ! 久しぶりだな。まあここに座って採れたてのミルクでもどうだ」
シュタウファッハとブルクハルトは、その場で岩に座り込み、近況を話し合った。
「シュタウファッハよ、わざわざシュウィーツから訪ねてくるなんて、一体何があったんだ?」
「それが大変なんだ。ラッペルスヴィル家の断絶が決定した」
「ご実姉のエリーゼ様が女伯継承するんじゃなかったのか?」
「それがだ。若い女伯の継承を王が許可しなかったのだ」
「それは横暴だな。修道院が既に認めていたし、女伯継承なんて時にあることじゃないか」
「女伯継承にも条件がある。婿がいること、もしくは次代を継ぐ男児がある事だ。残念ながら未婚のエリーザベト様には二つとも無い。あまりに若い弟君の急逝が惜しまれるな」
「未婚なら、これから婿を迎える事だって出来るはずだ。時間を与えるべきだろう?」
「その通りだ。結婚の予定があるなら、考慮の余地はあるはずだ。新しい王は断絶した貴族の領土を掠め取って来たからな。また狙っているのさ」
「ラッペルスヴィル家と言えばウーリにも別邸と農園があるぞ」
「ああ。あの土地はヴェッティンゲン修道院預かりになっていたからそのまま保持するらしい。チューリヒ湖畔の本領地もそのままだ。だが他の領主権やアインジーデルン修道院と聖母聖堂の守護権は没収になったんだ」
「そうか。だが、修道院の守護権なんて、うちはそんなに騒ぐことは無いじゃないか?」
「それが大ありだ。両修道院の守護権は財産管理と人事権が含まれる。それが王の一時預かりとなるんだ。ウーリの多くは面目上、聖母聖堂の領地だろう? 人事権でもお前の首くらいは飛ばせるわけだ」
「何だって! じゃあ、このウーリもシュウィーツのように重税が掛けられるのか?」
「このままだといずれ……そういうことになるだろう」
「そういうことって……シュタウファッハよ。ウーリは一体どうなってしまうのだ」
シュタウファッハは改めて状況を説明した。
「ウーリは今、特許状によって、土地の税や人頭税は無いな」
「そうだ。税はラントの共益費と修道院に献納する一割の税だけだ」
「それに王領の税が上乗せして掛かってくるだろう。人頭税と土地の税だ。収穫に対する税も徴収されるだろう。戦争があればさらに上乗せだ。人も徴発される」
「そんな! 二重取り、三重取りじゃないか」
「住民は修道院と王とさらにラントにも税を払うことになるだろう。とても払えないという人が溢れて、大混乱になる。そうなれば、まず払わないのは罰の少ないラントの方だ」
「それではウーリの自治はとてもやって行けなくなる。どうすればいいんだ……」
頭を抱えるブルクハルトにシュタウファッハは言った。
「そこでだ。私に腹案がある」
ブルクハルトは目の色を変えて向き直った。
「どんな案だ?」
「ホーンベルク伯をラッペルスヴィル家の後継者として擁立するのだ」
「ホーンベルク伯?」
「ホーンベルク伯はアインジーデルン修道院縁の方だ。前王家ホーエンシュタウフェン家の血を引いている。おそらく何処からも反対されず上手く纏まる」
「しかし、どうやって?」
「これはまだ秘密の話しだが、さっきの婿の話だ。ホーンベルク伯には跡取りがいなくてな。親族を養子に取っている。ルーディック二世と言うんだ。この方とエリーゼ様を結婚させるのさ」
「それは名案だが、出来るのか?」
「合意さえしてもらえればな。ただ、少しでも疑われるとこの話はダメになる。特に王家に漏れれば何をされるか判ったものではない。秘密裏に進めなければならない。それにこの話を持って行くのは、縁遠い私だと残念ながら不適任だ。信用が足りない。ウーリのアーマンのアッティングハウゼンさんなら、ラッペルスヴィル家とも、ホーンベルク家とも昵懇にしていると聞いた」
「そうか、アッティングハウゼンさんか! あの人ならいつもはアルトドルフの宿駅にいるはずだ。案内しよう」
長話をしていると、放牧を終えたエルハルトとアルノルトが羊を連れて帰って来た。エルハルトは遠くから父を認めて手の平を上げた。
「ただいま!」
「おお。あれは我が息子達だ」
エルハルトとアルノルトは近くまで来ると、客の姿を認め挨拶をした。
「こんにちはシュタウファッハさん」
「こんにちは」
シュタウファッハはエルハルトとアルノルトを見て言った。
「やあやあ。しばらく見ないうちに二人とも立派になったな。エルハルトの方は背がもう父を抜いたか。ブルクハルトはいつ引退しても大丈夫なんじゃないか? いい跡継ぎに恵まれたものだ」
と言いつつシュタウファッハはエルハルトの肩を叩いている。
「まだまだ父には敵いません」
「これから村は自立のため、君たち若い人が頼りになる時が来るだろう。お父さんも忙しくなる。家を支えて頑張って欲しい」
いつもより熱の籠もった言葉にエルハルトは戸惑った。
「はい。シュタウファッハさん………ところで何かあったのですか?」
「ハプスブルク王家との争いが始まるかもしれない。ウーリの諸権利が一時ながらハプスブルク家の手に移ったのだ」
「何ですって!」
ブルクハルトはエルハルトに言った。
「エルハルト、これから村長のところへ言って、夕方に広場で緊急ゲマインデを開きたいと伝えて欲しい。私達はこれから話を纏めて来なければならない」
「わかった。羊を戻したらすぐ行って来るよ」
「シュタウファッハ。早速だが行こうではないか。馬車を出そう」
四人は牧舎へ帰り、その後ブルクハルトとシュタウファッハは荷馬車に乗って山を下った。
二人はアルトドルフの外れにある、ヴェルナー・フォン・アッティングハウゼンの宿駅を訪ねた。道の険しいザンクト・ゴットハルト峠を越える人は、必ずメイン通りにあるこの宿駅で泊まり、荷を運ぶ馬や強力の手配をした。そのための費用に加え、峠の通行料もここで一括精算するのが常であった。
二人の訪問を受けて、アッティングハウゼンはウーリの古株のアーマンらしく、努めて落ち着いて言った。
「その事か。まあ落ち着いてくれ。実は昨日、代理執政官とラッペルスヴィル家のお嬢さん、エリーゼ様がここに来たのだ」
「何だって! で、何と言われたのだ」
「その代理人によると、ラッペルスヴィル伯が亡くなって、エリーザべート様の継承資格をハプスブルクのルドルフ王は認めず、その本領地以外の諸権利や修道院の守護権は王家の預かりとなったそうだ。移管されたその権利により、ウーリの多くを占める修道院の領地はその新しく代理執政官に任命されたその者が管理するという事だった」
「まさか! 多くの土地は領主が入らないように、面目として聖母聖堂に預けて、そのまま自治体の共有地として仕立てているんだ。それを取られると言うのか?」
「エリーゼ様は全ては代理人に任せるとの事だった。その時に渡された聖母聖堂からの書面によると、領有地の管理をその代理人に委任するとの事でな。まだ様子を見ないと判らないが、上位の権利は渡ってしまったんじゃ」
「そんなことになるとは……」
シュタウファッハは沈痛な面持ちで言った。
「シュウィーツのアインジーデルン修道院もラッペルスヴィル伯の守護権下なので、全く同じような事態が起こっているのです。その代理人は王の腹心で、実質はハプスブルク家に領地と守護権が渡ったのです」
アッティングハウゼンは悲痛な声で言った。
「やはりハプスブルク家、ルードルフ王か。実は、取られる権利はそれだけではないのだ。ザンクト・ゴットハルト峠のあるウルゼレンは、ルードルフ王の子のアルプレヒトの管理地になった。ハプスブルクはザンクト・ゴットハルト峠の権利をも奪うつもりだろう。そして国境には関所が作られて通行税が取られるそうだ。そうなると、ここで集めている通行料は二重取りの謗りを受けて取れなくなって行くだろう」
「そんな馬鹿な! ウーリは開発者をウルゼレンに集めながら長年あの峠を開発して道路と橋を整備して来たんだ。その通行料はウチで貰わなければ割が合わないじゃないか。自治の発足も峠の開発事業で始まったようなものだ。それがそんな簡単に取られるって言うのか!」
「儂の家もそうだが、町の多くの民は峠の工事や荷運びをし、通行料で成り立って来た。これはウーリの命を取られるに等しい! これを取られて儂等はどうすれば良いのだ……」
アッティングハウゼンは机に手を突き、嘆きのあまり涙さえ見せた。
シュタウファッハは怒りを覚えて言った。
「王になったとは言え、本領地の少ないハプスブルク家は、領地を少しでも広げたいのです。我がシュウィーツの大半の土地も領主であったキーブルク家の断絶を理由に手中に収め、残りの土地も買い漁っていましたが、ウーリにもここまで横暴をするとは……」
「しかし、今さらどうすることも出来んのだ。王家が相手ではな……」
頭を抱えるアッティングハウゼンにシュタウファッハは言った。
「私にひとつ策があります。ご協力頂けますかな?」
アッティングハウゼンは目の色を変えて向き直った。
「対抗策があるとおっしゃるのか?」
シュタウファッハは頷いて言った。
「ホーンベルク伯にラッペルスヴィル家の後継者となって頂けるよう働きかけるのです。これは婚儀によってです」
「フリードリヒ・フォン・ホーンベルク伯か! だが確か伯爵には子が無かったはずだが」
「仰るとおりです。跡継ぎがおらず断絶に瀕したホーンベルク家は、御親類の子を母御様が猶子にしています」
「アーデル様か」
「母御様をご存じで?」
「よく知っている。先代の旦那様からの家族ぐるみのお付き合いじゃ。あのお方なら話が分かる方じゃ」
「そうでしたか。それは話が早い。そのアーデル様の御猶子、ルーディック様とエリーゼ様とのご婚儀を持ちかけるのです」
「その手があったか!」
「この婚姻が成れば両家を併せてチューリヒ湖からバーゼルまでが影響圏になるでしょう。そこに我々も加わる事になれば王を包囲する形になります」
「それはすごい目論見だ。ホーンベルク家は前王家のホーエン=シュタウフェン家の血を引いている。家柄では王家とも張り合えるだろう」
「その通りです。自慢になりますが私も実はシュタウフェン家の遠縁で、ホーンベルク伯とは些か縁があるのです」
「おお、そうであったか。どおりで名が似ている」
「この縁談は断絶の危機に瀕した両家が家領安泰となる上、家系を見てもこれ以上無いものです。先代のホーンベルク家はハプスブルク家とも縁戚関係があります。王家も反対はしますまい。これが成った暁には、両家はその恩義で自治の権利を保護してくれる事でしょう」
「思った以上にこれは良い話しだ!」
ブルクハルトが手を打って言った。
「アッティングハウゼンさんはホーンベルク伯とも昵懇の仲でしたでしょう?」
アッティングハウゼンは顎髭を撫でて頷いた。
「うむ。なにせバーゼルは山越えの入り口、ここウーリは出口だからのう。よく連絡を取るのじゃ。それに以前はラッペルスヴィル家ともウーリに別邸がある関係で家族ぐるみのつき合いじゃった。エリーゼお嬢さんも小さい頃からよく知っている。よくここへ来て遊んで行ったものだ」
シュタウファッハが手を大きく広げて言った。
「それは願っても無い幸運。このキューピット役は両家に縁の深いアッティングハウゼンさんにしか務まりますまい。願えましたらこの大役を託してもよろしいですか?」
「是非もない。お引き受けしよう。エリーゼお嬢さんは、まだしばらくウーリの別邸におると言ってたしのう」
「ああ、有難いことです。アッティングハウゼンさんにお引き受け頂けたなら、これはもう成ったも同然です」
「こちらこそ恩に着よう。わざわざこのウーリに危機を知らせて下さり、その上こんな良い策を出して下された」
「ハプスブルクに対抗するには、貴族をも味方にして出来るだけ大きく合同することです。それにはこの対抗策は最大に有効な方法。互いに協力出来ると思ったのです。それに我々は旧領主キーブルク伯の断絶以来ハプスブルクの領下となり、王の圧政と戦っています。断絶に付け込んで領地を取り上げるのは、奴らの常套手段なのです。隣の友邦、ウーリにも手を伸ばした今に至っては、座して見ているわけには行きません」
アッティングハウゼンは目で頷いた。
「そうじゃったか……シュウィーツは既に戦いの中にあるのだのう。これからは互いに協力して事に当たろう」
ブルクハルトは平和惚けから覚めたような心地で言った。
「及ばずながら、私も出来るだけの協力はする」
「ありがとう。頼りにしている」
ブルクハルトは強く頷いてから、アッティングハウゼンに言った。
「善は急げだ。早速これから皆でエリーゼ様のところへ行こう。ここまで来たら別邸はすぐ向かいだ」
「おお、そうか。ではそうするとしよう」
三人のアーマンは新たな使命を帯びて馬車に乗った。
アルトドルフの隣町、シャトドルフにあるラッペルスヴィルの塔を備えた別邸は山間に建っており、家というより古城だった。低い石積みの塀を巡らせた周縁の一帯はラッペルスヴィル家がヴェッティンゲン修道院に寄進した小農園であり、そこで働く人々も修道院に属し、ウーリの中で唯一自治には組み入れられない土地だった。別邸の門にあるアカシアの花を巡らせたアーチを潜ると、色とりどりの花を咲かせた花壇があり、花壇の世話をしていた家臣のブリューハントがアッティングハウゼンを見つけて声を掛けた。
「どうしたねアッティングハウゼンさん。シュッペルさんもご一緒で」
「やあブリューハントさん。お嬢さんに大事な話しがあって来たんだが、いてくれて丁度良い。ブリューハントさんにも聞いて欲しい。一緒に来てくれるかの」
「それは良いですとも。ではご案内しましょう」
「お嬢さんはどうされているかな。弟御を亡くされてさぞ悲しんで居られるでしょう」
「はい。一日中気を塞いでいるご様子で」
「そうですか、そんなに……」
ブリューハントは奥の応接間へと一行を案内し、女中にエリーザベトを呼びに行かせた。
エリーザベトは庭のバラ園の小さな建物のテラスにいて、女中に呼ばれると何か指示を出して遠くから一行に一礼をするのが見えた。細身で背が高めなので、長い白のチュニックスカートが眩しく映える。エリーザベトは二十二歳の若さだったが、利発そうな面立ちは既に修道院長のような貫禄がある。
四つ下の弟のルードルフが伯位を継いだ頃、まだ年少であったので、修道院の後見はエリーザベトが行い、実務の実際はブリューハントが仕切っていた。弟のルードルフを亡くしてまだ間も無いながら、家臣達はエリーザベトを女主人とし、ブリューハントが仕切る事で変わらない秩序が成り立っていた。
エリーザベトが少し心苦しそうな笑顔を見せると、アッティングハウゼンは両手を広げて言った。
「エリーゼ様。この度は辛うございましたな」
エリーザベトは目に涙を溜めて言った。
「私は、たった一人になってしまいました。継承が認められず、領地も権利も殆どを失ってしまうことでしょう。でも、思い出の多いこのお屋敷は残りました。ここへ来ると変わらず賑やかですわ」
「気に病んでもパンは得られぬというもの。それにこのブリューハントさんがいるではないか」
「そうですね。ブリューハントさんもこうして変わらず支えてくれています」
「我々もお力になりますぞ」
「私も支えますとも」
アッティングハウゼン、そしてブルクハルトも胸を叩いた。
エリーザベトは少し目頭を熱くした。
「ありがとう」
シュタウファッハが腕を胸に置いて進み出た。
「この私めもお加え下さい。御紹介を……」
「ああ、こちらはシュウィーツのアーマン、コンラット・シュタウファッハ殿です」
アッティングハウゼンがそういうと、エリーザベトはスカートを広げ礼を取って言った。
「シュウィーツから! ようこそお出でいただきました。アッティングハウゼンさんには昨日お話致しましたが、この度の事は皆様には受け容れがたく、ご迷惑をお掛けする事でしょう。私に出来る事がありましたら何なりと仰って下さい」
エリーザベトは家領を多く失ったというのに未だ領民を思う良い領主だった。その事にシュタウファッハは胸を打つ思いだった。
「聖母マリアのようなお心、感服致しました。時に遠くよりお見かけしておりましたが、改めてご挨拶するのは初めてです。今日は折り入った話もありますが、いいお話を持って参りました」
「いいお話? 興味深いですわ」
シュタウファッハがアッティングハウゼンに目配せをしたので、アッティングハウゼンが続けた。
「お嬢様の問題は、我々にもまた自治を脅かす問題でしてな。今後の対応を苦慮しておったところ、ラッペルスヴィル家の諸権利を取り戻すいい策があると、このシュタウファッハが申すのじゃ」
「まあ。それは是非お伺いしなければ。どのような策でしょうか?」
エリーザベトは胸で手を合わせ、シュタウファッハの顔を覗き込んだ。シュタウファッハはその邪気の無い笑顔に目眩を覚え、威儀を正してから話をした。
「この度は残念ながら、女伯継承の承認をハプスブルク王より得られませんでした。しかし、もう一つの方法があります。それは……」
「それは?」
「伯爵位を併せる事です。ホーンベルク=フローベルク伯は二つの伯位を婚儀によって併せ持ちました。そして現在のご当主は母方であるホーンベルク伯を名乗られています。領地権の継承を認められるのが男子継承のみとあらば、男子を家に入れるのです。理解あり頼りになる人と家を結ぶのです」
「そのために私は何をすれば良いのでしょう」
「もしお心に適うならば、御結婚を……」
エリーザベトはその言葉を受け、畏まってスカートを摘まみ、礼を取った。
「承知致しました」
互いに笑顔で首を傾げ合い、数瞬後、訪れたのは驚きだった。中でも驚いたのはブリューハントだった。
「いきなり求婚だなんて! 何を言い出すのですか!」
エリーザベトはブリューハントを押し止めるように言った。
「いい話です。あなたが当家の婿に入って頂ければ、継承の仕切り直しとなります。その結果こそ分かり兼ねますが、大変助かりますわ」
「そういう手も……いや! しかし私には妻が……」
「妻があるのでしたら、ちゃんとお別れ戴かなくては! 私、浮気は許しませんことよ」
「お待ち下さい。誤解です。お相手は私では務まりません」
「あなたは私をお嫌いですか? 私はあなたなら良いと思えましたのに!」
エリーザベトはハンカチを噛み、目に涙を浮かべて悔しがっている。
シュタウファッハはアッティングハウゼンを振り返り、目で救いを求めた。アッティングハウゼンは慌てて言った。
「エリーゼお嬢さんや。お相手はその方では無い。さっきお話に上がったホーンベルク伯の御子を考えておるのじゃ」
「あら。私ったら何て思い違いを。恥ずかしい……」
「これは言葉の綾というものじゃな……」
「立ち話も何ですから、あちらで座ってお飲物でも」
エリーザベトは顔を真っ赤にして一行を席に案内した。ブリューハントは阿吽の呼吸で飲み物の準備へ行った。
一行は窓辺に拵えたテーブルに着き、落ち着いた所で話を再開した。
「お恥ずかしい……取り乱しまして失礼を致しました」
「お気に召さるな。不躾な話をしておるのはこちらの方じゃ。急にこんな話を持ちかけられても戸惑うのは当然じゃろう。だがこれは良い話だと思うんでのう。もし嫌だと思うなら断ってくれてもいい」
「まだ雲を掴むようで……そのお相手はどういった方なんでしょう」
「ルーディック二世というお子でな。分家の子をアーデル様が養子に引き取ったと聞いている。こういうのは猶子といって、まあよくあるんだがの。実は継承の事で困っているのは先方のホーンベルク伯も同じでのう。ホーンベルク伯の現当主は子がおらず、次の継承者がおらんのじゃ。その場合は弟に譲られる所なのだが、この弟というのが一人は亡くなっており、もう一人がそのルーディック卿なんじゃよ。ホーンベルク伯の名を残すためにアーデル様も苦労しておる。エリーゼお嬢さんの境遇もよく解ってくれることだろう」
「そうですね。その方と是非一度お会いしてお話を伺ってみたいですわ。この縁談のお話もありますが、継承のために女の側で出来る事についても」
アッティングハウゼンが言った。
「そう言ってくれると助かる。では今度場所を設定して会う機会を設けよう。ルーディック卿ともご一緒でのう」
「よろしくお願い致します」
エリーザベトは深々と頭を下げた。
ブルクハルトは大いに喜んだ。
「これは両家ともうまく収まる、我々も安泰で万事うまくいく、本当にいい話ですよ。いやー目出度い。目出度い事だ」
アッティングハウゼンはこれを見咎めて言った。
「まだ早いぞブルクハルト。お嬢さんが決めるのは会ってからじゃ」
「ハア。でも大事な一歩ですからな」
エリーザベトは言い含めるように言った。
「こんなことが噂になったら、私、困りますわ」
シュタウファッハが神妙な面持ちで言った。
「その通りですね。ブルクハルト、軽口は慎むべきだ。他の方々も、この話はハプスブルク周辺に知られればあらぬ疑いを懸けられるかもしれません。くれぐれも内密に進めなければ。ここに我々は秘密の盟約を結びましょう。頷く事で誓約とします。宜しいですか皆さん」
一同は互いに頷くと同時に、堅い盟約を交わし合った。それこそは大事な一歩となる出来事だった。
一仕事を終えて家に帰ってきたカリーナは、マリウスに労いの声をかけた。
「看病ご苦労様。リンゴも剥いてくれたの? 偉いわねえ」
マリウスは自分が半分を食べてしまっていたので慌てて言った。
「おかえり! お姉ちゃんがリンゴが欲しいって言ったのに、水を取ってくる間に寝てしまったの」
「そう。おしぼりもよく替えてくれたみたいね」
「うん。お客さんがたくさん来たよ」
「シュタウファッハさんね。さっき牧場の方へも見えたわ」
「それとアニ様……だったかな?」
「アニ様?」
「ウーン。呼び捨てにしちゃいけないんだって」
「どなたかしら?」
カリーナはおしぼりを取り替えながら、アフラの額に触れてみて、異変を感じた。
「まあ。熱がこんなに!」
アフラはその声に少し目覚めて、うわごとのように言った。
「お母さん……頭が痛い……」
「頭が痛いの?」
「うん……馬車が来たわ……きっとまた来るわ………」
「馬車? 馬車が来たの?」
「うん……頭が痛くて私……行けない……イサベラさん……」
アフラはそう言って、そのまま眠ってしまった。
「何の馬車を言っているかしら?」
マリウスは母のカリーナに言った。
「そうだ! イサベラ様だ。お迎えの馬車だよ。さっき来たんだ」
「何てこと!」
カリーナは王家の縁者から迎えの馬車が来るなんて予想だにしてなかった。それを無下に断ることは、王家への反逆とも取られるのではないか。そんな心配が渦巻いた。
そんな母を余所に、アフラの病状は悪化して行った。夕方が近付くにつれ、次第に息が荒くなり、額の熱さも今までよりさらに上がっている。
「大変。お医者様を呼んだ方がいいかしら!」
しかし、医者にかかるにはチューリッヒの町にまで行かなければならなかった。この時間からは行けばもう着くのは夜遅くなり、医者も来てはくれまい。
ブルクハルトが用事から帰ってくると、カリーナは夫に声を掛けた。
「あなた! 大変なの」
「そんな慌てて、どうしたんだ?」
「アフラの熱がとても高くて。お医者様に診せないと……」
「まあしばらく様子を見よう。明日になれば熱も冷めるかもしれない」
「でも、とても熱が高くて。苦しそうなの」
「まあ子供の熱だ。すぐに治まるよ」
「それにマリウスが馬車が来たって……」
「ちょっと待て、今は、それどころでは無い事態なんだ」
「シュタウファッハさんのこと?」
「そうだ。ウーリの存続の危機だ。事によるとハプスブルク王家に呑み込まれるかもしれない」
「まあ。そんなことって!」
「これから広場で緊急ゲマインデを開く。男達はもうそろそろ集まって来ているだろう」
「緊急ゲマインデ? それは大変……」
ゲマインデは民主的な会合とも言えたが、参加は自由人の成人男性に限る。女達や子供達はその話に参加出来ず、遠くからその歓声を聞くだけだった。
エルハルトとアルノルトの二人も本来ゲマインデに参加出来なかったが、もう十八になるエルハルトは今回、特別に参加を許された。エルハルトは村長のところへ行って、ゲマインデを開くように伝えた後、村のあちこちにその報せを触れて回っていたので、自然とその流れになったこともある。
ゲマインデは昔からの風習で武器を持って集まったので、戦の前の会合にも似ていた。普段壁に飾ってある武器は、この時のためにあるとも言える。それらは始まりの礼を取ったり、挙手の替わりに武器を鳴らすために使われた。
村の広場には古びた武器を持った男達が集まって来ていた。ブルクハルトが到着すると、待ちかまえていた村長がやって来て言った。
「おお。ブルクハルト。皆ももう集まって、ゲマインデの準備は出来ておるが……一体何があったんじゃい」
「ここで話せば長くなる。まあ村の皆も一緒に聞いて頂こう。ゲマインデを始めて欲しい」
村長は頷くと壇上に上がって言った。
「これより緊急ゲマインデを始める」
村人はそれぞれの持つ武器を前に立てて礼を取った。
「今日我々をここへ呼んだのは管区長だ。ブルクハルト。皆に話をしてくれ」
ブルクハルトが壇上に上り、村に起こった出来事を告げた。
「村の諸君。緊急に集まって貰ったのは他でもない。村の大事が起こったからだ。ハプスブルク王家が隣国を買い漁っていることはもう知っていることだろう。このウーリも今、その危機にある」
「なんだって!」
村人達はざわめいた。
「静粛に。ウーリは前王より特許を得た自治の州だ。我々は多くの農地や牧草地を教会に預けて共有し、共同して峠道や土地の開発に人を回すことで村を発展させてきた。我々の生活、生命はこの自治によって成り立っている。我々の結束は固く、領主の入る隙など無い」
村人たちは「そうだそうだ」と頷いた。
「ところがだ。この修道院の守護権が王家に渡った。また、この程、峠のウルゼレン一帯が王家の息子の領地となった。隣のニートヴァルデンやオプヴァルデンの修道院の領地が買収された例もある。ハプスブルク王家はこの辺の領地持ちの修道院の守護権を得る事で、王家の領地と同じような扱いにしていくつもりだろう」
「王家の領地だって!」
村人達はブルクハルトに喰ってかかった。
「自治の特許状があるんだ! そんなことを許していいのか!」
「このまま指をくわえて見てるのか!」
村人の声にブルクハルトはサーベルを地に打ち付けて言った。
「無論、座して見てはおれぬ。とは言え相手は王家だ。まずは、皆の意見を問いたい。王家の横暴と戦うべきかどうかを!」
「王家だろうと何だろうと、このウーリは渡すものか!」
「王家なんてまだ無冠だぞ! そんな奴の言うことなど聞く必要は無い!」
村人から口々に怒号が飛んだ。
ブルクハルトはサーベルを抜き、高く掲げた。金属音が糸を引いて響く。
「我らの剣は自治の権利の上に捧げられている。王家と言えども戦うべし! 皆の声はそれでいいか?」
村人はブルクハルトと同じようにサーベルを抜いて鞘で叩き、金属音を上げ始めた。
「戦うべし!」
「戦うべし!」
サーベルは鳴り続け、村人は口々に「戦うべし」と叫び、剣を掲げた。
「静粛に!」
村長の声ですぐに騒音は止んだ。頷いてブルクハルトが続けた。
「流石はウーリの民。よい覚悟だ。誇りに思う。皆の意見は判った。これから難事もあることだろう。今後は村で協力して事態に当たろう。良いな?」
村人はまたサーベルを打ち鳴らした。ブルクハルトが両手を挙げると、それは止んだ。
「友邦シュウィーツでも今、同じようなことが起こっている。シュウィーツのアーマンであるコンラット・シュタウファッハ殿が今日こちらに来ているので、その詳しい話を聞きたいと思う。ではシュタウファッハ。話を頼む」
ブルクハルトから紹介されて、シュタウファッハは壇上に上り、シュウィーツの現状を語った。
「ご存じの通りシュウィーツはウーリと同じく前王より独立自治の特許を頂いた領邦であります。しかし大空位の時代の内に領主断絶によってハプスブルクの保護下になり、以来王と教会、二重の税がかかり、人々は重税に苦しんでいます。ウーリと同じように我々にも自治の特許があったのにです。我々は自治を取り戻すため、以前よりこの不当な圧政と戦って来ました。それが故にウーリの自治は我等にとって理想であり、希望の国だった! それが今、破られようとしているのです! 私は、居ても立ってもいられなかった! いかなハプスブルク王家と言えどもこんな横暴を許すことは出来ない!」
群衆から拍手と喝采の声が沸いた。
「ありがとう。ありがとう。我等は今、運命を共にしようとしています。ウーリとシュウィーツはずっと隣の友邦だった。共にラントの自治を守るため戦おうではないか!」
「おお!」
村人達はシュタウファッハの言葉に呼応の声を上げ、武器を打ち鳴らした。
エルハルトも父のサーベルを打ち鳴らし、大いに声を発した。
アルノルトは窓を開けて眼下に広がる広場の明かりを見ていた。この日のゲマインデは夜遅くまで行われ、とても騒がしかった。遠くからよく怒号のような声が聞こえた。武器を打ち鳴らす音も大きく聞こえた。
しばらくして、アルノルトはアフラの様子を見に行った。看病していたマリウスはベッドの傍らで眠っていて、アフラの額のおしぼりは額の上から落ちていた。額におしぼりを乗せ直しながらアフラのこめかみを触ると、その熱はまだとても高かった。
アフラはうわごとを言った。
「お花畑………」
アルノルトはしばらくアフラのおしぼりを替えて看病をした。汗を拭きながら、アルノルトはアフラに話しかけた。
「寝ててもお花畑か……花くらいは明日取って来てあげるよ」
しばらくすると、母が入って来て言った。
「マリウスは寝ちゃったの?」
「うん。看病しながら寝ちゃったみたいだ」
「あなたももう寝なさい。看病は私が代わるから。マリウスも今日は頑張ってくれたわ」
そう言って、母はアフラの隣に羊毛の布団を重ねて敷き始めた。そしてそこへマリウスを寝かせた。
自室に帰ったアルノルトは、父と兄の帰りを待っていたが、夜遅くなっても、父とエルハルトが帰って来なかったので、いつしか眠気が勝り、そのまま先に眠った。
明くる日の日曜日は雨だった。村の風習として日曜日は皆、仕事を休み、教会へ礼拝に向かう。子供達はその後に日曜学校があり、教会で勉強をする。シュッペル家では牛や羊の世話を休めないので、朝早くに多くの仕事を片付け、それから教会へ行かなければならなかった。
エルハルトとアルノルトが牧場での仕事を終えて帰って来る頃には、次第に雨が強くなった。
「こんなに雨が降るなんて。今日は日曜日で助かったなあ」
「まあ朝からこんな天気なら、最初から山へ行くことはないと判るさ」
「兄さんなら雨が降る時はすぐ判るもんね」
「まあな」
「僕は兄さんの弟で良かったよ。便利だし」
エルハルトはアルノルトの肩を拳で叩いた。
「こいつ。俺を便利に使う気か?」
「違うよ」
小突き合いながら家に帰ってきた二人を迎えて、母のカリーナが言った。
「雨で大変だったわね。お父さんは昨日遅かったせいでまだ寝てるの。先に朝ご飯を食べてて」
「ああ。父さんの分も仕事はしておいたよ。お腹も減ったし、待ってられないよ」
「それはご苦労様。それと今日の礼拝へはお父さんと三人で行って来て」
「母さんは?」
「アフラがまだ良くないの。家を空けられないわ」
アルノルトが部屋を見回して言った。
「マリウスは?」
「マリウスは看病するから行かないって言うの」
「マリウスも頑張るなあ」
エルハルトとアルノルトは朝食のパンを手早く食べてしまうと、二階のアフラの様子を見に行った。マリウスがそこでうつらうつらしながら看病していたので、エルハルトは戸口で人差し指を立て、二人は起こさないよう静かにアフラの様子を窺った。
アフラの熱は下がるどころか、とても苦しそうな息をしていた。悪化しているのがそれだけでも見て取れた。
エルハルトとアルノルトはそんなアフラを気にしながらも、教会へ行く時間なので準備を始めた。
父のブルクハルトも起き出してきて準備を始めていた。
「おおエルハルト。牛の世話までしておいてくれたようだな」
「ああ。牛の呼ぶ声で目が覚めたからね」
「お前には助かるよ」
「シュタウファッハさんに助けるように言われたしね」
「そうか。いや。それはでも少し違うな。国を跨いで駆けまわるあの人をこそ、いつか助けたいものだな」
エルハルトはその言葉に頷いた。アルノルトにはその意味するところが判らなかったが、その真摯な心を感じ取っていた。
三人が雨避けの外套を着て、帽子を被り、教会へ行く準備を整えると、カリーナが来て言った。
「行ってらっしゃい」
「アフラをよろしく頼むよ」
「教会でアフラの病気が早く治るように祈って来て。みんなもね」
「うん。そうする。じゃあ行って来る」
三人の親子は雨の中を歩いて村の教会へ向かった。
シュッペル家は村でも山間にあり、村の中心にある教会までは少し遠かった。フェルトに蝋を塗り込んである雨避けの外套も、強い雨では次第に浸み込んで来る。
三人が教会に着く頃には水が浸みてきて、あちこちが濡れていた。
教会にはもう村人が集まっていた。
ブルクハルトが入ってくると、村人はブルクハルトに目礼をする。
アーマンは修道院の後見貴族が任命する村の管区長であり、領主の手下のように思われる面もあって、村のゲマインデで伝統に則って決められる村長ほど人望が無かったが、シュッペル家は古くからビュルグレン村の共同牧場を切り盛りする要職にあって、家畜が世話になっている家も多かったので、やはり一目置かれる存在だった。
シュッペル家の礼拝の席はいつも最前列の村長の隣と決まっていたので三人はその席に着いた。
すると村長が声を掛けてきた。
「やあブルクハルト。昨日はありがとう。遅くまでご苦労だった。エルハルトも昨日はいい働きじゃった」
そう言われたエルハルトははにかんで会釈した。ブルクハルトが憮然と言った。
「今はまだあまり誉めんでくれ」
「良いことをしたら、良いと誉める。それでいいじゃないか。なあ」
「今回は相手が王家だ。少し事が事だからな」
「おお。まあ違いない」
村長は頭を掻いて笑った。
後で手持ち無沙汰にしていたアルノルトの所には村娘のソフィアとポリーがやって来た。この近くに住む二人は姉妹だ。
「ねえ。今日はアフラは来てないの?」
そう言うソフィアはアフラの一つ上で、仲のいい友人だった。
「ああ、ちょっと熱を出してね。病気なんだ」
「そう。大変ね」
「マリウスは?」
ポリーはマリウスと同い年で、マリウスの友達だった。
「マリウスは看病を買って出てね。今日は来ないってさ」
「残念ね〜」
そうしている内に教会のシスター達が祭壇に蝋燭を灯し始め、そしてパイプオルガンの音が響き出し、聖歌隊が賛美歌を歌い始めた。教会は厳かな雰囲気に包まれる。
そこへ牧師が出て来て礼拝が始まった。礼拝の間、牧師が聖書の一説を読み上げる声にも耳を貸さず、アルノルトはアフラの病気が治るようにとただ祈り続けた。
教説が終わると、そこへ一人の若い修道女が壇上に立って浪々と響く声で話しを始めた。
「ウーリの皆様。私はボヘミアにある聖アネシュカ修道院から来ました。先年の飢饉の折りに、皆様には多くのご寄付を戴き、誠にありがとう御座いました。皆様のご寄付は戦争で農地を失い、飢えと病で困窮する人々に届けられ、多くの人々がこの冬を越える事が出来ました」
アルノルトがその話に興味を覚え、顔を上げると、その修道女と目が合った。一時、話しが止まった。その顔には見覚えがあった。それは若く凜々しい修道女、クヌフウタだった。アルノルトは咄嗟に顔を下げた。
「隣人を愛するように隣の国、その向こうの国まで救いの手を差し伸べる。その行いは主の御心に叶いましょう。このウーリの人々に大いなる祝福があらんことを。アーメン」
クヌフウタはしばし祈りを捧げ言葉を結んだ。
礼拝と小講義が終わって、牧師が退席しても、アルノルトは祭壇に祈り続けた。エルハルトもそれを見てしばし十字を切り、そして声を掛けた。
「アルノルト。そろそろ行くぞ」
アルノルトが見回すと、もう教会の中の皆が席を立って、解散していた。隣では村長一家が席を立って出て行くところだった。席の後ろには隣の家に住むオイゲーン・ビュルギ一家がいて、ブルクハルトと話していた。
「昨日は名演説でしたな。シュッペルさん」
「いやいや。ウーリの一大事となれば私も黙ってられないよ。全てはシュウィーツのシュタウファッハが教えてくれたことだ。我々だけなら何が起こったのか判らないままだったろう」
「演説していたあのシュタウファッハ殿だね」
「ああ。彼とは旧知の仲なんだ。我々はさらにシュウィーツと連携して、ハプスブルクへの対抗策を練らねばならん」
ブルクハルトがそう演説ぶっている横を縫って、オイゲーンの息子が二人やって来て、兄のモリッツ・ビュルギがエルハルトに話しかけた。
「エルハルト。お前、ゲマインデに出たんだってな」
モリッツはエルハルトの一つ年上だったが、背は少し低く、それでも骨格が一回り太かった。エルハルトは言いたいことに予想が付いて、時間を置いて言った。
「……ああ。ものの成り行きでね」
「どうしてお前が出て、俺が出られないんだ?」
モリッツは何かとエルハルトと張り合うようなところがあった。それは、一つ下のエルハルトが何でも一つ先を行ってしまうせいもあったろう。
「ゲマインデの招集に村全部を回ったから、村長に言われて確認のためにも出席することになったんだ」
「そうか! そうすれば出られるんだな」
「簡単に言ってくれるが、村の大事を預かるんだ。遊びじゃないんだぞ」
「そんなことくらいは俺でも出来るよ」
エルハルトは呆れて笑うしかなかった。
「じゃあ、今度は手伝って貰うとするよ」
「おう……いつでも言うがいい」
モリッツは何かもの足り無さを感じたが、何が足りないかは判らなかった。
モリッツの弟のテオドールがアルノルトに言った。
「アフラはまだ良くないの?」
テオドールはアルノルトと同い年で、性格も優しかったので仲が良かった。
「やあ。テオ。そうなんだ。ものすごい高熱でね、大変なんだ。今日はマリウスが看病してる。まあ日曜学校が嫌なだけかも知れないけど」
「そうか……それで必死に祈ってたんだ。早く元気になるといいね」
「うん……」
「雨が止んだみたいだ」
「本当だ。みんな外へ出て話している」
「見て来よう」
テオがドアの方へ行くと、アルノルトを後ろから呼び止める声があった。
「お兄さん」
振り向くと、そこにいたのはシスター達だった。一人だけ白い修道服を着たシスターがいて、歩み出て声を掛けて来た。
「アフラさんは、まだご病気なのですか?」
「そうですけど………どうしてそれを?」
「私です」
シスターが頭を覆っていた白のキャップを取ると、それはイサベラだった。隣りにはキャップを目深に被ったユッテがいた。後にはクヌフウタが微笑んでいる。
「あっ。君逹!」
驚いたアルノルトは転びそうになり、周囲を見回した。
「あっ。被って!」
アルノルトは慌ててイサベラのキャップを戻させた。周囲の目を気にしたと言うより、今、イサベラはここにいる村人全員の仇敵とも言える立場だと思ったのだ。
「どうしてここに………」
ユッテはアルノルトの気も知らず、さも楽しそうに言った。
「修道院の学生だから、ウーリの分教会に賛美歌を歌いに来ることもあるわ。アフラさんのお見舞いをしたいの……」
「今日は日が悪過ぎる。帰った方がいい」
「どうして?」
「悪いが今日はダメなんだ」
ドアを開けたテオが振り返って言った。
「雨はもう止んで来たよ! あれっ? 懺悔でもするのかい? アルノルト」
「いや。ちょっと……ぶつかっただけだ」
アルノルトは小走りにテオの待つ出口へ向かった。
「あっ。待って」
ユッテはアルノルトを呼び止めたが、その声は届かず、アルノルトはテオの後に付いて外へ走って出て行ってしまった。二人の家族もその後に付いて教会の外へ出て行く。
ユッテとイサベラはそれを追うように教会を出た。入り口からアルノルトを探すと、広場の隅の木の下でアルノルトとテオは笑顔で話している。
外の雨は小降りになっていたがほんの少しは降っていて、そんな中でも教会前の広場では村人達が話し込んでいた。話題はやはり昨晩この場所で行われたゲマインデについてだった。村長がそこに加わると、村人は村長を囲んで話を求めて群がった。
「村長! 詳しい話を聞かせてやってくれ」
「詳しいのは儂よりブルクハルトだ」
ブルクハルトが外へ出ると、それを母のサビーネが見つけて駆け寄って来た。
「いいところに来たよ。みんなお待ちかねだよブルクハルト」
「母さん。そんなに走って来るなんて。元気で何よりだ」
「そんなことより今回の騒ぎは本当なの? このウーリに何が起ころうとしているんだい」
ブルクハルトには村人達、特に女達からの目が注いだ。男達はゲマインデで知っていたが、参加していなかった女達は噂で聞くのみで、はっきりしたことを知りたかったのは当然だった。
「話せば長くなるからかいつまんで言うと、聖母聖堂の守護権者が変わった。教会の元締めが変わったということだ」
「教会が変わるのが村に何かあるのかい?」
「それによって、教会預かりのウーリの土地が王の領下に入りそうなんだ。ザンクト・ゴットハルト峠のウルゼレンは既に王領になったそうだ」
広場の村人達は一斉にどよめいた。
「教会預かりって……村の殆どじゃないか!」
「うちの土地は教会に預けてるわ!」
「ザンクト・ゴットハルト峠は俺達が命懸けで開いたものだぞ! 我々の権利じゃないか」
「王家が泥棒するの!」
一斉に驚きと抗議の声が上がって、ブルクハルトは質問攻めに遇い、その質問を聞き取ることすら出来なくなった。
「それに対抗するためにだな! 我々は然る方と協議して司法の面から尽力している! だから今騒ぐのはまずい。表立っては騒がず、私等に任せて欲しい」
村の古老のヘンゼルが言った。
「お主、いざとなったら王家の犬になるんじゃないか。アーマンはもともと領主の使いっ走りみたいなものだからな」
「何を言う! この私がか? 牧場の為、村の為に私財も献げて働いているこの私がか? それを取られてまず一番の被害者は私だぞ! その言葉は許せん!」
ブルクハルトはヘンゼルの方へ歩んで、鼻を突き合わせるくらいの近くへ立った。
サビーネはブルクハルトの手を引いて言った。
「ブルクハルト! 話を混乱させないで! ヘンゼルさんも!」
村長も間に割って入って言った。
「そんなことで啀み合ってる場合じゃない。今は皆で協力して王家に対抗せねばならん時だ」
ブルクハルトは我に返って言った。
「いかんいかん。そうだった。私は昨日からそう言いもし、行動もしてきた。ただ、言いがかりは止してもらいたい」
古老はブルクハルトの肩を叩いて言った。
「すまんかった。ついな。しかし、王家が敵となれば、誰が尻尾をまくるか判らん」
村長は古老の意を汲んで頷いた。
「ここにいるみんなは大丈夫さ。のう?」
村長が振り返ると、村人は口々に頷いた。
「皆よありがとう。少しでも裏切りもんが出れば、ウーリは取られかねんぞ。皆もよく肝に銘じて、裏切りもんが出んようにして欲しい。この戦いはみんなで結束してするんじゃ。無冠の王なんぞ、全員が言うことを聞かなければ帰るしかあるまい」
「おお! そうだ! 無冠の王など村に入れるものか!」
「王家の犬がいたら追い出してやる!」
村人は口々に王を罵った。
その騒ぎは当然、ユッテとイサベラの耳にも入った。ユッテは足が震えるほどショックを受けた。ユッテは立っていられなくなった。王女である気高い誇りが崩れて、謝るように地面に崩れた。隣にいたイサベラが肩を揺すって言った。
「大丈夫?」
ユッテはアルノルトとの約束を思い出していた。それはこんなに簡単に破られようとしている。遠くから心配そうに見ているアルノルトと目が合った。その目に点る疑念は心を突き刺すような気がした。
「こんな事って……」
アルノルトの目には始めから全てを見透かされていたように思えた。そしてはらはらと涙が溢れて来て顔を伏せた。
アルノルトはそれを見かねて歩み寄った。アルノルトを見上げたユッテの目には、大粒の涙があった。アルノルトは掛けるべき言葉を探し、ユッテに手を差し出して言った。
「そうしてると目立つ……立って」
ユッテは何か言おうとしても声にならず、その手に掴まって静かに立ち上がった。
「君のせいではないさ。それは判っている………」
ユッテは顔を上げ、何か言おうとした。
そのとき、騒ぎを聞き付けた牧師とシスター達、そしてクヌフウタが教会から慌てて出て来て、囲み込むようにユッテとイサベラを教会内に連れて行った。しかし次の瞬間には牧師が村人に捕まって、質問攻めに晒された。村長が牧師に言った。
「レッセマン牧師。何か聞いていないか。我々の預けた土地をまさか、はいどうぞと王家に譲り渡すんじゃないだろうな」
「それは……我々にもまだどうなるかよく判らないのです。新しく代官に任命された者の指示に従うように言われています」
「まずいな。その男は王家の犬だ。王の名でお触れを出したらもう手出しも出来なくなる。レッセマン牧師。我々の預けている土地を今のうちに返してはくれまいか」
「そうだ! 返してくれ!」
村人達も口々に頷き牧師に詰め寄った。
「それは無理です。証書は聖母聖堂にあります。この分教会には置いていないのです」
村人がまた騒然となる中、ブルクハルトが静かに考えていた。
「では! こうはどうだ」
ブルクハルトが大きな声で言うと、村人は静かになって続きを聞いた。
「判る範囲でいいから土地の預かり証を書くのはどうだろう。預けただけだとはっきりさせるために」
「いいでしょう。双方の記憶が合うものならば、更新して書くことが出来ます。シュッペルさんなら大抵覚えているでしょう?」
「ああ。新しい所はそうだが、古い所は村長かな」
「うむ。そうさのう。順番にやってみるかのう」
村人に安堵が広がった。
村人達は教会へ入り、一人一人順番に、証書の作成に取りかかった。
「あら。お帰りなさい。遅かったのね」
カリーナは先に帰ってきた兄弟に泥拭き巾を渡して出迎えた。エルハルトがため息を吐いて答えた。
「ただいま。昨日より凄い騒ぎだったよ。聞こえた?」
「そうね。そう言えば騒がしかったわね」
アルノルトは母に言った。
「アフラの様子はどう?」
「今日はずっと静かに寝ているわ。これだけ眠れば良くなるんじゃないかしら」
「教会で治るように祈って来たかいがあったよ」
「アルノルト……ありがとう」
それからかなり遅れてブルクハルトが帰って来た。カリーナは同じように泥拭き布を渡して出迎えた。
「お帰りなさい。大変だったみたいね」
ブルクハルトは靴の泥を落としながら言った。
「いやいや大変だった。土地の預かり証を作るので結構揉めてなあ。思うようには進まんよ」
「預かり証?」
「教会預かりの土地が王家に取られないように、預けた人が皆証書を書いておく事にしたんだ」
「うちのは書かなくてもいいの?」
「うちの土地の殆どは逆に教会から預かっているものだからな」
「この家の土地はビルゲンさんの預けている土地でしょう?」
「そうだ。ビルゲンさんを忘れてた」
「しっかりして下さいよご主人様?」
「ビルゲンさんはあまり村には出てこないから言っておかないといかんな」
「早くしないと、ここの土地が取られたら大変よ」
泥を落とし終わったエルハルトが言った。
「じゃあ今から馬車で行って来るよ」
「今から行くの? 戻るなりすぐじゃ大変じゃない?」
「ゲマインデの時もビルゲンさんの所までは呼びに行けなかったから、まだ何も知らないと思うんだ」
「それはまずいな。私も行こう」
「これくらいは一人で行くよ。任せて。ここまで連れて来るよ」
「そうか。では頼む」
エルハルトはその足で荷馬車を出し、山間のビルゲンの家へ向かった。
それを見送りながらカリーナは言った。
「それにしても……ビルゲンさんもどうしてここを貸して、山奥に引っ込んでしまったんでしょう」
「粉挽きするには水車小屋に近い方が何かと便利なんだろうよ」
「でも家族もなくてたった一人だもの。寂しいと思うのよ」
「まあサビーネ母さんとは旧い間柄だし、うちとも家族付き合いだけどな」
「いつかお返しをしないと駄目ね……」
アルノルトがアフラの様子を見に行くと、アフラは息を立てて眠っていた。マリウスが横で看病しながら林檎を弄んでいる。
「マリウス。様子はどう」
「うん……今日は殆ど寝たままなんだ」
「そうか。お母さんはこれだけ寝ていれば治るって言ってたよ」
「でも、お姉ちゃん……ずっと食べてないんだ」
「そうなのか? 普通、お腹空いて目が覚めないかな」
「ほんの一瞬目を覚ましたら、すぐに寝ちゃうんだ。だから食べる暇もないんだ。だからずっとリンゴ剥いて構えてるんだよ。ボク、リンゴ剥くの上手になっちゃった」
皿の上に山盛りになった林檎は変色して茶色になっていた。
「なんだこの林檎。変色してる」
「置いておくと色がこうなっちゃうんだ」
「古いのはアフラも食べたがらないんじゃないか?」
「でもつい暇だから全部剥いちゃったんだ」
「全部? もう無いのか?」
「うん…」
「そうか……いいものがある」
アルノルトはイサベラに貰った篭を台所から持ってきて、マリウスにそれを渡した。
「わーっ。すごい一杯」
「ここに林檎も沢山入っているだろう。アフラに食べさせてやるといい」
「どうしたのこれ」
「イサベラって言う貴族の娘に貰ったんだ。羊を連れて行ったお詫びにってね」
「イサベラ様知ってる」
「何かあったの?」
「昨日イサベラ様の馬車が来たんだよ」
「来たのか! 何て言ってた?」
「熱出して寝てるって言ったら帰って行った。明日教会にゴランリンと鐘が鳴るって言ってた。昨日の明日だから今日?」
「そうか……」
アルノルトはイサベラの気が知れないと思った。昨日は馬車、今日は教会にも顔を出している。そんなにもアフラに会いたいものなのか。だとすると、いつかは連れて行くつもりなのかもしれない。アルノルトはそう思うと信用出来ない気がして来た。すでにイサベラの誓いも意味を失いつつある。王家がウーリを丸ごと王領にしてしまったら、領内のものは王家のものになってしまう。
「くそっ!」
アルノルトはあの誓いの時、イサベラを信用していいと思った。それはこうも簡単に裏切られようとしている。優しかった村人も今日は暴徒のように荒々しかった。アルノルトは信じていた全てが信じられなくなりそうな事態に、初めて恐ろしさを感じていた。
次の朝、いつものようにエルハルトとアルノルトは早朝から羊の放牧へ出かけた。
カリーナは二人を送り出し、アフラの様子を見たが、アフラは苦しそうな息をして眠り込んでいて、まだ熱は下がらなかった。
カリーナは夫に言った。
「あなた。今日は町へ行ってお医者様を連れて来て貰えないかしら」
「医者って言っても大して効かない薬を出すだけだ。それに今それどころじゃないのは、お前だって判っているだろう。私にはウーリの為にやるべき事がたくさんある」
「じゃああなたはアフラをこのまま放っておくって言うの?」
「そんなことは言っていない。ここで出来るだけのことはしよう。後で実家の母さんを連れて来ればいいさ」
「サビーネお義母さん?」
「ああ。昔は熱を出したらサビーネ母さんがハーブ茶を作ってくれたものさ。なんとかしてくれると思うんだ」
「でも。アフラの熱は少し普通じゃないのよ。一度医者に診せた方がいいわ」
「下手な医者よりサビーネ母さんの方がいいって、みんな言ってるじゃないか」
「でも。こんな高い熱は見たことが無いわ。きっと何か特別な病気なのよ。手遅れになってからじゃ遅いのよ」
「まずはサビーネ母さんに聞いてみよう。それから聖ラザロ修道院の医者を呼んでも遅くはないさ」
「今はラザロの医者は不在なのよ。もしチューリッヒまで往復すれば、今出ないと間に合わないわ。だからすぐ行って来て欲しいの」
「今日は用事が立て込んでいるんだ。とても行けない」
「じゃああなたはアフラがどうなっても構わないって言うの!」
「そんなことは言ってない。母さんは今までどんな病気だって治してくれた。母さんでは何がいけない?」
そう言い合っている頃、シュッペル家の前に馬車が止まった。
「こちらです」
馬車のドアを開けて丁寧にそう言った御者は牧師姿だった。馬車から修道女が一人降り立った。ベールから覗く端正な顔立ちは、異風の修道女、クヌフウタだった。
「私も行くわ」
馬車からもう一人、小さな修道女が降りた。その修道服は学生のもので、白いベールから見えた顔はユッテだった。
クヌフウタは家のドアをノックした。
カリーナが玄関に出てこれを出迎えた。
「こんにちは。シュッペルさんのお宅ですか?」
「はい。そうですけど」
「私は聖アネシュカ修道院のクヌフウタと申します。昨日こちらのアフラ様がご病気と伺いまして、さる方より診療の依頼がございまして参りました」
「お医者様は後ろの牧師様?」
「私です。医療の心得があるのです」
カリーナは感激して言った。
「まあ! こんな若い方がお医者様だなんて! どなたでしょう。こんなことをして下さった人は!」
「イサベラさんをご存知でしょうか」
カリーナはその名前を知っていた。王家の関係者である事を思うと愕然とした。しかし今に至ってはこの処置に感謝せざるを得ない。
「あなた! お医者様がいらしたわ!」
駆け込んで来たカリーナの言葉に、ブルクハルトも当然驚いた。
「なんと。何故そんなことが!」
「……偶然寄ったみたい。それが、シスターさんなの!」
カリーナは急ぎ戻ってクヌフウタを出迎えた。
「遠くまでお出向きを有り難うございます。宜しくお願い致します」
後から顔を出したブルクハルトにクヌフウタが言った。
「こんにちは。アフラさんはどちらですか?」
「こちらです。五日も前から熱を出して殆ど寝たままなんです」
牧師と二人の修道女はカリーナに案内されて家に入った。
階段を昇り、アフラの部屋へ通されたクヌフウタは、見た途端に顔色を変えた。
「土色の顔色……」
アフラの顔色を見て重篤さを見て取ったのだ。素早くクヌフウタがアフラの額を触ると、その熱の高さに驚いた。
「こんなに熱が………」
そして脈を取り、目の下を捲って見たりしている。
「熱いわ……」
ユッテも額に少し触ってから、その汗を拭こうとした。しかしクヌフウタはそれを止めた。
「あなた逹は少し離れていて下さい。移染るかもしれないから」
カリーナはその様子に心配になる。
「大丈夫でしょうか?」
「このおしぼりでは足りません。革袋に氷を詰めて、氷嚢にしてしっかりと頭を冷やさなければなりません。首にもおしぼりを当てておくのもいいでしょう」
「判りました。すぐに袋と氷を用意します」
一通りの診察を終えると、クヌフウタは薬を取り出して言った。
「この解熱の薬を呑ませて下さい。それから水分を多めに摂ることです」
「でもアフラは殆ど目を覚まさないんです。だからここ最近は食べものも食べていません。どうすればいいのでしょう」
クヌフウタは何かに気付いたように目を見開いて、しばらく考えていた。
「水を一杯頂けますか?」
水を受け取ったクヌフウタはアフラの体を起こし、水の中に薬の粉末を入れ、少しずつアフラの口に水を流し込んだ。
アフラは少量ずつ水と薬を呑み込んでいく。それを根気よく何度も繰り返した。
「こうして呑み込ませるのです。食べ物も摺り下ろして流動食にして、同じように少しずつ食べさせて下さい」
「はい」
診療を終えて、カリーナは居間で牧師と修道女達にセイジ茶をもてなした。
ブルクハルトはクヌフウタに聞いた。
「アフラは何の病気なのでしょう?」
「こんな高熱になって意識が無いなんて、特殊な熱病かもしれません。今は風邪の処方ですが、薬が効いてくれば熱も下がるでしょう。しかし滅多に無いケースですが、このままこの高熱が続くと………もしかすると脳に損傷が出て、眠ったままになるかも知れません。そうなると命にも関わります」
後からユッテが叫ぶように言った。
「何ですって!」
その声に驚いたカリーナだったが、気を取り直して言った。
「滅多に無いケースですよね?」
「経過を見なければまだ判りません。今は氷嚢で頭を良く冷やして、頭の熱を下げるよりはありません」
カリーナはクヌフウタの手を握り、頭を下げた。
「シスターのお医者様。どうかアフラを助けて下さい!」
ブルクハルトもそれに続いて言った。
「どうか命だけはお助け下さい!」
クヌフウタは小さく十字を切った。
「主に祈りましょう。医師として出来る事はこれ以上は無いのです。後は看病を頑張って頂かなくては。間断なく氷嚢で頭を冷やして、三度の食事時に流動食をしっかり飲ませて衰弱しないようにして下さい。私は医師としてはまだ未熟です。しかし神に仕える修道女でもあります。ご回復を心よりお祈りしています」
二人の修道女が呼吸を合わせて祈るので、一同もそれに習った。
そうして修道女一同は帰途に就いた。
それを見送りに立ちながら、カリーナは言った。
「お代の方は……」
「受け取れません」
カリーナはクヌフウタに重ねて言った。
「本当にありがとうございました。しかし、お代無しに診て貰う理由が御座いません」
「教会へご寄付を頂いています。それで良いのです。あとは依頼主のイサベラさんに感謝をして頂けましたらと。それでは失礼させていただきます」
ブルクハルトとカリーナは出て行く馬車に礼を取って見送った。
「誰だ? イサベラって」
「……あの馬車に乗っていたのよ。きっと」
隣の部屋で聞いていたマリウスは、カリーナに聞いた。
「お姉ちゃん大丈夫なの?」
「大丈夫よ。きっと大丈夫よ」
クヌフウタの言うとおり薬が効いてくれば熱が引くはずだと、カリーナは信じるより無かった。言われた通り、氷の入った氷嚢をアフラの額に置き、おしぼりを喉元に当て、アフラの熱を冷ました。しかし、時がいくら経ってもアフラの熱は少しも下がらなかった。それどころか、だんだんアフラの顔色が悪くなって行き、とても苦しそうな息をする。薬は一向に効いて来なかったのだ。
中世ヨーロッパの本格歴史大河小説として、欧米での翻訳出版を目指しています。ご支援よろしくお願いいたします。
