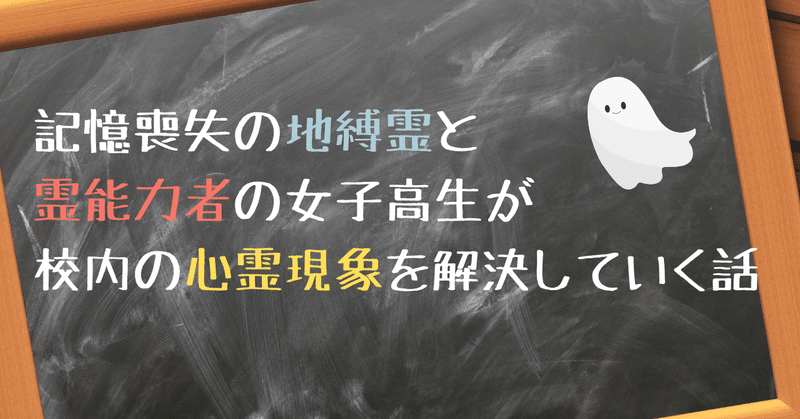
【長編小説】陽炎、稲妻、月の影 #28
第4話 天秤に掛けるもの――(9)
「……さて。中庭の浄化も終わったことですし、僕らも戻りましょうか」
展開していた護符を全て回収し終え、浄化作業も全て済ませたところで、ハギノモリ先生はアサカゲさんに向かってそう言った。
「……オレは、ろむの状態を確認してからでも良いですか? 先生の結界のおかげで、消えたり悪霊化したりはないと思うんですけど、その、新しく連絡手段も持たせてやらないとだし……」
珍しく、もごもごと煮えきらない様子のアサカゲさんである。
そんな彼女の態度から、先生はなにを読み取ったのか、微笑を浮かべ、
「わかりました。では、ろむ君のことはお願いしますね」
とだけ言って、帰ってしまった。
そういえば、アサカゲさんが助けに来てくれた直後、「まだ言い足りねえけど、話は後だ」と言われていたことを思い出す。
助けを呼び損ねたときは、まだ活路を探していたが、靄に呑まれた後は、自分でも驚くほど潔く終わりを受け入れたことは事実だ。どんな叱責も受け入れよう。俺は姿勢を正して、アサカゲさんの言葉を待つ。
「……中庭に様子のおかしい霊が居ること、高橋さんたちから聞いたんだってな」
アサカゲさんは俺の正面に胡座をかいて座り、冷めた視線を向け、淡々と話し始める。
「中庭からでけえ音がして、咄嗟に教室を出ようとしたとき、二人から教えてもらったんだよ。なあろむ、どうしてすぐに、オレや先生にその情報を共有してくれなかったんだ?」
「最近は迷い込んだ霊の対応くらいはできてたから、一人で様子を見に行くくらいなら大丈夫だって思ったんだ。それに……」
「それに?」
言い淀む俺に、アサカゲさんは容赦なく切り込んできた。これは相当怒っている。
「二人が、昼休み明けの授業で小テストがあるって言ってたから、アサカゲさんには余計に言いにくくなっちゃって。だから、先生から貰った組紐が黒焦げになっちゃってからも、アサカゲさんに連絡するのを躊躇っちゃってたんだ。だけど、その結果があのざまなわけで……」
俺は、背筋を伸ばし、頭を下げる。
「心配かけて、ごめんなさい」
少し考えるような間のあと、アサカゲさんは、ろむはさあ、と言う。
「オレとの約束、忘れたわけじゃないんだろ?」
「もちろん。『勝手に消えんじゃねえぞ』、でしょ?」
その言葉があったからこそ、情けなく逃げてでも生き残ろうと思えたのだ。
結果としては無様に捕まってしまったわけだけれど、何故だろうか、あそこまで必死に抵抗したのは、生まれて初めてだったような感覚があった。
因果に逆らい、摂理に反して。
そうまでして俺は、生き残りたかったし、生徒を守りたかった。
「じゃあ良い。許す」
ほら、頭上げろよ。
アサカゲさんにそう言われ、俺はゆっくりと言われた通りにする。
その正面にあるアサカゲさんの表情は、すっかり見慣れた不器用な笑顔だった。
「ちなみに、だけど。さっきの〈あれ〉はレア中のレアだ。いつもなら、この間の食堂の厨房に出た霊と同じで、パニックにはなるけど話は通じただろうよ」
「それじゃあ、どうしてあの人は悪霊化しちゃったの?」
「テスト前だからじゃねえか? 校内の空気が、中間テストのときよりピリついてるのは、ろむもわかってただろ?」
「うん」
「これだけ人の集まる場所で、あれだけピリつくと、空気がいつもより澱みやすくなるんだろうな。だからあの人は、運悪く澱みに呑まれちまったんだと思う」
たとえオレが最初に声をかけたところで、同じ結末だっただろうな。
アサカゲさんは、悔しそうにそう続けた。
期末テスト前。校内の雰囲気。土地神の加護が弱まっている土地。そこに迷い込んでしまった運の悪さ。全ての歯車が最悪のかたちで噛み合ってしまった結果がこれというわけだ。
「二度と同じことは起こさねえ、なんて無責任なことは言えねえ。だけど、失敗から学んで対策できることはある」
そう言いながらアサカゲさんは、胡座から正座に変え、姿勢を正す。
「まずはお前からだ、ろむ。手ェ出せ」
「責任を取って指を詰めろってこと……?」
「違ェよ馬鹿」
俺の憶測をばっさりと切り捨てて、アサカゲさんは、それとそれ、と、焼き切れた組紐とリストバンド指差す。
「さっき先生の前で、新しい連絡手段を持たせるって話をしただろ。新しいの作るから、さっさと両手を出せ」
「ああ、そういうこと……」
ほっと胸を撫で下ろし、俺は両手をアサカゲさんに差し出した。
アサカゲさんは、ポケットからまっさらな護符用の紙を取り出すと、それを右手に持ち、左手で組紐とリストバンドだったものに触れる。
「先生への連絡は、この霊術か……そこにオレとの連絡機能も組み込んで……防衛機能はもうちょい強化して……なんだったら、反撃もできるようにしとくか……」
アサカゲさんはぶつぶつと分析しながら霊術を構築し、それを独特な文字や模様として護符に刻んでいく。素人目には判然としないが、恐らくこれが、霊力を注ぎ込んで護符を作る、ということなのだろう。
「……おい待て、なんだこの機能」
順調そうだった作業がぴたりと止まり、アサカゲさんはぎろりと俺を睨む。
「おいろむ、なんで自爆機能なんてもんがあるんだよ。これ、お前の同意の上でつけてたのか?」
「そ、それは……俺の同意云々っていうより、むしろ、俺が先生にお願いして、無理くりつけてもらったと言いマスカ……」
あまりの迫力に、思わず敬語になってしまった。
これ以上話すのだって怖いが、先生の名誉の為にも、俺は続ける。
「ほら、少し前に、死神のイチギくんから、俺っていう存在の危険性について話してもらったでしょ。だから、万が一の場合に備えた保険が欲しくてさ。だから、その……え、アサカゲさん? その拳をどうするつもり?」
「こうだよ!」
ゆらりと立ち上がったアサカゲさんの、左手を使った握り拳で、思いきり頭を殴られた。
「痛い!」
「おう、そうなるようにして殴ったからな。これに懲りたら、二度とそんな馬鹿なこと考えんな。クソ、これでもかってくらいにお前の魂を守る霊術を組み込んでやる」
「ええ、そんな……いや、ありがと」
「わかりゃ良いんだよ」
ぶつくさと文句を言いつつ、アサカゲさんは座り直して、護符を作り上げていった。
「よし、完成。ほらよ」
アサカゲさんは俺の手首から組紐とリストバンドの残骸を取り払うと、右手首に今しがた完成した護符を巻きつけた。
それは俺と反発することなく身体に馴染み、見慣れた秘色色のリストバンドへとかたちを変えていく。
「前の組紐もリストバンドも、現物に霊術を付与してて、いざってときの耐性が弱かったみたいだからさ。今回は、一から霊術で組み上げた特製品だ。よっぽどの大怨霊とかち合うことがなければ壊れないと思うぜ。ろむ、違和感とかはねえか?」
「びっくりするくらい、なんともない……かな」
術の種類にもよるだろうが、あれこれと機能を引っ提げた護符が常に巻きついていても、霊体に全く影響がないというのは、とんでもない技だろうに。相変わらず、しれっとすごいことをやってのけるものだ。
「それなら良し。これはオレと先生のどっちとも話ができるようにしたから、話したい相手を思い浮かべて使ってくれ。さっきみたいな瘴気を受けそうになったら、倍の威力にして反撃する機能も追加しといたけど、無敵ってわけじゃねえから、今後も下手に首突っ込もうとはするんじゃねえぞ」
「りょーかい」
俺の身を案じ、たくさんの機能のついたリストバンドをくれたアサカゲさんには、感謝しかない。むしろ、なんにもできない無価値な俺に、ここまでしてくれたことに涙が出そうになって、俺は無理矢理に笑顔を作って見せた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
