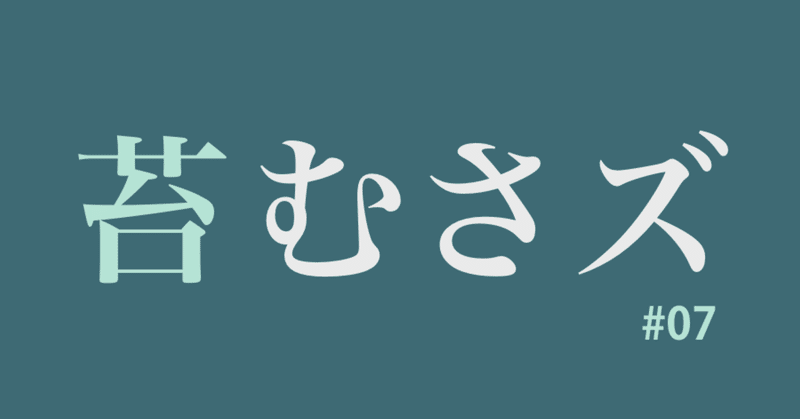
「苔むさズ」 #07
ゴリさんの「秋の港でデート」特集の入稿と戻しの繰り返し作業は5-6回にものぼり、その後やっと責了となり、あとは刊行を待つのみとなった。
ゴリさんと2ヶ月近くペアを組んだ編集のヤマさんはこれまたベテランの体育会系男子でゴリさんと馬が合い、楽しそうに日々取材や撮影に忙しそうに動き回っていた。そこまでの二人の生き生きとした日々はこの1ヶ月間でいつのまにか、地獄の徹夜続きに変わり、二人とも口数が少なくなった。
ゴリさんは張り切って毎朝ドレッド風に仕上げるヘアスタイルも、ついには落ち武者の様に肩くらいまでの髪を後ろでくくるだけになり、入稿準備に入る頃には冗談も言えないほど疲弊し、周囲がどんなに談笑して盛り上がっていても、一人闇のベールをまとっていて顔は硬直したままになってしまった。
「ゴリさんっていつもああなっちゃう感じ。すぐなおるべ。」と、心配する私にリンちゃんはカラッと答えてきたが、
私はこの時期ゴリさんを左横のデスクで右斜め前のMacに向かう彼の背中を見ていただけに、日に日に魂の抜け殻になる様子を見て人ごとには思えなくなっていた。リンちゃんはそのゴリさんの右横のデスクなのでゴリさんから背中を見られるかたちになっていた。リンちゃんは振り返った時と正面を向いてゲラのチェックをする時以外はゴリさんの仕事中の様子を見る事は出来ない。
それにしてもゴリさんの疲弊っぷりは、編集プロダクション・フリーライターをまとめながら自ら原稿を書き編集長からの校正を何度も直し、デザイナーとのスケジュール調整を行うプロデューサー的存在の編集担当ヤマさんの仕事量と比較すると、不思議なくらい酷いレベルになっていた。
正直、編集者と比べると、デザイナーの仕事量は相当限られていた。
こだわりを強く持てば側からみると地獄の徹夜続きになるが、
手を抜けばそれほど苦しまずに刊行まで進める事ができる様だった。
モトヒロさんやヒロシさん、リンちゃんがその様に程々に手を抜きながら仕事をしているのに対し、ゴリさんは異常なまでに最後までこだわりを通していた。
私はこの1ヶ月、このゴリさんのこの習性を目の当たりにする事になった。
あの日、ショウタ君と埠頭のカフェで別れてから、戻ったオフィスではモトヒロさんとゴリさんが残業をしており私はそこに居合わせる事になった。本来ならばショウタ君との間にできた元に戻せない亀裂の様なものを埋めるために仕事場に向かうべきではなかったのだが、私はあの夜は、くだらない話を一人で喋り続けるモトヒロさんをBGMにして仕事でもすれば頭もスッキリとするだろうという安直な考えでいたのだが、
戻ってきた私を待っていたのはもっと意地悪なモトヒロさんだった。
「あれ?彼氏さんとあってたんじゃないのぉ?」何故か知っている風に質問してくるモトヒロさん。
「いや、終わりました。」私は一気に不機嫌になる自分を抑えられずにぶっきら棒に答えた。
「こーっわ。おこってるぅ。エリコお嬢は彼氏さんとけんかとかしちゃったり?」
それには答えずに私がデスクの前に座ると、モトヒロさんはニヤニヤしながら恐る恐る私の表情を見ている様子だった。
「ゴリ君、メシ食いに行くべ。」突然モトヒロさんが聞いたが「いや、俺はホカ弁でいいや。エリコさんも買い行く?」と私に振ってきてくれたので同行する事にした。
11:00pm。そう言えばショウタ君とあっている間も何も食べていなかった。
「あのさぁ〜、エリコさん、スキャン作業結構あるんだけどお願いねー。」
突然モトヒロさんは、編集部から渡されたゴリさんの「秋の港でデート」用に撮影された数々の飲食店や雑貨屋、夜景やカップルの写真などがゴッソリ入っている茶封筒を投げる様に私のデスクに放った。封筒にはマジックで乱暴に「港522」と書き殴られている。522点のポジが入っているという意味だ。
「チミは子供なんだから、サヤさんから頼まれたデザインの仕事が本業じゃなくてこっちだからね〜」
「..........................はい。」
気まずい空気が一瞬ながれた。
「まあ、まずはメシ買いいくべ。」とゴリさんが言ってくれたので、タバコをふかし出したモトヒロさんを置いて、その場から逃げる様にゴリさんと外へ出た。
ホカ弁屋はビルを出て徒歩5分ほどの近所にあったから少し話す時間があった。
「エリコさん、ごめんね。俺の特集の写真が大量で。ヤマさんも結構神経質じゃん?同じシーンを10枚位撮影させちゃうのよ。ポジチェックして綺麗なのだけスキャンすればいいからね。」と労いの言葉をかけてくれた。
「俺さ、去年ここに入社して特集持たせてもらうのこれが初めてでスゲー嬉しくてさ、でもQuarkも使えないから相変わらずIllustratorのレイアウトでみんなに迷惑かけてるし。Photoshopもそんなに得意じゃないから手作りのを撮影する事になっちゃったし。でも頭んなかにはアイデアがいっぱいあって。」
私が雑用係の不思議ちゃんからデザイナーの端としてお手伝いの仕事をしている間に、小慣れた様に見えていたゴリさんは彼なりに深い悩みを抱えていたのだ。
「私なんて、ただの雑用係の子供だから、気にしなくていいですよ。」悲しいけど、誠実に話をしてくれるゴリさんに対しては本心でそう答えた。
「エリコさんはQuarkを使える様になったんでしょ?サヤさんがスゲー褒めてたよ。まじですごいよ。俺絶対むりだもん。X,Y数値でレイアウト決めなきゃいけないんでしょ?むりくない?」
この時ゴリさんとはなんでも話せそうな気になった。
恐らく、ゴリさんも人に心を開いていられたのはこの時期までだったのだが。闇に落ちて行くゴリさんを、私はこの後毎日無力に傍観せざるを得なくなっていった。
[続く]
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
